|
随分と遅れた、 とあるあとがき This was written into Nifty in May 4, 2009. Hiromasa Noguti --- Cotosiro --- 野口博正 |
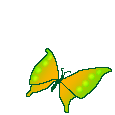
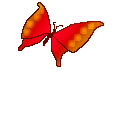
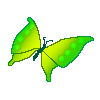
|
||||||||||
社会問題、思考や文化の問題、そして、進化について | |||||||||||
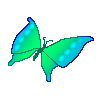
|
それにしても、我々は本当に懲りない生物です。未だに多くの罪を犯し、反省し、また、それを忘れて、更なる罪を犯し続けております。 正義や神の名の許に、実は自分の欲の為に、多くの人間を苦しめたり、蔑んだり、あるいは、抹殺すら、しております。 また、その事で苦しめられる人々は平和を求めて、抵抗し、銃を取る事も、それほど希ではありません。さもなくば、自殺や犯罪に走ります。 その種の自殺や犯罪は先進諸国、特に我が国で顕著です。 ストレスの解消の為に、我が親や我が子すら、いとも簡単に殺して仕舞うのですから、 これはただ事ではありません。我々も生物ですから、悪しき環境が整えば、その様な事態も自然の摂理、とは思われますが、それで良いのか、 と問われるならば、はい、と即答する人は少数でしょう。 私はこのような悲惨な状況を避けるのが政治のひとつの大きな使命である、と思うのですが、果たして、今の実情はどうなのでしょう? | ||||||||||
|
しかしながら、我々はその優秀な脳の故に、その様な蔑みや、殺戮を様々な理由を付けて、正当化する術を身に付けております。 その理論武装は精々、自分自身を欺す事が出来る程度で、相手を納得させるほどではないのですが、それでも、それは事ある毎に理屈を変えて、 雨後の竹の子のように顔を出します。そして、そのような理論武装は、労働者や貧困者などのいとも安易な切り捨てなどにおいても、 往々にして、見られます。 罪の意識を麻痺さなければ、相当に苦しまなければならないのですから、 その様な言い逃れの理屈が後を絶たないのは当然であるのかも知れません。あるいは、その様な切り捨ても、やむを得ぬご時世である、 と言う事なのでしょうか? |
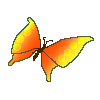
|
||||||||||
|
ちなみに、私は長い間、貧乏ですので、ひょっとしますと、既に捨てられた人間なのかも知れません。 いずれにしても、その様な安易な切り捨てが褒められる事でない事は確かです。また、その様な言い逃れの理屈は今、 恐ろしい副産物をもたらしております。つまり、それは罪の意識、そして、恥の意識の希薄化です。人殺しが罪深い行為である、 と言う事を知らぬ人間すら、増えております。倫理観を持たぬ方が生活しやすい世の中に成ってしまった、と言う事でしょうか? いずれにしても、民衆あっての共同体であり、共同体あっての企業ですから、このような文化の退化は大問題です。 日本の企業が発展して来たのも、先人の培った文化があった、と言う事を忘れては為らない、と思うのですが、どうなのでしょう? 私は日本文化が他国には見られない思考回路を育んで、産業などにおいて、優秀な技術を生み出し続けた、と考えております。 その故に文化の退化は問題なのです。残念な事に、文化の担い手であるべき民衆は今、仕事に遊びに、あまりにも忙しく成り過ぎました。 あるいは、極度の貧困の為に、食うだけで精一杯、と言う人も増えております。 いずれにしても、食事ですら、しばしば、レトルトもので済ますご時世ですから、個々人の、そして、家族間の情報交換はともすると、 希薄と成りがちです。簡単に言うと、文化を培う暇がありません。マスコミから与えられる情報の狭間でただ、右往左往しているだけです。 日本文化は消費をされる一方であるので、まさに今、すり切れようとしております。 | |||||||||||
|
近年、日本の漫画が世界で、もてはやされているそうですが、その内容は既に、退化の兆しを見せている、ように思われます。 おそらく、これも文化の荒廃の表れでしょう。 ひょっとしますと、このような文化の荒廃は各分野の指導的立場にある人々が自分の欲にあまりにも多く捕らわれている所為であるのかも 知れません。つまり、社会的な責任にあまり関心が無く成った所為なのかも知れません。 それとも、世界情勢の、特に経済情勢の激変の所為であるのでしょうか? いずれにしても、今のような風潮がこのまま、続いて、社会が何事もなく安泰を保てる、とは思えません。 その様な国家をその構成員が心から愛せるとは思えないからです。 現に今、個々人の繋がりは希薄と成って、互いの信頼感は失われつつあるように思われます。 さもなくば、忌まわしい非人間的な殺人がこれほど頻繁に起こるでしょうか? 企業や国家がしばしば、その構成員、あるいは消費者を裏切る事も、その遠因であるのかも知れません。 |
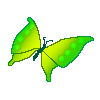
|
||||||||||
|
いずれにしても、人々は今、国や企業を信用しなく成りつつあります。このままでは、最悪、国の中に、 ある限定された社会のみに通用する規範、あるいは、無法な共同体が幾つも出来上がって、力を増して、互いに争い、 収拾の付かない事態に陥る事も無きにしも非ずです。あるいは、この言明は私の病的な心配性の故であるのかも知れません。 ですが、世界の情勢、歴史を見るならば、起こり得ぬ事でも無いのです。私は、大国に囲まれた古代のイスラエルが滅びたのも、 その種の事態が進行した所為ではないのか、と想像しております。あの当時、多くの予言者が現れて、神の声を人々に伝えました。 それはおそらく、上に述べたような共同体への危機感が彼らを駆り立てたからであるのでしょう。 ですが、彼らの声は伝わらず、あれほどの繁栄を謳歌した古代イスラエルは分裂の末、恐ろしい悲劇に見舞われました。 これは必ずしも古代イスラエルの事ではありませんが、共同体がしっかりと纏まっているなら、そして、指導者が賢明であり、 国民の事を本当に考えているのなら、たとえ、強大な外敵があったとしても、そう簡単には、滅びぬものです。 無謀な戦争に突入する事もないでしょう。必ず、耐え難きを耐え、忍び難きを忍んで、次善の策を模索する筈です。 事実、戦後の日本はその様にして、復興しました。いずれにしても、我々は今、その様な歴史の重みを感じるべきではないのでしょうか? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||||
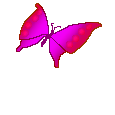 |
ところで、現代の文明社会に於いては、政治制度や司法制度、そして、学問などの大部分が近代、特に十九世紀に打ち立てられた原理、 原則に基礎を置いて居ります。そして、それらの諸制度や学問などは更に精緻を求めて、あるいは、社会的な利便性を求めて、 その専門化を押し進めて参りました。言い換えるなら、既に過ぎ去った二十世紀はその様な原理、原則の応用の時代であったように思われます。 しかしながら、その様な専門化は各々の専門分野の更なる細分化をもたらしました。無論、それは社会にとって、必要な事ではあったのですが、 逆にそれは今、全体を見る目を失わせつつある、とも言われております。人々は技術的処理のみに捕らわれて、原理、原則への考察を軽視する、 あるいは意識せず、忘れようとしているようにすら思われます。その事は様々な分野において、哲学的な基盤のない単なる数学的な、 あるいは論理的なモデルが横行している事にも現れております。 | ||||||||||
|
この事は、文明と人間に取って、非常に危険な事態であるように思われます。それは言うまでもなく、哲学無き思考は人間性の退化、 ひいては社会の退化をもたらすからです。人間社会の新たなる発展と平和のためには、 過去の遺産を基礎とした二十一世紀の哲学が必要であるように思われます。そして、それは量子論が示唆する新たなる物質観と、 相対性理論に見られる観察者へのより深い考察に基礎付けられる哲学と成りそうです。そして、それはおそらく、 唯心論と唯物論を止揚したものと成るでしょう。何故ならば、その哲学は世界を情報と認識との関係で捕らえる事に成るだろう、 と思うからです。 ちなみに、この場合の情報と認識の関係は物質間の反応にも適用される、と考えますので、従来の情報と認識の概念よりは、 もっと広義の概念と成りそうです。いずれにしても、新たな哲学的考察が為されず、技術論のみに終始するなら、最悪の場合、かって、 ローマ帝国が滅びたように、世界は退化の一途を辿る、と言う事も無きにしも非ずです。 |
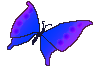
|
||||||||||
|
ローマ帝国が滅びたのは外敵の侵入、経済問題などの所為であるように言われておりますが、
私はそのもっとも大きな要因は共同体としての纏まりを失った所為である、と考えております。
無論、それはローマ帝国内の文化の整合性が損なわれた、と考えるからです。そして、近年の世界の状態を見るならば、既に、
先進諸国はその様な状況へと陥り兼ねぬところまで来ているようにも思われます。
イギリスはかつて、植民地などの独立運動に対する政策を変更して、宗主国と成る事を選び、全てではないにしても、それらの独立を容認した、 と言う歴史を持っております。私の想像ですが、これは意識的な政治判断の所為ばかりではなく、 ローマ帝国崩壊の歴史が彼らの心の奥底にあった所為であった、のかも知れません。考え過ぎでしょうか? ただし、これは当然ながら、ローマ帝国が独立運動の所為で崩壊した、と言っているのではありませんので、誤解などはしないで下さい。 |
|||||||||||
|
いずれにしても、ある共同体が他の共同体を植民地とする時、物質的な豊かさを獲得する代わりに、
共同体としての纏まりを失うリスクを背負わねばならない、と言う事は真実であるように思われます。
それは異文化の共同体を取り込む事で、文化の整合性が怪しくなって、共同体の纏まりが危うく成るからです。
また、その様な植民地を持つ事で、一部の人々の恐ろしい腐敗、堕落を生むからです。
更に、その様な情勢下では、共同体内の権力闘争や利害対立も激化する傾向があるようです。その様な問題がしばしば、暴動、そして、 クーデターやテロなどと成って現れる、という事は言うまでもない事であるでしょう。 また、その場合、国が強権を持って対処する事に成るでしょうから、強権政治に傾く事は当然の成り行きです。 ですが、それは共同体にとって、果たして、良い選択でしょうか? その故に、あの当時の英国は引き際を上手く見つけ出して、あのような判断をしたのでしょう。 |
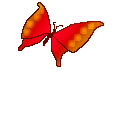
| ||||||||||
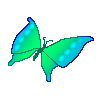 |
ついでながら、その意味で、私は開放的な移民の受け入れには否定的です。限定的な受け入れは良い刺激と成る筈ですので、肯定しますが、 日本はアメリカとは違うのですから、制約の少ない受け入れは必ず、共同体の纏まりを弱めます。 日本という共同体は日本文化によって纏まっているからです。また、日本人の脳の特性を考えるなら、少なくとも幼少期においては、 日本語のしっかりとした教育が必要であるように思われます。 なぜなら、日本人の脳と日本の文化などで述べましたように、 日本文化の根幹はあくまでも、日本の言葉であるからなのです。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ところで、我々人間はこの先、どのような生物と成るのでしょうか?その答えを即座に見出す事は難しい様に思われます。 ただ、此処では述べませんが、そのヒントは既に見つけております。そして、そのヒントは私の進化への理解の中にありました。 私は宇宙に内在する情報が進化を続けて、遺伝子を産み出し、生体という存在を産み出した、と考えております。 | ||||||||||
|
そう考える理由は「文明と生体」などで、述べておりますが、我々が少なくとも、この地球上で、もっとも、
認識能力に長けた存在である事を考えるなら、
そして、私の述べた生体に於ける進化のベクトルに関する数式が適正ならば、
我々の体験や情動や思想などがその様な進化の一翼を担い得る、という事は確かなように思われます。
つまり、その様な情報の交換が我々の脳の機能、ひいては遺伝子の進化に作用しない筈がありません。
私は進化というものを偶然の積み重ねで生起する、とは考えておりません。前述の進化のベクトルに関する方程式に見られるように、 生物の進化には、何らかの論理的な計算が介在している、と考えるからです。ならば、直接的かどうかは別として、 我々の意識のあり方が進化の方向を決定する、言い換えると、遺伝子の変異に関係する事も可能であるように思われます。 脳と生体、そして、生体と遺伝子などがしばしば対話(論理学的な計算)をしている、と考えるからです。 そして、その対話の結果はおそらく、生体の何処かに、ひょっとして、遺伝子に、すぐには発現せぬ遺伝情報として、ストックされております。 あるいは意味不明の遺伝子はその類であるのかも知れません。 |
|||||||||||
|
勿論、その様な対話が進化の結果として現れるのには、外的な条件も必要である、と考えますので、場合によっては、数万年、 あるいは数十万年もの歳月が必要であるのかも知れません。しかし、良き進化を求めるのなら、整合性のある主観的世界観は、進化の方向付け、 つまり、進化のベクトルを形成する意味に於いて、絶対に必要な条件であるように思われます。あるいは、遺伝子操作で人間を進化させよう、 と言う方も居られるのかも知れません。 しかしながら、進化の方程式を見るならば、失敗する事は自明です。 進化のベクトルを決定する諸条件全てを人間がコントロールする事は不可能である、と考えるからです。 私はやはり、我々の意思を含めた自然界の論理計算に任せるべきであるように思うのですが、あなたはどのようにお考えに成りますでしょうか? |
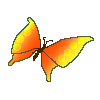
|
||||||||||
|
さて、以上の問題を凡庸な私が語るのは身の縮む思いではありましたが、この先、どのくらい生きられるのか、 あまり自信も無く成って来ましたので、頭が完全にぼけぬ前に、述べて置きたい、と考えました。身の程を知らぬ発言とは思われますが、 私の急速な老化に免じて、お許し下さい。 |
|||||||||||
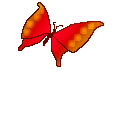
|
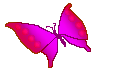
|
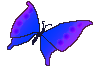
|
|||||||||
| Cotosiro | |||||||||||