| 日本文化の源流、その論理的帰結としての世界観 | 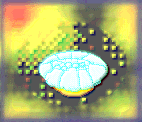 | |||||||||||||||||||||||
| Hiromasa Noguti Mail-address cotosiro@js6.so-net.ne.jp 2003.9.12 | ||||||||||||||||||||||||
|
縄文の世界観 縄文の世界 |
||||||||||||||||||||||||
|
我々の精神の根底には、縄文の魂、そして、縄文的な世界観が殆ど意識をされる事も無く、鬱々として眠っております。それ は先に述べた通り、 我々の縄文の魂に弥生の精神が覆い被さる社会的、精神的な二重構造の故でした。しかしながら、それは内面的には一種の 自己疎外であるよ うに思われます。そして、そのような自己の疎外は我々を社会、及び、組織がその様な自己疎外の上に成り立っている、と 言う諦観的世界観へ と誘う可能性を含んでおります。しかし、これは個人の尊厳の否定であり、個人の自由、精神性の否定であるように思わ れます。逆に言えば、組 織至上主義の肯定であるように思われます。また、個々人の組織化が進んだ今日、この様な社会は、強き者、富める者の 自由と権利が弱き者、 貧しき者の自由と権利を際限なく阻害する可能性を孕んでおります。もし、その可能性が現実と成るなら、それはヨーロッ パ的な階層社会とは 質の異なるより悪辣な階層社会へと繋がるでしょう。 その様な社会は組織の論理に馴染まぬ者を幾何級数的に増加させさせます。また、そのような人々を社会的に疎外するにも 関わらず、彼らと 彼らの疎外の心理を自らの体内に抱え込みます。そして、多くの人々を規範の基である自我の融合から閉め出すでしょう。 文化や規範の堕落、 そして、崩壊をもたらす事は自明であるように思われます。人間はただの労働力、また、組織の部品として存在するのでは ありません。彼らは あくまでも、精神的存在、すなわち、認識主体として存在します。にも関わらず、特に文明社会は人間を組織の部品とし て扱う傾向があるよう に感じられます。実のところ、このような社会の傾向が文化の堕落をもたらして、社会の荒廃をもたらすのです。勿論、 その具体的な動因と様相 はそれぞれの国家や組織などで異なるでしょう。しかし、少なくとも我が日本では、縄文の魂と弥生的な合理主義的 精神の歴史的な相克がそ の根底にはあるのです。我々はこの事について謙虚な態度で考えなければならないでしょう。 ところで、整合性を持つ主観的な認識が現実世界を規定するなら、意識体、すなわち、自我が認識の主体と思われます。 従って、組織至上主 義は主観の否定であり、また、主観の否定はオブジェクトたる世界の否定でもあります。それは無であり、生の反対の極に ある滅びの哲学で しかありません。もし、その様な哲学が蔓延するなら、過去の歴史を見るまでも無く、国家は早晩、滅びるでしょう。先に、 述べたように共同 体には、個々の自我を融合させる精神的基盤が無くては為りません。また、本当の哲学というものはその様な原理原則を探 り当てる事に他な りません。その意味で、整合性を持つ認識者は大切にされねば為らないでしょう。 いずれにしても、借り物の原理が賞味期限切れと成った今日、我々は我々本来の世界観、すなわち、縄文の世界観を再認識 しなくては為りませ ん。また、其処から我々本来の精神的原理を抽出しなくては為りません。その事無しに、我々の整合性のある認識は確 立される事が出来ないか らです。そこで、ここではまず、その世界観を呼び覚ます為に縄文人の世界をおさらいし、次いで、その世界観を考え る事と致します。 とは言っても、縄文時代は非常に長きに渡って続いて居ります。そこで此処では、縄文文化の最盛期と思われる縄文中期 から後期の辺りに焦点 を合わせたい、と考えます。その時期はおおよそ、BC2000年ないしBC1000年の辺りです。そして、その時 期、列島は比較的、温暖でしたが、 それは寒冷期に向かう途上であり、また、大陸では殷王朝(BC1500年頃)が成立し、新モンゴロイドの優位性が少なく とも客観的には顕著と成っ た時代でもあります。ちなみに、縄文晩期は縄文文化の衰退期であり、弥生時代へと向かう激変の時代であった 事を付言して置きます。 従って、当時の縄文人は少なくとも縄文後期に入りますと、無意識ながら世界の激変の予感を抱き始めたのではないのでし ょうか?そして、その 不安はおそらく縄文文化が爛熟の域にあった事とも関係しました。今日よりも明日が良い日である、とは限らない。少なく とも、その様な心理はあ った様に思われます。縄文人達の前途には、心理的にも現実的にも、暗雲が立ち込めておりました。 おそらく、一部の縄文人はその様な不安の現実性に気付いていたように思われます。列島の縄文人は四方を海に囲まれた いわば海洋民族で す。また、その時期は縄文文化の隆盛期でもありますので、外界に対する好奇心は旺盛であり、非常に行動的であった、と 推測できます。その 故に、彼らは彼ら独自の航海技術で、列島各地の交易ばかりでは無く、大陸の旧モンゴロイド、あるいは新モンゴロイド化さ れつつあった旧モン ゴロイド、そして、間接的かも知れませんが、力を持ち始めた新モンゴロイドなどとも、交易し、見聞を広めていたのではな いのでしょうか? いえ、彼らはそうとうに大陸の事情に通じていたように思われます。しかしながら、少なくとも、その時期に於いては、新 モンゴロイドの文化に劣 等感を感じる事は無かったでしょう。むしろ、彼らは自らの文化の優位性を感じていた様に思われます。それは先に述べた 通り、縄文文化 が最も隆盛を極めた時代であったからです。出土した土器や土偶を見るならば、彼らが自らの文化に誇りを持っていた 事は手に取るように分 かります。また、新モンゴロイドの文化の影響が未だ微弱であったが故に、縄文の世界観もおそらくは完成の域にあっ たでしょう。 ところで、従来は、彼らの生活の多くが狩猟採集によって支えられていた、とされておりました。また、ドングリなどが主 要な食糧であった事は良 く知られております。更に、貝塚などで見られる貝、魚、動物の骨などから窺えるように、その食料は非常に多彩で あった、と言われております。 しかしながら、近年、その様な見解は変わり始めております。栗林らしき痕跡など、農耕の形跡も見られるか らです。また、当時の縄文人の虫歯 の発生率は他の狩猟採集民族と比較すると、非常に高く、むしろそれは農耕民族に近い事が分かっております。 当時、縄文人の集落は急速にその規模を大きくしております。それは大量の食料の安定供給が為されて居た証拠である、と 考える事が可能で すので、現在は、農耕は想像以上に行われて居た、とする見解が有力と成っております。また、その事は土器や道具の形状 などからも窺える、 と言われております。無論、農耕の普及については、地域差はそうとうにあったでしょう。しかし、その様な地域差はおそ らく、各集落の交易で 埋められていた様に思われます。事実、黒曜石などの交易の痕跡も見られますので、特に海沿いの共同体は数多くの交 易で潤ったのではない のでしょうか?当時の交易は物々交換であった筈ですが、それでも利潤は生じるからです。 |
|
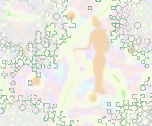
|
また、その様な理由から、食料などの保存技術も発達していたように思われます。食料、衣料は交
|
易の重要な対象であり、長い航海を要する交易では、特に食料の保存技術は必要不可欠である、と 考えるからです。あるいは、貨幣の役割を果たす何等かの特定の物資すら存在した可能性が考えら れます。頻繁な交易には、基軸通貨に類した物が必ず必要に成る、と思われるからです。 |
|
|
|
Cotosiro | | |||||||||||||||