|
可能世界・陰の神話 第十三章第一話 |
野上と恵比寿 This was revised in December 7, 2006. This was revised in September 18, 2008. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
押知と京子が妻良に向かった五日ほど前、影浦のところに、札幌に居る典子から、電話があった。野上と言う男が電話で、影浦に面会を求めて来た、と言うのである。典子が男に、影浦が不在である事を告げると、男は「是非、会って頂きたいので、よろしく、お伝え下さい」と、連絡先の電話番号を典子に伝えた、と言う。だが、野上という人物は果たして、何処の誰なのか?影浦は受話器を持ったまま、考え込んだ。野上、と言う名前には、聞き覚えがあったものの、それがどうも、特定の人物に繋がらない。年の所為か、最近、一時的にこの様な事が起こるのである。「ああ、誰だったかなあ」影浦は試みに、男のフルネームを典子に問うた。すると、典子は男が野上敏信と、名乗った、と言う。「ああ、あの野上か?」影浦の脳裏にようやく、その人物の事が浮かび上がった。 野上敏信は夷(恵比寿)神社の神主であり、神道研究家としても、知られていた。影浦は彼とは面識は無かったけれども、以前、彼の著書を読んでいたのである。だが、その電話は本当に、その人物からであったのだろうか?電話を切ると、その様な疑念が頭を擡げた。怪しげな目的を持つ何者かが名前を騙った、と言う事も十分に考えられるのである。影浦は少し、不安に成った。人を疑う事は好まぬけれども、最近は、人心が荒廃している。そして、祈言宗や亜真野達の暗躍もある。油断をすると、どんな落とし穴があるか、分からない。其処で、影浦は懇意にしている出版社に電話を入れて、野上の電話番号を調べて貰った。すると、それは確かに、野上と名乗った男の連絡先と一致する。差し当たり、影浦は安堵した。だが、野上は何故、面会を求めて来たのか?影浦はすぐに、野上のところに電話を入れた。野上と言う人物には、ある理由で、少し興味があったのである。だが、野上は電話では、多くを語らなかった。「用件はお会いしてから、お話ししたい」と、言うのである。はっきりとはしないのは不満であったけれども、影浦は結局、申し入れを受け入れた。野上は今日、この道場を訪れる事に成っていた。 だが、小林の失踪や康夫の事など、不測の事態が生じた所為か、どうにも、気分が落ち着かない。頼りに成る宮城は相も変わらず、祈言宗の調査で、地方に出ているし、逆崎は今、押知と共同経営をする筈の農場の件で、帯広に居る。そして、押知と京子も妻良から戻らぬ。出来得れば、延期をしたいところであった。だが、約束をしたものは、し様が無い。野上は時間通りに現れた。それにしても、国家神道とは一線を画するこの神官が一体、何の目的で、接触をしよう、と言うのだろうか?問題の男を目にすると、野上への興味はいや増しに、掻き立てられた。 影浦が野上を道場に通すと、野上は影浦を知った経緯などを織り交ぜながら、長々と挨拶をし始めた。三十そこそこの若さと言うのに、その物腰は妙に年寄り臭い。そして、態度も異様に堅苦しい。緊張をしている所為であろうか?それとも、腹に一物でも、あるのだろうか?いずれにしても、心地の良い印象とは言い難い。「用件は一体、何なんだ?」影浦は湧き上がる疑念を押し殺しつつ、じりじりとしながら、話を聞いた。そして、彼のオーラに注意を払った。だが、彼のオーラに、怪しい陰りは見られない。見たところでは、極、一般的な人間である。ならば、この異様な態度は何処から来るのか?あるいは、単に、極度のあがり症である、と言う事なのか?いずれにしても、彼をその様に振る舞わせる彼固有の要因がありそうである。影浦はその要因に興味を持った。 野上の顔は顎が張って、角張っており、首は太くて、短めである。そして、体の造りも骨太である。影浦はこの様なタイプの人間が謹厳実直である事を知っていた。粘り強い性格でもあり、その中には、馬鹿の付く程に丁寧な態度で、人に接する人間も、そう希では無かったのである。野上はその様な人間の典型の様に思われた。其処に、極度のあがり症が加わると、こう成るのだろうか?だが、問題はそれだけでは無さそうである。おそらく、其処には、彼の過剰な自負心やコンプレックスがあるのに違いなかった。いずれにしても、どの様に謹厳実直であるのかは、人によって、若干、異なる。あるいは、場面によって、変わり得る。その様な態度だけでは、彼の今の本心が如何様にあるのか、までは、推し量れない。謹厳実直であるとは言っても、無条件で、信用をする事は難しかった。 さて、堅苦しい挨拶をようやく、終えた野上はフウッと、息を吐き出した。見ると、彼の額には、汗がうっすらと染み出している。野上はハンカチで汗を拭うと、再び畏まって、語り始めた。「先生、今日、お伺いを致しましたのは、ある事に付いて、是非、ご意見をご拝聴致したく、お忙しい所を、お邪魔致しました次第なので御座いますが」随分と大仰な態度ではあるのだけれども、性格ならば、致し方ない。影浦は黙って、耳を傾けた。野上は言う。「実は私、以前から、恵比須と言代主の関係を考え続けて参りました、そして、ある重大な問題に気が付いたのです」そして、彼は右手に握ったハンカチで、止まらぬ汗を再び、拭った。 聞いている方も疲れるけれども、野上はやはり、緊張をして居るらしい。何故、それほどまでに、緊張するのか?影浦には、その様子が妙に滑稽にも思われた。無論、その様な態度を揶揄するつもりなど、無いのだけれども、笑いの虫は容赦ない。影浦をしきりと突き上げて、笑え、笑え、と迫るのである。このままだと、つい、吹き出してしまわぬとも限らない。影浦は、「ちょっと失礼」と、席を立つと、離れへと、足を急がせた。そして、障子をしっかり閉めると、しつこく迫る笑いの虫を心置きなく解放させた。これで、しばらくは持つだろう。影浦は何食わぬ顔で席に戻ると、素知らぬ顔で、問い掛けた。「いや、どうも失礼を致しました、それで、何に気付いた、と言うのです?」「はい、少々、長く成りますが」野上はそう前置きをして、自分の問題を語り始めた。 野上は古来から言われる恵比寿(恵比須)と言代主命についての同一説に大きな不満を持っていた。明治維新の仏神分離策の際、恵比寿が神々の正当な系譜に属さない、と言う理由で、異端視をされた事が我慢為らなかったのである。(仏神分離策 ・ ・ 明治以前、仏と神々は何時からか、渾然一体と成り、明確な区別が無く成っていた。そして、明治の時代、それを分離して、その違いを明確にしようとする政策が打ち出される。日本を神国として位置付ける為のものだった。)だが、恵比寿が異端視をされたのには、それなりの理由は確かに在った。古事記、日本書紀に恵比寿の記事は何も無く、また恵比須を表す「夷」の文字も夷狄の神を想像させる。当時の国学派がこの神を天照大御神にまつろわぬ怪しげな神として軽視したのも、無理からぬ事ではあったのである。そして、その事が当時の神社の態度にも、多大の影響をもたらした。夷(恵比寿)を祭るべき恵比須神社が異端視される事を嫌う余りに、同一説を利用して、その祭神を次々と言代主命へと変えたのである。だが、恵比須を信ずる野上には、許し難い行為と思えた。そして、そうさせた国学派の考え方も承伏し難いものだった。 実を言えば、この同一説は言代主命がその昔、漁をしていた、という故事と、恵比須がしばしば、海岸に現れた、という伝承から推測をされたものだった。だが、学術的な意味などは全く無く、野上はその様なこじ付けが許せ無かった。「しばしば、海岸に現れた、という事は其処には、住んでは居ない、という事では無いのか?其処に住んでいるのなら、常に居る、と言うべきだ、恵比寿は内陸の神に決まってる」野上はあえて、その様なひねくれた態度を取っていた。祭神をいとも簡単に変えて仕舞う神社の態度も情けが無い。便宜的に変えた事は明白であり、祭りを司る人間の取るべき態度とは言い難かった。「彼等は本当は、神など信じては居ないのだ」野上はそう疑っていた。其処で野上は事の真相を見極めようと、その研究に乗り出した。恵比須の神の源を明らかにして、本来の神性を回復させる。それが野上の願望だった。だが、恵比須に付いての資料は少なく、僅かな伝承が在るだけである。其処から真理を汲み取って、推理をするしか仕方が無かった。「だが、何故、こうも資料が少ないのだろう、何故、記紀には、恵比須の記事が無いのだろうか?」野上に取って、恵比須は神代の昔から祭られた由緒正しい神である。それだけに、聖典とも言い得る記紀に記載の無い事は不可解であり、不愉快だった。 「しかし、私は気が付いたのです」野上はそう述べて、話を続けた。恵比須の資料は何故、少ないのか?其処には、それなりの理由が在るのでは無いのか?野上は其処に思い至ると、一応の推理を導き出した。夷は文字流入の遥か昔から祭られて居た為に、時と共に、その口碑などの資料が次第に散逸して、その因って立つ大元の神性が忘れ去られたのでは無いのか、と考えたのである。だが、恵比須は古今ともに祭られており、多くの人々に親しまれている。忘れられた神とは言い難い。そして、神祖熊野櫛御気野命(カムロキ、クマヌノクシミケヌノミコト)の様に神性の不明な神で在っても、記紀には、はっきりと記されている。時間経過の説明だけでは克服出来ぬ問題だった。 そこで、野上は恵比須は意識的に記紀から外されたのでは無いのか、と考えた。だが、記紀には、言代主をはじめとする大和に反抗した神々までもが余すところ無く記されて居る。従って、外された理由はまつろわぬ神であるからでは無く、神性が分からぬからでも無さそうである。ならば、夷(エビス)の記紀からの排除には、特異な事情が在らねば為らない。野上はそう考えた。だが、その事情とは、果たして、何か?記紀の編纂に至るまで、大和は屈服した先住民の神々を自らの神々の体系に組み込んで、その序列化を推し進めている。それが先住民懐柔の国策であり、最優先の課題であった。たとえ、恵比寿が当時、大和にまつろわぬ神であった、としても、その例外では無かった筈である。ならば、恵比寿は何故、記紀に載せられては居ないのか?「謎は深まるばかりで、私は途方にくれて仕舞いました」野上はそう述べると、一息、付いた。かなりの苦労をしたのだろう。その事は話のし様で窺い知れる。だが、真実という厳しい女神は希望的な観測や単なる努力などには、微笑まない。あくまでも、正しい認識にこそ微笑むのである。影浦は内心、がっかりして居た。一般的に恵比須が祭られ始めたのは、せいぜい遡っても、平安時代の初め頃、と言われて居る。恵比寿がそれ以前に編纂された記紀に記載の無い事は至極、当然の事だった。夷への思い入れは理解も出来るが、余りに頑迷と思われる。「皮肉のひとつでも言って遣ろうか?」影浦はそんな衝動にも捕らわれた。だが、生真面目そうな男を見ると、そんな意地悪も出来兼ねる。「とにかく、最後まで聞いて見よう」影浦は野上の話を促した。野上が言った。「はい、それで、しばらくは何もせずに居たのですが、その内、あるひとつの事に気が付いたのです」 実を言えば、記紀に記載された神々はそれが編纂された時代に入ると、全てが天尊族に屈服して居り、正確に言えば、それは以前のまつろわぬ神々だった。とすれば、未だまつろわぬ神々はどう扱われたのだろう?当然、記紀からは排除された、と考えねば為らない。夷の記載が記紀に無いのは、その所為なのに違い無かった。つまり、恵比須は大和にとって、未だまつろわぬ外敵の神、と考えられた。だが、その事は恵比須の神と、当時、外敵であったエミシ、そして、エゾとの関係すら連想させる。夷(恵比寿)を古来からの神、と考える事は可能と成ったが、彼は新たな問題を背負い込んだのである。野上はいやしくも、日本神道の神主である。夷が夷狄の神であるなど、考慮の外の問題だった。だが、その事を認めなければ、古来からの神である、とする事は難しい。然も無くば、やはり、平安期からの新興の神、と考えるしか無かったのである。だが、その様な結論は受け入れ難い。野上は二律背反に追い込まれた。またしても、新たなる思索を迫られたのである。恵比須は昔、「蝦夷」とも表記をされた。つまり、エビスを蝦夷、とも書いたのだった。そして、その表記は古事記、日本書紀、そして、続日本紀などにも、散見される。ただし、それは神の恵比須では無く、あくまでも、蘇我蝦夷などの人名や、大和とは一線を画する東北住民の呼称として使われていた。 エビスは初め、エミシ(愛瀰詩)と発音された。だが、時代が下るに連れて、それはエミス(江美須)、エヒス(依比須)と、変化して、平安時代に入ると、おおむね、エビス(恵比須)で落ち着くのである。これが発音の変遷だった。だが、その漢字表記は各々の時代を通じて、毛人、蝦夷、夷、等々が使われる。ただし、人名などに関しては、その発音を表す、依比須などもそのまま、表記として使われた。今、我々に親しまれている恵比寿の文字は元来は発音を表す文字であり、体を表す文字では無い。野上はその事にも、強い不満を持っていた。 さて、その「エビス」が神の呼称として、初めて、文献に現れるのは、平安も末期に成っての事である。そして、その表記が、「夷」の文字で表されている。その神性も今の様な福々しい神では無く、荒々しい戦闘的な神として表現された。そして、何故か、同じ頃、北方の夷狄がエゾと呼ばれ始める。つまり、その呼称が何故か、エミシやエビスから、エゾへと移行し始めたのである。恵比寿の神の登場と、東北住民の呼称の変化は絡み合いながら展開している。神としてのエビスの登場と東北住民の呼称の変化には、何らかの関わりが在りそうだった。だが、野上に取って、それは認め難い関係だった。其処で、彼はその様なジレンマから抜け出したい一心で、一応の逃げ道を考え出した。 当時、東北住民をエミシ、と呼んだ事は間違い無かった。だが、それが即、北方の夷狄を表す、とは限ら無い。東北には、大和にまつろわぬ倭人が居り、それをエミシ、と呼んだのかも知れ無い。つまり、エミシはエゾでは無く、倭人の一種であったのかも知れ無い。そして、もしもそうならば、夷(エビス)は倭人の神とする事も出来るのである。この考え方は野上に取って、都合が良かった。未だまつろわぬ神ならば、記紀に記される事も無く、古来からの神、とも言い易い。野上は取り敢えず、二律背反からは抜け出せたのである。彼はその発音と表記を手掛かりに、更に研究を積み重ねて、恵比寿の神性を探って行った。野上が最初に注目したのは人名に使われるエミシであった。毛人、蝦夷、依比須、などがそれである。元来、愛瀰詩(エミシ)は強い人の意味だろう、と言われて居り、その意味で、人名に使われたものと考えられた。夷狄の呼称を名乗るなど、常識的には考え難い。従って、愛瀰詩の呼称は夷狄のエミシとは、由来を異にする、とも推測できた。野上はその推論をより精緻なものとする為に、更なる思索を重ねて行った。 だが、彼の苦しみは其処から始まる。そうした飽くなき探求心が彼の信念を揺るがして、彼を恐ろしい崖っ縁へと追い込んだのである。第一に、「毛人」という表記が問題だった。これは明らかに毛深い人の意味であり、エゾの容貌を思わせる。そして、日本書紀の景行紀には、エミシに付いて、多毛で文身(入れ墨)などの特徴が記されている。更に、中国最古の地理誌、と言われる山海経の海外東経の部分には、日本列島の事を紹介したものと思われる記事が在り、その東北には、毛民の国があると記されていた。毛人の表記と人種としてのエミシ(エゾ)との間には、深い関わりが在りそうである。そして、第二の問題は「愛瀰詩」の意味の解釈だった。どう見ても、単に「強い人」の意味とは思え無い。もっと、奥深い意味が在りそうだった。 「愛瀰詩」は日本書紀の神武紀に、その文字が記されている。神武軍の大来目部が畿内に根を張る八十建(ヤソタケル)の残党を酒に酔わせた上で襲って、絶滅させた時の歌謡である。「愛瀰詩は一人で百人力である、と人は言う、だが、我々の前には手も足も出ない、我々はもっと、強いのだ!」ほぼ、この様な内容の戦勝の歌である。実は酒に酔わせて、動け無くして置いたのだが、勝利の歌としては、こう成るのだろう。いずれにしても、この「愛瀰詩」が文献に見えるエミシの最古の表記であった。ところで、愛瀰詩(エミシ)が強い人の意味である、とされたのは、八十建(ヤソタケル)の呼称に由来するものと思われる。これは多くの荒々しい者達という意味であるから、大和は愛瀰詩をその様な目で見たのだろう。八十建はその象徴として語られた、想像上の人物、とも考えられた。そして、この戦勝の歌でも、エミシは一人で百人力、とされている。やはり、強い人の意味なのだろう。一般的には、その様な解釈が定着していた。だが、野上には、それがしっくりとはし無かった。彼は躊躇をしながらも、自分で推理を組み立て直した。野上は今までの推理から、愛瀰詩は八十建に象徴される共同体、あるいは部族などを表す、と考えたのである。 ならば、愛瀰詩本来の意味は別にある様にも思われる。八十建(ヤソタケル)は強い人の意味にかなり近いが、倭人は彼等を八十族などと呼んでは居ない。あくまでも愛瀰詩、と呼んで居る。それとも、やはり、愛瀰詩は強い人の意味なのだろうか?だが、味方の勇者を愛瀰詩と呼んだ例は見当たら無い。僅かに、人名に使われただけだった。愛瀰詩には、やはり、もっと別の、奥深い意味が在りそうである。野上は蝦夷(エミシ)本来の意味を探り始めた。蛮族を意味する愛瀰詩と強い人を意味する愛瀰詩、そして、その背後に在る、と思われる本来の意味。それらの繋がりを見付ける事が問題を解き明かす鍵だった。そして、彼の魂はやはり、その鍵を記紀に求めた。野上は天尊族の東征を事実である、と考えている。八十建の記事も、その過程を象徴的に表現したものと考えている。そして、其処には、エミシが愛瀰詩の表記で記されていた。また、これが文献に見える最古のエミシでもあるのであった。もし、八十建の話が史実を表して居るのなら、畿内はやはり本来は、エミシの縄張りであった、と考えなくては為らない。其処に、大和が東征して、エミシと戦った。そして、畿内を奪った。そう考えるのが自然であった。本来的なエミシの意味は、やはり、この関係の中に在りそうだった。 |
|||||||
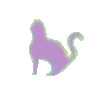
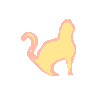
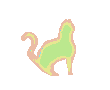
| |||||||
| Cotosiro | |||||||