|
可能世界・陰の神話 第九章第三話 |
神殿の謎 This was revised in February 23, 2012. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
その1 能登の部族派 その日、羽咋は霧雨だった。朝方から、陰鬱な雲がたなびいていて、しとしと、降ってはいたのだけれども、その状態は夜に成っても、変わらない。一向に、止む気配も、窺えず、陰鬱な闇を煙らせている。宮城には、それがこれから為すべき探索の、不透明な先行きを象徴するかにも、想われた。気多の神社の辺りでは、人の通りも、殆ど、見られず、僅かに並ぶ外灯が闇に微かに、浮かんで見える。宮城は今、その様な闇の狭間から、祈言宗の本部を窺っていた。雨の滴が身体を濡らすが、其処に潜入をするのには、むしろ、味方とも成りそうである。 だが、一キロ平米ほども在りそうな、その敷地はブロック塀にぐるりと囲まれて、厳重な警戒を思わせる。ブロック塀の最上部には、鉄条網が螺旋状に張られてあって、鉄骨の返しまでが施されている。中の様子は皆目、分からず、闇雲によじ登る事は躊躇をされる。やはり、出入り口から入る以外、進入する方法は無さそうなのである。宮城は監視カメラなどの有無を確認しながら、塀の周りをぐるりと歩いた。 だが、以前、出入り口であった、と思われる三カ所に設けられたゲートには、その全てに、鉄柵が施されており、堅く閉鎖されている。今、開放されているのは、たったの一カ所、守衛の居る東向きのゲートだけである。どうやら、其処が今、使われている唯一のゲートであるらしい。「仕方無い、彼処から入ろう」宮城はそう決断すると、直ちに、守衛の老人に、念波を送った。眠りを促す為である。余り念波を使っては、覚られる事も考えられるが、別段、何事も起こらずに、老人はすぐに、眠りに付いた。ゲートの周辺には、さっきまで、数人の警備員らしき男らが歩いていたが、今のところ、彼らの気配は窺えない。宮城は足を忍ばせて、素早く、ゲートを擦り抜けた。 見回すと、東へ五十メートルほど、行った所に、古めかしい木造の建屋が佇んでいる。二階建てで、洋風の、かなりの立派な造りであった。東西に走る塀からは、五メートルほど、離れており、塀に沿った、横に長い造りで、建てられている。部屋数は二十前後も、在るのであろうか?幾つかの窓からは、明かりが漏れていて、人の気配も窺える。他にも、建屋は幾つか、在るが、皆、小さく、人の気配は窺えない。目指す建て屋はそれで、決まった。だが、注意は要する。時折、敷地の暗闇で、ライトの様な光るものが動いている。見回りが居るのに違い無い。おそらくは、先ほど、目にした警備員だろう。宮城はブロック塀に張り付く様に、暗闇の中を歩き始めた。 敷地の所々には、建築資材か、何かだろうか?雨よけの黒いシートを被せられた物資が、かなりの高さにまで、積まれてある。神殿建設の資材だろうか?だが、ざっと、見渡したところでは、建設中の建屋など、見当たらぬのである。宮城は少し、小首を傾げた。この様な広大の敷地を購入したのであるから、普通の教団であれば、神殿は既に、出来上がっていても、良い筈である。これも、知らねばならぬ問題である。宮城は目指す建屋へと、歩みを進めた。 だが、彼が今、居る位置では、建屋の出入り口の様子が分からない。宮城はブロック塀から、素早く離れて、目指す建屋へと、取り付いた。其処は建屋の北側に位置する外壁である。彼はその外壁に沿って、人の気配の無い西側に回り込むと、更に、南の側へと、歩みを進めた。そして、建屋の角から、南側をそっと、覗いた。と、その中央の辺りだろうか?見事な造りのベランダ風の出っ張りを見る事が出来る。そして、その出っ張りからは、優雅な造りの階段が緩い傾斜で、末広がりに、前庭の方へと、迫り出していた。おそらく、其処が玄関なのである。前庭には、数本の街灯様の屋外照明が据えられている。白っぽい明かりが建屋と前庭を仄かに照らして、落ち着いた佇まいを演出していた。玄関とおぼしきベランダ風の出っ張りのすぐ、脇には、小さな部屋も在るらしく、窓から漏れ出す白い明かりがカーテンの無い窓を通して、幾人かの影を浮き出させている。三、四人は居るのだろうか?部屋の位置と大きさから見て、彼らは警備員なのに違い無かった。 それにしても、この物々しさは何だろう?木材工場の事務所だった、と言うこの建屋と言い、鉄条網に守られた敷地と言い、とても、信仰の殿堂とは思えない。むしろ、秘密の軍事基地か、何かの様で、怪しげな雰囲気すら、漂わせている。「だが、何処から、入ろう?」玄関は警備員によって、守られている。人も、頻繁に出入りしている。幾つかの部屋からは、灯りも漏れて、やはり、人の居る事が窺える。窓から入る予定であったが、この様子では、それはとても、無理である。宮城は一旦、建屋の北側に引き返した。そして、外壁の脇に蹲ると、「どうしようか?」と、考え込んだ。だが、良い考えなど、浮かんで来ない。彼はふと、屋根の方を仰ぎ見た。 と、二階の窓と屋根との間に、横長の四角い窪みの様な物が僅かに、見える。明確ではないが、縦、五十センチ、幅は三メートルほども、在るのだろうか?「だが、何だろう?」宮城はじっと、凝視した。だが、建屋の北側には、明かりが無い。雨雲の所為で、月の明かりも、届いていない。「くそっ、明かりが欲しいな」宮城は思わず、呟いた。と、その刹那、通り掛かりの車のライトが一瞬、くぼみを僅かに照らした。見ると、それは窓である。建屋の中央に、三つほど、並んでいるが、どれも、灯りは付いては居ない。おそらく、使われては居ないのである。工場だった当時、屋根裏部屋を利用した、その名残であるのに違い無い。開ける事が出来るなら、潜り込む事も、出来そうである。「だが、道具が居るな」宮城は明日、出直す事にして、其処を離れた。 宮城はホテルに取って返すと、此処、羽咋で、これまでに入手した気多神社に関する情報を纏めてみた。すると、それらの情報はやはり、気多神社が言代主などと、無縁ではない事を示唆したのである。祈言宗の本部がこの羽咋に置かれた秘密がどの様なものであるのかも、朧気ながら、浮かび上がった。 気多神社は古くは、気多大神宮と呼ばれる歴史のある神社である。その祭神は多穴牟遅命であった。また、気多神社に伝わる口碑によれば、孝元天皇の治世の折り、この地には、不逞の輩が多くあり、悪しき行いで、世情を乱した。其処に、多穴牟遅命が現れて、その様な不逞の輩を懲らしたのである。長い間、苦しんで来た能登の住民は大いに喜んで、その神徳を称える為に、この神をこの地に祭った、と言うのである。一般的には、それが気多神社の始まりである、とされているのである。 だが、それは果たして、真実だろうか?口碑に於いて、不逞の輩とされたのは、実は、多穴牟遅命を称えた、とされる当の住民達では無かったのか?宮城はその様な疑念を抱いたのである。 おそらく当時、能登の住民も他の地域の部族と同様に部族特有の風習や祭事などを持っていた。そして、この口碑からは、大和の影響下に在った事も窺い知れる。いや、支配下に在った事すら考えられた。いずれにしても、能登の祭事は天津神々の浸食を受けながら、大きな変化を遂げつつあった。と成ると、自らの魂を守ろうとして、反抗する一派が現れるのも歴史的な必然である。能登の住民は大和従属派と部族派とに分かたれ、血みどろの戦いをしたのに違い無かった。だが、大和は当然の如く、従属派の側を支援した。部族派はその圧倒的な力の前にあっさりと葬られたのでは無いのだろうか?いや、それはまず、間違いなかった。大和の覇権は盤石と成り、能登の住民の部族の誇りは無惨なまでに砕かれたのである。 さて、その様な事情を考慮に入れると、口碑に於いて、不逞の輩とされたのは盗賊などでは在り得なかった。自らの文化を守ろうとして、大きな大和に歯向かった、部族派だったのに違い無い。土着の民の心情も、部族派側により、近かった様に推測される。一方、部族派を破り、能登の支配者と成った大和はその証として、自らの神を能登の地に祀らねば為らなかった。だが、どの神を祀るのかが問題である。選定は土着の民の心情も、考慮に入れて、禍根を残さぬよう、せねば為らない。然も無くば、何時また、不逞の輩が現れるか、分からぬのである。其処で、大和は一計を案じて、多穴牟遅命に、その役割を担わせた。 この神は国津神では在るものの、大和の勢力拡大に多大の貢献を為している。また、その一方で、大和の出現以前、畿内と山陰、能登に掛けての支配者、保護者でもあったのである。大和に荷担したとは言え、当時、多穴牟遅命への信仰は能登では未だ、絶大だった。多穴牟遅命に対する彼らの敬愛の情には、いささかの陰りも無かったのである。その故に、大和は征服民懐柔の切り札として、また国譲りの神として、多穴牟遅命を崇めたのである。現に、その方針は明治、いや、昭和の敗戦に到るまで、受け継がれて居る。日本が占領した土地に創建された神社の祭神は、その殆どが多穴牟遅命であったのである。その様な意味で、多穴牟遅命は大和に取って、欠かせぬ神と成って居た。だが、裏切られた筈の国津の部族が何故、多穴牟遅への敬愛を持ち得たのだろう?実を言えば、その事も歴史の深層に隠されていた。 また、宮城はその事に関連する問題を、影浦の書いた祟り神の悲劇の中に見出した。それは小説ではあるものの、古代史については、影浦の歴史認識に従って、忠実に、述べられている。そして、宮城も、あの熊野すら、それは真実であろう、と考えていた。 その祟り神の悲劇によれば、多穴牟遅が国譲りを迫られた時、彼は大和に対抗すべき術を失っていた。生き延びる為には、国を譲るしか、無かったのである。無論、無条件の降伏などでは、部族の証、神々までもが奪われ兼ね無い。「譲るにしても、祭事だけは守らねば為らぬ」それが畿内を束ねる多穴牟遅の偽りのない心情だった。其処で、彼は賭けに出た。国を譲る条件として、祭事の存続を願い出たのである。「然も無くば、徹底抗戦、在るのみ」多穴牟遅は大和にそう告げて、弱者の恫喝を為したのである。そして、彼はその時、この願いが成就したあかつきには、自らが隠り身の神と成る事を大和に告げた。約束をもしも、違えたならば、祟りを為すぞ、と言う大和への婉曲的な圧力である。歩の悪い掛け、とも思われたのだが、多穴牟遅の一念は通じたらしい。大和は祭主の任免権譲渡を条件に、彼の提案を容れたのである。おそらく、その受け入れには、畿内住民懐柔の思惑も、作用した。いずれにしても、その時、多穴牟遅の目論見は成功した、かにも思われたのである。 (隠り身の神と成る ・ ・ 肉体から離脱した神、つまり、死んで神に成る、と言う事) だが、言代主に取って、任免権の譲渡は祭祀権の放棄と変わりはない。それは部族の長としての資格を失う事を意味するからであった。「祭主は自分で在らねば為らない、さもなくば、部族は求心力を失って、我が民はその全てが大和の民と成ってしまう」言代主はそう、考えたのである。おそらく、それは畿内の文化と一族の政治を司る者の当然の心情であったろう。大和が示した条件などは、如何にしても、承伏し兼ねたのに違いなかった。その故に、彼は勝算の無い戦いを大和に挑んだ。無論、多穴牟遅には、何の相談もして居ない。多穴牟遅の怒りは凄まじかった。このままでは、せっかくの自分の工作も水の泡とも、帰し兼ねない。彼は止む無く、大和の側に荷担して、言代主と刃を交えた。言代主など、古い国津の部族に取っては、元々が無謀な戦いである。彼等は次々と敗走して、無惨なまでに、打ち砕かれた。そして、言代主も、自殺した。美保の沖へと、船を漕ぎ出し、海の藻屑と消えたのだった。一方、多穴牟遅は大和の勝利を見届けた後、宣言した通りに死を選んで、隠り身の神と成るべく、此の世を去った。そして、大和は多穴牟遅命を出雲に祭り、言代主命を御大津姫命の美保神社へと、合祀したのである。彼等の最後の言の葉を恐れた故の行動だった。かくして、多穴牟遅の目論見通り、出雲の神々は生き残り、部族の証も、守られたのである。そして、まさに、その事が能登の住民に、多穴牟遅への敬愛を、長く保たせた理由であったのである。 だが、其処に気付いた宮城は此処で、能登に於ける部族派には、その住民だけでは無く、言代主の一族も加わったのでは無いのか、と疑った。いや、もしかすると、部族派の中心は言代主の一族であったのかも知れ無い。大和に敗れた彼等の一部は北に逃れた筈だった。能登に潜んで、再興の時を窺っていたとしても、それは決して、不思議では無い。ならば、彼等はこの地に於いて、言代主命を祭っただろう。大和を滅ぼして、故郷を奪回せしめる救い主の神として、である。そして、言代主が祭るべき入り江の神、御大津姫命は羽咋の置かれた地形から見て、やはり祭られていた、と考えられる。もしかすると、気多神社の本来の祭神は御大津姫命であったのかも知れないのである。本部が羽咋に置かれた事と、その事に関わる大きな秘密は其処にあるのに違い無かった。 その二 奇妙な神殿 さて、その翌日、本部に忍び込んだ宮城は重大な発見をして、ホテルに戻った。盗み見た資料から推測すると、神殿はその殆どが仕上がって居る様に思われる。だが、奇妙な事に、その建設現場は市街地では無く、何と、碁石が峰の山中だった。殆どの建設資材はヘリコプターを使って、運んだらしい。「だが、何故、その様な不便な所に、神殿を建てる必要があったのか?」宮城は急ぎ、登山具を整えると、借りた車へと、飛び乗った。碁石が峰への山道は市街地から、かなり離れた御子原に在る。時計を見ると、午後の九時。明日の日の出は五時頃だろう。神殿の調査に使える時間は多分、二時間か、三時間である。急がねばならない。宮城は目一杯に、車を飛ばした。 車が神子原に差し掛かると、宮城は道路脇の標識に碁石が峰への矢印を見て、速度を緩めた。ふと見ると、少し、前方の林の影に碁石が峰への山道がある。宮城は適当な場所に車を止めて、登山具を背負って、歩き始めた。だが、道を歩くのは危険に思える。祈言宗の手の者が何処に潜んで居るか、分からない。彼は山道を避けると、林の中へと、分け入った。幸いにも、月の明かりが木々を縫って、山の斜面を浮き出させている。宮城は足元に注意しながら、ただ、黙々と、登り続けた。だが、斜面は凹凸が極めて、きつい。朽ちた小枝や灌木がしばしば、足に絡み付く。山の起伏や倒れた樹木が度々、行く手を遮った。宮城はしばしば、足を止めて、磁石を頼りに、迂回した。だが、時間が気に成る。時々は、急勾配をがむしゃらに、這う様にして、登って行った。吹き付ける風が肌を刺す。春とは言え、やはり、夜の山は冷えるのだった。斜面の窪んだ辺りには、解け残った雪も、まだ在って、青白く、月の光を反射している。樹木の影が幾筋も、その青白いカンバスを横切って、美しい縞模様を演出していた。妙に神秘的な気分にも、させらる。宮城はふと、足を止めると、その光景を眺め見た。気の所為か、疲れがスーッと、抜けて行く。宮城は其処で、数分、休憩すると、再び、傾斜を上り始めた。 さて、それから、一時間ほども、歩いたろうか?森がやにわに開けると、視界が一気に広がった。前方には、満天の星が輝いている。遥か彼方に目を遣ると、連なる山々の稜線が月の明かりを反射して、微かに、白っぽく、浮かんで見えた。ふと、左右に目を振ると、絶壁の断崖が馬蹄形に谷をえぐる様に、落ち込んでいる。彼は今、その馬蹄形の頂点の辺りにいるらしい。ルートに間違いが無いならば、此処が目標の山腹である。宮城は其処に立ったまま、足下の谷に視線を送った。だが、谷底は見えない。相当に深いようである。宮城は少し、歩を進めると、身体を乗り出して、下を覗いた。 と、無数の灯りが小さく見える。どうやら、それは篝火らしい。そして、其処に照らされたのは無数の蠢く人影だった。祈言宗の信徒に違いない。見付かっては不味い。宮城は慌てて、身体を引いた。咄嗟の事であったので、まだ、神殿の確認は出来ては居ない。宮城は地面に腹這いと成ると、体を少し、前にずらして、今度は慎重に、覗き見た。下までは、三十メートルほども、在るのだろうか?その深みには、神社風の建物がその屋根半分を覗かせて居る。手前の方は、岩が邪魔をして、見えては居ない。宮城はふと、腕の時計に目を遣った。すると、針は既に、午後の二時を指している。普通なら、生き物の寝静まる時刻であった。「今頃、何をしているのだろう?儀式だろうか?」宮城は人の動きに注意を払った。すると、彼らは幾筋かの列を為しながら、二人、一組と成って、畚の様な物を担いで居る。 だが、その動作は何故か、緩慢で、異様な雰囲気を漂わせている。赤々と燃える篝火の脇には、棒状の物を携えた別の人影も、確認出来る。監視役なのに違いない。宮城は更に、彼等の様子を窺った。それにしても、畚を担いでいる連中は何と、奇怪な姿だろうか?黒っぽい頭巾様の布で、顔まで覆って、のろのろと、俯き加減に行進している。「これでは、まるで、亡霊の行進だ」宮城は唸る様に、呟いた。神殿の周辺には、異様な妖気も漂っている。一瞬、宮城の脳裏を、悪徳の羽虫が過ぎって行った。それにしても、畚の中身が気に掛かる。宮城は畚を凝視した。だが、それは一瞬、篝火を反射して、赤く染まるだけである。何かの不定型な固まりである事は分かったものの、それ以上の事は分からない。宮城は一旦、顔を引っ込めると、その場に伏したまま、考え込んだ。普通であれば、あれは土砂の類と思われるが、祈言宗の遣る事であるから、そうは、即断も出来兼ねる。宮城はあれこれと想像を巡らしながら、再び、亡者の列に注意を向けた。 頭巾を被った亡者達は神殿から、次々と湧き出して、鳥居の方へと行進している。狭くて、急な石段をただ、黙々と、下り降りると、森の闇へと吸い込まれていた。そして、同じ闇からは、同様の列がゆらゆらと、幽霊の様に戻って来る。歩みは幾分、軽いので、畚の中は空らしい。何処かへ捨ててでも、来たのだろうか?あるいは、何処かへ運んで居るのか?いずれにしても、用意周到な様子からして、今日だけの作業とも思えない。と、すれば、かなりの量が運ばれている事は間違いがない。「やはり土砂かな?地下室だろうか?」だが、見回したところ、建設資材など、見当たらず、神殿も外観は完成している。地下室を後で、造るなど、普通であれば、考えられない。そして、夜更けにする作業とも思えない。いずれにしても、今、魔性に満ちた神殿の奥では、怪しげな何事かが、進行していた。 「「だが、それは果たして、何なのか?」警備はかなり、厳重そうだが、探る為には、降りねば為らない。登山具の用意はして来たので、降りる事は可能なのだが、実際に使った事など、殆ど無い。若干の不安が脳裏を過ぎった。だが、此処まで来ては、致し方ない。宮城は再び、崖の斜面に目を遣った。改めて見ると、恐ろしいほどの傾斜である。その高さも、生半可ではない。此処を降りるのか、と思うと、足がすくむ。そして、問題は他にもあった。今、降りよう、とする神殿の裏手は張り出した岩場が邪魔をして、様子が全く、分からない。おそらく、其処は、神殿と崖とに挟まれた相当に狭い空間なのである。闇雲に降りて、見付かったなら、逃げ道などは無いだろう。「どうしようか?」宮城は少し、思案した。だが、此処での時間は限られている。「差し当たり、あの岩場まで、行ってみよう!」宮城はそう、決断すると、足下の岩に、素早く、ザイルを固定した。いよいよ、崖を降りねばならない。彼は一回、大きく、息を吸い込んで、呼吸を整えると、注意深く、崖を下り始めた。 だが、案ずるより、産むが易し、である。落石を起こす事もなく、彼は意外とスムーズに、張り出した岩場に取り付いた。そして、すぐに、其処に腹這いと成ると、首を伸ばして、下を覗いた。と、神殿の全容がはっきり見える。だが、その有様は全く、奇怪なものだった。神殿は崖に密着しており、その屋根がコンクリートで固められた岩の肌へとめり込んでいる。「ん?どういう事だ?」宮城は思わず、首を捻った。だが、その所為で、其処は下からの死角でもある。「案外、巧く、行くかも知れん」宮城はザイルをそろっと、下に延ばすと、岩盤を支えるコンクリートの壁を滑る様に素早く、下って、雑作もなく、屋根に降り立った。 が、何故だろう?屋根が異様に振動している。宮城は一瞬、動転して、屋根の上に這い蹲った。そして、辺りを窺った。だが、その振動以外、妙な気配は窺えない。差し当たり、彼は屋根に耳をあてがった。すると、確かに、断続的な振動が間断無しに、伝わって来る。だが、音源はどうやら、神殿では無く、崖の様に思えるのである。宮城は少し、首を捻った。そして、再び、屋根に耳を押し当てた。すると、やはり、音は崖の方向から伝わってくる。そして、それは機械の発する音らしい。何処かで、聞いた音でもあった。「だが、何の音だったか?」宮城はコンクリートで固められた岩盤にへばり付くと、再び、耳を押し当てた。と、音は前より、いっそう、はっきり、聞こえる。それはやはり、機械的な振動音であった。状況から判断すると、おそらく、それは削岩機だろう。トンネルでも、掘っているのだろうか?いずれにしても、亡霊達の畚の中身は排出土なのに違い無かった。だが、その目的は果たして、何か?解いたばかりのひとつの謎が、新たな謎を産み出していた。 |
|||||||
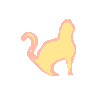
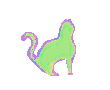

| |||||||
| Cotosiro Home | |||||||