|
可能世界・陰の神話 第九章第四話 |
伯母の場合 This was revised in March 3, 2012. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
宮城が碁石が峰で、例の神殿を探っていた頃、影浦と、押知らは一睡も出来ずに、宮城からの一報を、待っていた。実を言えば、宮城が碁石が峰に向かう直前、電話をして来た。彼の話によると、祈言宗なる教団の支部が亀戸にあり、その教団は祟り神と化した御大津姫と言代主を信奉する邪教集団であるらしいのである。だが、その実態に付いては、まだ、殆ど、分かって居ないらしい。にも関わらず、宮城は、「本部が羽咋にあるので、潜入を試みる」と、言うのである。影浦はその時、「ちょっと、無謀ではないのか?」と、宮城に自重を促した。だが、宮城は、「祈言宗は今、恐ろしい何事かをしようとしている、すぐに、潜入しなければ為らない」と、語気を強めて、言うのである。宮城の決心は固そうなので、影浦も、了承せざるを得なかったのである。 宮城の事であるから、大丈夫であろう、とは思うけれども、宮城が今、どの様な状況にあるのか?皆目、見当が付か無いだけに、不安ばかりが募るのである。いきおい、誰もが寡黙と成って、重苦しい空気が漂い始めた。 この様な雰囲気は好ましくない。影浦は気まずい雰囲気を何とかしようと、「けど、祈言宗って、どんな、教団なのかな?」と、独り言の様に、呟いた。だが、押知も、逆崎も、反応しない。彼らも、やはり、知らないのである。会話の切っ掛けにでも、と思ったのだが、どうやら、それも、空振りらしい。影浦は卓袱台のタバコに、右手を伸ばした。と、京子が、何かを言いたげに、影浦を見る。影浦は、「ん?どうしました?」と、問い掛けた。と、彼女は、「あの、私、気言宗の事を知っています、恐山の近くに、東北支部が在ります」と、言う。影浦も、驚いたが、押知も、坂崎も、初耳らしく、「何故、今まで、黙っていたのか?」と、いう顔付きで、京子を見詰めた。だが、京子には、ある事情の為に、その事を隠したい、という心理があったのである。彼女はその様な自分の心境を少し、述べると、祈言宗について、語り始めた。 京子によれば、彼女の伯父、野辺地泰造は祈言宗の熱烈な信者であった。彼女の家にも、何回か、入信を勧めに遣って来て、霊験などを語ったのである。泰造は祈言の神が信者の祈りを実現させる救世主としての神である、と盲信していた。彼は、「祈言の神への信仰が、祈りの言葉を実現させる・・これは信ずる者のみに許される、因果を越える力なのだ」と、言うのである。だが、京子も、彼女の両親も、まともに聞いては居なかった。いかにも、怪しげなその話に、危険な臭いすら、感じたのである。そして、その様な彼等の予感は見事なまでに、的中した。平穏であった泰造の家庭はまるで、悪霊にでも、魅入られたかの様に、崩壊の一途を辿ったのである。特に、その妻、清美には、過酷な運命を強いたのだった。 清美によれば、泰造が神に祈る時、その青白い顔を紅潮させて、恍惚とすら、して居たらしい。他には、別段、妙な所は無かったけれども、自分に注がれる夫の視線が何故か、妙に、薄気味悪く、鳥肌の立つ想いに、捕らわれる。「夫が怖い」彼女はしばしば、その様な気分に陥った。だが、そう感じる理由は、はっきりしない。夫の性格が変わった訳でも無いし、粗暴な振る舞いをする事も無い。ただ、夫の何かが変わった、と言う微妙な感覚があるだけなのである。「気の迷いね?きっと」彼女は妙な感覚に陥る度に、自分の想像を否定した。そして、無視する様に、努めたのである。 当時の清美はしばしば、酷い眩暈に悩まされていた。その所為か、些細な失敗にも、気分が滅入る。彼女自身、自分の神経を疑っていた。「考えぬ方が良いのだわ、気にせぬ様にしなければ」彼女は妙な感覚に陥る度に、その様に、自分に言い聞かせたのである。だが、心は納得など、していない。彼女の願いとは、裏腹に、夫への疑念は治まるどころか、日を追う毎に、深まるのである。ふとした、拍子に、「妙な、目眩は、あの人の仕業に違い無い」と、思ってしまう。時として、「夫は自分を殺そうとして居る・・」と言う想像にすら、捕らわれるのである。 だが、実際は、その様な証拠など、何処にも、無かった。「疑う自分が情けない」疑念が清美を苛む度に、彼女はそう、自分を責めた。「頭がどうにか、成ったのだろうか?何故、眩暈ばかり、するのだろう?」事在る毎に、考え込むが、何時かしら、夫への疑念へと、戻るのである。考えあぐねた彼女は神経科の病院や、精神分析医の所にも、足を運んだ。だが、相手がいくら、医者とは言っても、昔気質の彼女としては、全てを語る事は躊躇をされる。夫の異常、あるいは、自分の異常を、他人に知られるのは、恥ずかしかった。彼女は助けを求めながらも、ついに、真実を話す事は出来なかったのである。精神分析医に取って、これほど、やっかいな患者はいないだろう。結局、彼女は有効な治療も、そして、助言すら、受けられず、あっさりと、病院通いを止めたのである。彼女にとっては、家の面子が大事であった。 「やはり、夫の信心だろうか?それとも、自分の妄想なのか?」彼女はひとり、根拠の薄弱な想像で、ただ、ただ、鬱々と、考え続けた。だが、悪い想像など、想いたく無い。「やはり、私の妄想なのだわ」彼女は妙な疑念に捕らわれる度に、その様に、自分に言い聞かせた。そして、疑念の嵐を堪えたのである。そうすれば、何時かは、それも、過ぎ去って行く。そんな期待が清美を支えた。 だが、彼女の願いとは、裏腹に、症状は益々、悪化して行く。目眩はもとより、妙な頭痛すら、しばしば、襲う。ほんの微かな物音が、針の様に、頭脳を突き刺す。記憶力も、めっきりと、悪く成った。状態が悪い時には、些細な思考すら、まま為らない。家事にも、支障が出始めた。「このままでは、本当に、狂って仕舞う!」清美はそんな不安にも、怯え始めた。そして、何故だろう?怪しげな夫の背後には、魔物の影すら、感じ取られる。彼女の苦しみを何処かで、見つめて、ほくそ笑む様に思われた。「いや、夫、自身がその魔物なのかも知れ無い!」在らぬ想像とは、思ったけれども、打ち消す勇気など、もはや、無かった。「何とか、しないと、もう持たない、やはり、夫を探らなくては」彼女はそう、心を決めた。 その日、清美は泰造と、二人っきりの食事を取った。子供等は夏の休みで、実家のある田舎の方へと、遣っている。以前の清美であるならば、甘え声の一つくらいは、発していても、妙では無かった。だが、今の二人は俯き加減に、無言で、ご飯を掻き込んでいる。心なし、蛍光灯の光も、弱く、部屋の全体がくすんで、見える。そして、例の頭痛が始まった。「ああ、まただわ!」清美は思わず、頭を抱えて、夫の顔を盗み見た。 だが、目は奇妙に、霞んでいて、夫の顔がぼやけて見える。「気分が悪いわ」清美は夫に、そう告げて、傍らのソファーに、座り直すと、ゆっくりと、身体を横たえた。「大丈夫か?」と、夫が振り向く。清美は無言で、頷いて、「大丈夫」と、合図を送った。しかし、清美はその直後、夫の舌打ちを聞いている。夫の心配そうな問い掛けも、清美の返事も、心に全く、響かない、上辺だけの遣り取りである。果たして、この状態はいつ頃からであったろう?清美はふと、仲むつまじい、昔の事を想起した。だが、それは遠い過去に垣間見た夢、幻の様に思われる。清美はすぐに、その回想を止めてしまった。 清美はしばらくの間、目を瞑って、忌まわしい頭痛と眩暈とを堪え続けた。すると、幾分かは、治まって来る。夫の様子が気に成って、薄目で、そろっと、窺った。見ると、夫は食事をしながら、何時もの様に、テレビを見ている。清美はその後ろ姿を複雑な想いで、眺め見た。が、妙である。夫は清美が見ているのを、知ってか、知らずか、微妙に、体をねじって、食事をしている。清美に対して、意図的に、顔を背けている様にも、見えるのである。「きっと、私が苦しんでいるのを見て、ほくそ笑んでいるのだ」清美は咄嗟に、そう、思った。 だが、自分の感覚に、自信は無い。「錯覚かしら?そうよ、きっと、錯覚だわ」と、思ってしまう。そこには、自分の想像を否定したい幸せだった当時の清美がいた。だが、その清美はすぐに居なくなる。清美と泰造の位置を考慮するなら、後頭部しか、見えない、と言うのは、やはり、不自然なのである。夫の不自然な姿勢には、何らかの意図があるのに違いないのだ。清美はそう、考え直すと、僅かに、身体を起こして、壁に掛けられている大鏡へと、視線を向けた。鏡は丁度、夫の斜め後方にある。夫は振り向かなければ、鏡を見る事は出来ない。だが、清美からは、首を伸ばすと、夫の横顔が辛うじて、見えるのである。が、彼女が其処に見たものは、夫の不可解な笑いであった。テレビは何の変哲もないニュースなのだが、時折、眼が上目と成って、陰湿な笑みを漏らすのである。深い皺がその都度、顔に刻まれて、不気味に、ヒクヒク、と蠢いていた。 「これが夫の顔であろうか!」清美は思わず、目を背けると、ソファーの縁へと、視線を落とした。「夫はやはり、普通ではない」清美は自分に、そう言った。絶望感と寂しさが真綿の様に、締め付ける。「見なければ良かった」清美は一瞬、後悔の念にも、捕らわれた。だが、今更、後戻りなど、し様が無い。清美は自分を叱咤して、再び、夫に視線を向けた。泰造は晩酌の杯を傾けながら、まだ、ニタニタと、陰湿な笑いをし続けている。充血した眼が、宙をふらふらと、彷徨って、犬歯を剥き出しにした唇が妙に、濡れて、光って、見える。「何と、おぞましい!」清美は凍て付く様な恐怖を覚えて、一瞬、意識が遠退いた。 だが、見ねば為らない。そして、聞かねば為らなかった。清美は勇気を振り絞って、体を起こすと、「あなた、何がおかしいの?」と、問い掛けた。と、泰造の身体がピクリ、と動く。そして、顔を慌てて、背けた。それは確かに、やましい心の証明である。「ねえ、どうしたの?何がおかしいのよ!」清美は泰造の顔を覗き込むと、かさにかかって、責め立てた。 が、何故だろう?今し方の忌まわしい顔付きが、幻の様に消えている。何時もの泰造が其処にいた。泰造は、「エッ?どうしたんだ、薮から棒に、大丈夫か?」と、怪訝な顔付きで、清美を見つめる。今までの事は錯覚なのか?一瞬、清美に、迷いが生じた。彼女はまたしても、何時もの様に、自分の感覚を疑ったのである。そして、再び、夫を見詰めた。夫がしげしげと、清美を見返す。清美は酷く、狼狽して、纏まりも付かぬまま、夫に言った。「あ、私、ちょっと変、少し、寝てみる、九時に起こして?」そして、彼女は居間から、寝室へと、足を運んだ。 だが、眠るつもりなど、元より無い。化粧台の前に、腰を掛けると、じっと、自分を見つめ続けた。最前の忌まわしい情景が、脳裏に焼き付いていて、離れない。「イエ、確かに、何か、企んでるのよ、今のを見たでしょ、あの顔を!」錯覚かも知れぬ、と言う自分の心を、清美はそう、叱咤した。思い返すと、激しい頭痛や眩暈の時には、必ず、夫の視線が在った。見ては居ないが、確かに感じた。酷く陰湿で、おぞましい、鳥肌の立つ様な感覚である。酷い目眩や激しい頭痛はやはり、泰造の企みなのだ。清美はそう、確信した。 清美が目眩に見舞われるのは、必ずと言って良い程に、二人っきりの時である。泰造は自分の行為を知られぬように、その様にして居たのに違い無い。「ジワジワと私を痛めては、ほくそ笑んで居たのだ」清美は悪寒が全身を駆け抜けるのを感じながら、鏡に居る自分に、そう言った。だが、夫をその様にさせたものは、果たして、何か?自分の落ち度とは思えぬし、仕事のストレスとも、思えない。「やはり、祈言宗の所為だわ、邪教なのよ、あれは!」だが、それは、同時に、自分の感じる夫の殺意が妄想では無い可能性を大きくしている。考えたくはないが、やはり、考えざるを得ない。 「あのめまいや、頭痛は、やはり、あの人の仕業に違いない、なら、毒だろうか?でも、どう遣って?」清美は薬の類など、全く、使っていなかった。食事も、彼女が料理している。膳を出すのも、清美である。何かを混ぜ入れる機会など、在り得るだろうか?だとしたら、やはり、妄想なのか?清美はまたしても、迷ってしまった。だが、それから、十日ほど、後、その謎はあっさりと、解き明かされる。それは実に、簡単なトリックだった。 その日、彼女は午前中、買い物があって、外出していた。だが、その途上、湿った風が吹き始めると、分厚い雨雲が垂れ込め始める。自宅の庭には、下着などの洗濯物が干しっ放しと成っていた。泰造は仕事が休みで、家に、ゴロゴロとして居るが、取り込む事など、考えないだろう。彼女は急いで、買い物を終えると、予定を切り上げて、家へと戻った。玄関脇から、庭を覗くと、案の定、洗濯物はそのままである。折からの寒風に煽られて、冷え切った身体を棚引かせていた。早く取り込まねば為らないけれども、買い物袋が邪魔である。彼女はそのまま、庭へとまわって、ベランダの脇に、荷物を置いた。 と、窓越しに、泰造の姿が垣間見られる。何故か、うろうろとして、落ち着きが無い。「変だわ?」清美は夫を窺った。と、何故だろう?近付かぬ筈のキッチンへ、そわそわと向かう泰造が居る。清美は夫に気付かれぬよう、庭伝いに夫を追った。そして、窓の隅から、そっと、覗いた。見ると、泰造は何かの小瓶を携えている。位置は調理用のガスレンジの前である。泰造は其処で、陰湿な笑みを漏らしつつ、左手に握られた小瓶のキヤップを慎重な仕草で、開けていた。そして、小瓶が少し、傾けられると、何かの液体が、一、二滴、レンジの上へと滴り落ちた。「薬物なのに違い無い!」清美はそう、直感した。おそらくは、低揮発性の毒物である。調理の熱が加わると、一気に蒸気へと、変わるのだろう。ひどい眩暈や激しい頭痛は、その所為なのに違い無かった。 京子がこの話を聞かされたのは、丁度、その頃、三年ほど、前の春先だった。だが、学生だった京子には、清美の言葉が理解出来ない。京子の知る泰造は極めて、穏和で、おとなしく、近所の人にも、親切で、悪判なども、殆ど、聞かない。「伯母の思い過ごしでは無いのか?」彼女はそう、考えていた。そして、清美にも、そう言った。だが、そんな時、清美は決まって、こう言った。「誤解じゃ無いわよ!祈言宗の所為なの、別れる事に成るかも知れ無い」 だが、京子は想った。「伯母の愛情が無く成ったのだ、それが妄想の原因だろう」京子は時折り、冗談めかして、「いっそ、警察にでも、相談してみたら?」と、心ない暴言まで、吐いたのだった。今にして思えば、残酷な事を言ったものだが、当時の京子には、その様な悪意など、無かったのである。 すると、伯母はそんな時、寂しげな笑みを僅かに、浮かべて、判で押した様に、こう言った。「だって、身内の恥は晒せ無いでしょ?子供達だって、肩身が狭いし、将来の事だって、在るんだし」当時の京子には、それほど、理解は出来なかったが、今、考えると、昔気質の清美であるから、そう考えるしか、無かったのである。彼女は子供や家の為に、じっと、忍ぶ人だった。人伝に聞いた話では、伯母は離婚も出来ぬ侭、癌に冒されて、死んでいる。だが、それはただの病では無く、陰湿なる計画に基づいた、殺人であったのに違い無かった。 影浦達は黙って、話を聞いていた。京子の心を思う時、口を差し挟む事は躊躇をされる。ふと、見ると、京子の頬が濡れていた。「もう少し、親身に成って上げれば、あんな事には、成ら無かったのに!」京子は咳き込む様に、述べ立てた。坂崎が言った。「でも、それは、どうしようも無い事だよ、知ら無い事が幸いしたのかも知れ無いし」すると、押知が頷く様に、京子を見つめた。思えば、京子の陥った怪しい地獄も、その事と無縁では無いのかも知れない。泰造の、いや、祈言宗の健やかなる者への妬みの念が、京子の魔物を呼んだのかも知れない。 恐ろしきは祈言宗の想念であり、我々、人間の嫉妬の炎と、拭い難き怨念だった。それは理性を奪い取り、人を害して、顧み無い。いや、正当化すらして、はばから無かった。此の世に人間の在る限り、この苦しみは続くのだろうか?影浦はそう、問わずには居られ無かった。そして、もうひとつ、心配なのは、犠牲者達の魂である。人知れず嘗めた苦しみを、ひとり、胸に抱いて、死んで行く。これ程の悔しい死に様が果たして、他に在るのだろうか?恨みを残さずに、死ねるだろうか?だが、今は、その事は語れ無い。立ち直ったばかりの京子には、酷な問いとも、成り兼ね無かった。 |
|||||||
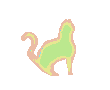


| |||||||
| Cotosiro Home | |||||||