|
第三章 第一話 忍び寄る憎悪 |
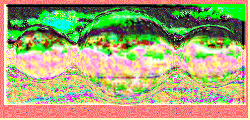
|
||||||
|
山際に広がる農村に山岸昇、と言う男が居る。一応は農業の経営者である。 だが、彼が畑に出る事は皆無、と言っても過言では無く、畑にはあらゆる雑草が蔓延って、荒れるが侭に任されていた。 彼は今、自宅の縁側に横に成り、惚けたように昼寝をしている。そして、それは今日に限った事でも無かった。 別段、病弱な訳では無く、むしろ頑健な方であるから、ものぐさである、としか言いようがない。 彼の心理は分からぬが、少なくとも、この村の住人達は彼をその様に理解していた。 実を言えば、彼はかなり以前に職を失い、実家のあるこの村に舞い戻っていた。 だが、農作業などに興味はない。かと言って、趣味に興ずる訳でも無く、ただ家に居て、日がな一日、ぶらぶらしていた。 両親はその心労からであるであろうか? 相次いで病に倒れ、帰らぬ人と成って仕舞った。 兄弟も無く、頼れる人間など皆無と成ったが、それでも彼は変わらない。いや、以前にも増し、怠惰な日々を過ごしたのである。 だが、幸いであった、と言うべきだろうか? 彼には親の残した僅かばかりの畑が在る。 彼はそれを切り売って、辛うじて食い繋いでいた。だが、悪びれた様子など窺えず、傍目には極めて脳天気な生活である。 食べたい時に食事をし、眠りたい時にはすぐに寝る。立ち働いている姿など見掛ける事など殆ど無かった。 たまに見掛ける山岸と言えば、あぜ道をもの凄い形相で駆け回る異様な姿だけである。村人達は彼を変人として扱った。 そして、嘲笑の標的でもある。彼が畑に出て草でも取ると、雨が降るぞ、と笑って囃した。 分からぬ物には不安感が湧くものだった。攻撃心も湧いて来る。だが、心優しい村人としては、余り酷い行為にも出られぬのである。 村人の虐めとも思えるからかいは、その代償行為、とも言えそうだった。 | |||||||
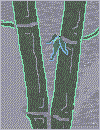
|
だが、昇の性格はいたって穏和で、その点は村人も安心していた。いや、昇という奇妙な男の存在は平和な村の暮らしに取って、 一種の刺激剤とも成ったのである。在らぬ噂を互いに語り、自らの隠微な欲望を気付かぬ侭に投影し、そして、彼に被せたのである。 昇の内面への理解など、試みる者すら殆ど無かった。 彼等は何時の頃からか、昇の事を神憑りの昇とあだ名した。「奴はあれで幸せなんだ、余計な世話など焼く事は無い」 村人達はそう思う事で、辛うじて彼を受け入れていた。 だが、彼等は山岸の夜を全く知ら無い。山岸昇の心には、様々な欲望と葛藤が濁流と成って渦巻いていた。 |
||||||
|
昇は人間というものが好きでは無かった。仕事を辞めたのも其処に行き着く。性格的なものなのだろうか?
人の身勝手や、陰湿で残酷な振る舞いを敏感に感じて仕舞うのである。人とは関わりなど持ちたく無かった。 だが、彼も人の子には違い無い。人並みの欲望は持ち併せている。 そんな心の有り様が退屈で長い孤独な夜を過酷な時間ともさせるのだった。 人と関らなければ仕事は出来ない。 生活をする金も稼げ無い。孤独で貧しい生活に甘んずるしか仕方が無かった。 だが、欲望は彼を逃すまい、と、あらゆる機会に頭を擡げる。 特に夜が更け、辺りに静けさが漂うと、言い知れぬ寂しさが突き上げて、彼を追い詰め、苛んだのである。 昇はふと顔に冷たいものを感じ、目を開けた。何時から降って居たのだろうか? 青空も見えるので通り雨らしいが、見る間に激しさを増して行く。「いやな雨だ ・ ・ 」彼は上目を使って、空を睨んだ。 既に日は西に傾き、山の稜線に沈みつつある。西の空を茜に染めて、雲間から幾筋もの光線を放射していた。 昇はのっそりとした動作で身体を起こし、胡座をかくと、その光景をジッ、と見つめた。 沈み掛ける太陽を見、一日の終わりを感じ取る時、何故か気分が落ち着くのである。 だが、今日の太陽は何時もと違った。雨に煙った所為であろうか? 腐った卵の黄身にも思える。 今にもドロッ、と溶け落ちそうで、陰湿な想いすら抱かせた。 と、何故だろう? 丁度、背中の辺りから、言い知れぬ憎悪が浸み出して来る。恨みの念、と言っても良かった。 身体にしつこくまとわり付いて、しきりと昇を責めたてる。 「チッ、けたくそ悪い!」彼は思わず身体を震わせ、振り解こうと少しもがいた。 しかし、怪しい恨みの念は陽炎のように揺らぎ出て来る。彼の周りをゆらゆらと、纏わり付いて離れ無かった。 その儘、ジッ、として居ると、飲み込まれそうで恐ろしい。昇はやにわに腰を上げると、その儘、縁側を飛び降りた。 裸足で居る事にも気付いて居ない。ランニングシャツとステテコの儘、狂ったように走り始めた。 と、畑仕事の帰りだろうか?数人の村人が振り向いた。すれ違いざま、「精が出るねえ」などと笑って囃す。 何時もなら会釈くらいはするのだが、今の昇にはゆとりなど無い。阿修羅の様な顔付きで彼はひたすら走り続けた。 | |||||||
|
「昇の奴、偉く張り切ってるな、挨拶も無しだぜ!」「聞こえないのよ!何たって、神憑りだから!」
嘲るような笑いと罵声が夕べの空へと響き渡った。
「冗談じゃねえや!こっちの身にも成ってみろ!」昇は罵声を聞きながら、前にも増して足を早めた。 その所為だろうか? しばらく走ると憎悪は失せた。 見上げると、沈んだ太陽の残光が白い雲間に反射している。穏やかないつもの夕暮れのひとこまだった。 「だが、あれは一体、何だったのか?気の迷いだな、きっと ・ ・ 」そして、一日が過ぎ、三日が過ぎた。 憎悪の念は形を潜めて、現れる兆しすら窺えぬ。「だから、言ったろう?疲れてたんだよ ・ ・ 」 それ以来、意識する事は無く成っていた。 |
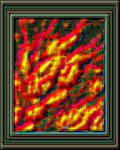
|
||||||
|
だが、それから数日後、雨が降った。時刻も夕時、あの時と同様の通り雨である。昇は不安を感じたが、すぐにそれを押し込めた。 いや、押し込めた、と錯覚をした。彼の願望の故である。 しかし、例の憎悪の念は彼の体内で膨張していた。やにわに背中の辺りから、怪しい何ものかを吹き出し始めた。 一瞬、抱いた僅かな不安が魔界と彼を繋いだらしい。恐ろしきイメージを昇に示した。 辺りには、地獄の業火が吹き出している。針の山でのたうつ亡者を鬼がむんずと掴み取り、その血を啜り、肉を食らった。 業火に焼かれる美しい女人が、身体をよじって苦しみもがく。昇は一瞬、その光景を恍惚として見るのであった。 「ああ、何という事を!気の迷いだ、走れば直る!」 昇は幻影を振り切るように家を飛び出し、走り始めた。すると、憎悪は消えて行く。 彼はその儘、家に戻ると、何も考えずに眠りに付いた。だが、それはほんの一時の、儚い安息に過ぎぬのである。 憎悪の念に衰えは無く、日を追う毎に力を増して、悪への衝動を揺り動かした。 時折は、しわがれた声までが囁き掛ける。「殺せ、殺せ、殺して仕舞えーっ!」頭の中から漏れ出して、邪なる欲望をそそるのだった。 「ああ、この儘では気が狂って仕舞う、本当に村人を襲うのかも知れ無い」昇はそんな恐怖にも怯え始めた。 だが、あの憎悪の念は一体、何処から来るのだろうか?「神経でも、おかしく成ったのだろうか? それとも悪霊にでも見込まれたのか? くっそ、どうすりゃあ良いんだ!」 あれこれと考えては見るものの、昇には何にも分から無かった。考えあぐね、途方にくれた。 |
|||||||


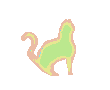
| |||||||
| Cotosiro | |||||||