|
第三章 第二話 |
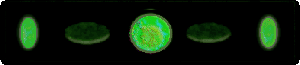
|
||||||
| 隠された魂 | |||||||
|
宮城が影浦を連れて帰京をしてから、既に三日が経過をして居る。だが、最初の会合以来、話し合いは中断し、 何の進展も為されて居ない。影浦の疲労が予想以上に厳しく、日を置く事にしたからである。 肉体的な疲労と言うより、精神的なもの、と思われる。突然、奇妙な世界に引き込まれ、「さあ、どうする」と、 言われたのであるから、混乱するのも当然であった。 だが、その日、影浦は午前中こそホテルで寝ていた、と言う話であったが、午後からは、あちらこちらと歩いたらしい。 ジッとしていると、気分が余計に滅入る、と言う。 宮城が彼からの電話を受けたのは丁度、午後の七時であった。 良い店があるので、飲みに行こう、と言う。宮城が返事をためらうと、「熊野さんとご一緒に、どうですか?」と、 追い打ちを掛ける様に、しきりと誘う。 「だが、疲労を助長させぬだろうか?」宮城は少し躊躇した。だが、ホテルで鬱々とするよりは酒の方がましかも知れない。 宮城は酒はあまり嗜まぬが、結局のところ、誘いを受けた。そして、熊野共々、看板まで飲み明かし、梯子して、 影浦をホテルに送る頃には空が白々と明け始めていた。 影浦の機嫌はすこぶる良いが、この調子では会合はまた延期だろう。「それにしても、これ程の大酒のみとは」 宮城は幾分、後悔していた。 だが、その別れ際、影浦が言った。「明日からまた、始めましょう!いや、こう見えても、わりとタフなんですよ?」 だが、話の様子から判断すると、それは明日では無く、どうやら今日のつもりらしい。 「本当に大丈夫なの?」宮城は幾分、不安に成った。だが、影浦は酔った勢いだろうか? 「熊野さんの教室で良いんですよね、一時までには伺いますから」 そんな風に勝手に決めると、心許なくふらふらとホテルの階段を登って行った。 | |||||||

|
宮城は今、熊野の控え室でその影浦を待っている。だが、熊野は此処には居なかった。
二時までは授業だ、と言う。彼は昨夜、その事をすっかりと失念して居た。時計を見ると、一時をもう十分も経過をしている。
「電話でも、して、聞いてみようか?」宮城はチラッ、と電話を眺めた。 だが、その数分後、ドアがコツコツ、と叩かれた。影浦である。見たところ、疲れた様子など窺え無い。 「なるほど、タフなんだ」宮城は妙に感心していた。 |
||||||
|
影浦は熊野が戻ると、待ち兼ねたように話を始めた。言代主が何故、祟り神として現れたのか? その謎が少しではあるが、 分かった、と言う。其処には、日本人の持つ精神の未だ知られざる構造が極めて深く関与していた。 縄文的な魂と弥生的な合理精神、その歴史的関係に醸し出された極めて根の深い構造である。 言代主が現れた今、影浦には、その軋轢が極限に達した様にも感じられたのである。そして、彼はその構造について語り始めた。 日本人の心の底には、縄文的な魂が存在している。日本人がその遺伝的基層として、縄文の血を持つ如く、その文化的、 精神的な側面をも受け継いだからに他ならなかった。 それが本来の日本の魂、つまり、縄文の魂である。 だが、その精神は何時しか、その表現を妨げられた。その発露は祭りなど特殊な状況でしか許されぬのである。 それは権力の忌む精神であり、我々日本人の各々が無意識とは言え、それを抑えたからだった。 そして、その抑圧の論理こそが弥生的合理主義的精神だった。 だが、それは文明の精神であり、権力と組織の精神である。個の精神とは馴染まない。 その故に、縄文の本来の魂は心の奥底へと 押し遣られ、其処に弥生的な精神が覆い被さる、我々日本人の精神はそんな二重構造を持つに至った。 また、その事が弥生の支配への恨みを産み出し、拭い難き怨念として個々人の心に巣くったのである。それが縄文の怨念だった。 影浦は言った。「この精神の構造は言代主が大和に破れて以来、我々の性と成りました、個を殺し、全体につくす、 自己疎外の習性と言っても良いのでしょうか? 基本的な問題はそこいら辺に在りそうです」 と、宮城が僅かに頷いた。そして、確認をするように問い掛けた。 「つまり、言代主の怨霊は我々の心が産み出した、いや、現象させた?」 「エエ、本当に怨霊が居るのなら、そう考えるしか在りません、彼はただの怨霊ではありません、 我々個々人の心に巣くう縄文の怨念、そのものなのです」 その昔、縄文人は弥生的文化を受け入れながら、その血も同様に受け入れて、あるいは、力によって押し付けられて、 倭人の血と文化とを形成して来た。縄文人に取って、その受け入れが必要であったからに他ならない。 そして、その先進性が輝いて見えた事も推測し得た。 |
|||||||
|
また、戦いに勝ち、権力を握る者はその殆どが弥生的な色合いの濃い勢力である。
弥生的精神を重く見て、縄文的精神を軽んずる、その様な性癖の増進は当然の事とは言えそうだった。
影浦は言った。「ですから、縄文的な精神は権力に取って、忌むべきものと成りました、それは弱き者の精神であり、 また、権力に反抗する精神でも在った訳です」 宮城が言った。「なるほど、それで権力は縄文文化の排斥に血道を上げた?」 「エエ、そして、個々人も権力におもね、取り入る為に、あるいは生き抜く為に、縄文の魂を押さえたのです」 |

|
||||||
|
各々の時代の支配者達は個の精神である縄文の魂を忌むべき精神として抑え続けた。 そして、縄文の魂は心の奥底に圧縮されて、熱を持ち、恐ろしい怨念として現れたのである。 それは現代の日本人の心にも受け継がれている。また、十数世紀に渡って燻り続けた怨霊としての言代主の恨みの念でもあるのであった。 祟り神、言代主の出現はまさにその事が原因している。この様な個々人の怨念が増大した故なのに違い無かった。 影浦が言った。「今の日本人は言って見れば抑圧した者と抑圧された者との混血です、そして、 抑圧者は大和に代表される弥生的精神であり、被抑圧者は言代主一族に代表される縄文的精神であった訳です」 実を言えば、この事は今、社会のあらゆる場所で現象している。個は効率の論理で絞り上げられ、個の論理は悉くが葬り去られる。 怨念の恐ろしいほどの増大も、当然の事とは言えそうだった。 そして、これらの事は日本人の魂が権力に関わるほど、抑圧される、という避け難い矛盾をも明示している。 弥生の精神への傾斜は即、魂への抑圧でもあるからだった。「それは自身の魂と言えども例外とは成らないのです」 影浦はそう言葉を括った。 宮城が言った。「なるほど、その怨念は自らの権力志向を呪うのかも知れ無い、自らを滅ぼそうとするのかも知れ無い、と?」 「エエ、そうです、でも、それは物理的に権力に近いとか、言う問題では無く、心理的なものでしょう、 あの怨霊はその様な日本の現状が呼び込んだんです」 影浦の言葉には力があった。確信があるのに違いない。 宮城は無言で頷くと、話の続きを促した。 | |||||||
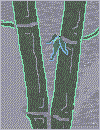
|
影浦が言った。「ですから、言代主の怨念はその様な抑圧者に向けられている、つまり、倭人の権力機構と、
それを支える人間達に向けられて居る、彼は縄文の魂を解放したい、のかも知れません」
と、熊野が傍らでぼそっ、と問うた。「あの、弥生的支配の体制、なんですが?」 「あ、自分勝手な造語ですからね、説明が要りますね」影浦は皆まで聞かずに頭を掻いた。 熊野が言った。「イエ、大体は分かります、縄文的な魂を抑圧する事によって、権力の求心力を高めよう、とする支配の体制、 そう考えて良いのでしょうか?」 「エエ、その主体が弥生文化の担い手だった、いや、弥生文明、と言った方が良いでしょうか」 | ||||||
|
大和の出現以前、各部族は各々の神々を戴きながら、互いの神々を尊んだ。その意味で、彼等の魂は自由で在り得た。 だが、それは同時に権力の求心力が希薄な事を意味して居り、弥生の文明とは馴染ま無かった。 弥生の文明に限らず、文明、と名の付くものは必ず、効率を追求し、その故に権力強化を要請して行く。 そして、その事は古代に於いて、神々を抜きにしては語れ無かった。 文明は個々の神々を統一し、あるいは序列化をして、 個の縁と成るべき神々を権力を支える神々へと変質させる。また、その事が文明を高度に育て上げ、更なる権力集中へと向かうのだった。 奇しくも、それは記紀の神話の筋立てに、はっきりとした形で描かれている。 縄文の神々は抑圧されて、個々人は文明の器官へと組み入れられて、個のアイデンティティーすら無くすのだった。 その図式は今に到るまで変わって居ない。祟り神、言代主の出現も其処に関わるのに違い無かった。 と、宮城が言った。「でも、妙ですね、我々が祟り神の敵であるなら、弥生の支配に荷担する事にも成り兼ねません、 いや、そんな筈は在りませんがね?」 だが、影浦は一瞬、絶句した。祟り神の怨念は確かに弥生的支配に向けられて居り、滅ぼそう、として居る事も間違いは無い。 そして、弥生の体制が崩壊すれば縄文の魂は解放される。怨霊に対決をする事はその解放を阻害する事に成るのだろうか? 影浦は妙な矛盾に陥った。 と、熊野が言った。「でも、相手はあくまでも怨霊です、余り難しく考えるのも問題ですよ、全てが滅ぼされたなら、 解放どころでは在りませんから」「あ、そうだよな」影浦は思わず赤面して居た。 言代主への妙な想い入れがそんな具合にさせたのだろうか? あるいは、推理に酔いしれた論理的暴走の結果だろうか? 単純な真実すら曇らせる思考という物の危うさだった。 影浦はつい、知らぬ間に、そんな罠に填ったのである。言代主の怨念は当時の大和政権、また、それを支える生身の人間に 向けられている。 | |||||||
|
だが、その弥生の支配の体勢は魂の抑圧という基本的な部分で、現代の支配と同一だった。
縄文の魂は抑圧をされ、個々人は弥生の支配に奉仕する、その様な存在として生かされている。 そして、今、抑圧者と抑圧される者の血は混じり合い、弥生の支配に奉仕していた。 つまり、全ての日本人が言代主の標的なのである。例外などは在り得なかった。 熊野が言った。「言代主が怨霊では無いなら、彼は解放者なのかも知れません、しかし、現実はそうじゃ無い、これからは、 弥生的な支配とあの恐ろしき怨念と本来の縄文の魂の、三つ巴の戦いと成るのでしょう」 |
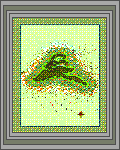
| ||||||


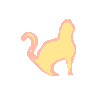
| |||||||
| Cotosiro | |||||||