|
第七章 第一話 大いなる想念 |

|
||||||
|
宮城は此処、数ヶ月、影浦を道場に住まわせて、禅の指導を行っている。「自己破壊の悲劇くらいは免れる様にせねば為らない」 それが宮城の目標であり、ささやかな期待でもあったのである。 だが、此処に来てその様子が随分と違って来ている。影浦の発する想念が何故かやにわに膨張し、思わぬ広がりを見せたのである。 ちなみに此処に言う想念とは認識対象と彼との関係に於ける整合性のあるイメージを指し、 彼の主観的な世界を規定する基本的なイメージである。 従って、その様な想念の拡大は本来、歓迎をすべき兆候ではある。だが、影浦の場合、その変化は余りにも急であった。 この様なケースは往々にして、悪霊などが絡むので、手放しで喜ぶ訳にも行かぬのである。宮城は警戒を怠らなかった。 だが、この二ヶ月間、悪しき霊波などは現れず、何の問題も起こって居ない。当初の疑念は杞憂の様にも思われた。 ならば、彼の変貌は一体、何に拠るのであろうか? 半年にも満たぬ修行であるから、影浦自身の力とは到底、思えぬ。 と成ると、其処から導かれる結論はただのひとつしか在り得なかった。 宮城が以前、そうであった様に影浦の変貌も、その何者かの仕業であるのかも知れない。そう考えると、納得が行く様にも思われた。 だが、奇妙な気分はなおかつ残る。「どうも分からん ・ ・ 」宮城はポツリ、と呟いて、昔の自分を顧みた。 その当時、彼は啓示の主を信じながらも、時折は言い知れぬ不安に襲われて、考え込んだものである。 そして、その様な不安と疑念とは、あの墳墓を見、影浦と会った辺りから、彼の脳裏に形を為した。 その正体はひとつの偉大なイメージであり、全ての基とでも表現すべき極めて巨大な想念である。 自分自身も言代主も、そうした想念の赴く儘に、此の世に存在をし、戦っている。宮城には、そう思われて仕方が無かった。 | |||||||

|
だが、自分や影浦の想念は、言代主の物とは正反対のまるで異質なイメージである。
相対する想念が果たして、同じ想念から生まれ得るのか? 一見すると、在り得ぬ事にも思われる。「だが、そう言い切って良いのだろうか?」
想念には形など無く、数える事も、区別する事すら容易では無い。また、善から悪が生じる事もあるいは可能であるのかも知れない。 想念の世界は極めて深く、人知では到底、測り知れ無い。全てを産み出し、あるいは消し去る、その様な実在とも思うのである。 あえて言えば神であろうか? だが、宮城に取って、その神は善悪、美醜を併せ持つ、得体の知れぬ何かであった。 そして、今、その人知を越えた何者かが、この状況に在る全ての者を戦わせよう、として居るらしい。 | ||||||
|
彼は果たして、我々を何処へ導こう、と言うのであろうか? 宮城は今、それが知りたい、と切望していた。
だが、あるいは、それは問うべき事柄では無いのかも知れ無い。自分がもし大いなる想念から産まれたのなら、 自分の置かれた状況は想念の赴く現実であり、それ以上でも無く、以下でも無かった。 つまり、彼は魂としての我々を通して、認識を得よう、と欲して居るのでは無いのか? 我々の意識はその事を知らず、未来への不安を募らすが、それは自分の認識すべき、いや、見ざるを得ない、 その様な現実でもあるのだろう。 おそらく、全ての人間は此の世へと送られたその瞬間、その様な魂の理を忘れ去るのに違い無かった。 明日、自分の見る物は、それは自分が決めている。いや、自分を産んだ大きな何かが決めているのに違い無かった。 影浦が所用を終え、道場に戻ると、どうやら、誰かが来ているらしい。朗らかな笑いが離れの方から廊下を伝わり、 漏れ出して来る。宮城と談笑をしているらしい。「熊野君だな? けど、俺が帰ったのも気付かぬなんて」 影浦は忍び足で廊下を歩くと、襖の影から部屋を覗いた。宮城かチラッ、とこちらを窺う。熊野は気付いては居なかった。 「やあ、熊野さん、今日わ」影浦は襖の影から顔を覗かせ、さりげの無い口調で呼び掛けた。熊野がクルリ、と振り返る。 そして、顔に赤みが注した。「あ、影浦さん!すごいですね、大変な反響ですよ!」 実は二ヶ月ほど前、影浦の作品が、「祟り神の悲劇」と、表題を付けられ、出版された。 特定の層を念頭に構想を練った作品だったが、それが予想外に評判が良い。 「いや、こんな筈では無かったんだけど? まあ、良かった、良かった」影浦は少し照れ気味にニヤリ、と笑った。 宮城が言った。「これで、こちらのメッセージも、伝わりが良く成るでしょう、古代史ブームに乗っただけでも無さそうですから」 影浦が言った。「うん、多分、彼等は自分達のジレンマを無意識ながら気付いていたんだ、と思う ・ ・ 」 | |||||||
|
日本列島の住人は何時かしら弥生の支配に埋没し、安住をする様に慣らされて来た。
そして、それは弥生的な支配の論理を自らが内面化をせねば生きては行けぬ、その様な社会の体制に大きな理由が在ったのである。
それはまさに日本的な自己の疎外の構造だった。
影浦は今、この事が極限に在る様にも感じるのである。魂を見失った人間達が溢れ返って居るからだった。 そして、人々の無意識も、その事はとうに知っていた。 だが、意識はされず、その解決はそう簡単な業では無かったのである。 確かに、人々は自分自身を取り戻そうと、あらゆる試みに手を染めて、試行錯誤を繰り返していた。 仕事や趣味に没頭する者、社会福祉や宗教活動などに勤しむ者など、その行動は多岐に渡った。 |
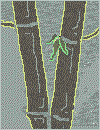
| ||||||
|
だが、その方向は必ずしも正しい、とも言い切れず、危険な状況に陥る者も、そう少なくは無かったのである。
自己の認識を社会に依存し、自らを無くした故なのだろうか? 自らの確かなものを顧みず、遠くに在るガラクタに憧れて、
フラフラと虚空を彷徨ったのである。そして、確かなものを得たのだ、と、他愛なくも錯覚し、迷妄へと足を踏み入れた。
しかしながら、その様な迷妄の世界には、一欠片の真実も存在しない。それはまさしく虚無へと通じる真っ暗闇の洞穴だった。 其処に住むのは皆の亡霊、迷い込む者を更に迷わせ、魂無き亡者へと変えるのだった。 そして、「皆」の亡霊は亡者らの魂と成って彼らを操る。自らが唯一絶対なる魂として、彼等の上に君臨をしたのである。 そして、捕らわれた人々はその亡霊に魂を預け、ただの肉と成る事で安易な生を約束された。いや、その様な錯覚を植え付けられた。 その故に、物質的で外面的な偽の平安がはびこったのである。自らの魂の無き事を一時、忘れさせる平安である。 実は彼等も、自らの魂は欲したのである。にも関わらず、人々は自己の悲しい喪失を協調、と称して賛美した。 「皆」は一体として繋がって居り、「皆」が考える様に考えて、「皆」が行動をする様に行動をする。 それが亡霊に魅入られた、彼等の悲しい生き方だった。 だが、「皆」は本来、魂などは持っては居ない。 魂に取って代わるなど、言語道断も甚だしい。「この儘では、日本は何とも薄気味の悪い、陰湿なる世界へと落ち込んで仕舞う」 影浦には、そんな予感もあるのであった。 言代主の羽虫に否応も無しに取り憑かれ、犯され尽くした魂の忌まわしき腐臭すら感じ取られる。 | |||||||
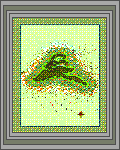
|
無論、その事は即、生物としてのホモ・サピエンスが滅ぶ事を意味はしないが、ヒューマン・ビーイングの滅亡は迫って
いるようにも思われた。今、巷を覆う似非宗教の野放図とも思える氾濫も、そして、人々の持つ不安や焦りも全てが其処に
起因をしている。魂の危うい兆候は至る所に現れていた。
影浦は言った。「自分をどう取り戻すのか、それは今や社会的な問題なんだ、危機感は在る訳だから望みが無くは無いんだが ・ ・ 」 と、熊野がやにわに述べ立てた。「なるほど!分かりましたよ、二番目の敵の正体が!」 皆の亡霊を操って、魂の抑圧を好む悪しき想念、それを信奉する集団が新たなる敵なのに違い無い。熊野はそう言うのである。 無論、宮城と影浦もその事は全く同感だった。 | ||||||
|
さて、その数日後、典子からの電話が入った。葉書や手紙が山のように舞い込んでいて、処理に追われて大変だ、と言う。 影浦は急いで札幌へと飛んで帰った。舞い込んだ書簡の内容は好意的なものが殆どである。 しかし、精神病者から、と思われる物も混在して居り、中には、脅迫まがいの物すら在った。 自分の事を書いたのでは、と見当違いの邪推をして、抗議をする長文の封書なども含まれている。 だが、それはやましい気持ちの裏返しでもある。おそらく彼等は自らの邪なる心の内を無意識かも知れぬが、気が付いていた。 それにしても、あまりの誤解や曲解には、さすがの影浦も辟易とする。 いずれにしても、かなりの刺激を与えた事は確かな事のようだった。凶と出るのか、吉と出るのか? それは想像も付かないが、書簡の内容のチェックには細心の注意が必要だった。 好意的な内容に、罠の紛れている事も在り得ぬ事とは思われぬ。 また、未知の仲間からの信号も一朝一夕に読み取る事は困難であるように思われた。 彼らも相当に警戒し、気を使って書いているのに違いないのである。明日には、宮城が駆け付ける。 典子はそれと入れ替わり、戻る手筈と成っていた。 |
|||||||

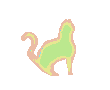

| |||||||
| Cotosiro | |||||||