|
可能世界・陰の神話 第二章第二話 |
縄文とアイヌ This was revised in December 16, 2007. This was revised in August 30, 2008. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
影浦は一通り、自分の見解を述べ終えると、一息、置いて、突然、アイヌに付いて語り始めた。唐突の様に見えるけれども、古代の怨念を語る為には、これは避けては通れぬ歴史的な、そして、心理学的な意味合いがあるのである。そして、その意味合いは、日本民族が縄文文化と弥生文化、、そして、縄文人と渡来人との相克と融合によって、形成された事に関係していた。 熊野が言った。「エエ、そうです、ただ、沖縄、イエ、琉球人に付いては、大陸や東南アジアなどの影響が大きい様に思われますので、若干、様子は違うのですが」そして、何故だろう?彼は上目がちに成って、続けて言った。「ところで、土偶や埴輪には、入れ墨らしい模様の入った物が在ります、髭だ、という人も居るようですが?」その態度からして、どうやら、熊野は影浦の歴史認識を試すつもりで居るらしい。影浦にとって、これは余り面白い状況とは言い難かった。ともすると、影浦はこの様な場合、感情をストレートに出しがちであったが、相手はまだ、初対面の人間である。彼もさすがに憎まれ口など利かぬよう、気をつけていた。「あ、髭ですね?でも、あれは偏見が入ってますから、どうも、疑問ですね、私は刺青だ、と思いますよ?」影浦は取り敢えず、そう言って、返答を述べるに留め置いた。と、熊野がニヤリと笑みを浮かべる。我が意を得たり、とでも思ったのだろうか?それとも、反論でもあるのだろうか?いずれとも良くは分からぬけれども、熊野は突然、真顔に成ると、早い口調で、話を始めた。「ともかく、東夷伝には、倭人は鯨面文身、つまり入れ墨の事ですが、そう書かれています、デタラメとして、無視する学者も居りますが、私は信用するんです」 影浦はこの発言を聞いて、僅かばかり安堵した。熊野の見解も、影浦のものと同じらしい。影浦は僅かに頷いて、同意の意思を表した。 注;東夷伝は古代中国の魏の歴史書の一部であり、東夷の条を指す。ちなみに、その中の倭人に付いて書かれた部分が魏志倭人伝、と呼ばれる。 熊野が言った。「この様な入れ墨の模様はアイヌと縄文人との近縁性を臭わせます、そして、埴輪にも、入れ墨の模様がある事を考えると、縄文人と弥生人との文化的な関係を暗示する様にも思われます、私としては、血縁関係も感じるのですが、いずれにしても、弥生人が縄文人を攻め滅ぼした、と言う単純な考え方はおそらく間違いです」だが、影浦は内心、戸惑っていた。熊野の話は同感なのだが、彼の視点は余りにも、自分の視点に近いのである。影浦はその事が妙に気に入らなかった。そして、何処かに違いがあるのではないのか、とも思うのである。「つまり、アイヌの先祖たる縄文人の血は倭人の基層をも為している、と、そういうお話でしょうか?」影浦は慎重を帰して、そう問うた。と、熊野の顔が輝いた。「ええ、そうです、アイヌの先祖たる縄文人はその血において、我々と深い関わりが在ります」余りにも簡単に同意をするので、影浦は妙に、もやもやとした気分に陥った。 熊野によれば、昔、日本列島には、縄文人が幅広く分布していた。それはアイヌ人の先祖と同系種である、と考えられる。そこに渡来人が弥生文化を持ち込んで、また、その血も持ち込んで、混血をした。それが倭人の始まりだった。おそらく、縄文人の族長達は競って、彼等を迎え入れて、高い地位などの特権で、手厚い処遇をした筈である。それはその様にせざるを得ぬ、切迫した事情があるからだった。 当時、各部族は覇権を争い、武力によるとは限らぬけれども、多くの競争、闘争に明け暮れている。食糧の増産も急務である。渡来人の持ち込む優れた技術は無くては為らぬものだった。そして、その事が渡来人との関係を濃密に保たねば為らぬ、と言う、その様な圧力を産んだのである。「ですから、縄文人と渡来人との混血は加速度的に進んだ訳です」熊野はそう述べると、影浦の反応を窺った。と、沈黙していた宮城が口を開いた。「けど、混血がそんなにも早く進みますかね?どうです?」そして、彼は返事を促すように影浦を見た。だが、影浦にも、即答は出来かねる。実を言えば、影浦は熊野とほぼ、同意見ではあったのだが、立派な説明を出来る程、勉強してはいなかったのである。影浦はただ、「うーん」と、唸るだけだった。 すると、熊野が言った。「でも、縄文時代は長いですし、混血は支配者層から始まった、と考えられます、これですと、一般の縄文人より死ぬ確率も低いでしょうし、子孫も多く増やせます」そして、何故か、上目勝ちにニタリと、笑うと、幾分、高い声で、のたまった。「あの大国主が良い例です、記紀に拠れば、彼は多くの女性とセックスしました、今の事は判りませんが、昔の支配者は偉くトドに近かった訳です。」どうやら、冗談のつもりらしいが、余り面白いとも思えない。影浦は、「なるほど?もし、そのエピソードが史実とすれば、その時代は縄文時代からは、大幅に下ると思われますがね」と、熊野の反応を窺った。だが、どうした事か?熊野は下を向いて、「あ、ちょっと、すみません」と言いながら、ニタニタしている。堪えようとする様子は窺えるのだが、それがどうも、出来ないらしい。どうやら、自分の冗談に、自分が填まって仕舞ったらしい。影浦は差し当たり、笑顔を見せると、やんわりと、話の続きを促した。熊野が懸命に真顔を作る。そして、再び、自分の考えを語り始めた。 倭人の形成には、部族間闘争も大きなファクターとして関わっていた。弥生の血を受け入れぬ古い部族は戦術的にも、技術的にも、劣っていたであろうから、部族ごと、絶滅する事も在ったろう。少なくとも、部族の繁栄は望め無かった。つまり、縄文の血の色濃い部族を、弥生の血の入った部族が同化する、あるいは、滅亡させる。また、その事で、生きながらえた部族を更に弥生的な部族が同化、あるいは滅亡させる。熊野はその様な過程が積み重なって、倭人が産まれた、と考えていた。熊野が言った。「この事はまず、間違い無い、と思います、それが古墳時代に入る辺りの倭人の姿を作ったんです」影浦が言った。「でも、地域によって、時間的なズレは在ったでしょうね?たとえば、北九州と畿内とかで」熊野が言った。「ええ、それで、若干の文化的な、そして、生物学的な違いが生じた、つまり、文化的、人種的な融合の流れには、方向性の違いや、地域差があった、それが記紀の神話に於いて、天津神と国津神の対立として記されたのでは無いのでしょうか?」 当時、列島では、農業技術の発達が食糧の増産をもたらしていた。そして、それは人口を飛躍的に増大させる。特に、北九州と畿内では、その特徴が際だった。その事はその地域の人々の弥生人化が早かった事を示唆している。「時代は下りますが、大和の東征も、この事と関りが在ったのかも知れません、いえ、中国の激動がその引き金では在ったのですが」熊野はその様に自説を補足した。影浦が言った。「ところが、その様な流れに乗り遅れたり、拒んだりした縄文人は滅びて仕舞うか、北へ逃れるしか道は無かった?」熊野が答えた。「ええ、少し、時代は下るのでしょうが、言代主の一族も、それと似た状況にあったのだ、と思います、彼等の一部は北に逃れた筈でした」だが、影浦は若干、へそを曲げていた。自分がひとつ、何かを話すと、熊野はその十倍を語るのである。しかも、それはこれから語ろう、とする、自分の発想でもあるのであった。「少しは、俺にも喋らせろ!」影浦は心の底で呟いた。 と、熊野が言った。「ところで、影浦さん、アイヌ語はどうです?銅鐸の文言が気に成るのですが?」どうやら、順番が来たのらしい。影浦はおもむろに話を始めた。「ええ、確かに、あの文言には、アイヌ語、と言いますか、縄文語、と言いますか、その様な臭いが感じられます、ひょっとしますと、あれは日本語の原型なのかも知れません」すると、熊野の顔が輝いた。そして、話を横取りすると、例の調子で、語り始めた。「エエ!言代奴佐のヌサはアイヌ語のヌサ、つまり、神送りの祭場ですが、それが祭事を司る者の尊称と成り、名前の最後に加えられた、それが後年、ヌシ、という具合に変化した、どうでしょう?」「ああ、なるほど?」「ちょっと、ど忘れしましたが、沖縄にも同系統の言葉が在りますし、あの銅鐸の文言は、アイヌ語、いや、プレ日本語、と呼ぶべきでは無いのでしょうか?」ヌサの下りについては、よく分からぬけれども、プレ日本語の下りについては、影浦も全くの同意見である。アイヌ語と日本語とは確かに、何処かで、繋がっていた。 例えば、アイヌ語の「イタ ク」は「話す」という意味で使われる。原義は「何それを呼び寄せる」と、いう程の意味であり、それは霊を呼ぶ、と言う意味合いを含むのである。これは東北の霊媒師をイタコと呼ぶ事に通じるし、言霊の概念にも通じるのである。他にも、日本語とアイヌ語には似た発音を持ち、しかも意味の近い言葉がかなりの程度、在るのであった。それは特に、宗教的なものに顕著である。以前、この事はアイヌが日本語を借用した証拠である、と手前味噌に解釈されたが、これらの言葉には、アイヌ語の要素に分解出来る物も少なくは無い。今、旧来の見解は疑問視されて、変わりつつある。例えば、イタ クはイ(接頭辞)と、タク(呼び寄せる、の意)とに分解出来る。従って、「イタコ」と言う言葉も、アイヌ語を基礎に持つ日本語だった。どう見ても、日本語とアイヌ語とは、少なくとも、その根っこの部分では、繋がって居るように思われる。そして、その根の部分には、縄文語が在るのに違い無かった。 影浦が言った。「多分、モイワもそうなのでしょうね、アイヌ語では、神聖な小山を表すそうです、奈良には、三輪山が在りますが、これも母岩なのかも知れません」熊野が言った。「ええ、ミワとモイワ、音も近いし、神を祭る、と言う共通点も在ります」「エエ、札幌の藻岩山、ご存じですよね?北海道には、他にも、モイワ、と呼ばれる山が幾つか、在ります、アイヌがそう呼んで居たのを日本人が受け継いだ訳です」「そう言えば、東北には、もや山、と言う山がありました、私は一つしか知らないのですが、藻岩山と同じで、複数、有るそうです、あるいは、それも元来は、母岩であったのかも知れません」 影浦が言った。「エエ、私もそう思います、それで、銅鐸の文言なのですが、あれを残したのが言代主一族の残党ならば、相当に縄文的要素が強かったのだ、と思います」「日常生活は弥生的だった筈ですがね?」熊野がそう口を挟んだ。影浦が言った。「エエ、勿論、でも、あそこに刻まれたカミイはアイヌ語のカムイに非常に近い、おそらく、それは縄文語が日本語のカミ、に移行する、過渡的な言葉であった様に思われます」すると、珍しく、熊野は何も言わずに、頷いた。影浦としては、このまま、自説を述べたい状況である。だが、彼は何故か、そうはせず、少し話の間を置いた。影浦の言わんとする事は熊野もその様に考えている。その事が何故かは知らぬが、気に障る。「ところで、手名椎、足名椎ですが、どう思われます?」影浦は少しの沈黙の後、唐突にそう問い掛けた。意識的では無いものの、それはちょっとした意地悪であったのかも知れない。 だが、一方の熊野には、影浦の問い掛けが曖昧過ぎて、質問の意味が分から無い。「えっ、あの、どういう意味でしょう?」彼は咄嗟にそう問うた。影浦が言った。「ご存じかも知れませんが、アイヌのユーカラにオマンペシウンマツ、というのが在ります、その中に相手の身体を撫でさする、挨拶の礼が出て来ます、どうです?手撫で、足撫で、ですよね?」「はあ?」「これは記紀の手名椎(テナヅチ)、足名椎(アシナヅチ)に繋がる様に思うんです、須佐之男に対する挨拶としての行為が伝承されて、手名椎、足名椎、と記されたように思うのですが」だが、熊野は返事を模索している。影浦は畳み掛ける様に、話を続けた。「ですから、これがアイヌの習慣ならば、その先祖たる縄文人にも同様の習慣が在った、と考えられます」「なるほど?」「つまり、手名椎、足名椎の属する言代主一族には、縄文人の血が色濃く残っていた、いや、少なくとも、その文化には、縄文の色合いが強かった、そう考えるんです、言代主はまさに、イタ クの主ですしね」 だが、熊野は一瞬、言葉に詰まった。それは余りにも、突飛な発想である。奇妙な嫉妬も何処かに在った。無論、彼も、このユーカラは知って居る。だが、手名椎、足名椎、との関連などは想いも寄らぬ話であった。第一、古事記とユーカラとでは、時代背景が全く違う。地理的範囲も全く異なる。熊野は半ばからかい気味に、すぐさま、反論を開始した。「でも、あのユーカラの舞台は島根からは遠く離れた北海道ですし、言代主の時代から見ると、時間も遥かに下って居ます、結び付けるのは、どうでしょう」そして、影浦を一瞥すると、続けざまに述べ立てた。「それと、影浦さん、実はもう一つ疑問が在るんです、記紀では、何故、言代主や建御名方を多穴牟遅の子としたのでしょう、事実は逆で、多穴牟遅の方が新しかった、妙ですよね?」おそらく、これは意図的な反撃としての意地悪である。だが、影浦は然りげの無い態度で、すぐさま、答えた。 「はい、其処なんですが、人間社会は時々、文化や文明を押し留めたり、後退させたり、する事があります、アイヌはその典型とも思うのですが」「なるほど?」「ですから、基本的な慣習に付いては、時間的隔たりは、そう問題には成ら無い、とも考えられます、それにユーカラは古い伝承を口伝える叙事詩ですから、その事も考慮に入れねば為りません」「ええ、まあ」「そして、地理的範囲も、あのユーカラからは、はっきりしません、事実はともかく、北海道らしい、と考えるのは我々の主観に過ぎません」 確かに、影浦の論理そのものに、矛盾は無い。だが、熊野は少し首をひねった。時間的な隔たりや地域的な隔たりを甘く考えて居るのでは無いのか?そう思ったのである。けれども、確たる反証も存在しない。この問題はもう少し、考えてみる必要がありそうである。熊野はあえて、反論を差し控えると、影浦の話を促した。影浦が言った。「そこで、言代主と多穴牟遅との関係ですが、神話に於ける神の系譜、部族間の近縁関係、時間的前後関係などには、吟味が必要なように思うんです」「ええ、それは仰る通りです」「記紀は当時の支配層が纏めたものです、都合の悪い話をその侭、伝える、とは思えません、そのような隠蔽工作は今の民主主義の世の中にも見られますから、当時の事は推して知るべきです。勿論、まるっきりの創作では、編纂した意味は無い訳ですがね」「ええ、同感です、大和は史実を自分たちの都合に合わせて、ねじ曲げた、と言う事でしょう、実際は言代主の一族は縄文人、いや、その血の色濃い先住民の末裔だった、ですが、大和は支配の都合上、彼等を自らの系譜の中に描きたかった」 その時、宮城はあくびをかみ殺しながら、聞いていた。実を言えば、古代史はそう得意ではないのである。だが、二人は議論に熱中して、宮城など、忘れたかの様にやり合っている。面白くは無いけれども、致し方ない。彼は沈黙を守り続けた。影浦が言った。「古事記では、言代主が死んだ後の一族の記述が無いんです、ですが、大国主の一族は大和の時代に入ってからも、かなりの活躍が窺えます、つまり、大和の扱い方が違う訳です」「エエ、確かに」「勿論、最後まで、抵抗した言代主と大和に協力した大国主ですから、扱いが違って当然ですが、その根底には、言代主の一族の持つ縄文的な血と文化への警戒心が在ったのでは無いのでしょうか?」「それが大和の憎悪を掻き立てた、そう言う事に成るのでしょうね?」熊野はそう話を受けた。 実はその時、熊野には、古から伝わるある伝承が蘇っていた。恵比須(昔は、蝦夷、とも表記した)と言代主命が実は、同じ神である、という一種の根強い信仰である。それがどうも、今までの影浦の話と符合する。その伝承も案外、真実を突いて居るのかも知れ無かった。熊野が言った。「ところで、影浦さん、恵比須の神をどう思われます?」「あ、そう言えば、言代主と恵比須とは同一の神である、と、そんな説も在りましたかね?」「はい、初めて文献に現れるのは平安も末期の頃なのですが、そこで、恵比須を表す文字が」「夷てきの夷ですね?確か蝦夷(エミシ)を指す文字としても使われました」影浦は既に熊野の論旨を把握していた。 もし、言代主が縄文人の血を持つならば、それはアイヌと蝦夷(エミシ)との関係にも関わって来る。言代主が蝦夷(エミシ)である可能性すら考えられた。 記紀において、大和の手強い敵として描かれている蝦夷(エミシ)は「夷」の一文字でも表されて居る。一方、恵比須も「夷」の一文字で表記をされた。しかも、当時の恵比須は今のような福々しい神では無く、荒々しい戦闘的な神として表されている。この事はこの二神が実は一神である事の証の様にも思わせた。「どうでしょう、この伝承は言代主が実はエミシである、と、そう言って居る様にも思うのですが」熊野はそう述べて、影浦を見た。だが、即答などは出来かねる。「うーん、判断材料が少ないですからね、ちょっと、分りません」影浦はそんな具合に言い回して、一応の疑念を表した。後年、言代主と恵比須(蝦夷)との関係はある男によって、証される事に成るのだけれども、今、論じている二人には、思いも寄らぬ話であった。 それにしても、彼らは何時まで、取り留めのない議論をし続けるのか?宮城の忍耐も、もう限界である。古代史の論争も必要ではあろうが、怨霊の話はどう成るのだろう?宮城はついに、しびれを切らして、彼らの議論に割って入った。「なるほど、歴史的な背景はよく分かりました、ですが、問題は今の祟り神の狙いです、其処に話を移しませんか?」だが、二人には、どうも、納得が行かないらしい。一瞬、顔を見合わせて、「どうしようか?」と、合図を送った。だが、宮城を沈黙させて居た、後ろめたさも、少し在る。「じゃあ、そうしましょうか?」影浦が仕方なさそうに、熊野に問うた。熊野も同じ心境らしい。幾分、顔をしかめたけれども、「そうですね」と、頷いた。だが、妙である。一旦、言葉が途絶えると、つい、さっきまでの興奮が嘘の様に消え失せて居る。頭も妙に、回転しない。「あの、少し疲れました、ちょっと、休みましょう」影浦はふっと、宮城を振り向くと、そんな具合に同意を求めた。「あ、そうですね」と、宮城が頷く。影浦はゆっくりと、椅子から腰を上げると、窓際に寄って、一服、付けた。首を伸ばして外を覗くと、空一面の鰯の雲が異様なほどに燃えている。本館の塔に視線を移すと、巨大な深紅の太陽が塔のシルエットを飲み込む様に、怪しいコロナを放射していた。 |
|||||||
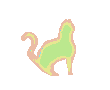


| |||||||
| Cotosiro | |||||||