|
可能世界・陰の神話 第五章第三話 |
祟り神の謀り事 This was revised in December 2, 2006 This was revised in September 1, 2008. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
宮城はふっと眠りを覚ました。とは言っても、完全に目覚めた、と言うのでもない。妙に、寒さを肌に感じて、意識が少し動いたのである。睡魔はまだ、彼を解放しては居なかった。だが、肌に感じるこの寒さは普通では無い。執拗に、宮城の神経を刺激する。彼の想いとは裏腹に、睡魔は見る間に萎んでしまった。「しようがない、起きようか?」宮城は致し方なく、目を開けた。だが、部屋の中は薄暗い。「ん?朝では無いのか?」彼は訝しそうに、上半身を少し起こすと、枕もとの時計に目を遣った。見ると、針は五時三十分の辺りを指示している。「なんだい、まだ、こんな時間か?」宮城は再び寝そべって、毛布をズルッ、と引き上げた。「けど、まだ十月だろ?何で、こんなに寒いんだ?」彼はふっと、呟くと、蒲団の中で小首を傾げた。どちらかと言うと、寒さは苦手な方なので、もう少し蒲団に包まって居たいけれども、気に成ると、確認せずには居られない。彼は蛮勇をふるって、布団を跳ね上げると、窓のカーテンを素早く開いた。と、やけに薄暗い町並みが妙に静かで白っぽい。気が付くと、無数の白い結晶がちらちらと、儚げな様子で漂っていた。雪である。宮城は身体を震わせながら、不思議な物でも見る様に淡雪の舞をぼうっと見つめた。 実は今、彼は札幌に在住している。影浦の自宅にほど近い、とあるアパートの一室を借りて、其処を生活の拠点としていた。島根とは遠く離れた土地とは言っても、あの怨霊の事である。何時、此処に現れぬ、とも言い切れない。影浦には、その為のガードが必要だった。「それにしても、寒いな」宮城は窓から離れると、オイルヒータに火を入れて、其処にしばらくジッ、としていた。影浦のアドヴァイスで、半信半疑ながら、灯油を買って置いたのが役に立った。それにしても、この時期に、これだけの寒さに見舞われる、などとは、全く思ってはいなかった。 これから、ジョギングに出るのだけれども、余りに寒くて、怖じけて仕舞う。「仕方無い、飯でも作るか?」彼は適量の米を軽く磨いで、炊飯器に移すと、まるでノックでもするかの様に、無造作な仕草でスイッチを入れた。「だが、みそ汁は何にしよう?」野菜は昨日、全て使って、何も残っては居ないのである。今度の事では、長期戦にも成りそうだった。幾ら蓄えがある、とは言っても、出費の抑制はせねば為らない。「まあ、しょうが無い」宮城は肩を竦めると、冷蔵庫の扉をクイッ、と引いた。中を覗くと、塩漬けワカメが少し在る。「ま、いいか?」彼は塩を落として鍋に入れると、コンロに掛けて火を付けた。沸騰したなら、味噌を溶いて、火を止める。料理になど、成ってはいないけれども、腹に入れば、同じであるから、細かい事は気にしない。「それにしても、何か、美味いものが食いたいな」彼はブツッと、呟いた。 と、その時、やにわに部屋に明かりが射した。ふっと振り向いて、外を覗くと、曇天の空がほころびて、雲間から、幾筋もの淡い光線がモノトーンの街へと降り注いでいる。見る間に白っぽい風景がカラフルな街並みへと変わって行った。雪は既に止んでいる。朝の太陽が雲間から、少し、顔を覗かせていた。屋根に積もった僅かな雪が水の滴を滴らせている。シャーベットの様な淡雪がトタンの屋根をツーっと滑って、次々と軒下に落下をしていた。「おっ、これなら走れる!」宮城はいい加減のところで、コンロを消すと、もどかしそうに味噌を溶いた。そして、ジョギングウエアーへと着替え直した。 宮城がジョギングから戻って、朝食を済ませた午前の九時頃、影浦からの電話が在った。言代主が何故、この現代を選んで蘇ったのか?その謎が幾分、解けた様に思う、と言う。宮城はすぐに駆け付けた。 影浦によれば、言代主がこの現代に蘇った原因はやはり、歴史の深層に隠されていた。日本列島では、四世紀、弥生の政治体制は大和の東征によって、ひとつの頂点を迎えようとしていた。弥生文化の中核を為す合理主義的な精神が支配の論理ともあいまって、益々、縄文の魂を心の奥底へと追い遣ったのである。縄文の魂は鬱屈をするしか、仕方が無かった。そして、その様な政治的、精神的な傾向は紆余曲折を繰り返しながらも、時代の進展と共に制度化されて、揺るがぬものへと変わって行った。縄文の精神の担い手達は弥生の文化と血に次々と同化をされて、本来の形質を隠して行った。縄文の文化も、そして、その形質も魂も、葬られた、かにも見えたのである。 だが、実際には、縄文の血と魂は身体と心の双方の奥深い所で生き続けていた。縄文の血が遺伝子によって受け継がれている事は言わずもがなであるけれども、絶えざる抑圧にも拘わらず、何故、縄文の魂は生き延びたのか?それが此処での最も重要なテーマであった。けれども、その真相は未だ、見えてはおらず、今後の推理を待たねば為らない。此処までの推理で、はっきりとしたのは、縄文の魂が抑圧をされて、鬱屈をした結果、根深い怨念を伴って、現代に到るまで生き続けた、と言う歴史的な真実だった。弥生的な合理主義、そして、それに基づく支配の体制が今も厳然として在る以上、それは当然の成り行きだった。そして、その様な歴史的、社会的な状況が祟り神、言代主の現代における出現を可能にしたのである。 今、この現代に於いて、弥生と縄文の血は混じり合い、殆どの列島住民はその血のみ為らず、精神的な意味に於いても混血と言って間違い無かった。そして、まさにその事が縄文の魂を基底に保持し、また、其処に弥生的支配が覆い被さる、その様な社会的、精神的構造を作り上げた。また、その事が縄文の怨念をも産み出して、現代に至るまで保たせたのである。つまり、古代の文化の対立が我々、個々人の心の内に、転写をされる事と成ったのである。 おそらく、言代主が破れた当時、彼はこの事を予感していた。勝利者の中に、自らの怨念が息づくであろう事をである。言代主はこの歴史的皮肉を利用しよう、と、そう目論んだのに違い無かった。その故に、言代主はその蘇りを全ての血と精神とが混じり合う、この現代にまで待ったのである。そして、その復讐の第一歩は列島に暮らす人間達の心の奥底に蹲る、その様な縄文の怨念を眠りから覚ます事だった。それが首尾良く為されたならば、矛盾を孕んだ魂は自ずから葛藤を産み出して、自らが自らを呪うだろう。そして、魂は引き裂かれて、霧散し尽くして、滅ぶのである。それが言代主の目論見だった。その様な自らの葛藤に、物理的抵抗など意味を為さない。如何なる武器も役には立たない。それはあくまでも純粋に個々人の内なる魂の戦いだった。 だが、多くの人はその事を知ら無い。縄文の魂を保持しつつ、弥生の支配体制に荷担をして、益々、自らの怨念を根深いものへと育てたのである。その故に、言代主はあの忌まわしき羽虫を此の世に送った。後は愚かな魂が勝手に、その中で戦い始める。ひとつの魂は三つに分かたれ、妥協などは在り得なかった。言うまでも無く、その三つとは、本来の縄文の魂と、それを抑圧する弥生的な合理主義の精神、そして、縄文の怨念である。だが、その様な魂の戦いに勝者などは在り得ない。縄文の魂を保持しつつ、弥生の体制に荷担をするのは元々、自己の否定であった。それは決定的な矛盾であって、ひと度、それらが衝突したなら、精神の崩壊から逃れる事は難しい。そして、個々人の崩壊が進行すると、それが社会を蝕み始めて、社会の崩壊へと進むのだった。それこそが歴史の裏面に隠された逃れ難き筋書きだった。 日本の権力構造は弥生の支配にへつらって、おこぼれを頂戴する、という単純なる一点に集約される。それは恐れとへつらいと、密かな裏切りの構造であり、自己の魂を抑圧する故、自己の疎外の構造だった。従って、世俗的欲望に捉われて、心を顧みぬ人々は自己の疎外を以てして、自己の表現を計るしか無い。彼らが崩壊の萌芽を抱え込むのは当然の事ではあったのである。だが、この問題は詰まる所、日本の住人、個々人の人間性の問題である。言代主の怨霊はその様な自己矛盾に付け込む事でしか、祟りを実現できないのである。列島住民の個々人がもしも、その事を意識するなら、言代主の目論見も、あるいは、成功などはしないのだった。 だが、事はそれほど単純でも無い。安易に自己矛盾を認めて仕舞うと、自らの矛盾に翻弄されて、精神のバランスを崩し兼ね無い。我欲に捕らわれた人々はその事を本能的に察知して居り、意識せぬよう、触らぬよう、無意識の底へと沈めたのである。ならば、自分の魂を無意識の内に疎外して、時の権力に身を委ね、異を唱えず、しかも、密かに裏切って、生物としての欲望だけを追求するしか、仕方が無い。それが権力に執着する人々の、そして、媚びる人々の、愚かな自衛の本能だった。だが、言代主の狙いは其処にある。解き放たれた羽虫達は矛盾を意識せぬ魂をこそ、好んで餌とするからだった。 影浦に言わせると、その対抗手段はただの二つしか在り得ない。言代主の怨念を癒して、鎮める事と、自らの浄化、つまり、権力志向とそこへの怨念の悪循環を、何処かで断ち切る事だった。そして、権力は社会的な仕事を仕上げる為の、ひとつの手段と考える。心の何処かで、その様な意識を保持する事も必要だった。影浦が言った。「まあ、だいたいは、こんなとこかな?けど、妙なんだ、どうも、それがしっくりしない、何か重大な問題を見落としているのかも知れない」だが、宮城には、意味するところが分からない。「あの、重大な何か、って、何です?」彼は思わず、そう問うた。だが、それが分かっているのなら、影浦だって、苦労はしない。影浦は腕を組んで、うーん、と唸った。いずれにしても、更なる思索が必要だった。 宮城はアパートへの道すがら、影浦の話を反芻していた。普通、神の祟りはなおざりな祭事に起因している。例えば、古事記には、祟神天皇の時代の祟り神に付いて、以下の様な記事が載せられている。三輪山の大物主命が大いに祟りを為し、病が国中に広がった。そこで、天皇はその神を崇める多穴牟遅(オオナムチ)の一族の中から、意富多々泥古(オオタタネコ)なる人物を選出して、大物主命を祭らせた。結果、祟りは無く成った、と言うものだった。神の祟りは大方がその様な類のものである。だが、言代主の祟りはその様な単純なものでは無かったのである。その故に、言代主は影浦の言う歴史的皮肉を利用するしか、仕方が無かった。つまり、全ての血と文化とが混じり合う、この現代に至るまで、その祟りを封印して、じっと、時の来るのを待ったのである。 あるいは、その封印は日清戦争、あるいは、日露戦争の辺りで既に、破られて居たのかも知れない。何故なら、日本の社会はその辺りから、弥生的な合理精神、また、その支配の体制に席巻されつつあったからである。そして、その趨勢は大正時代の一時の揺り戻しにも影響されず、太平洋戦争に到って、頂点へと達しよう、としていたのである。言い換えると、大正時代における大衆の自由への感覚とは裏腹に、軍部を中心とした権力機構は、その腐敗にも拘らず、益々、強化をされて、経済的、および軍事的な効率の論理をもってして、人々を操り、支配したのである。ここに至って、縄文の魂への抑圧は頂点に達した。そして、縄文の怨念もかつて無いほどに強まったのである。無論、言代主にとって、それは待ちに待った歴史的状況であったのに違いない。その故に、言代主はあの忌まわしき羽虫を此の世に送った。言代主の予定では、日本の社会は早晩、崩壊を始める筈だった。だが、皮肉な事に、言代主の策謀は日本の敗戦により、挫折をしたのである。権力機構の綻びが一時的にせよ、縄文の魂を復活させて、弥生の支配への怨念を弱めたからに他ならなかった。 既に、それから四十年余りが経過をしている。経済は驚異とも言うべき発展を遂げて、人々は自由を手にした様に思われた。だが、日本の現状を見るならば、それは表面的な変化に過ぎない。個々人の魂の尊厳は取り戻される事も無く、今に至った。日本の経済の成功も、多くの人々を物質的に豊かにして、ただ、尊大にさせただけである。その内、飛んでも無いしっぺかえしを食らうのでは無いのか?いや、言代主の出現こそが、そうであるのかも知れ無い。いずれにしても、宮城には、これから先に起こるであろう、人心の荒廃が手に取る様に見えるのだった。「日本は、いや、日本人の魂は生きながらえる事が出来るのだろうか?」影浦の話が正しいのなら、言代主の出現は宮城の想像を遙かに越える巨大なうねりの現れである。今、言代主の羽虫は至る所で飛び交っており、貧しき魂に蛆が湧くのは日を見るよりも明らかだった。 |
|||||||
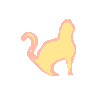


| |||||||
| Cotosiro | |||||||