|
可能世界・陰の神話 第一八章第二話 |
回帰 This was revised in September 28, 2008. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
神々と宇宙の果てしの無い創造は果たして、何を産み出すのか?それが永遠に続くとすれば、無限の混迷である、としか、言いようがない。しかしながら、その結論を受け入れるなら、生そのものを否定する事になりそうである。その故に、彼はその結論を是としなかった。必ず、その混迷を止揚した、魂を安らぐ何かが何処かに、存在している。彼はそう考えた。「だが、何故、自分には、それが見えないのか?」その意識体は模索した。だが、思索は何時も、空回りをして、その糸口すらも、見えては来ない。辺りに向かって、問うては見るが、その問いはこだまと成って、虚しく響いた。「やはり、ひとりで、考えるしか、無いのだろうか?」彼はふと、その様に自問した。そして、再び、鬱々として考え始めた。だが、何時もの様に、答えは出ない。彼はついに考えあぐねて、疲れを感じて、知らぬ間に、寝入って仕舞った。すると、自我が消え去った。そして、世界も同時に、消え失せた。其処はもはや、何も存在をせぬ無の世界である。いや、無、とも呼べはし無かった。其処には、時間も空間も無く、何よりも、認識する主体が欠落している。それを無、と言うべきか?あるいは、有と言うべきか?その事すら、確定など、出来ぬのである。従って、其処には、想念すらも、存在し得ず、あえて、言葉に表すならば、絶対無、とでも、言うしか無かった。従って、その様な虚無の世界では、如何なるものも産まれ得ず、また、何者の認識も在り得なかった。因果関係に基づいて、論理的に考察するなら、そうで無ければ、妙だった。 だが、その様な結論はやはり、条件付で、有効であるだけであるらしい。何も産まれ得ぬ筈の、その無とも呼べぬ無の世界から、突如、何かが揺らぎ始めた。どうやら、それは得体の知れぬ泡である。無の直中を漂いながら、徐々に大きく膨らんで行く。そして、それはイメージとも呼べぬほどのイメージを醸し出して、混沌としたまま、動き始めた。すると、自我が現れた。時間と空間とが認識されて、自我は夢を見る主体と成った。夢の中は薄暗く、空気の淀みが重苦しい。色彩は無く、煤けた様に、煙って見えた。辺りには、多くの人間が蠢いている。陰鬱な靄が彼等を覆って、影法師の様に、ぼやけて見えた。彼らは群を成して、皆、同じ方向へと移動をしている。奇妙にすすけた空間の故、表情も定かでは無かったけれども、生気の失われつつある事は朧気ながら、窺い知れた。彼等を包む、陰鬱な靄の周囲には、暗黒の霧が立ち篭めている。だが、奇妙な事に、暗黒の霧は彼らの歩く道筋には進入せずに、彼らの頭上と、その左右に、まるで黒いベールの様にゆらゆらと、怪しく揺れながら、漂っていた。 彼の前方には、得体の知れぬ靄を通して、過去から未来への道筋が細長く、そして、遙か遠くにまで、続いているのが微かに見える。それはまさしく、暗黒の霧を壁とする、果て無く続くトンネルであった。彼等はそのトンネルをただ、黙々と、前進していた。「けど、一緒に歩いていて、良いのだろか?」彼はふっと、自問した。もし、この道筋から離れて、暗黒の霧に立ち入ったなら、別の世界への抜け道が見えて来る様にも思うのである。彼は一瞬、立ち止まると、決断しようか、と考えた。しかし、怖くて、踏み切れない。一歩でも、暗黒の霧に立ち入ったなら、縋るべき何ものも存在をせぬ虚無の世界が待って居るのかも知れないのである。暗黒の霧の印象が立ち入る事を許さ無かった。だが、彼の意識は混濁しており、自らの自問にすら、気付いていない。彼は陰鬱で暗いトンネルを人々と共に、歩き続けた。 人の群は列を作って、幾重にも蛇行を繰り返しつつ、無限の彼方にまで、連なっている。トンネルのカーブを回り込んで、見えぬ筈の群衆が何故か、彼には、見通せた。暗黒の霧へと立ち入る者はただの一人も見当たらない。皆、揃って、俯き加減に、ただ、黙々と前進していた。何者かに、操られてでも居るのだろうか?彼らの姿は心を悪魔に奪われた亡霊の様にも、見えるのである。だが、彼の意識は混濁しており、その様な印象にも、気付いていない。ただ歩く事、それが彼の全てであった。彼は群衆に埋没しながら、何も考えずに、歩き続けた。ただ、足の重さは気に掛かる。疲れだろうか?それとも、急ぐ事への躊躇だろうか?気の急く程に、足が縺れた。後ろを歩く群衆が次々と、彼を追い越して行く。彼は突如、言い知れぬ焦りに襲われた。そして、妙な不安が脳裏を過ぎった。おそらく、それは置いて行かれる事の不安なのである。だが、本当の事を言えば、それは、「自分は果たして、何を見ているのか?自分は果たして、認識されているのか?」と、いう根源的な不安であった。人には、認識を得よう、とする本姓と、認識をされよう、とする本姓があるのである。だが、彼はその本当の不安にも気付いていない。「とにかく、早く歩かねば」彼はただ、その様な想いに突きあげられて、重い足を引きずった。 「だが、何時まで、歩けば良いのだろうか?」彼はやがて、その様な疑問に捕らわれ始める。彼は動かぬ足を叱咤しながら、懸命に歩いて、しばしば、前方を窺った。けれども、見えるのは何時も、同じ光景である。出口の明かりは未だに見えず、群衆の列の先頭も、やはり、定かには、分から無かった。陰鬱なトンネルの光景が無言で、彼を威圧している。彼はその圧力に、始めて、明確に恐れを感じた。すると、その明確な感覚が彼の意識を揺るがした。彼は、自分が今、何処にいるのかを知らない事に、ようやく、気付いたのである。そして、黙々と歩き続ける群衆の想いも、知りたくなった。「何故、彼らはこの道を歩くのだろうか?何処へ、何をしに行こう、と言うのだろう?」彼は辺りを見回しながら、群衆の様子に注意を払った。だが、彼等には、さほどの迷いは感じられない。彼らは脇目も振らずに、黙々と、前へと向かって、行進していた。きっと、彼らは行き着く先や目的を、知って居るのに違い無い。「あのう、もし、此の列は何処まで、続くのでしょう?」彼は怖々、傍らの影法師に聞いてみた。だが、返事は無い。無表情な顔付きで、一瞥もくれずに過ぎ去った。他の連中にも、声を掛けるが、まるで、彼など、無いかの様に、次々と、脇をすり抜ける。心にポッカリと穴が開いて、空虚な風が吹き抜けた。「彼等と自分とは、違うのだろうか?」その様な想いも、脳裏を過ぎる。すると、やにわに世界が変わって、全てが他者として、意識をされた。 それにしても、此処は何と、薄気味悪く、陰鬱なる世界であるのだろうか!彼は戸惑い、そして、恐れた。見ると、居並ぶ群衆は彼に似ながら、全てが非なるものである。何故か、曖昧として、忌まわしい。「此処は自分の居場所では無い!」彼の心がそう言った。もはや、一緒には、歩め無い。行くべき場所は何処か、他に在る筈だった。だが、一体、何処へ歩めば良いのだろうか?僅かな指標すら、無いのである。「初めから、行き先などは無いのだろうか?」だが、本当にそうであるのなら、歩く必要など、無さそうだった。「自分が群衆と歩いて来たのは、果たして、何の為だったのか?」やはり、目的は在る筈だった。群衆に付いて歩く間に、何時しか、流れに埋没をして、失念をしたのに違い無い。「だが、その行く先は何処であったか?」しかし、意識ははっきりとはせず、記憶も靄に包まれて、雲の様に曖昧である。彼は止む無く、手探りで、記憶の靄へと分け入った。 だが、やっと、見付けた微かな記憶はほんの僅かな欠片のみである。拾い集めて、合わせてみるが、何も、分かりはしなかった。未来ばかりか、過去、現在、そして、自分自身もが、記憶の断片と成って、散乱しており、それらの関係は曖昧である。いや、その欠片が果たして、自分のもので在るのか、他者のものであるのか、それすら、はっきりとは、分からない。「これは、一体、どうした事か!」彼は唖然として、今、来た道を振り向いた。と、妙である。後ろを歩く群衆が妙に歪んで、ぼやけて見える。見る間に、それは色あせて、セピア色へと変わり始めた。ふと、気が付くと、暗黒の霧のトンネルがさらさらと崩れて、崩壊している。流砂のごとく、トンネルの空間に押し寄せて、群衆達を飲み込み始めた。過去への道筋が消えて行く。全てが霧に覆われて、虚無の予感が彼を捕らえた。心細さと寂しさが針の様に、心を苛む。「果たして、未来への道はどう成ったのか?」彼は咄嗟に、振り向いた。しかし、彼の予想の通り、既に、群衆は掻き消えている。そして、行くべき道も失われている。気が付くと、彼は漆黒の暗闇で、無の直中を漂っていた。もはや、触れる物は何も無く、空気の動きすら、感じられない。踏みしめる大地も既に、無く、彼、自らの肉体も、何時の間にか、消失していた。意識は他者を欲するけれども、感覚すらも、消失している。孤独と不安とが闇を深めて、心を更に、虚しくさせた。がらんどうの心の中で、氷のかけらがカラン、と鳴った。 朝であった。此の処、毎日の様に、怪しい夢に魘される。熟睡出来ずに、疲れが取れない。「何故、妙な夢ばかり、見るのだろう?」影浦は何時もの様に首を捻った。仕事の進まぬ苛立ちだろうか?それとも、身体に、異変でも、あるのだろうか?しかし、そうとも思えない。「まあ、分からんものは、しょうがない」影浦はそう呟くと、重い身体をむっくり、起こした。ベッドの脇には、旅行鞄が置いてある。彼はふっと、視線を送って、「あー、行きたくないな」と、呟いた。彼はこの昼、羽田で、三木と落ち合って、島根に飛ぶ事に成っている。疲れがあって、気は進まぬが、約束であるから、行かねばならない。彼は自分に気合いを入れようと、ベッドの上で、伸びをした。実を言えば、つい、この間、島根で、古墳が発見された。どうやら、それは言代主命に関わる墳墓らしい。仕事の関係上、一度は見て置こう、と決めていたのである。「夢の事は暇な時にでも、考えよう」彼はそう呟いて、ベットを出ると、枕元の聖書を書棚に仕舞った。 人は時として、現か、まぼろしか、すら、判然とはせぬ、怪しげな世界を垣間見る。だが、多くの人は幻夢と見なして、記憶の淵へと沈めてしまう。あるいは、それが生きている事の証明である、と言うべきだろうか?もし、うっかりと、怪しげな世界に踏み込んだなら、自らの悪魔にも、出会い兼ね無い。それよりは、生物の論理に従って、物理世界を生き抜く方が無難であるように思われる。だが、それで、満足をして良いのだろうか?いや、果たして、満足が出来るのだろうか?お仕着せの認識に安住したままで、良い様には思えない。今、宇宙は生物なる物理的な存在を此の世に産み出して、意識の窓が開かれ始めた。そして、認識の進化をもたらしている。意識の窓は物理世界に向かうが如く、それは精神世界へも向かうのである。その行く手には、神々と宇宙の混迷が恐ろしい悪魔として、立ちはだかるが、其処を越えた所には、それらの混迷を止揚する何等かの救いも予感をされた。彼には、未だ、見えないらしいが、魂の声を素直に聞くなら、ひょっとして、それは鮮やかに見えるのである。だが、その担い手は、いわゆる神では在り得なかった。 |
|||||||


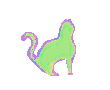
| |||||||
| Cotosiro | |||||||