|
可能世界・陰の神話 第九章第一話 |
押知の秘密 This was revised in September 10, 2008. This was revised in February 19, 2012. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
影浦は三木を何とか、落ち着かせると、学生に、家まで、送ってもらった。だが、三木の状態は心配である。暴漢の件は予期せぬ事態ではあったけれども、三木の過剰反応と思えるほどの動揺ぶりには、やはり、一端の責任を感じるのである。三木をこの件に巻き込んだのは、やはり、間違いであったのだろうか?「悪化しなければ、良いのだが・・」影浦はそう、祈らずには居られなかった。だが、事、此処に至っては、三木自身の力で、乗り越えて貰うしかないのである。影浦はやり切れぬ想いに捕らわれた。そして、今の戦いに身を置いた事も、あるいは、間違いであったのかも知れない、と考えてしまう。影浦の心は揺れていた。だが、自分は既に、火中の栗を拾ってしまった。もはや、後戻りなど、出来ないのである。「この戦いは、何としてでも、勝たねばならない」影浦はそう、自分に言い聞かせると、卓袱台のメモに、視線を移した。 メモによれば、宮城は希言宗なる教団を調べる為に、既に、羽咋に出掛けたらしい。そして、その下には、新たな仲間の事で、典子からの連絡もある、と認めてある。仲間が増えるのは良いのだけれども、何故か、影浦には、それが戦闘開始の合図の様に感じられて、複雑な気分にも、陥った。「いよいよ、正念場が来たのかも知れない」影浦は心の中で、呟いた。それにしても、宮城は羽咋で、何を、どの程度、探るつもりでいるのだろうか?もし、羽咋が敵の本拠地ならば、余り、深入りし過ぎると、危険な状況にも、陥りかねない。影浦は再び、メモを手に取った。 だが、メモは余りにも、簡潔で、詳しい話が分からない。「こういう事はもっと、詳しく書いて欲しいな!」影浦はメモを見ながら、なじる様に、呟いた。だが、宮城は此処には、居ないのだから、何を言っても、致し方ない。影浦はじりじりと、しながら、典子からの電話をしばらく、待った。だが、電話は来ない。影浦は結局、しびれを切らして、札幌の自宅に、電話を入れた。希倭子に、帰りが三日ほど、遅れる旨を告げる都合も、あったのである。だが、電話に出たのは、希倭子ではなく、居候の典子であった。希倭子が近所のスーパーに出掛けて、まだ、戻らぬ、と言う。影浦は希倭子への言伝を典子に託すと、早速、宮城の予定を典子に聞いた。 ところが、典子も、詳しい事は聞いては居ない、と言う。祈言宗なる教団があの祟り神に関係するらしい事、その本部が羽咋にある事、そして、その教団を調べに行く事、その三点しか、聞かされてはいない、と言うのである。これでは、殆ど、メモと変わらない。「何たる事か!」影浦は呆れてしまって、「ああ、そう、もし、連絡があったら、知らせて下さい」と、言って、電話を切った。それにしても、宮城は何故、これほどまでに、急いでいたのか?あるいは、表現不能の直感が宮城を羽咋に急がせたのか?だが、此処で、あれこれ、心配しても、今の状態では、致し方ない。「まあ、宮城の事だから、大丈夫だろ?」影浦はそう、自分を納得させると、煙草を一服、燻らせた。 だが、落ち着かず、五分ほど、経つと、またしても、タバコに、手が伸びる。それは間違いなく、焦燥感の表れである。「あ、いかん」影浦は伸ばした手を慌てて、引っ込めた。いずれ、宮城からの連絡も、あるだろう。「その時は、一言、言って遣らねばならん」影浦のイライラは止まらなかった。そして、もう、一つ、気に成るのは、新しい仲間の事である。果たして、どんな連中なのか?影浦は先ほどの電話で、聞くつもりでいたのだが、典子の話に、偉く、がっかり、とさせられて、つい、聞きそびれてしまった。 メモには、新たな仲間が三人いて、こちらに向かっている、と書かれてあるが、果たして、何時、こちらに着くのか?もし、飛行機で来るのなら、もう、着いていても良い筈なので、おそらく、急行か、特急列車にでも、乗ったのだろう。札幌から上野までの所要時間はおおよそ、二十時間ほどである。仮に、彼らが朝の十時頃に出た、とすると、明日の早朝には、上野に着く。彼らが道に迷っても、八時までには、おそらく、道場に着くだろう。影浦は何時もより、早めに、床に入った。だが、妙に、神経が高ぶっていて、寝付く事が難しい。どうやら、三木の問題や、新たな仲間の事、宮城についての心配などが、神経をチクチクと刺激して、睡魔を遠ざけているらしい。彼は床の上で、三十分ほど、座禅を組んで、気持ちを落ち着かせると、再び、体を横たえた。 影浦はふと、気が付くと、妙に、ひんやりとする、見も知らぬ場所に、佇んでいた。暗くて、良くは、分からぬけれども、どうやら、廃屋の中に居るらしい。打ちっ放しのコンクリートが無惨なまでに、床に崩れて、彼の足下に、散乱している。ふっと、顔を上げて、頭上を見ると、天井の一部が崩れている。そして、その真下には、数本の朽ちた鉄骨が瓦礫や折れ曲がった鉄筋などと一緒に、乱雑な様子で、重なっていた。どうやら、建設中のビルが、何らかの理由で、放り出されて、雨ざらし、と成ってしまったらしい。景気が急速に冷え込むと、時として、見られる光景ではある。 「それにしても、此処は一体、何処だろう?」いくら、記憶を辿っても、この様なビルは全く、覚えがないのである。影浦は少し、不安に感じて、辺りをぐるりと見回した。だが、積み重なった瓦礫と闇が彼の視界を遮っている。とにかく、此処を出ねば為らない。だが、どちらに行けば、出られるのか、見当も、付かない。影浦は仕方なく、余り、自信のない山勘で、瓦礫の上を歩き始めた。だが、廃屋の中は非常に暗いし、瓦礫や折れた鉄筋などがしばしば、行く手を遮って、歩く事は容易では無い。彼は何度も、鉄筋や鉄骨の僅かな隙間を、どうにか、こうにか、すり抜けた。「それにしても、何故、こうも、瓦礫が多いんだ?」影浦は、ぶつぶつと、そう、言いながら、瓦礫の山を這う様に、暗闇の中を歩き回った。と、前方から、微かな明かりが差し込んで来る。彼はその僅かの明かりを必死に、辿って、やっとの想いで、瓦礫を抜けた。 と、其処は既に、屋外である。空は妙に、薄暗く、辺りには、陰鬱な靄が立ち込めている。広い車道の向こうには、ビル様のシルエットが靄のただ中に、亡霊の様に、林立していた。見たところ、皆、廃屋である。それにしても、何と、寒々とした光景だろうか?車道を走る車は一台もなく、歩道にも、人の影は見られない。影浦はその異様さに、呆然とした。と、何処からか、湿った空気を震わせて、重機の音が伝わって来る。時折は、瓦礫の崩れる音であろうか?恐ろしいほどの地響きが辺りの廃屋を共振させた。「ビルの解体に違い無い」影浦は靄の向こうに、注意を向けた。 と、その刹那、靄の向こうで、異様に低いエンジン音が獣の様な唸りを上げた。そして、巨大なキャタピラーが突如、濃霧を突き抜けて、影浦の目前へと、せり出して来た。全容が現れると、それは異様に巨大なクレーンである。不気味に、機械音を唸らせて、右に、左にと、蛇行をしながら、危なっかしい挙動で、近付いて来る。吊り下げられた鉄球が鈍く、光って、ユサッ、と揺れた。「何処のビルを壊すのだろう?」影浦はその様子をただ、漫然と、眺め見ていた。と、クレーンの腕が突如、動いて、巨大な鉄球が大きく揺れた。唸りを上げて、空を切る。そして、傍らのビルの側面へと、打ち付けられた。何と、乱暴な解体だろうか?恐ろしいほどの衝撃音がビルの谷間へと、こだました。コンクリートの固まりが弾ける様に飛散する。そして、弧を描く様に、ばらばらと、地面に落下した。巨大な壁面が崩れ落ちると、地響きが影浦の足下を揺るがした。 「けど、こんなに近くで、危ないな、運転者はこっちに、気付いているのか?」影浦はふと、不安に成って、運転席を仰ぎ見た。と、どうした事か!其処には、誰も、乗ってはいない。運転席の操作レバーが生き物の様に、勝手に動いて、巨大クレーンを操っていた。「何だ?これは!」影浦は唖然として、立ち尽くした。その間も、クレーンは鉄球を振り回し、辺りのビルを破壊して行く。瓦礫が四方に飛散して、一瞬、影浦の脇をすり抜けた。鉄球の軌跡も、怪しげである。 「クソッ、あんなものにぶつかったなら、一巻の終わりだ」影浦は避難しようと、試みた。だが、どうしたのだろう?足が全く、動かない。そして、身体も、硬直している。額から、油の汗が滴り落ちた。ふっと、顔を上げて、クレーンを見ると、じわじわと、こちらへ迫って来ている。一瞬、鉄球が唸りを上げて、影浦を目掛けて、襲い掛かった。「ああっ、潰される!」影浦は危うい所で、目が覚めた。「だが、何の暗示だ?ただの夢なら、良いのだが・・」影浦は心の中で、呟いた。このところ、不吉な夢を見ると、つい、何かの予兆ではないのか、と、思ってしまう。「夢、過敏症、と言うところかな?」影浦はそう、自嘲気味に、呟いた。 時計を見ると、既に、朝の七時である。だが、部屋の中は、何時もより、ずっと、薄暗い。そして、屋根の瓦を叩く雨音が窓のカーテンを通して、伝わってくる。落雷の音も、しばしば、聞こえる。相当に、激しい雨らしい。樋から溢れた雨水が直接、地面を叩くのだろうか?時折、激しい水音が、窓のすぐ、外で、響き渡った。そう言えば、昨夜、眠りに付く頃も、雨だった。どうやら、そのまま、降り続いていたらしい。影浦はむっくりと、体を起こすと、カーテンを捲って、外を覗いた。と、林立するビルの輪郭が灰色の闇へと、溶け込んでいる。一瞬、稲妻が雲間を走ると、立ち並ぶビルの輪郭を、くっきりと、闇に、浮き上がらせた。と、三木の顔が脳裏を過ぎる。昨夜は何とか、宥めたものの、彼の心の状態が非常に気に成る。昨日、感じた後悔が、再び、影浦を苛んだ。 その日の夕刻、道場に、三人の男女が現れた。宮城の言伝に在った連中である。青森の恐山に立ち寄ったので、予定より、かなり、遅れてしまった、と言う。いずれにしても、皆、穏やかなオーラを放射して居り、典子の見立てに狂いは無かった。だが、いずれも、若く、一番、年かさに思われる髭面の大男も、せいぜいが、三十そこそこ、と思われる。風貌は一風、変わっているが、ただ者で無い事は窺い知れた。話を聞くと、彼は名を押知松男、と言い、アイヌの長の末裔である、と言う。帯広の近郊に、牧場を持っており、その経営者でもあるらしい。その傍ら、アイヌ史の研究も、手掛けているが、本業は彫刻家である、と彼は言う。アイヌ文化の伝統を生かした現代彫刻、という事らしい。「中央にも、ちょっとは、知れて居ります!」若干、照れ気味ではあるものの、誇らしい様子で、そう述べた。と、その時、影浦の脳裏に、男の記憶が過ぎって行った。はっきりしないが、何処かで、見た様に感じたのである。「あの、以前、会ってますかね?」影浦は思わず、そう問うた。だが、押知は会った記憶は無い、と言う。影浦は小首を傾げて、記憶を辿った。 と、押知が言った。「テレビでは無いでしょうか?NHKの北海道で、去年、紹介をされましたので」「ああ、それで・・」影浦の脳裏に、徐々に、記憶が蘇って来た。確かに、影浦はその番組を見ていたのである。押知についての記憶の断片が脳裏を巡ると、線と成って、繋がり始めた。その番組に拠れば、押知はやはり、彫刻家であり、牧場主であった。初めは、酪農が主体であったけれども、今では、様々な動物を飼育して居り、観光にも、一役買って居る、と言う。場内には、レストランやワイルドな感じの遊戯施設が適当な間隔で、設けられおり、それなりの賑わいは見せたのである。だが、従業員は余所とは、かなり、毛色が違った。彫刻や絵画など、芸術を志す者で、占められている。その人数も、極めて多く、とても、採算が合う様には思えない。ナレーターはその理由として、押知が彼等の後押しをして居るらしい、と述べていた。だが、大金持ち、とは言い兼ねる彼が何故、その様な事をし始めたのか?テレビの興味はその一点に注がれていた。アナウンサーはその事を彼に尋ねるけれども、彼は口を濁して、答え無い。ナレーターはその補足として、彼の生い立ちや親分肌の性格を挙げて、人柄の良さを強調していた。影浦はその時、奇特な人間も居るものだ、と、感心した事を記憶している。だが、今、こうして、押知に接すると、テレビのその様な見解は表層的に思われた。 さて、もうひとりの痩せぎすの男、坂崎相舜は僧侶の家系に産まれ育った。だが、彼は僧職を嫌い、若い時に、家を出ている。彼は今、株式投資で、生計を立てており、座禅三昧の毎日だった。投資に失敗をした事は一度も無い、と豪語をするなど、相当の自信家、とも受け取れる。だが、それだけの力は在りそうだった。坂崎は押知との出会いを語り始めた。坂崎はある日、たまたま、押知の個展を見る事と成り、忽ち、その作品に魅せられた。写実的な作風からは高い精神性が窺える。生命への畏敬と謙虚さが作品の全体から、溢れ出ていた。坂崎は無性に、その作者に会いたく成った。ある意味、自分と対極にありそうな、その人となりに興味を持ったのである。だが、あいにく、押知はその時、彼の牧場で、ちょっとした問題が起きて、戻っていたので、面会をする事は叶わなかった。其処で、彼は即座に、押知の牧場に電話を入れて、アポイントメントを取り付けたのである。そして、まだ、酪農専業であった押知の牧場を訪れた。 会ってみると、押知は想像通りの人間である。「彼はやはり、自分に足りないものを持っている」坂崎はそう、確信すると、その後も、時間を作っては、押知の牧場を訪れたのである。そして、やがて、押知が自分と共通の問題を抱えている事にも、気付いたのである。実を言えば、彼等は、人には語れぬ、ある秘密を持っていた。それはある種の自由な魂と、人並み外れた霊の能力である。その様なものを持つ事が彼らに、慎重な行動を余儀なくさせた。もしも、その事を露わにしたなら、故無き攻撃にも、晒され兼ねない。掛け替えの無い心の自由を奪われない、とも限らない。その故に、彼等が互いを知るまでは、ひたすら、自分に閉じ籠もり、唯我独尊を決め込んだのである。だが、奇しくも、彼等は其処で、出会った。また、その事が彼等の生き方をも、変えたのである。自由な魂を持つ事は彼等に限らず、誰もが望む事である。と、すれば、平凡な生活を営みながら、ひっそりと、自由な魂を保ち続ける、その様な人間も居るのでは無いのか?二人の親交が深まるほどに、その様な想いも、強まったのである。 だが、その様な魂を保つ平凡な人間が本当に、存在するなら、相当の苦難に在る事も、確かな様に思われる。その様な自由な魂はおおむね、世間の習慣には、従順な筈だが、世間のしがらみとは、相容れぬ面も、併せ持つ。その故に、彼らは誤解や曲解に晒され易い。また、その為に、有形、無形の攻撃に、晒される可能性も、大きいのである。しかしながら、普通の人々である彼等に取って、その様な苦難を切り抜ける手段は、息を潜めて、じっと、耐える事しか、無さそうなのである。彼らの自由はおそらく、その様な忍耐と、悪しき習慣を拒否する故の貧困の上に、成り立っている、と、二人はそう、推測した。だが、皆の亡霊が力を増している今、たとえ、息を殺して、潜んで居ても、彼らが安全である、とは言い切れない。皆の亡霊が嗅ぎつけて、彼らを奈落へと、落とそうとするのに違いないからである。今や、陰湿ないじめが効率の論理の許で、制度化されたかの様に、ちまたを覆っている。この事からも、皆の亡霊が活発化している事が窺い知れる。「だが、我々の予感は、当たっているのか?」彼等はその問題について、密かに、真偽を探り始めた。そして、程なく、その推測の正しい事が確かめられた。自由な魂の所有者は予想外に多く、また、様々な苦難に遭遇している事も、分かったのである。 だが、その様にして、虐げられた人々は何故、反論も抵抗もせず、理不尽な圧力に耐えるのだろう?無論、それは社会的な弱者の故、あるいは、彼らの気弱さの故、などとは、考えられる。だが、果たして、それだけが原因だろうか?押知や坂崎には、少し、違う様に思われた。おそらく、彼等の無意識は加害者の心を知って居た。加害者の被害者としての苦しみをである。だが、被害者でもある加害者達は自らの醜さには、気付か無かった。地獄の鬼に苦しめられて、鬼へと変わった人々である。悪魔に、あるいは、皆の亡霊に、魂を売った人々だった。鬼に対して非難をしても、反撃を食らうだけである。たとえ、理を以てして、諭しても、改心させる事は難しい。鬼と成った人々が自身の魂を取り戻すのには、自らの姿を鏡に映して、自らの醜さを知るしかないのである。だが、それは容易に行える業ではない。その故に、自由な魂の所有者達はジッと、耐えるしか、仕方が無かった。 だが、彼らが特別に我慢強い人々であるのか、と言えば、そうではない。彼らはその意味においても、普通の人々なのである。その苦しみが厳しい事は確かであった。それにしても、この様な人々が増え続けている現状は極めて、理不尽で、重大である。皆の亡霊と巨大資本の圧力、そして、彼らに向けられる、真綿で締め付ける様な攻撃が、日々、彼らを苦境に追い詰めている。「才能に恵まれた自分らだけが、のうのうと、生きるのは心苦しい」ふたりはそう、考え始めた。 だが、何故、その様な鬼が生まれるのか?ふたりはやがて、その問題についても、考え始めた。そして、ある真実へと、辿り着いた。鬼へと変わった人々も、その多くは元来、社会的な弱者である。社会的抑圧に晒されながら、それに耐えて、生きている。ただ、彼らは社会的にも、精神的にも、その様な境遇から、抜け出す手段が無い、と諦めていた。そして、その様な諦めが、イマジネーションの欠如を招いた。それはまさしく、思考停止の状態である。その様な心の有り様が他者の心を推察し得ぬ恐ろしき無知を生み出した。そして、一方では、社会から、何時、疎外をされるか、分からない、と言う恐怖心も、募らせた。あるいは、皆の亡霊がその様な心理を助長させた。 「たとえ、自己を疎外してでも、社会からの疎外は避けねば為らない」無意識ながら、彼らはその様な強迫観念に捕らわれたのである。だが、その様な強迫観念に捕らわれて、自己を疎外しながら、生き続けると、内的フラストレーションは増大して行く。その事が本人すら、気の付かぬ、恐ろしき怨念を産み出したのである。それは少なくとも、彼らにとって、本来、社会に向けるべき、晴らして、然るべき怨念であった。だが、不思議にも、その怨念が社会に向けられる事は余り、無かった。大方は遣り場の無い鬱屈をした恨みと成って、弱い人々への攻撃心を無残なまでに、募らせたのである。あるいは、皆の亡霊が陰湿な空気を醸し出して、自由なる者、弱き者への無反省なる攻撃心を募らせた。そして、彼らを鬼へと変えて、ある種の人間を攻撃させたのである。いたぶられる者が被害者ならば、いたぶる者も、また、被害者であった。 「やはり、このままに、しては置けない!」押知と坂崎は無理を承知で、動き始めた。人々に、自らの問題に気付かせて、再考を促そう、と考えたのである。だが、人の悲しい性なのだろうか?他人の醜さは認めるものの、自分に付いては、分からぬらしい。彼らにとっては、醜さを映す鏡など、生きる上では、邪魔なのだった。其処で、押知と坂崎は止む無く、被害者の救済に、心を注いだ。彼らが鬼と成る前に、心の平安を与えるのである。押知が牧場を解放したのも、実を言えば、その為だった。必要な資金の一部は坂崎が捻出した。そして、その様な援助は今も、なお、続いている。従業員の人数は増加の一途を辿って行った。 |
|||||||

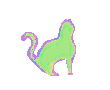

| |||||||
| Cotosiro Home | |||||||