|
可能世界・陰の神話 第十章第三話 |
特異民族 This was revised in December 4, 2006. This was revised in March 7, 2012. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
影浦はこのところ、しばしば、道場を訪れて、宿泊する様に成っていた。祈言宗が碁石が峰に神殿を建設した理由は未だに、はっきりとは、分かっていない。宮城は今、その問題を解明すべく、日本各地を飛び回って、情報収集にあたっているが、上手く行っている、とは言い難い。その所為だろうか?此処に来て、肉体的にも、精神的にも、相当に、疲れが出て来た様である。「何も、出来んが、留守番程度なら、手助けできる」影浦の心情はその様であった。 それにしても、暇である。日がな、一日、座禅をして、過ごす訳にも、行かず、かと言って、長時間、道場を空ける、と言う事も、難しい。何時、どの様な連絡があるか、分からないし、不測の事態が生じる、と言う事も、全くない、とは言い切れない。軽い気持で、始めたのだが、長く続くと、この暇は一種の拷問の様にすら、感じられる、何とも、窮屈な暇であった。 唯一の救いは、今、書いている新聞の連載ものである。小説家の日常を淡々と、書き綴ったのものであるので、試料探しや推理に、時間を掛ける必要もない。仕事に要する時間は大幅に減っているし、気を紛らわすには、最適な仕事でもある。しかし、仕事に、没頭する事は難しかった。あの神殿を建設した真の目的について、考えなくては為らないのである。だが、それは余り、進んではいなかった。何しろ、情報が不足している。今はまだ、宮城の調査待ち、と言う状態だった。 それにしても、東京の夏は酷く、暑い。人間の産み出す廃熱が淀むからなのに違いない。住み慣れた札幌と比べると、湿度も相当に、高いのらしく、汗が吹き出すと、なかなか、引か無い。慣れぬ影浦には、少々、こたえた。クーラーくらいは、欲しいところだが、宮城の方針で、付けては居ない。精神修養の場としては、止むを得ぬ選択ではあるのだろう。 「だが、離れくらい、良いのでは無いのか?」これだけ暑いと、その様な誘惑にも、突き上げられる。それにしても、この所、随分と、蝉が煩い。暑い時に限って、ジージーと、鳴くので、余計に、暑さを感じてしまう。道場の庭の大きな立木が蝉を呼ぶのに違い無い。だが、何故、アブラゼミばかりが繁殖するのだろう?たまには、ヒグラシの様な涼しげな声も、聞きたいのだが、ひょっとして、都会の喧噪を嫌って、寄り付かないのか?アブラゼミは元々、うるさい奴だから、都会の喧噪が好きなのかも知れない。類は友を呼ぶ、と言う事だろうか?だが、アブラゼミも、一応、夏の風物だから、しょうが無い、と言えば、しょうが無い、のだろうか?影浦は中庭を見渡せる縁側に座布団を敷くと、ゆっくりとした仕草で、腰を下ろした。そして、足を組むと、瞼を閉じた。 此の処、祈言宗も、形を潜めて、怪異な事件は起こって居ない。それが逆に、不気味であったが、表面上は、さし当たり、平穏な毎日である。心配の種は尽きないのだが、ともすると、緊張感は欠けて仕舞った。 座禅を始めてから、三十分ほども、経ったであろうか?からから、と、引き戸を開ける音がする。影浦はふっと、目を開けると、組んだ足をゆっくり、解いた。時計を見ると、既に、午前の十時である。「熊野君かな?」影浦は急いで、玄関へと、足を運んだ。見ると、やはり、熊野である。行楽帰りの出で立ちなので、羽田から、直で来たらしい。影浦と顔を合わせると、日に焼けた顔がニッと、笑った。「影浦さん!凄いお土産が在りますよ、縄文の魂が何故、心の底で、生き続けたのか、その科学的根拠が分かったんです!」靴を脱ぐのも、もどかしそうに、熊野は夢中で、語り始めた。だが、影浦は熊野が余りに、早口なので、頭の方が付いて行かない。「まあ、とにかく、話は入ってからだ、まだ、時間は在るんだろう?」影浦は堪らずに、そう述べて、熊野の話を遮った。だが、熊野のお喋りは止まらない。影浦は仕方が無しに、聞いていた。 熊野は夏期休暇の間、典子と共に、札幌にいた。道内巡りも、して来たらしい。それも、典子と、一緒であったのかは、聞きそびれたが、空いた時間は専ら、読書に当てたらしい。だが、専門書などは殆ど、読まずに、話題の本を読破した、と言う。その中に、角田博士の右脳と左脳に付いての著作が在った。(この人物とその著書は実在します)その角田博士によると、人間の脳は原則として、その右半分では、非言語音(言葉ではない音)、つまり、音楽や雑音、動物や虫の声などを処理して、左側では、言語音、つまり、人間が喋る時の声を処理するらしい。言葉を処理する、とも言えるのだろう。 だが、日本人と西欧人とでは、その処理の仕方に、若干の違いが在るらしいのである。欧米人の場合、その原則はその侭、当て填る、と言うのであるが、日本人は虫やある種の楽器(篠笛などの和楽器)の音などを、言語脳たる左半球で、処理をするのだ、と言うのである。それが非言語音(言葉ではない音)であるにも関わらずである。もし、それが事実とするならば、欧米人が虫や楽器の音を単なる音として、捕らえるのに対して、日本人はその一部を言の葉的に捕らえる、つまり、意味を感じる、とも言えそうである。熊野には、その様な日本人特有の認識の在り方が極めて、重大である様に思われた。 人間に取って、意味を発する主体は意識体で在らねば為らない。従って、普通、楽器などの奏でる音は非言語音(言葉ではない音)として処理された。だが、日本人に取って、非言語音がその一部とは言え、語り掛けるものならば、それが生物では無い以上、別の意識体として、捕らえる事にも成りそうである。つまり、意識するか、しないかは、別として、霊魂、神々、魔物など、霊的存在を感じるのである。そして、その様な脳の認識が日本人の精神の基層を為して、おそらくは、言霊の概念も、その辺りから、産まれたのに違い無い。熊野はそう、述べるのだった。熊野は言った。「ですが、この脳の特性はどうも、遺伝では無さそうなんです」そして、その訳を続けて、述べた。 角田博士に拠ると、幼年期を欧米で、過ごし、英語やフランス語で、育った日本人は欧米型の脳に成り、日本語で、育った欧米人は日本型の脳に成るのだ、と言う。つまり、幼年期に使う言葉によって、脳の機能が決まるのである。従って、それは文化なのに違い無かった。「フーム、面白いね、でも、何がそうさせるのかな?」影浦が呟く様に、問い掛けた。熊野が言った。「エエ、日本語には、母音ひとつで、意味を為すものが少なくありません、博士はその特性が関係するのでは無いのか、と、言うのですが」「母音?・・で、その根拠は?」「さあ、其処までは、言ってなかったので・・でも、言葉の特質に関わる事は確かな様に思うのですが」「うん、そうかも知れんね」「なら、幾ら、異文化が流入しても、日本の根底に在る文化、精神は変わらんのでは無いんでしょうか!」 だが、影浦は少し、首を捻って、言った。「うん、縄文の魂は日本語がある限り、消える事は無い、という話だね、けど、飛躍のし過ぎでは無いのかなあ」すると、熊野が、「えっ?どうしてです?」と、影浦の顔を覗き込んだ。様子からして、どうやら、影浦の反応が不満らしい。影浦は言った。「うん、確かに、今の日本語は、その様な特質を産んだのかも知れ無い、でも、縄文期や弥生期の言葉に、同じ事が言えるのかな?」そして、熊野の顔を下から覗いた。 だが、本当の事を言うと、影浦は本気で、そう言ったのでは無かった。何時ぞやの議論の仕返しに、ただ、混ぜっ返しただけだったのである。そして、熊野が彼の冗談を読み取る事も、計算していた。だが、熊野は真面目な顔つきで、言った。「エエ、其処なんです、実はですね、この日本人、特有と思われたパターンが他の民族からも、見付かってるんです」どうやら、熊野は自説を述べる事に没頭して、他の事には、頭が回って居ないらしい。せっかくの冗談が台無しと成って、影浦は幾分、拍子が抜けた。だが、致し方無い。彼はもやもやとした気分を引きづりながら、熊野に、耳を傾けた。 角田博士の調査よると、いわゆる黄色人種の中には、日本型の脳は見付から無かった。日本人に最も近いとされる韓国人にしても、欧米型なのである。だが、太平洋に点在する島々の住人、つまり、その現地語を話すミクロネシアなどの人々は日本型、と判断された。ポリネシアンの言語も、ミクロネシアの言語と、その形態のが近い事から、同様の脳を作る、と考えられる、と博士は言う。この事が何を意味するのか、熊野はすぐに、理解した。実を言えば、縄文人の直系の子孫と思われるアイヌ人はポリネシアの人々に近いと言われる。それは最近の研究で、確かな説と成りつつある。ならば、アイヌ語も、ポリネシアンやミクロネシアンの言語、そして、日本語と同様に、日本型の脳を作るのでは無いのだろうか?アイヌ語と日本語は共に、縄文の言語の形態を色濃く、残している。つまり、日本型の脳は本来的には、縄文語に端を発するのでは無いのか?熊野はそう、考えたのである。 「さっきも、ちょっと、言いましたが、アイヌ人の肉体的な特徴は太平洋諸島の人々に極めて、近い、と言われて居ます、つまり、ポリネシアンやミクロネシアンは旧モンゴロイドの子孫として、分類出来るのだ、と」 「うん、氷河期以前のモンゴロイド、という事で、そう、名付けられたようだね、いわゆる黄色人種、つまり、新モンゴロイドは氷河期の寒さに耐えられるように、旧モンゴロイドから、少進化したのだ、と」 熊野が言った。「ええ、そうです、ですから、ポリネシアンやミクロネシアンの言語、そして、アイヌ語や縄文語は旧モンゴロイド系の言語として、括れる、と思うんです」 「うん、その全てが日本型の脳を作るとすれば、そうかも知れんね、けど、今のアイヌは日本語で育ってるから、その証明は出来ないな」 「エエ、でも、今までの状況を勘案しますと、アイヌ語が日本型の脳を作る事はまず、間違いは無い、と思います、そして、その原型とも言える縄文語も、日本型の脳を作る訳です」 影浦はその完璧なまでの推理に、脱帽せざるを得なかった。発想の自由度も、凡庸ではない。事実と当為(人間として、為すべき事、あるいは、理想)とを峻別して、推理を為し得るからに他ならない。そして、おそらく、その様な彼の推理には、彼の当為の内容を変革する力も、持っている。多くの場合、当為には、当人の欲望が隠されている場合が多いけれども、彼ならば、当為から、個人的な欲望を追い出す事も、可能なのかも知れない。彼の推理は影浦に、その様な予感すら、抱かせた。「買いかぶりだろうか?だが、ひょっとして、こいつは将来、大物に成るかも知れない」影浦は、心の底で、その様な期待が膨らむのも、感じていた。 熊野が言った。「言語学者には、叱られるのかも知れませんが、太古の昔に遡れば、旧モンゴロイド語族、あるいは、環太平洋語族、みたいな分類が為されても、良いのでは無いのでしょうか?」そして、影浦をチラッと、見ると、事のついでに、とでも、言うかの様に、別の話を持ち出した。 「ところで、日本語のルーツがインドのタミール語では無いのか、という説が在りますよね、色々と、批判も在るようですが」「うん、知ってるよ」「もし、その説が正しいのなら、タミール人のルーツは旧モンゴロイドなのかも知れません」 だが、遺伝的な検証はしたのだろうか?影浦はその事だけを指摘した。と、熊野が少し、はにかんで、言った。「あ、イエ、そこまでは、でも、タミール人がモンゴロイドであるなら、彼等のインダス文明が太平洋の同族に影響しない筈が無いんです、あの説も、簡単に無視は出来ません」「うん、そうかも知れないけど、僕は日本列島を中心にした縄文文化圏があった、という考え方を取りたいんだ、山海経の記述も、気に成るし、でも、この話は次にしよう、話がずれた」すると、熊野が苦笑いをしながら、頭を掻いた。「あ、脳の話でしたね、日本型の脳を作る縄文語の要素が何故、日本語へと、受け継がれたのか、私はこう、考えるんです」 日本列島に縄文人が広く分布した縄文時代、今の韓国人などの先祖たるアルタイ語系新モンゴロイドは絶える事無く、南下を続けた。だが、元来、内陸の民である彼等の航海技術は縄文人に比して、相当に、低かった様に思われる。また、海上における交通手段も、同じ理由で、貧弱であった筈である。日本列島への渡航には、少なくとも、その初期、縄文人の手を借りた事すら、考えられるのである。いずれにしても、新モンゴロイドが大挙して、列島に押し寄せる事は不可能だった。 ならば、苦難の末、列島に辿り着いた新モンゴロイドは数も少なく、縄文の社会に依存をしなければ、生き抜く事は難しかった、と考えられる。そして、もしも、そうならば、彼らが列島の言葉、つまり、縄文語を使う様に成るのは自然な成り行き、と思われる。だが、航海や、異文化への同化など、様々な困難が在るにも拘わらず、彼等は次々と、日本列島へと遣って来て、縄文人に同化した。また、自らの文化を縄文の文化に、融合させたのである。その趨勢は少なくとも、古墳時代、いや、おそらくは、大和の時代に至るまで、絶える事なく、続いて行った。その様な状況下で、列島住民の形質が新モンゴロイドへと移行をしたのは当然の帰結であった、と考えられる。「その理由は初対面の時、詳しく、お話ししましたよね」熊野はそう、述べると、話を続けた。 おそらく、縄文人は縄文時代の後期まで、あるいは、弥生時代の始め頃まで、日本列島のみならず、朝鮮半島においても、生活していた。だが、彼等の運命は列島の縄文人とは、違ったのである。其処は内陸と地続きの為、同化が早く、ほぼ、完全に、アルタイ語系モンゴロイドの血と文化とに、吸収された。つまり、大陸の縄文人はアルタイ語を話す新モンゴロイドと成って仕舞った。 日本海の存在がその様な状況の違いを産んだのである。 熊野は言った。「おそらく、列島の縄文人は大陸の文化が優勢と成った頃から、高い文化を感じさせるアルタイ語風の言い回しを使ったのでは無いのでしょうか?」 「うん、単語などには、その様な形跡も見られるしね」 「エエ、太平洋戦争終結後のカタカナの氾濫を見れば、想像が付くと思います、いえ、それ以上のものがあった筈です、それが縄文語を日本語へと変える力と成ったのでしょう」 「うん、言葉を統制する文部省も、無かったろうしね?」突然、悪戯心が湧いて出て、影浦はそう、混ぜっ返した。と、今度は、冗談が通じたらしい。熊野がニヤリと、笑みを漏らした。だが、彼はすぐに真顔に成ると、言った。「ところが、その様な変化にも関わらず、縄文語の基本的な部分、つまり、日本型の脳を基礎付ける何らかの要素は変わら無かった」 「つまり、アルタイ語には成り切ら無かった?」 「エエ、日本海がその違いを産んだのでしょう、その証拠に、我々の脳の型は韓国人とは、違って居ます」「ウン、韓国人の脳は欧米型だからね」「エエ、ですから、その様な脳を作る文化的な要素、つまり、縄文の魂を産む基本的な要素は、縄文語から古代日本語、そして、現代の日本語へと、綿々と、受け継がれて来た、と言う事でしょう、もし、そうでなければ、我々の脳は韓国人などと、同じに成っていた、と考えられます」 その事は影浦にも、異存は無かった。言語の基本的な部分がそう、簡単に変貌するとも、思えない。日本の魂を基礎付ける日本語に秘められた何等かの要素は、数千年の異文化の流入にも関わらず、心の奥底に生き続けて、縄文の魂を保ったのである。だが、中国や朝鮮半島から流入した多くの文化はあくまでも、新モンゴロイドのものだった。脳で言うなら、それは紛いも無く、欧米型の文化なのである。仏教のある部分を除いては、それらは如何にしても、日本人の魂とは成り得なかった。そして、憂うべき事に、弥生を初めとする外来の文化、いや、文明は時代を超えて、権力膨張の手先と成った。また、それら、外来の文明の多くは権力から、大衆へと下されて、縄文の魂を押し込めたのである。そして、人間の暗い部分は縄文の魂へと、押し付けられて、その魂は卑しめられた。その故に、怨念や屈折をした情念の数々が、日本文化の根底を彩って、その表現をなさしめたのである。 また、縄文の魂を忌避する権力の姿勢は往々にして、権力者自身の魂すら、喪失させた。日本人でありながら、民族意識を鼓舞して居ながら、本当は、日本の心を持たないのである。しかも、その事には、気付いて居ない。その故に、全体への奉仕、と言う美名の許、一部の特権階級の欲望が野放図に満たされる一方、大衆、個々人への、冷たい政治姿勢が蔓延ったのである。そして、今も、その傾向は変わっていない。共同体意識の希薄化はこの様にして、加速して、国の力を弱めたのである。それは全て、権力に媚びる人々が自らの言霊を滅ぼして、自らの思考を失った事への、歴史の必然から、生ずる咎めであった。言い換えると、彼らは自らの欲望の為に、皆の亡霊に操られて、同胞への愛情を失って、縄文の魂を卑しめたのである。言代主の怨霊は其処で、生まれた。 |
|||||||


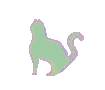
| |||||||
| Cotosiro Home | |||||||