|
可能世界・陰の神話 第十章第二話 |
茂の欺瞞 This was revised in March 7, 2012. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
正午と言うのに、茂はまだ、布団に包まっている。頭が少し、疼いていて、胃にも、少し、痛みを感じる。障害だらけの取材に嫌気が注して、深酒をしたのが行け無かったらしい。あの失踪事件で、祟り神に言及した手前、邪教集団について、書かねばならない羽目に陥ったのだが、宗教法人のガードは極めて、堅い。面会を申し込むが、断られる事が多く、面会は出来ても、突っ込んだ質問には、殆どが、ノーコメント、と言う有様である。取材は思うに任せなかった。しかも、最近は、脅迫まがいの手紙も、しばしば、受け取る。心当たりは二、三、あるけれども、警察に届け出ると、取材について、根掘り葉掘り、聞かれて、貴重な時間を無駄にするなど、心が安らぐ暇もない。 その所為か、どうかは、知らないけれども、最近は、妙に、疲れやすく、体調も、余り、良くない。特に、今日は、具合が良くない。「風邪でも、引いたか?」彼はふっと、額に、手を遣った。だが、思った通り、熱はない。「やっぱり、二日酔いだ、確か、頭痛止めは、在ったよな?」だが、何処に入れたのかを想い出せない。体が異様にだるいので、探しに起きるのも、おっくうである。 「しゃあない、煙草でも、吸おうか?」彼は仰向けの侭、片手を伸ばすと、枕の辺りをまさぐった。と、カサッと、指先に、何かが触れる。感触からして、それは確かに、ハイライト(これは昭和の煙草の代表的な銘柄である)である。その横には、使い捨てのライターも、置かれてある。「おっと、在った、これで、頭痛も、さようなら?」茂はつまらぬ冗談を呟くと、煙草とライターとを引き寄せた。そして、煙草に、火を付けると、スウッと、一息、吸い込んだ。だが、喉の粘膜が妙に、張り付く。ピリピリと痛んで、気持ちが悪い。「チッ、こん畜生!」茂はゴロンと、俯せに成ると、すぐさま、灰皿で、揉み消した。 ふと見ると、灰皿の脇に、水差しが在る。どうやら、昨夜、置いたのらしい。「まだ、在るのかな?」小林は水差しを引き寄せると、左右に、二、三度、振ってみた。ピチャピチャと、湿った音が寂しく響く。少しは、残っているらしい。「ま、いいか?」彼は注ぎ口を銜(くわ)えると、一気に、それを飲み干した。乾いた喉には、ぬるい筈の水も、甘く感じる。彼はようやく、一息、付いた。だが、それで、万事、Okと、言うのでもない。仕事の進まぬ苛立ちが依然として、彼を苛み続けた。そして、言い知れぬ憤懣も、突き上げる。小林は上半身をやおら、起こすと、「ベーロ、ビンチョ!」と、怒鳴り散らした。別に大して、意味は無い。馬鹿野郎とビンタとが、頭の中で、絡み合い、訛っただけの事である。まだ、昨夜の酒が利いて居たのかも知れ無い。彼はその侭の姿勢で、「うーっ」と、唸ると、部屋の壁をジーッと、睨んだ。 だが、頭は依然、もやもやと、していて、気分も、全く、スッキリし無い。「何で、世間は俺の邪魔ばかり、するんだろう?」彼は自分勝手に、世間を呪った。だが、そんな自分も、情けが無い。「あー、やだ、やだ!」彼はバタンと、上半身をいきなり、倒すと、再び、布団へと、くるまった。こんな場合、クヨクヨするのは、体に良く無い。心臓も、やけに重たいし、まどろみに任せて、寝惚けて居るのが、無難な対処、と言うものだろう。彼は布団の中で、身体を伸ばすと、再び、寝入ろう、として、目を閉じた。それにしても、平日の昼寝は気持ちが良い。睡魔はすぐに、遣って来た。夢の欠片が脳裏を過ぎる。彼はその事に満足していた。 だが、何という間の悪さだろうか?熟睡をしよう、と言うその矢先、電話のベルがいきなり、鳴った。せっかくの安息が台無しである。「ああ、めんどうくさい、放っておこう」彼はしばらくの間、居留守を使って、布団の中で、頑張った。だが、けたたましい音は堪らぬし、鳴り止むつもりも、無さそうである。「この、ぼけ電話が!」茂はそう、悪態を吐くと、いきなり、上半身を起こして、電話を睨んだ。そして、渋々、受話器を取った。 電話は週刊渦潮の下山女史からのものだった。どうして、女史なのかは分からぬけれども、昔から、そう呼ぶ事に成ってるらしい。尖った眼鏡の所為かも知れ無い。「お客さんよ!待たせてあるの、来られるんでしょ?」女史は早口で、そう、言った。電話の主は海淵、と名乗ったらしいが、心当たりは全く、無い。時折、舞い込む脅迫状が茂の脳裏を過ぎって行った。「でも、どんな人です?心当たりが無いんですけど」「そうねえ、田舎の普通のおじいさん、て、とこかしら?あなたで無いと、話が出来ないって言うのよ、思い詰めた感じもするし、気に成るの、早く来て?ひょっとすると、特ダネかもよ?」「ん?特ダネ?」茂はその一言で、目が覚めた。老人がアパートでは無く、編集部を訪ねた事を考えるなら、女史のその推察は当たって居る様に思われる。小林はすぐさま、家を飛び出した。 小林が編集部に着くと、下山女史が目配せをして、来客用に仕切られた一角を指で、示した。覗いてみると、痩せ形で、ごま塩頭の老人が一人、ぽつねんと、腰掛けている。用件などは分からぬけれども、どう見ても、ただの老人である。小林は一応の観察をし終えると、「お待たせしました」と、呼び掛けた。と、心持ち丸い老人の背がバネ仕掛けの様にビクッと、動く。そして、クルリと、振り向くと、茂の顔をしげしげと見て、沈痛な面持ちで、頭を下げた。その表情には、不安と疑心が混じった様な、複雑な心理も、読み取れる。その理由は無論、知らないけれども、どうやら、深刻な話らしい。何故かは知らないが、茂の腰が、一瞬、引けた。 老人の赤銅色に焼けた肌には、深い皺が刻まれて居る。その所々には、老人に特有のシミも、浮き出している。だが、外見上、細身の体にも関わらず、その風貌はある種の力強さも、漂わせている。磯の香りがフッと、した。老人が言った。「ああ、小林さん、つうのは、あんたかね、ワシ、海淵というだが、話を聞いて貰いたいんだ」如何にも、浜言葉風のイントネーションである。だが、この何の変哲も無い老人に、どんな問題が在るのだろうか?「で、どの様なお話でしょう?」茂はさりげのない口調で、その様に、老人の話を促した。 だが、老人の態度は妙である。しばしば、上目で、茂の顔を見るものの、何故か押し黙って、モジモジしている。どうやら、込み入った事情が在りそうなのだ。小林は煙草を銜えると、箱から一本、覗かせて、「どうぞ?」と、老人の前に、差し出した。と、老人が、「いや、わしは」と、言って、押し戻す。「ア?失礼、吸わないんですね?」小林は慌てて、銜えた煙草を口から外すと、傍らの灰皿で、もみ消した。と、老人が言う。「イヤ、ワシはこれだから」そして、腰の辺りから、細長いキセルを取り出すと、刻みを摘んで、捻込み始めた。小林が言った。「ところで、海淵さんはどちらから、いらっしゃったんです?随分と、日に焼けられて居られますが」「ああ、ワシ、漁師だもんで、妻良、つうて、分かるかねえ」だが、小林は其処を知っていた。「ああ、彼処ですか、駿河湾の、確か、伊豆半島の先の方でしたね、学生時代ですが、旅の途中に立ち寄りました、海が綺麗で、驚きましたよ!」「ああ、そうかね!知って居たかね!」老人がニコッ、と僅かに、微笑んだ。 だが、やはり、老人は妙である。世間話はするものの、肝心の話は明かさない。何かの迷いが在るのらしいが、小林は少し、苛立っていた。「そう、大した話では無いのかも知れ無い、お引き取りを願おうか?」だが、話の内容が分からぬ内は、やはり、気分も、落ち着かない。小林は老人の心が開くのを辛抱強く、ひたすら、待った。と、十分ほども、経ったのだろうか?老人が一瞬、沈黙すると、居住まいを正して、話し始めた。「いや、やっぱり、話さにゃならん、頼みが在るんだ」 「はあ、何でしょう、私に出来る事でしたら、お力に成りますよ?」茂はそう、話を受けた。すると、老人が少し、上目と成った。「けど、あんたを信用しても、良いのかね?ワシの喋った事は週刊誌に載せるんだろう?」と、言う。全く、煮え切らぬ年寄りである。茂は思わず、ムッと、した。だが、相手は何しろ、老人である。要領を得ぬのは、致し方ない。茂は怒りを堪えると、はっきりとした口調で、返事を返した。「いえ、海淵さんのお考えは尊重します、それはお約束します!」「うん、名前が出るのは、困るんだ」老人はそう、前置きすると、ようやく、ボツボツと、語り始めた。 その日、老人は気分が優れず、早めに漁を切り上げた。だが、家に戻ると、様子がおかしい。表の戸が僅かばかり、開いている。締め忘れでは無い。老人は何時も、施錠を確認して、鍵は所定の場所へと、隠して在った。誰かがそれを盗み取って、忍び込んだのに違い無い。「何で、こんな貧乏所帯に?」老人はソッと、引き戸を開けると、中の様子を覗き見た。と、土間の所に、ぼろを纏った人間が俯せに成って、倒れている。動く様子も、窺えない。「行き倒れか?冗談じゃあ無いぞ、こんなところで・・」老人は顔を見よう、と首を伸ばした。だが、黒っぽい頭巾に被われて、男か女かすら、はっきりし無い。「死んで居るのじゃあなかろうな?」老人は戸口に在った箒を掴むと、怖々、側へと、近付いた。そして、箒を逆さにすると、柄の先端で、及び腰と成って、つっついた。だが、やはり、そいつは動か無い。「どんな奴なんだ?」老人は少し、大胆に成ると、箒の柄を頭巾の端に引っ掛けた。そして、少し、横にずらすと、頭巾が捲れて、顔が半分、現れた。 だが、これはどうした事なのか!老人が其処に、見たものは、やつれ果てた康夫であった。「あ、康夫じゃないか!」老人は一瞬、絶句した。顔の色は青白く、無残なまでに、痩せている。老人は咄嗟に、康夫を抱きかかえると、息の有、無、を確かめた。幸い、康夫は息をしている。老人は康夫に、毛布を被せると、すぐさま、消防署へと、電話した。そして、救急車が到着すると、町の病院へと、向かったのである。だが、其処では、対応が出来ないらしい。康夫は直ちに、富士市の病院へと、送られた。あのツアーで、康夫が居なく成ってから、既に、一年余りが経過していた。 幸い、康夫はその一命を取り留めた。医者に聞いた処では、極度の栄養障害が認められるらしい。昏睡の理由を問うと、医者は、「肉体的な疲労に、神経の極度の疲労も、重なっている、家に戻って、安堵した事で、それが一気に、出たのだろう」と、言う。意識は未だ、戻らぬけれども、医師はその回復を約束している。老人はひとまず、安堵した。だが、康夫に、何が在ったのだろうか?何処で、何をして、居たのだろう?あの奇妙な頭巾と出で立ちは一体、どうした事なのか?老人には、酷く、気に成った。「けど、ワシ、そんな事はどうでも、良かったんだ、康夫は戻って来た、それだけで、良かったんだ!けど」老人は咳き込む様にそう、述べると、悲しそうに、頭を振った。 康夫は二日ほどで、意識を戻した。だが、元の康夫では無かったのである。「ワシは悔しくて、仕方なかった、何で、康夫があんな事に・・」老人の眼が微かに、潤んだ。意識を回復した康夫は、気が触れていたのである。 だが、小林はどう、言葉を掛けたものか、戸惑っていた。下手な慰めなど、してみても、歯が浮きそうで、恐いのである。老人が落ち着きを取り戻すのを、ひたすら、待つしか、仕方が無かった。そして、頃合いを見計らうと、言った。「お気持ちは、お察しします、でも、私に、何をしろ、と御っ者るんです?」成り行きからして、それは当然の問いではあったが、この場合、茂は既に、老人の想いを察知しており、それは確認の意味での問い掛けだった。 おそらく、康夫の狂気には、精神科医も、手を余して、匙を投げたのに違い無い。現に今、康夫は老人の家に居る、と言う。おそらく、病院での投薬は治療の為ではなく、康夫をおとなしくさせるのが、目的であった。その為に、康夫は生きる屍に、成り掛けていた、のに違いない。医者から、それなりの説明はあったのだろうが、老人は納得など、しなかったのだろう。それで、業を煮やして、連れ帰ったのものと、想像された。 老人が小林の記事を読んだのは、おそらく、その様な時だった。それは無論、サンツーリストのオカルトツアーについての記事である。「言代主の祟りか!」と、言う見出しが、老人を引き付けたのに違いない。それで、彼は藁をも掴む、そんな想いで、遣って来たのに違いないのである。老人が言った。「あんたなら、何か、知ってるんじゃ無いか、と思って・・どうだろう、どうすれば、直るのか、分からんだろうか?」そして、探る様な目で、小林を見た。だが、茂の記事には、取材による裏付けが不足している。まして、老人の意に添える情報などは、皆無、と言っても、良いのである。茂は少し、やましい気分に陥った。「だが、どうしよう?」何故かは知らないが、うんざりとした気分にも、させられる。茂は思わず知らず、天を仰いだ。 だが、此処まで、さんざん、聞いて置いて、何も知らぬ、では通らぬだろう。そして、このまま、彼を帰すのも、フリーライターとしては、もったいない。康夫の事を聞き出す為にも、上手く付き合うしか、無さそうなのだ。だが、どの様に、答えたなら、老人は納得するのか?「そうですねェ、力に成れるか、どうかは、分かりませんが、もし、よろしければ、もう少し、詳しい話をお聞かせ頂けますか?」小林は取りあえず、そう、言って、老人に話を促した。 老人は最初、確かな答えを期待していたらしく、少しばかり、不満そうであったが、小林の対応が、良かったのだろうか?彼は思惑通り、今までの経緯を詳しく、語った。だが、その話は酷く、混乱しており、事実か、どうかは、怪しい様に、思われる。康夫の狂気の有様や、康夫の生き霊の話など、とても、まともとは思えない。「これは祟りか、何かに、違い無いんだ、あんたも、そう思うんだろう?」老人は真面目な顔で、そう、言った。 老人に取って、康夫の狂気は大変なショックだったのに違い無い。それが元で、惚けて仕舞い、あらぬ妄想に捕らわれた。おそらくは、そんなところが真相なのではないのか?自分の記事にも、一端の責任は在るのかも知れ無い。「困ったな、どうしようか?」茂は一瞬、返事に窮した。だが、妙である。影浦が著した祟り神の悲劇と、老人の妄想とも、思える今の話が、小林の心の中で、ひとつの様に、絡み合う。そして、それはあたかも、現実であるかの様に、小林の脳内を巡り始めた。「本当に、これは祟りなのか?馬鹿な!有り得ない」茂はチラッと、老人を見た。 |
|||||||
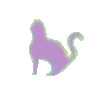
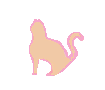
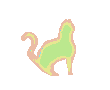
| |||||||
| Cotosiro Home | |||||||