|
病ではない病 ・ 発達障害へのより良き理解とは? 野口博正 |
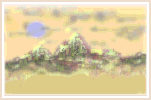
|
||||||||||
|
最近、発達障害、と言う言葉が大阪の呆れた条例案などの為に、しばしば、聞かれる様に成った。其処で少し、この症状について、調べてみた。 |
|||||||||||
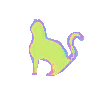
|
しかし、一見、明白に思える発達障害という言葉は自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害などの症状を示す総称らしく、また、その原因には、様々な先天的要因が関係しており、症状も様々であるらしいので、一律な原因を見出す事は難しいらしい。 ちなみに、後天的な要因によって、同様の症状を引き起こす場合もあるが、その場合は発達障害とは言わないらしい。 其処で、最近では、この発達障害は「その人間の本来的な個性である」と、考えられているらしい。つまり、発達障害という症状は一定時期、あるいは生涯、ケアーを必要とする個性である、と言う事らしい。 考えてみると、この考え方は納得出来る。 | ||||||||||
|
我々、人間は、いや、全ての生物は、此の世に生まれ落ちてから、様々な経験をしながら、成長して行く。しかし、その成長の在り様は、個々人によって、様々に異なる事は、既に、我々も、知っている。 そして、身長の伸びる時期も、それぞれに応じて、少しづつ、違っている。身長が伸びにくい人間もいれば、すくすくと育つ人間もいる。無論、そこには、環境も関わっているが、その人間の先天的要因が深く関わっている事も確かである。 |
|||||||||||
|
私見ではあるけれども、この観点から、発達障害を考えるなら、それは病と言うよりは、やはり、個性と考える方が良い様に思われる。つまり、ケアーが必要と思われるほどの症状について、発達障害という言葉が使われる、と考える方が良さそうである。ならば、その欠点に気付いて、ケアーをすれば、譬え、その障害が何であれ、その障害を乗り越えて、成長をする余地は十分にある。努力する価値は十分にある。 ただ、その場合でも、一般的な子供達の成長の仕方、成長の度合い、成長の時期とは、大きく異なる、と思われる。また、多くの場合、発達障害の症状は知的レベルなどの精神活動の極、一部に於いて現れるらしい。 たとえば、具体的な意味づけの出来る事物については、普通に理解できるけれども、単なる数字への理解は難しい、などという事例も、あるらしい。すると、何も知らない他人は、「何だ?こいつは!」と言う事に成りがちである。 |
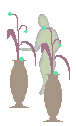
|
||||||||||
|
社会で活動する場合、この種の問題が多くの誤解を生む事も、想像するに難くはない。怠け者、横着者、とレッテルを貼られる事もあるかも知れない。これは当人に取って、非常に辛い事だろう。従って、発達障害の改善の為には、社会的な理解が是非とも、必要である。 また、当人が自身の成長の過程で、その様な自分に向き合う事も必要だろう。だが、この「向き合い」は他律的なものであっては為らない。社会が出来る事は、その様な「向き合い」をなし得る環境を整える事だけである様に思われる。 | |||||||||||
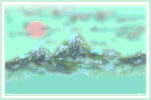
|
発達障害を持っているとしても、それは一個の人格であり、その事は一般の人間と変わらない。また、一般的な人間達も、様々な問題を抱えながら、生きている。あるいは、さしたる問題もなく、健やかに生きている幸運な人間もいるかも知れない。しかし、それは例外中の例外だろう。悩ましい重大問題を抱える人間は数多い。そして、その問題は多くの場合、個別的な問題であり、その悩みは当人にしか、分からない事が殆どである。我々、人間はそれらの問題と向き合う事で、自分なりに成長して行く。それが人格を持った人間のありのままの姿なのだ、と思う。 | ||||||||||
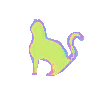
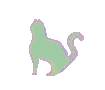
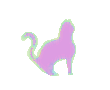
| |||||||||||
| Cotosiro Home | |||||||||||