|
第二章 第一話 |
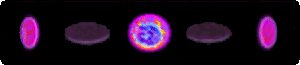
|
|||||||||
| 古代の怨念 | ||||||||||
|
「クソッ、どう成ってるんだ?」熊野は高速道路のただ中で、しきりと時間を気に病んでいた。 宇都宮での仕事が長引き、帰途に付くのが遅れたのだが、この渋滞は普通ではない。「衝突事故かな?」 だが、何処まで行っても車の列で、それらしき様子など窺えぬのである。理由は全く分からぬ侭に苛立ちだけが募って行った。 しばしば目線は時計へ行くが、針は冷酷に時を進める。今頃、宮城は羽田に降り立ち、手荷物でも受け取っているだろう。 影浦も一緒の筈である。「何とか成らんのか!」熊野はハンドルを握り締め、人差し指でしきりと叩いた。 彼の車にクーラーは無い。ノロノロ運転では風も入らず、真夏の渋滞は最悪である。 蒸し風呂の様な都会の暑さが彼の苛立ちに拍車を掛けた。だが、反面、言い知れぬ興奮にも捕らわれる。 あの銅鐸の発見と古代の怨念、そして、それを体現する祟り神、言代主の出現、熊野は今、その渦中に我が身を置こうとしていた。 熊野は約束の時間から三十分ほど遅れて、大学の門をすり抜けた。控え室に駆け込むと、宮城が窓際に突っ立っている。 「やあ、済みません、お待たせしました!」熊野は首を伸ばして呼び掛けた。 だが、影浦の姿が見当たらぬ。「影浦さんは、どうしたんです?」熊野の顔が少し曇った。 宮城が言った。「ああ、食堂にいる、直に戻る」「あっ、そうですか、で、どうです?彼の様子は ・ ・ 」 「うん、落ち着いたみたいだ」熊野は昨夜の電話連絡の折り、影浦の反応は聞いていた。 状態が落ち着か無ければ予定を変える事にもしていたのである。 だが、宮城の言葉通りなら、そのような心配など無さそうだった。そして、数分後、入り口のドアがスッと開いた。 影浦である。目線が会うと、幾分、緊張の面持ちで懐の名刺入れを取り出した。 そして、名刺を交換し、型どおりの挨拶を済ませると、早速、本題へと入って行った。 だが、以外にも、最初に口火を切ったのは影浦である。 「これはフィクションとして書いたのですが、少し説明をさせて下さい」 机の上には、数冊の分厚いファイルが乗せられている。彼はその一冊へと右手を伸ばした。 | ||||||||||
|
二年ほど前、影浦は新しい題材を言代主命の悲劇性に求め、その構想を練りつつ在った。 墳墓の特異な様相が創作意欲を触発したのである。既知の情報、資料に加え、最新の情報も其処に組み入れ、自らの考えを纏めて行った。 幸いにも影浦には学生時代からの友人、三木五郎が居る。京同大学の教授をして居り、その発掘にも関与をしていた。 影浦は発掘当初、一度ではあるが、墳墓を見て居る。だが、後は専ら三木の情報を頼りにしていた。 そして、その情報は極めて刺激的なものだった。今までの考古学の常識が到る処で翻っている。 |
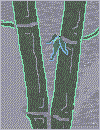
| |||||||||
|
特に小山の頂から発掘された奇妙な形の銅鐸は極めて特異な存在だった。
表面には模様が無く、変わりにぎっしりと文字らしき物が刻まれている。そして、銅鐸の周りには小さな石組みが認められた。
銅鐸を四角く囲み込み、しっかりとした造りで埋め込まれている。
銅鐸は普通、打ち捨てられた様な状態で見付かる事が多く、この様に石組みに守られた銅鐸などは前代未聞の発見だった。 何等かの特殊な意図も推測される。そして、不可解な謎は他にも在った。 その小山は頂以外、全てが自然の儘なのである。墳墓ならば在る筈の石室なども認められ無い。 当初、学者達は墳墓とする事には慎重だったが、当然の態度とは言えたのである。 また、その周辺からは縄文時代の土偶や土器が大量に発掘をされていた。埴輪では無いのである。 古い地層から掘り出して、埋め直されたものなのらしいが、副葬品として埋められた筈の銅鏡や鉄剣など、 期待をされた古代の遺物は全く出ては居なかった。不可解極まる墳墓と言えた。 当初、銅鐸の文字の判読は中央の大きく刻まれた箇所に留まっていた。 其処には、「言代奴左、神伊成坐而隠身也、故、此母岩者、立奉言代奴左神伊」と、刻まれている。 「コトシロヌサ、カミイトナリテミヲカクス、カレ、コノモイワハ、コトシロヌサノカミイニタテマツラン」と、でも読むのだろう。 言代奴左が神と成って身を隠したので、此の母岩(モイワ)、つまり、小山を言代奴左の神に捧げる、と言うのである。 あらゆる状況から判断をして、この言代奴左が記紀に見える言代主命と思われた。 とすれば、これは途轍も無く大きな発見である。学者等は他の部分の解読に持てる力を傾けた。 だが、文字が小さく、消えた部分もかなり在る。判読は困難を極めたが、エックス線など科学の粋を結集し、 地道な作業を続けて行った。そして、判読がある程度、進んで来ると、文言の内容もはっきりして行く。 言代主をあの母岩に祭る事と成った経緯が壮大なる叙事詩として、極めて詳細に描かれて居たのである。 神話上の人物が、その一族と共に実在をした、その可能性をも明示して居る。 また、その内容のかなりの部分は記紀の神話とも重なったのである。学者達は色めき立った。 | ||||||||||
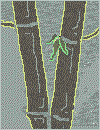
|
だが、叙事詩によれば、言代主と建御名方(タケミナカタ)は大国主の子では無いのらしい。
事実は神話とは幾分、違って、彼等はそれぞれの部族の長らしかった。だが、それは単なる叙事詩では無い。
敗者の立場から描かれた悲劇に彩られた古代史だった。
さて、その叙事詩によれば、当時、大和からの圧力は年を経る毎に強まっていた。 多穴牟遅は言を左右に大和の圧力を交わしたが、大和の武力は強大である。更なる圧力を以て要求して来た。 打つべき策はもはや無い。多穴牟遅は止む無く、二人の実力者、言代主と建御名方とに国譲りの方針を示すのだった。 | |||||||||
|
国を譲る代償として、国津の部族の安全と祭事の存続を持ち掛ける、と言う。
だが、二人には承伏し難いものだった。一旦、国を譲ったならば、必ずや反古にされるのに違い無い。そんな予感も在るからだった。
他の国津の多くの部族もその心情は同様である。大勢は拒否の方向へと動いて行った。
だが、彼等の保護者の筈だった多穴牟遅は大和と内密の取引をし、更に説得を試みた。 全ての部族を巻き込んだ激しい議論が交わされたのである。だが、結局、会談は決裂し、不穏な空気が畿内を覆った。 多穴牟遅への猜疑心、そして、鬱積をした大和への憎悪の念の故である。 だが、これ以上の混乱を招いたならば大和が黙っては居ないだろう。業を煮やし、攻め入って来ぬとも限ら無い。 交渉の余地など無く成るのである。無条件降伏の幻影が多穴牟遅の心を嘖んだ。 此処は反対論を押さえ込み、混乱は早急に収拾をせねば為らない。 その為には混乱の元凶、言代主を押さえる事が必要欠くべからざる条件だった。多穴牟遅は難しい決断を迫られた。 だが、多穴牟遅は極めて老獪な政治家である。多くの策略を巡らせて言代主を追い詰めた。 祭主の権限を徐々に剥ぎ取り、影響力を奪ったのである。国譲りへの極めて重い一歩であった。 無論、言代主は抵抗し、同調する部族も少なく無かった。大穴牟遅の遣り方に対して公然と批判をする者も現れたのである。 大勢に於いて、多穴牟遅の策謀は成功したが、命までをも奪われ兼ねぬ危うい状況とも成るのであった。 たが、彼は大和の軍を自国へ引き入れ、力をもって、其処に対した。無論、言代主等の抵抗は激化する。 平和だった古代の畿内はその全域が戦場と化し、屍の山を築くのだった。 しかし、言代主等の劣勢は明白である。そして、多くの裏切りがその様な趨勢に拍車を掛けた。 建御名方は屈服し、言代主も追い詰められる。船を漕ぎ出し、転覆させて、海の藻屑と消えたのだった。 言代主は自殺する前、何かの予言を残したらしいが、それは銅鐸には書かれて居ない。 ただ一行、時至らば明かされるだろう、と、妙に謎めいた一文が僅かに見えるだけだった。 | ||||||||||
|
影浦はこのような銅鐸の記述から、一つのインスピレーションを受け取った。
言代主は縄文期からの古い宗教形態を守る最後の祭主だったのでは無いのか? つまり、「言代主」は個人の呼び名では無く、
祭りを司る者の称号だったのでは無いのか?そう考えたのである。
言代主の最後の言葉は、その祭りを永遠に消滅させた大和への、 呪いの予言なのに違い無かった。そして、其処には、言代主の旧支配者としてのプライドも垣間見られた。 おそらく須佐之男の登場以前、畿内に勢力を張る言代主の一族は数多くの部族間闘争に苦しんでいた。 無論、須佐之男は多穴牟遅の神祖であるから、大和が畿内に現れる、 |

| |||||||||
|
ずっと以前の事である。
其処へ銅鐸の文化を持つ、須佐之男(スサノオ)の一族が現れて、言代主の一族に力を貸した。
畿内の秩序を回復させて復興の礎を築いたのである。八岐の大蛇の伝承はその象徴的叙述と思われる。
伝承中に見える手名椎(テナヅチ)、足名椎(アシナヅチ)は言代主の一族なのに違い無かった。
さて、畿内の部族間の勢力図は須佐之男のその様な出現で、其処から大きく動き始めた。 須佐之男一族の多穴牟遅、つまり、後の大国主の時代には、その力は言代主の一族を遙かに凌ぎ、 逆に言代主等の古い部族は徐々に力を無くしたのである。そして、その勢力範囲は裏日本へと押し込められる。 多穴牟遅の力は絶大と成り、彼は畿内とその周辺部族の保護者、支配者として君臨をする事と成るのであった。 多穴牟遅は古代に於いて、日本の統一を成し遂げた最初の王でも在ったのだろう。 古事記に於いて、多穴牟遅命が「大国主命」の名を賜った、と在るのは、その辺の事情を表して居るものとも考えられた。 つまり、「大国主」は、「言代主」と同様、固有名詞では無く、支配者の称号、として与えられた敬称であるのに違い無かった。 さて、そうして政治的権力を手に入れた多穴牟遅は、三輪山の大物主命を自らの神と成して奉り、宗教的権威をも手中に収めた。 ただ、旧来の祭祀権は依然として言代主の一族に帰属している。その人口比率では言代主一族の様な土着の部族が圧倒的に優勢であったし、 須佐之男の一族は言代主一族とは姻戚関係に在った。 つまり、彼等には言代主一族の血が流れる故に、多穴牟遅としても、その祭祀権の扱いに付いては、 慎重に成らざるを得なかったのである。だが、その後、軍事大国として登場して来た倭、つまり大和の東征でその様な事情は 一挙に変わった。部族の証として残された最後の砦、神々すらも奪われ兼ねぬ、そんな状況へと陥ったのである。 政治的屈服はともかく、自らの神々を否定され、天津の神を崇める事は古い部族には耐え難かった。 その敗北は誇りと魂との喪失であり、屈辱の何ものでも無かったのである。その故にこそ言代主は大和の軍勢に刃を向けた。 | ||||||||||
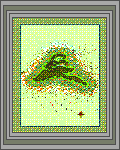
|
無謀なる挑戦を為したのだった。だが、奇跡は起こらず、彼等は敗れた。
その中には消滅する部族すら在ったのである。然も無くば、敗者の屈辱に甘んずるのか、北に逃れるしか道は無い。 時代は下るが、その図式は蝦夷(エミシ)の移動とも相通じ、在り得る事と思われた。 おそらくは、古い国津の多くの部族が北上をしたのに違い無い。 だが、銅鐸の記述に拠るならば、言代主だけは其処に残った。おそらくは、神々の座す古里を捨て兼ねたのに違い無い。 いや、怨霊と成っても守ろう、と、そう誓ったのに違い無かった。 事実、彼は其処で死んでいる。恨みを持って自殺したのである。 | |||||||||


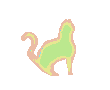
| ||||||||||
| Cotosiro | ||||||||||