|
第九章 第二話 |
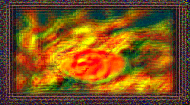
|
||||||
|
背中合わせの魔界 |
|||||||
|
押知と坂崎は話を終えると、膝をずらして彼らの間隔を少し広げた。そして、その後ろに正座をしている若い娘に目を遣った。 物腰などから育ちの良さは窺えるものの、幾分かの陰りが感じ取られる。 影浦が視線を向けると、彼女は自分の生い立ちをおずおずとしながら語り始めた。 彼女は名を野辺地京子と言い、青森の旧家に第一子として生を受けた。両親が結婚をしてから六年目、ようやく恵まれた子宝である。 そして、第二子はなかなか作れず、両親の穏やかな愛情は京子の一身へと注がれた。 だが、甘やかす事は決して無く、道理を諭して、育てたのである。その所為だろうか? あるいは、持って生まれた素質だろうか? 一人っ子に特有の問題も表立っては現れず、彼女は極めて穏やかな素直な子として育ったのである。 そして、両親も、そんな彼女の成長を信頼を以て見守った。 だが、彼等には、たったひとつだけ悩みが在った。家を継ぐべき男子がどうしても出来ぬのである。 いきおい、両親の期待は京子に向かった。「医者か弁護士を養子に迎え、その者に跡を継がせよう」彼等はそう考え始めた。 そして、京子も素直にそれを受け入れた。 京子は地元の大学を卒業すると、父の勧めで、青森の役所に就職をした。所内の評判も極めて良い。 二、三年もすれば養子も決まり、野辺地家と京子の行く末も安泰と成る、かにも思われた。だが、何処に間違いが在ったのだろうか? 見えざる何かが忍び寄り、彼等の運命を狂わせ始めた。 そして、当初、それは京子の不可解な行動と成って現れた。 彼女はある日、突然、上司に辞表を出して、そのまま、家へと戻ったのである。母親にすら何の相談もして居ない。 父親が役所の知人から聞かされて、初めて知った有様だった。知人に拠れば、辞表は押さえてある、と言う。 | |||||||

|
何かのへまでもしたのだろうか? だが、仕事上のトラブルも無く、人間の関係も良好だ、と言う。
両親は京子に理由を問うて、その説得に躍起と成った。だが、彼女は全く耳を貸さない。両親はひどく当惑し、
「何故、辞めるのか!」と、京子を責めた。
だが、彼女自身、辞める理由など分からぬのである。「とにかく、辞めたい!」再三の説得にも関わらず、京子は結局、役所を辞めた。 京子としても、自分の行為が問題なのは承知している。酷く惨めで後ろめたい。両親の話も理解は出来た。 「なのに、自分は止めて仕舞った、何故なのか?」彼女は鬱々として考え続けた。一つでも良い。 まともな言い訳を探し当て、分かって欲しい、と願ったのである。 だが、妙だった。「全てが忌まわしく疎ましい」そんな想いしか分からぬのである。 まともな言い訳とも思えぬし、自分自身も納得し兼ねた。親の視線も恐ろしい。 ひたすら部屋に閉じ籠もり、彼等の呼び掛けにも応じなかった。 | ||||||
|
だが、両親はそんな彼女の行動を自分等への反抗と受け取った。そして、心の変調を見逃したのである。 いや、おそらくは、認める勇気が無いのであった。「しばらく、ソッとして置こう、一時の迷いなのに違い無い」 彼等は心配をしながらも、時間の解決する事を心密かに期待していた。 だが、京子には、そんな両親の切なる願いも、まるで通じては行かぬのである。彼女の心は内向し、その殻は益々、堅さを増した。 両親の鋭い眼差しが彼女を嘖むからだった。いや、もしかすると、それは京子の錯覚だったのかも知れ無い。 両親の困惑の表情に、幾分かは紛れていたのかも知れないが、彼等に、そんな意識など在っただろうか? だが、少なくとも当時の京子には、そんな具合に感じ取る異常な心理が働いていた。 両親への負い目が四六時中、彼女を苛むからだった。京子はジッ、と蹲り、耐えて居るしか仕方が無かった。 そして、何故だろう?その苦しみは沈殿し、怪しい何ものかも産み始めていた。 「自分が此処にこうして居るのは世間がそうさせたからに違い無い、もしかすると、両親までもが関わっている」 そんな疑心が自然と湧いて、恐ろしい憎悪を呼んだのだった。「自分を責める気持ちが、そう思わせるのだろうか?」 時には、そうも思ってみるが、彼女の何かが退ける。京子は一人、想い悩んだ。 相談相手など端から居ない。いや、他人に話すのは怖かった。疑心暗鬼が邪魔をした。 見知らぬ他人の視線すら、今の京子には恐ろしい。彼女はひたすら部屋に籠もって、鬱々とした日々を過ごしたのである。 食事すら、家族が寝静まったのを見済まして、 こっそりと取る有様だった。生活のリズムは益々、乱れ、不眠が彼女を悩ませ始めた。そして、幻聴も始まった。 | |||||||
|
ある日、京子は夢を見た。真っ暗な闇に佇んでいる。透明感の殆ど無い、濁ったような暗闇だった。 闇の遙か向こうから、微かに旋律が伝わって来る。 異様に寂しげで陰湿な不気味な感じの音色だった。 「笙の笛だわ?」怖くはあったが、どこかで聴いた旋律でもある。彼女はじっと聞いていた。と、それは越天楽の旋律である。 だが、変調して居る所為であろうか? 雅な風情など感じられない。 むしろ、それは薄気味悪く、狂おしいほどにもの悲しい。 「魔性の笛に違い無い!」凍て付くような冷気と孤独が京子の心を苛んだ。 闇が微妙に蠢いている。京子は一瞬、邪念を感じ、恐怖の念に捕らわれた。 だが、眼は闇を凝視して居る。闇は次第に影を為し、奇怪なる造形を作り始めた。 |
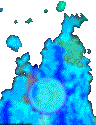 | ||||||
|
見ると、それは日本画の襖絵の様な這い松である。闇にクネクネと幹をくねらせ、京子の方へと迫って来ていた。
しかし、これはどうした事か? 奇怪に蠢くその松は一本の様にも思えるし、数本の様にも思われる。
暗がりの中で蠢く度に、あるいは解け合い、あるいは分離し、怪しい舞を舞うのであった。
「魔物の化身に違い無い!」恐れが身体を硬くした。
松の怪しげな蠢きは明らかに怨念の舞だった。だが、その松が果たして何者で、如何なる恨みを持っているのか、 京子にはまるで分からなかった。眼は松に釘付けと成り、恐怖に怯えるだけである。 不気味な松はその間も闇に溶け込み、あるいは現れ、京子へと向かって蠢き続けた。 恐ろしい邪念が京子を襲う。京子は邪念に圧倒されて、ジリッ、と一歩、退いた。と、奇怪である。 やおら生暖かい感触が京子の背中から張り付いた。ねっとりと京子に身体を押し付ける。 「松だわ!」京子の直感が囁いた。だが、妙である。彼女の眼は前方に松の姿を確かに見て居る。 なら、背後の魔物は何者なのか? 京子には既に察しも付いていた。松は魔物の仮の姿で、背後に居るのが実体なのだ。 「だが、その実体は何者なのか!?」京子は自分を叱咤して、「誰なのーっ!」と、大きく叫んだ。 と、背後の気配が僅かに怯む。 | |||||||
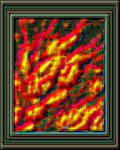
|
不気味な気配でニタリと笑うと、その儘、スウッ、と消え失せた。
気が付くと、不気味な闇が広がっている。凍り付くような恐怖が襲い、彼女は夢から解放された。
だが、妙である。目覚めた後も松の気配は漂っている。「夢では無い!」京子は咄嗟に呟いた。 だが、口の無い松が笑うだろうか? 京子は見ても居ないのである。心が感じただけだった。 「ただの夢よ、馬鹿馬鹿しい ・ ・ 」彼女は自分にそう言った。 だが、あの暗闇で見た不気味な舞は、そして、背後から襲った異様な気配は実際の体験そのものである。 「やはり、何者かが此処にいる!」此の儘、もしも寝入ったならば、必ずや夢に現れて京子を襲う筈だった。 京子は眠らずに朝を迎えた。 | ||||||
|
だが、それはその日だけでは無かったのである。陰湿極まる幻魔の舞は毎日のように京子を襲った。 彼女は昼間、うたた寝し、夜は殆ど眠らなかったが、夢の魔物は狡猾である。僅かなまどろみを見済まして、執拗に彼女を責め立てた。 眠る事は許されず、京子の不眠は悪化した。 「魔物など、居る筈が無いわ!」彼女は時折、自分に言って、合理的説明も試みた。恐れの生み出す錯覚なのだ、と。 だが、心はそうは思ってくれない。魔物は益々、露骨に現れ、彼女の現実へと浸み出し始めた。 京子のか細い神経は危うい所にまで追い込まれていた。 だが、両親は京子が其処に到っても、彼女の異変には気付かなかった。結局は何も為し得ずに自らの混乱をも深めたのである。 互いの心はバラバラと成り、京子のあからさまな反抗も其処に至って現れ始めた。 そして、何故だろう? 彼女の不可解な反抗は父に対して向けられた。京子自身、理由の分からぬ反抗である。 両親の戸惑いは当然だった。そして、彼らは考えあぐね、考える事すら止めて仕舞った。 しかし、そんな傍観は異様な苛立ちを産み出して、ついには不可解な京子への恐ろしい憎悪へと変わったのである。 些細な失敗を口実に手酷い罵声が京子に飛んだ。だが、両親の突然の変貌は京子に取って、予期のし得ぬ出来事だった。 「あの優しかった両親が何故だろう? 不甲斐ない自分を何とかしようと、わざと冷たく当たるのだろうか?」 だが、酷い仕打ちが重なると、そんな風にも思えぬのである。僅かな支えも失って、彼女の孤独は深まった。 抜け殻のように無気力と成り、死に場所を求めて、家を出た。 | |||||||
|
ちょうどその頃、札幌にいた坂崎は強い念波を察知した。凍り付くように寂しげで、すすり泣くようにも思われる。 救いを求める魂が無意識に発した念だった。いや、むしろ念の暴発、とでも言うべきだろうか? いわゆる念波とは言い難かった。 発信者は明らかにそのような能力には気付いて居ない。これは危険な事だった。 この儘、これを放置したなら、自らの念で滅び兼ね無い。悪しき霊や物の怪に飲み込まれぬ、とも限ら無かった。 坂崎は押知に連絡を取ると、早速、救出へと動き始めた。 押知等が発信地点を確認したのは渡島半島の先端部である。 だが、彼等が其処に向かう頃には別の場所へと移動をして居た。発信者はふらふらと、所在を変えて居るのらしい。 試みに発信者の足跡を地図で辿ると、それは確実に北上していた。 ならば、札幌は通るだろう。 其処で発信者を待ち受けるのが最善の策と思われた。 |
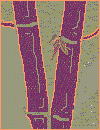
|
||||||
|
その頃、京子は死に切れず、当ても無しに放浪していた。家族の仕打ちに絶望した時、彼女は確かに死のう、と思った。 だが、それは魂が萎えたのでは無く、逃避の心理の故だった。あの魔物や薄情な家族、そして、不甲斐の無い自分など、 一切の疎ましい物からの逃避なのである。 彼女に取って、生の放棄はそのような逃避の突き当たる論理的な帰結であった。彼女は救いを求めて家を出たのである。 だが、それもいよいよ限界だった。手持ちの金も底を突き、死への誘惑は深まっている。 坂崎に札幌で保護されたのは彼女に取っては幸運だった。 京子は押知の牧場で魔物の正体を知らされた。それは精神錯乱の為の幻では無く、心的実在を現象化させ、 彼女が此の世に送ったのである。自分すらも気が付かぬ念の力の故だった。 そして、その実在とは彼女の場合、父親などに代表される日本の社会そのものだった。言い換えると、 彼女の精神に染み込んだ社会の裏面の想念である。だが、それは彼女の魂とは馴染ま無かった。 その故に、自分すら気の付かぬ葛藤が彼女の内面に生まれたのである。 彼女に取って、そのような相容れぬ想念はまさしく人格を持った敵だった。そして、まさにその事が魔物を産み出す力と成った。 逆に言えば、それは魂を守らんとして行った彼女の無意識の業なのであり、解決への方策でもあったのである。 | |||||||
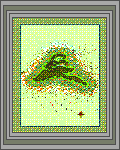
|
魂の抱える矛盾の多くは、社会の矛盾が精神に移植される事に起因をしている。だが、多くの人は生きる為、 その矛盾と上手く妥協をし、魂の葛藤からは逃れ得た。しかし、彼女の場合、その様な矛盾には気が付かず、 また、何の妥協も為され無かった。 その故に、就職という環境の変化が引き金と成り、遅ればせながらの葛藤が無意識の内に産まれたのである。 彼女は今、そのような敵対をする想念と睡眠中も戦っている。魔物が実在として現れた今、もはや妥協の余地など無かったのである。 魔物と戦う自分の姿を彼女は日夜、思念して、敵の正体を見つめ続けた。 そして、夢うつつに現れる忌まわしき幻魔と戦った。思念の効果は絶大である。魔物はやがて退散し、京子の精神も取り戻された。 元々が、彼女の生み出した魔物であるから、彼女の意志が其処に在るなら、当然の帰結ではあったのである。 |
||||||
|
だが、戻らぬものが僅かに在った。帰るべき家はもはや無い。京子の産み出した魔物の毒が両親の魔物を呼び覚まし、
彼等を虜にしたからだった。「全ては自分が悪いのだ」京子はそう自分を責めた。
影浦はその時、京子の話をある感慨を持って聞いていた。人間という存在は時として、多くの悪霊や悪魔に悩ませられる。 そして、それは殆どが自らとは相容れぬ想念の人格化をした存在だった。 つまり、内なる敵が実在として、彼女の世界に現れたのである。 釈迦やキリストの戦った、多くの悪霊や悪魔等も、更に厳しい内省が呼び覚ましたものなのに違い無い。 内なる敵を意識して自らの力で呼んだのである。 そして、それらと対決し、打ち勝ったのに違い無かった。 彼等の悟りは、その上にこそ成り立っていた。 だが、人はその事を余り知らない。また、その故に、ある種の真実には背を向けた。 自分に都合の良い真実だけで、丸く収まる小さな魂、それを保って行く事が彼等の無事な生き方だった。 彼等の思考が硬直するのも、この事を抜きにしては語れ無い。 受け入れ難い真実の一歩、手前で立ち止まり、引き返さざるを得ぬからだった。 其処を押して思考をすれば、抜き差しの為らぬ矛盾に陥る。真実を認めぬ彼等には、その様な危険が付いて回った。 そして、今、あの忌まわしき羽虫達が巷を覆い、イナゴの様に飛び交っている。偽りに満ちた魂は真っ先に餌食とされ、滅ぶのだった。 | |||||||


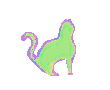
| |||||||
| Cotosiro | |||||||