|
第十二章 第四話 |
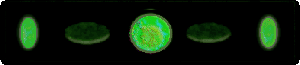
|
||||||
|
不信 |
|||||||
|
十日ほど前、道場に滞在する影浦に小林茂からの電話が在った。札幌の自宅に連絡を取り、この道場に居る事を 知ったのらしい。ある邪教集団に付いて話が在る、電話では話し難いので是非、会いたい、と言うのである。 だが、影浦は即答を避け、電話を切った。小林が食わせ者である事は宮城から聞いて知っている。 迂闊に話に応じると、妙な事にも成り兼ね無かった。影浦は小林の真意を探り始めた。 だが、数日後、小林の消息がプツリ、と途絶える。渦潮の編集部にも問い合わせたが、先方も困惑の表情である。 悪しき予感が脳裏を過ぎった。おそらく、小林の失踪は今回の用件に関わりが在る。危険を感じ、隠れて居るのか? あるいは、祈言宗の手にでも落ちたであろうか? いずれにしても、危うい状況とは思われた。 そして、その二日後、小林からの手紙が届いた。どうやら失踪の直前に投函をしたものと思われる。 海淵老人と康夫の事が事細かに説明をされていた。小林の失踪はやはり、この事に関わるのだろう。 早く連絡を取りたいが、行き方を突き止めるのには時間が掛かる。康夫の救出が優先された。 影浦に宛てた例の手紙が危険な影を落としたのである。おそらく、康夫はあの神殿で奴隷の様に使われていた。 その康夫と影浦との接触は祈言宗に取って、極めて危険な事態であろう。神殿の秘密が覚られぬ、とも限らぬのである。 もし、祈言宗がこの手紙の存在に気付いたならば、何を仕掛けるか分から無かった。 影浦は押知と京子に事情を話し、老人の家へと急がせた。 押知は小林の知り合いと偽って、老人の家に電話を掛けた。実際の経緯を話すのは複雑過ぎるし、 信じて貰えるとも思え無い。多少の嘘は致し方ない。彼は話が纏まると、京子を助手席に座らせて、早速、妻良へと車を飛ばした。 そして、妻良の標識を確認したのは夜中の九時を幾らか回った頃だった。予定よりは五十分ほども遅れている。 | |||||||
|
新月の夜で、曲がりくねった道筋でもあり、そうやたらとは飛ばせ無い。押知は標識に目を配り、慎重に車を走らせた。
大きなカーブを左に曲がると集落だろうか? 多くの明かりが密集し、辺りの風景を浮き立たせている。
妻良の街に違いない。漁船の明かりが港を照らして、立ち働く漁民を浮き上がらせた。
「わあ、何か、素敵ね!」京子がやにわに身を乗り出すと、感嘆の面持ちで夜景を眺めた。 道路を挟んだ反対側には商店や民家が建ち並び、柔らかい光を放射している。オレンジ色の一画が心にスッと染み込んで、 緊張感が少し和んだ。 |

| ||||||
|
だが、車はすぐに其処を抜け切る。街路灯もまばらと成って、闇が辺りを覆い尽くした。ヘッドライトの光線が夜道の白線に
反射して、闇にボウッと浮き立たせている。辺りの草木は闇に溶け込み、死んだ様に動か無かった。
異次元の世界にでも迷い込んだ様な、不思議な気分にも捕らわれる。 「ん? 此の道、さっき、通らなかったか?」 そんな錯覚にも捕らわれた。多分、疲れの所為だろう。押知はふっ、と我に帰ると、京子の様子を盗み見た。 疲れは京子も同様らしい。首を項垂れ、うたた寝している。 「イカン、つられて眠っては大変だ」 押知は目線を夜道に戻すと、前方の闇に注意を払った。 と、進行方向の左手で崖が道添いに連なっている。「だが、何時からだろう?」彼は記憶を遡らせた。 しかし、分からぬ。奇妙な苛立ちが押知を襲った。だが、分からぬものは致し方ない。「ま、良いか!」 押知は一人、呟くと、すぐに頭を切り替えた。 カーブを曲がると、ヘッドライトが闇を貫き、路肩の草木を浮き上がらせる。そして、前方の暗がりに標識の様な物が 微かに光った。バス停であるのに違いない。押知は慎重に速度を落とすと、停車場名を読み取った。 やはり、老人の言っていた目印である。押知は前方へと視線を移した。 道路はその少し先で崖を左まわりに旋回している。老人の家も間もなくだろう。押知は慎重にカーブを曲がると、 家の明かりを探し始めた。と、前方に、ほのかな明かりが確認出来る。しばらく行くと、家の形が浮き出し始めた。 他には家らしきものも見当たらぬ。押知はその儘、車を進めて、家の横へと車を付けた。 古びた表札に目を遣ると、海淵辰夫、と刻まれている。「あ、やっぱり、ここだ!」 押知は素早く車を降りると、玄関脇のチャイムを押した。だが、応答はない。「眠ったのかな?」 「でも、変ね、灯りも付けっ放しで」「ご免下さい? 押知ですが ・ ・ 海淵さん、おいでですか?」 彼は再び呼び掛けて、チャイムのボタンを数回、押した。 と、家の中から声が聞こえる。「はい、ハーイ、今、開けるだよー」と、慌てた様な老人の声だ。 多分、トイレにでも居たのだろう。考え事でもして居たのである。押知はニヤリ、と含み笑った。 | |||||||
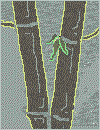
|
見ると、玄関のガラス戸越しに人の影が蠢いている。磨りガラスなので良くは見えぬが、老人であるように思われた。 引き戸がせわしく開けられる。「やあ、良く来てくれただねえ」と、にこやかな顔が押知を迎えた。 が、妙である。老人の顔付きがやにわに変わった。眼は大きく見開いて、見る間に顔が強張って行く。 其処には怯えも見て取れた。押知は慌てて挨拶したが、内心は酷く動揺している。自分の迂闊さに気付いたのである。 押知は強い髭面の大男である。しかも、アイヌ風に出で立ちに拘っていた。訪問の時刻も極めて悪い。 老人から見れば異様な風体の大男が闇からヌーッ、と現れたのであるから、その様な反応は当然だった。 | ||||||
|
「京子にでも、あらかじめ話して置いて貰うんだった」押知は内心、後悔していた。
押知はその郷里、北海道でもしばしば差別には泣かされた。だが、坂崎との出会いや此の処の影浦などとの付き合いで、 その事をすっかりと失念していた。差別というものへの防御の意識が希薄と成った為だった。 だが、今更、悔いても致し方ない。押知は素直に頭を下げて、老人の出方を窺った。追い返されるか、とも思ったが、 話を聞く気は在るのらしい。老人は警戒の態度は表しながらも、「まあ、其処では何だから」と、 ぶっきらぼうに言いながら、家の中へと彼等を招いた。 おそらく、京子の同行が良かったのである。押知は言われる儘に中へと入った。かなりの広さの土間である。 魚を入れる箱などが上手い調和で重なっていた。 その向こうには、板敷きと成った部屋がある。どうやら居間のようである。押知等は其処へと通された。 部屋の隅には、十四インチの古びたテレビが部屋の空気にでも溶け込むように、くすんだ感じで佇んでいる。 そして、部屋の中央部には、卓袱台代わりにでも使うのだろうか? 大きな掘り炬燵が据えられていた。 押知等は其処へと腰を下ろした。 土間と居間との間には二階へと上がる階段が在る。真新しい手すりが付けられて居り、どうやら康夫は二階に居るもの、 と思われた。居間の奥には畳の部屋が薄ぼんやりとくすんで見える。明かりは付いて居らず、真正面に見える仏壇が 部屋の闇に溶け込んでいた。 居間の階段の反対側には、ガラスの填められた引き戸から、流し台が透かして見える。くすんだ色の壁の面には、 川釣り用の釣り竿が大事そうに掛けられていた。「趣味もやっぱり、釣りなのだろうか?」押知はふっと小首を傾げた。 と、老人が言った。「随分と若いだねえ、小林さんとは、どういう知り合いかね?」 それは至極、有り触れた何処にでも在るような質問ではある。しかし、口調はぶっきらぼうで、別の意味合いをにおわせていた。 「何で、あんた達のような若造を寄越したんだ、もっとましなのは居なかったのかね!」そんな抗議とも受け取れる。 臍を曲げて居る事は十中、八、九、間違い無かった。だが、家には入れてくれたのである。 | |||||||
|
問題はこれから先の対応だった。押知は言った。「ハイ、実は私、北海道に住んで居ります、霊媒師をして居りますが、
小林さんと知り合ったのは、私への取材がきっかけでした」押知はありったけの嘘を並べ立て、老人の反応を窺った。
だが、老人は顔を背けると、京子の方をジロリ、と睨んだ。「あんたは誰かね」と、言う事らしい。 「あ、あのう、私、野辺地京子、と申します、精神科医の卵です、勉強中なんです」 だが、老人はプイッ、とそっぽを向いた。最初の印象が尾を引いて、気分が元に戻らぬらしい。 押知は老人を横目で見、これからの対応を考え始めた。だが、これは押知だけの責任とも言い切れない。 小林の対応が不味かったのである。 |
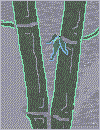
|
||||||
|
老人が初めて小林を訪れた時、全てを打ち明け、助けを求めた。だが、これと言った答えも貰えず、辛うじて後日 の連絡を取り付けたのである。だが、連絡は無く、電話や手紙での督促も用を成さない。「調子の良いだけの馬鹿者 だった ・ ・ 」老人は半ば諦めていた。 だが、そんな折り、押知からの思いも寄らぬ電話が在った。康夫を救ってくれる、と言う。諦め掛けて居ただけに、 その喜びはひとしおだった。 だが、いざ、会ってみると、待ち兼ねた筈の救いの神は日本人離れのした風貌で、 女、共々に若過ぎる。「こんなんで、頼りに成るのかね?」裏切られた想いが先に立ち、先の態度と成ったのである。 だが、無下に追い返すのも気が引ける。「まあ、茶でも入れるだよ」老人はそう言い残し、台所へと逃げ込んだ。 気持ちの整理をしたかったのである。 老人はやかん、いっぱいに水を張り、コンロに掛けて火を付けた。青白い炎がやかんを嘗める。表面に付いた水滴が炎 の上へと滴り落ちた。ジジッ、と微かな音がする。老人は無心でやかんを眺め続けた。と、その時、ミシ、ミシッ、と 何かが軋んだ。耳を澄ますと、音は天井を伝わって階段の方へと移動をしている。 「康夫だろうか?」だが、そんな事など在り得なかった。康夫は日が暮れ、闇が迫ると、決して自分一人では 部屋を出ようとはしないのである。老人は幾分、身体を堅くして、音の所在を窺った。しばしば聞こえる音ではあるが、 未だに音源ははっきりし無い。家の傷みの所為かも知れぬが、気味の悪さは募って行った。 「だが、あの連中はどう聞いたのだろう、あの大男は霊媒師だ、とか、言って居た ・ ・ 」 老人は首を伸ばして居間を覗いた。見ると、彼等は身じろぎもせず、階段の辺りを凝視している。 「何か、居るのか?」老人は釣られるように視線を向けた。だが、特別な物など何も見え無い。 「階段の陰かな?」老人は引き戸をソロッと少し開け、更に身体を乗り出した。 と、押知がやにわに振り向いた。「海淵さん、康夫君を起こして下さい、危険です!」 だが、老人は我を失った。忌まわしき想像が脳裏を駆けるが、認める事が怖いのである。そして、押知への不信も在った。 老人は動くに動けず、床の上に這い蹲った。 | |||||||
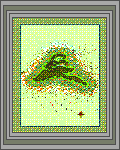
|
押知が言った。「海淵さん、認めて下さい、今、康夫君は怨霊と戦ってるんです!」 と、老人は指を震わせて、階段の辺りに腕を伸ばした。「彼処に何が見えるのかね! ワシには何も見えんがね!」 その目は異様に血走っている。老人は自分を説得させ得るだけの証が欲しいのに違いなかった。 押知は言った。「康夫君は今、悪霊に取り付かれまいと、必死で心を閉ざして居ます、ただの病では無いのです」 と、老人が首を項垂れた。薄々ながら察しては居たのである。押知は言った。 「あなたが一緒に戦わ無くて、誰が彼を助けるんです? 彼には、あなたが必要なんです!」 と、老人が弾けたように二階を見上げた。そして、「康夫!」と、一言、叫ぶと、押知等の前を擦り抜けて、 狭い階段を上って行った。障子を開ける音がする。康夫を呼ぶ声が微かに響いた。 |
||||||
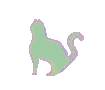
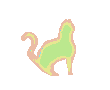
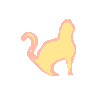
| |||||||
| Cotosiro | |||||||