|
可能世界・陰の神話 第四章第一話 |
神々の秩序 This was revised in September 1, 2007. This was revised in August 31, 2008. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
防衛大学で教授を務める中臣文雄は社会心理学の大家として知られている。その彼が数ヶ月前、防衛大学、戦時心理研究所、初代所長に任命された。彼が密かに研究を進めていた超心理学が学長である亜真野宮雄の知るところと成り、彼に白羽の矢が立てられたのである。実を言うと、亜真野には、ある秘められた野望があった。だが、その野望を達成する為には、人間の集団心理や霊現象などの超常現象を把握する必要があったのである。彼が戦時心理研究所の設立に全精力を傾けたのはその様な事情があるからだった。そして、いずれ、自分の野望を阻害する怨霊が現れる、という予感の様なものも、研究所の設立を急がせた理由であった。だが、その研究所を誰に任せるのかが問題だった。平凡な研究者では、成果を上げる事は難しい。その故に、亜真野は霊現象を研究している中臣に目を付けた。表向きは、亜真野が三顧の礼で、中臣を迎えた事には成っているのだけれども、実のところ、それは押し付けとも言い得る、半ば一方的な決定だった。 とは言え、中臣にとって、それは非常にありがたい要請であるから、彼が喜んで受け入れた事は言うまでもない。亜真野は元々、強引に事を運ぶ人間である。押し付けがましいのは気に入らなかったものの、それは何時もの事であるから、さして、気にしてはいなかったのである。まして、亜真野の秘められた野望など、知るよしもなかった。だが、亜真野にとって、中臣は彼の野望を達成する為の、単なる一つの駒に過ぎない。後に、中臣はその事で難しい立場へと立たされるのである。昇格である事は確かであったが、幸運である、とは言い難かった。 話は更に二年ほど前に遡る。丁度その頃、防衛庁では、超常現象の研究に付いて、その軍事的価値の検討の為、研究検討委員会が設置をされて、その研究の価値判断から、研究機関の必要性に到るまで、様々な討議が行われていた。既に、米ソの両超大国では、その軍事利用に向けて、科学的研究も為されて久しい。防衛庁としても、全くの無視はし兼ねたらしく、重い腰を上げたのだった。 だが、委員会のメンバーは、その多くが超常現象そのものを疑って居る。まして、軍事的な価値などに興味などは全く無かった。しかし、委員会の討議は結論を見ぬまま、一年ほど前まで続いたのである。軍事的価値の肯定派で、研究機関設置の推進派でもある座長の、亜真野の存在が非常に大きく、また、委員各々の政治的な思惑なども交錯をして、推進派、及び、肯定派が必ずしも劣勢では無いからだった。どのような結論で決着をするのか、については、当時、全く判然とはしなかったのである。 ところで、推進派である亜真野宮雄は厳格な神官の家に長男として生を受けた。本来ならば、家を継ぐべき立場であるので、彼もそのつもりで居たのだけれども、ある事情から神官への道を自ら捨てて、防衛大学へと進学をした。それは自らの信念を貫く為の、止むを得ざる選択である。「神々は神々の序列を守ってこそ、神々である、神々を祀る者はその様な秩序を護持しなければ為らない」それが彼の信念だった。 だが、彼の抱く信念は実を言えば、彼の父、足救の信念の刷り込みだった。おぞましい体験によって染み付いた、強迫観念とも言い得る代物である。それはまさに宮雄の父が企んだ壮大なる計画の一環だった。宮雄の父、足救は異常とも思えるほど、規則というものに執着して、厳格にそれを守ろうとした。神々の秩序には特にうるさく、実生活でも、社会的序列を重く見て、何をするのにも、そのような尺度が優先される。それは足救の性癖と言っても過言では無く、宮雄に対する教育も、そのような方針が貫かれていた。一般的儀礼から始まって、神官としての躾まで、それは厳しく叩き込み、一日に二時間の正座も義務付けたのである。 足救はその前に胡座を掻いて、神々の秩序を語って聞かせた。「神々の秩序は美しい、絶対的な存在なのだ」と。果たして、幼い子供に、その意味が理解出来たのだろうか?だが、足救はその様な事など全く意に介してはいなかったのである。頭脳というものは、幾度も同じフレーズを聞かされると、何時しか、その言葉を肯定的に受け入れる傾向がある。特に、子供の場合は批判力が未熟であるから、その様な傾向は顕著であった。「今はたたき込むだけで充分だ、理解は後から付いて来る」足救はそう考えて居た。 あるいは、それはある限定された範囲、たとえば、公衆道徳などにおいては、正しい見解である、と言えるのかも知れない。だが、人格や思想の形成、という側面から見るならば、それは非常に危険な考えだった。それは自己への無知を前提とした心の形成であるからである。有態に言うならば、それは建前と本音の異なるノウハウのみの人間を作り出す、と言う事である。しかも、本人はその事に全く気付いていない、と言う場合が殆どである。無論、宮雄にも、その様な危険が付いて回った。いずれにしても、遊びたい盛りの子供が長時間、意味も分からぬ言葉を聞かされるのであるから、並の子供であったなら、途中で逃げ出した事だろう。 だが、宮雄は少し違ったのである。彼は僅かの疑問すら表さず、素直にそれを受け入れた。厳しい修行にも耐え抜いて、足救の期待に応えて行った。その結果だろうか?あるいは、持って生まれた素質だろうか?中学校へ上がる頃には、かなりの霊力を身に付けて、足救をいたく感動させた。学業の成績も極めて良い。「この子は神童では無いのか!」足救は宮雄の将来に期待を持った。いや、むしろ、自分の密かなる願望が宮雄によって実現される、その事への独りよがりな期待であった。 だが、神々の序列に於いて、宮雄の仕える祭紳は最高の位置には無く、天照大御神に仕える、いわば、家臣としての神である。物心の付き始めた宮雄には、どうしても納得が行き兼ねた。「何故、自分の神は最高神では無いのだろう?神々の秩序は絶対なのか?何故、そんな秩序が在るんだろう?」疑問は次々と湧き起こり、宮雄の心を揺るがし始めた。そして、彼なりに考え始めた。 だが、それは俄に解決の出来るほど、容易な問題では無かったのである。考えあぐねた宮雄は父、足救へと疑問をぶつけた。叱られそうで、余り気分は進まなかったけれども、事は神々についての問題である。答えられる人間などは父を置いて他には無かった。だが、足救は言う。「疑問を持つなど、心得違いだ!考えてはいけない、ただ信じよ!」と。「何故、頭ごなしに怒鳴り付けて、まともに答え様とし無いのか!」戸惑いと怒りが込み上げて、父への不信も頭を擡げた。けれども、まだまだ、幼い宮雄であるから、父への敬愛は持ち続けて居る。彼は何とか、納得をしたくって、その後も、同じ質問を繰り返したのである。だが、足救の態度は変わらなかった。まともな返事など貰えずに、父への不信は深まった。そして、悩みも募って行った。 だが、親しい友人も、学校の教師や他の大人も、この件に関しては無知だった。いや、幾分かの知識は在ったのだろうが、敗戦も間もなくの事でもあり、唯物論的風潮が幅を利かせて、人々は神の「か」の字すら持ち出せぬ奇妙な呪縛に捕らわれていた。神々の話は、特に学校などでは、タブーの様に成っていた。「何だ、みんな、馬鹿ばっか、じゃないか!」宮雄は大人に失望していた。 宮雄の葛藤は彼の純粋なる魂と神々の秩序との戦いだった。だが、父から答えを貰えぬ今、頼みに足る人間は皆無、と言っても過言ではない。自分での解決もまま為らず、宮雄の精神は内向した。そして、怪しげな憎悪にも捕らわれ始めた。修行にも授業にも、まるで心が入って行かない。成績は下降の一途を辿って行った。足救は激しく叱責をするのだけれども、もはや、素直に従う宮雄では無い。「怒るばかりで、本当は何も知ら無いんだろう!神々の秩序なんて、信じるものか!」宮雄の心は益々、荒んだ。そして、素行も乱れ始めた。中学の三年に上がる頃には、手の付けられぬ札付きと成り、足救をいたく悩ませたのである。足救の叱責が激しさを増した事は言うまでもない。 だが、もしかすると、父を悩ませる事が宮雄のぐれた本当の目的であったのかも知れ無い。悩みを認めず、力で押さえようとする馬鹿親父、足救に対する腹いせと、悩みを抱える自分への理解への呼び掛けでもあったのである。だが、足救はその様な心を知ってか知らずか、ただ、怒鳴り続けるだけである。「神々の事など、どうでも良い!」宮雄は半ばやけと成り、更なる悪事を重ねて行った。二人の溝が決定的なものと成るのに、そうは時間も掛から無かった。 その所為だろうか?足救はある時点から何も言わなく成っていた。怒りの表情すら表さない。「何故なのか?」宮雄には、妙に不気味に思われた。そして、同時に不愉快だった。「くそったれ!俺の事など、どうでも良いんだ!」宮雄はその鬱憤晴らしに、霊力までをも露わに示して、自らの力を仲間に誇示した。仲間は彼を恐れ敬う。彼はボス的な存在に成ろうとしていた。「どうだい、俺はこれだけ凄いんだぞ?」宮雄は得意満面だった。だが、言い知れぬ虚しさも胸を突く。心の奥底に押し込めた、触れては為らぬ葛藤が時折、やにわに現れて、彼を苛むからだった。 だが、幼さの抜け切らぬ宮雄が、自身のその様な心理に気付く事は難しかった。彼は荒ぶる心に我が身を任せて、ただただ、虚しい悪事をし続けたのである。しかしながら、いくら暴れても、気分は晴れない。仲間と居る時は良いのだが、家に戻って、一人に成ると、妙に心が沈んでしまう。彼は理由が分からずに、苛立ちだけを募らせた。そして、何故だろう?気力が次第に衰弱して行く。自分の部屋にジッ、として、篭もる事も多く成り、鬱の兆候も現れ始めた。彼が自分の変調に気付く事は無かったけれども、彼には、助けが必要だった。 だが、足救にとって、これは千載一遇のチャンスであった。彼はあろう事か、この瞬間をこそ、待ち望んでいたのである。宮雄の悪事を無視していたのも、こう成る事を見越しての足救の冷徹なる策略だった。頃は良い。彼は先祖伝来の秘薬を調合すると、少しずつ、宮雄の食事に混ぜ入れ始めた。化学的ロボトミーを宮雄に施して、無気力にするのが目的である。足救の策は成功して、程なく効果は現れ始めた。宮雄は自らの葛藤にも打ち勝てず、自閉症の様な状態へと陥ったのである。足救は早速、次の計画へと事を運んだ。その様な子供はその閉ざされた心の内側で、必死に助けを求めて止まない。実を言えば、足救の付け目は其処に在った。宮雄に催眠術を施す事で、神々の秩序を思い起こさせて、それを唯一の救い、と思わせるのである。練りに練った計画でもあり、失敗などは在り得なかった。 足救に取って、神々の秩序は絶対だった。それを疑う者ならば、親であろうと、神であろうと、彼は絶対に許さぬのである。「神々の秩序を守る為なら、何をしようと許される」それが足救の堅い信念だった。その前には、我が子の自由な意志などは塵ほどの重さすら、持たぬのである。踏みにじる事に躊躇は無かった。足救はいよいよ、洗脳の仕上げに掛かり始めた。だが、その頃の宮雄は足救に対して嫌悪の情しか抱いて居ない。普通の遣り方では難しかった。そこで足救は一計を案じた。足救の書斎から床下を通して、直径二十ミリほどの鋼管を宮雄の部屋へと引き入れたのである。それは暗示の言葉を送り込む陰湿極まる小道具だった。宮雄の寝入ったのを見澄ますと、閉じた鋼管の蓋を開けて、呪文の様に語り掛けて、夜な夜な暗示を送ったのである。 鋼管を流れる足救の声は適度に響いて、その催眠効果を倍増させる。宮雄の心に密やかに、極めて速やかに浸み入った。宮雄の心に僅かに残る神々の秩序への信仰を彼が何も知らぬ間に、心の奥底から引き出したのである。宮雄の心には、もはや、抵抗をする力など残って居ない。乾いた砂か、何かの様に暗示の言葉を受け入れた。もしも、それを疑ったなら、今の地獄からは逃れられない。その様な暗示も功を奏して、宮雄はただ盲目的に神々の秩序を信じたのである。そして、長い混迷からも解放された。是非はともかく、足救の陰険な策謀が宮雄を混迷から拾い上げて、立ち直らせた様だった。そして、その宮雄には、一つの使命感も植え付けられた。神々の秩序の此の世への具現、それが亜真野の進むべき、天から与えられた仕事と成った。 その亜真野に取って、防衛庁の超常現象へのアプローチは千載一遇のチャンスであった。委員会の大勢は超常現象そのものに懐疑的であったが、それぞれの委員の思惑は各々に異なる。亜真野はその様な思惑を巧みに操って、研究機関の設置に向けて、陰に陽に動いたのである。提出された答申は亜真野の意向に添うものだった。そして、答申は一年ほど前、亜真野を責任者として実行に移された。それが戦時心理研究所として、実現したのである。 だが、亜真野を敵視する連中はこれで彼を葬り去れる、と、そんな具合に囁きあった。厳密に言えば、超常現象の研究は科学の枠をはみ出している。中臣の研究も公には、何の発表も為されて居らず、理論らしきものも出来ては居ない。端から見ると、雲を掴む話に思えた。「あんなものに肩入れする亜真野は大馬鹿野郎だ、 問題が出るのは間違い無い、足を引っ張るのには、格好の材料だ」そう考えても不思議は無かった。だが、彼等には、事の本質がまるで見えては居なかった。超常現象の何たるかも、亜真野の危険な計画も、全く知らぬ彼等には、無理からぬ事ではあったのだろうが、亜真野に取って、その侮りはむしろ非常に有り難い絶好の状況を作るのだった。 |
|||||||
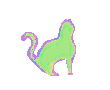
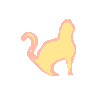
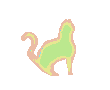
| |||||||
| Cotosiro | |||||||