|
可能世界・陰の神話 第七章第一話 |
大いなる想念 This was revised in January 8, 2010. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
1.認識不能な確かな実在 宮城が札幌で、怪しげな念波を感知してから、既に、七ヶ月ほどが経過した。もう五月である。理由は分からぬけれども、東京に戻ってからは、例の監視者の気配も感じられず、平穏な日々が続いている。彼は今、影浦を道場に住まわせて、日々、禅の指導を行っていた。その効果だろうか?影浦の心の状態は禅を始めてから、二ヶ月も経たぬ間に、安定の兆しを示し始めた。板敷きの床に背筋を伸ばして座る禅の姿勢も、随分と様に成っていた。だが、宮城はそれが釈然としない。影浦の禅の上達が少し、早い様に感じるのである。それまで、特別な指導など、した覚えはないのであるから、それは当然の疑問であった。ひょっとすると、影浦に、その様な素質でも、あるのだろうか?宮城は少し気に成って、以後、其処に注意を向けながら、彼の様子を見守り続けた。すると、しばらくして、宮城はその件とは別の、奇妙な事柄に気が付いた。今まで、全く、知らなかったが、影浦の心の様相が常人とは、かなり、違うのである。 たとえば、彼は人間的な暖かさと冷酷さとを併せ持っている。また、内に籠もる性質と人なつっこさ、あるいは、絶対的な自信と、極度の弱気などが併存している。彼には、その他にも、様々な相反する心が同居していた。無論、それらの心は影浦という人格によって、コントロールされているので、取りあえず、生活上の支障はないし、この様な心の状態は、人間ならば、誰しも、多かれ少なかれ、持っているので、異常である、と言う事も、出来ないのであるが、その併存状態は普通ではなかった。そして、影浦という人格はしばしば、それらの心に、自分ではない別の魂を感じるらしい。言い換えると、彼は、それらの心が別の人格であるように感じるらしい。多重人格、とは言えないけれども、見たところ、彼は、別人格としての、それらの心と、対話をしている様なのである。だが、影浦自身は、その対話や、自分の様々な心に別人格を感じる事に、殆ど、気付いていなかった。それはむしろ、無意識的な心の動きの様なのである。宮城は其処に懸念を持った。 これは一般論であるが、それらの心に、自分の心である事を自覚して、意識的に向き合うならば、それは魂の飛躍を遂げる要因と成り得るけれども、逆に、意識せずに、ただ、向き合っているのなら、それは人格の破壊等々の、危険因子とも成り得るのである。可能性は低いが、もし、極度の精神的なショックがあるならば、多重人格症などにも陥りかねない、その様な危険性も無くはなかった。 無論、影浦が即、この一般論に当て嵌まる、とは言えないけれども、影浦の持つ各々の心は非常に強い。しかも、その力は拮抗している。この事を考えるなら、影浦の心は、自己同一性を保つ為に、何時も、緊張状態にある、と考えるのが妥当であった。そして、影浦の今の心の安定が非常に際どい、バランスの上に成り立っている事も窺える。だが、影浦の心がこの様な状態に陥ったのは、職業からの影響だろうか?それとも、持って生まれた傾向なのか?いずれにしても、影浦が主として、霊的現象をテーマに小説を書いている理由がこれで、分かった。彼は無意識に自分の様々な心に、様々な霊を感じていたのである。彼の心について、解決すべき問題が少なくとも、一つ、見つかった。 影浦は小説家である。従って、常人よりは自分の心を知っている様に思われる。だが、彼がこの問題に気付いていたか、と言えば、そうではなかった。その事が時折、彼の内面的な矛盾を表面化させて、心を不安定にさせるらしい。おそらく、その引き金と成ったのが、影浦の抱いた祟り神出現の予感であった。それは宮城が影浦と会うかなり、前の事である、と推測される。だが、影浦はその時、その予感が何を意味するのか、分からなかった。ただ、得体の知れぬ不安や恐れを感じただけであったのである。その故に、彼が元々、持っていた精神の問題が表面化した。宮城はそう考えた。 だが、影浦自身は座禅を始めてからも、依然として、その事には、気付いていない。そして、自分の心の複雑性についても、明確に認識している、とは思えなかった。これはやはり、問題であった。確かに、彼の状態は良化しつつあるが、この問題を放置するなら、精神の問題が何時、ぶり返さない、とも限らない。影浦には、内省を深めて、その問題に対処し得るレベルまで、自分自身を引き上げる事が必要だった。だが、宮城が直接、力を貸す事は難しい。問題点を指摘する事は出来るけれども、あくまでも、影浦自身がその問題を意識して、自分の心と向き合わねば為らない。其処で、宮城は禅の指導を、その様な方針に基づいて、行うように修正した。すると、奇妙な事に、それから僅か、二ヶ月ほどで、影浦の発する想念(念の籠もったイメージ)が何故か、やにわに膨張を始めた。 ちなみに、此処に言う想念とは、彼の世界観を支える念の籠もったイメージを指し、彼の主観的な世界を形成する基本的なイメージである。従って、その様な想念の拡大は彼の内面的な矛盾が止揚をされて、新たな境地を産み出しつつある事を意味していた。本来ならば、歓迎をすべき兆候である。だが、影浦の場合、やはり、その変化は随分と急で、異常であった。常人ならば、到底、二ヶ月ほどで、到達出来るレベルではない。影浦が特別な人間である事は確からしいが、それにしても、この状況は妙である。宮城の心に、幾分か、不安が生じた。この様な急激な世界観の変化は往々にして、悪霊などが絡む事も、多いのである。無論、楽観視はしていたけれども、原因が不明の侭では、やはり、不安を払拭する事は難しい。宮城はそれから、今に至る三ヶ月間、警戒だけはし続けた。 だが、これまでのところ、影浦のオーラに陰りなどは、見られない。悪霊なども現れず、何の問題も起こって居ない。ならば、彼の急激な魂の膨張は一体、何に拠って、生じたのか?僅か、半年間、一日当たり、四時間ほどの座禅であるから、影浦自身の力である、などとは、到底、考えられない。と成ると、其処から導かれる結論はただのひとつしか、在り得なかった。宮城が以前、そうであった様に、影浦の変貌も、あの正体不明の何ものかが、彼をその様な状態に導いた、と考えるしか、ないのである。そして、その結論には、自信があった。だが、不可解な気分はなおかつ、残る。答えは既に、出ていたけれども、宮城は、「どうしてなんだ?」と、昔の自分を顧みた。 その当時、宮城は知られざる何者かの存在に気が付いて、その魂からの啓示を期待しながら、禅の修行に勤しんでいた。だが、相手が正体不明というのは、やはり、気分がすっきりしない。時には、もやっとした、言うに言われぬ不安に、ふと、捕らわれて、考え込んだものである。だが、その様な知られざる者の正体は、宮城があの墳墓を見て、影浦と会った辺りから、彼の脳裏に、あるイメージと成って、現れ始めた。それは、「人知を越える何ものか」と言う、極めて、曖昧なイメージである。宮城はその時、そのイメージを明確にしようと、考えた。 だが、人知を越える何ものか、とは、果たして、何か?それが第一の問題であった。そこで、「人知を越える」という言葉について、考えた。そして、その言葉は、人が理解し得ない領域の実在を前提とする、と言う事に気が付いた。そして、理解し得ない、と言う事は、識別が出来ていない、と言う事を前提とする、様に思われる。識別なくして、理解などは有り得ない。識別がたとえ、間違っていても、間違った理解は得られるが、識別不能であるならば、どの様な理解も得られない。識別はやはり、理解の大前提である。ならば、人知を越える、と言う言葉は識別不能な領域、つまり、何も区別し得ない領域の実在を前提とする。それはもはや、認識不能な領域、と言って、差し支えない。 そして、もしも、そうならば、人知を越える何ものかは、原理的に認識不能な実在であり、全ての基とでも表現するべき極めて、巨大な想念である、と考えられる。何故、それが想念、と表現出来るのか、と言うと、それは宮城に美保神社のイメージを、ある念を籠めて、送ったからであった。念の籠もったイメージでなければ、それは相手には伝わらない。しかも、その想念は現実を動かそうとしているらしい。さもなくば、宮城などに、そのイメージを示す事などしないだろう。その故に、想念は単なる平板なイメージではなく、念を持つ無数のイメージの集合であり、常に、現実世界とリンクしている、と考えられる。つまり、想念は現実を招来させる、あるいは、変える、何らかの力を持っている。宮城はそう考えた。ならば、自分自身も言代主も、そして、影浦も、そうした想念の赴く侭に、此の世に存在をして、戦っている、のかも知れない。そして、自分や言代主などの魂も、その想念に含まれるのである。 ならば、ひょっとして、この戦いは自分達の意思で生起した、と言う事も出来るのかも知れない。言い換えるなら、世界の全ての魂が、この世で生起する全ての事に、一端の責任を負っている、のかも知れない。集合、想念はその部分と同一であり、その部分としての想念は、その全体であるべき集合、想念を含むからである。この言明は論理的には、矛盾があるが、認識不能な領域に論理学は通用しない。啓示の主について、考えていた、あの当時、宮城はそう推測していた。だが、今、変貌する影浦を目の当たりにして、その推測はもはや、確信へと変わりつつある。そして、宮城は大いなる想念の意思が影浦を通じて、表れているのではないのか、とすら、感じていた。 おそらく、宮城のその様な印象は、影浦が様々な人格を内包している、と言う宮城の見立てと関係があった。いずれにしても、大いなる想念が認識不能な力で、この世界を動かしている事は間違いがない。人はそれを神、あるいは神々、と呼ぶのだろうか?だが、宮城はそう呼ぶ事を躊躇した。宮城のイメージは、その様な神、あるいは神々と、大きく違っているからだった。 大いなる想念は認識をする存在であり、認識をされる存在ではない。つまり、それは認識不能な実在である。その様な実在を明確に概念化する事など、出来るのだろうか?概念化した途端に、それは違った存在に成るのではないのだろうか?宮城には、その様に思われた。「認識不能な存在は実在する」それ以上の事は言い得ない。それが宮城の結論だった。だが、その様な想念については、解決すべき疑問がまだ、在った。自分や影浦の想念は、言代主が醸し出すイメージとは正反対の、まるで異質なイメージである。相対するイメージが果たして、同じイメージから生まれ得るのか?この世の理で考えるなら、それは難しい様に思われた。 だが、逆もまた、真、と言う言葉もある。一つのイメージを逆向きにするなら、相対するイメージが其処に産まれる。そして、想念には、形など無く、数える事も、区別する事すら、容易では無い。ならば、善は善、悪は悪、と、決め付ける事は出来るのだろうか?善が悪、悪が善と成る事も、あるいは、可能であるのかも知れない。想念の世界は極めて深く、人知では到底、測り知れ無い。全てを産み出し、あるいは消し去る、その様な実在とも思うのである。あえて、言葉に表すならば、やはり、神と呼ぶしか、ないのであろうか?だが、宮城に取って、その神は善悪、美醜を併せ持つ、正体不明の何かであった。 いや、元々、正体などは無いのかも知れない。我々がその姿を想起する時、それは我々に対して、その個々人にふさわしい、個別の姿を示すだけなのではないのだろうか?だが、その事を知る術など、何処にもない。科学的な知見を以てしても、証拠などはなく、ただ、推測し得るだけである。ただ、その人知を越えた何ものかが今、この状況に在る全ての者を戦わせよう、として居るらしい。そして、その意思は自分達では知り得ぬ、自分達の意思なのかも知れない。それにしても、大いなる想念は我々を何処に導こう、と言うのだろうか?宮城は今、それが知りたい、と切望していた。 だが、それはひょっと知ると、問うべき事柄では無いのかも知れない。比喩的な表現にしか、成らないけれども、自分がもし、大いなる想念から産まれたのなら、あるいは、その部分を成すのなら、自分の置かれた状況は想念の赴く現実であり、それ以上でも無く、以下でも無い。大いなる想念は魂としての我々を通して、想念自身の認識を得よう、と欲して居るのかも知れない。あるいは、想念の認識が我々を通して、現実を作るのかも知れない。だが、この推測には問題がある。想念については、その認識と現実世界の現象との間に、時間的な前後関係など、あるのだろうか?宮城はない、と考えた。強いて、言うならば、論理的順番がある、と言うべきだろうか?だが、それも怪しい。想念が行う認識は現実そのものである、と直感しているからだった。つまり、どちらが先かは問えないのである。 我々の意識はその様な理を知らずに、未来への不安を募らすけれども、その未来は自分の認識すべき、いや、見ざるを得ない、その様な現実でもあるのだろう。おそらく、全ての人間は此の世へと送られたその瞬間、その様な魂の理を忘れ去るのに違い無かった。比喩的に言えば、明日、自分の見る物は、それは自分が決めている。あるいは、自分を産んだ大きな何かが決めている、のに違い無かった。「その故に、自分の心をごまかし無く、認識する事が重要なのだ」宮城は過去のごまかしだらけの人生を顧みて、今、その様に実感していた。 注:物理的に認識不能な実在として、確実に挙げられるものは自己である。自己の手足などを見る事は可能であるが、それは自己そのものを見た、と言う事ではないからである。それにも拘わらず、自己が存在する事を否定出来る人間はおそらく居ない。当の本人にとって、自己は紛いもない実在である。ただし、「我は考える、故に、我は存在する」と言う言葉で、この事を説明する事は差し控える。その理由は論理学の初歩を知るだけで、理解が出来る。その思考に、「我」と言う概念が与えられる時、その思考は「我は存在する」と言う前提で始められる。つまり、論理的順序に従えば、「我は存在する、故に、我は考える(事が出来る)」と言う事である。従って、自己は論理的な関係を超越した実在である、と考えるのが適切である。 逆に、「私は存在しない」と言う言葉は、「我は存在する」の否定として、思考される。つまり、それは、「我は存在する」を「否定する」という事に成る。だが、この場合、「私」と言っているのは私であるから、「我は存在する」は真であるが、「否定する」は偽と成って、「我は存在しない」は偽と成る。従って、この場合、「我は存在しない」は、「私の何が、どこそこに、何時、なん時」と言う条件が付かないならば、間違いである、と考える。 認識する者とそのオブジェクトはそれぞれが、独立しては存在出来ない。認識者はオブジェクトを必要とするし、オブジェクトは認識者を必要とする。そして、「我」は認識者としての魂であるから、少なくとも、認識する対象(オブジェクト)がある限り、それは常に存在する、と考えなければならない。その故に、多分、肉体は滅びても、何らかの形で、存在している。オブジェクトもまた、様々に姿を変えて、存在し続けるからである。 また、認識不能な存在として、確実に揚げられるものは他者の自我である。他者の身体は認識出来るが、他者の自我が存在する、と言う確信は、実は、自分の自我が存在する、と言う確信からの類推でしかない。つまり、それは類推したのであり、認識したのではない。 2.ジレンマ 影浦は二週間ほどの予定で、札幌の自宅に戻っていた。とは言っても、この帰省は一ヶ月ぶりの事である。このところ、妻の希倭子も、典子と接したり、影浦の状態が日々、良く成って行くのを目の当たりにして、最近は、それほどの心配など、しなく成っており、二週間に一遍の帰省、と言う約束も、いつの間にか、消滅していた。電話連絡は始終、していたけれども、余りに長い間、家に帰らないのも、問題であるし、当面、する事も無いので、というよりは、奥さん孝行もしなくては為らないので、希倭子の誕生日に合わせて、戻ったのである。典子は東京に帰らせていた。だが、落ち付かない。実を言えば、一ヶ月ほど前、例の作品が完成して、「祟り神の悲劇」と、表題を付けられて、出版された。普通なら、新しい題材を見つけよう、と、活動を始める頃であったが、今回は、その様な気分には成れそうにない。あの物語の完成は影浦にとって、物語の終わりではなく、始まりであったからである。彼は予定を二日、繰り上げて、東京に戻った。 影浦は神田の出版社に顔を出して、所用を終えると、早速、新宿の道場に足を向けた。道場は狭い路地の突き当たりに在る。彼はその路地を道場まで、懐かしむ様に、ぶらぶらと、歩くと、玄関の引き戸に手を掛けた。戻る時間は告げていないので、もしかすると、鍵が掛かっている可能性もある。影浦は引き戸を、ソロッと、引いてみた。すると、簡単に、カラカラッと、開く。離れの方からは、朗らかに談笑をする二名ほどの声と、チゴイネルワイゼンの旋律が漏れ出していた。どうやら、熊野が来ているらしい。新しいレコードでも買ったのだろうか?だが、音楽鑑賞の方はそっちのけらしい。話が随分と弾んでいる。「引き戸の音にも、気付かないなんて、リラックスが過ぎるんじゃあ無いのか?」影浦は、そう呟くと、忍び足で、廊下を歩いた。そして、離れに着くと、襖の影から、そろっと、覗いた。と、宮城の眼がこちらに動く。熊野はまだ、気付いていない。影浦は宮城にチラッと、目配せすると、「熊野さん、しばらくですね」と、声を掛けた。熊野がクルリと、振り返る。そして、影浦を見ると、彼の顔が輝いた。「あ、影浦さん!すごいですね、大変な反響ですよ!」 熊野が述べたのは、「祟り神の悲劇」に対する世評の事であった。褒められて、悪い気はしないけれども、それは元々、特定の層を念頭に構想を練った作品である。それが予想外に、大衆受けした。「いやー、こんな筈では無かったんだけんど?まあ、これは、これで、良かったのかな?」影浦はおどけた言い回しで、そう言うと、卓袱台の横に胡座をかいて、少し照れ気味に、ニヤリ、と笑った。宮城が言った。「これで、こちらのメッセージも、伝わりが良く成るでしょう、古代史ブームに乗っただけでも無さそうですから」影浦が言った。「うん、共感してくれたのは、うれしい、読んでくれた人は自分のジレンマに薄々、気付いているのかも知れないな・・」 日本列島の住人は何時かしら、弥生文化に基づいた支配の論理に慣れてしまって、知らぬ間に、それを受け入れて来た。それはその様な支配の論理を自らが内面化をしなければ、生きては行けない、その様な体制に大きな理由が在ったのである。それは自分という立場から見るならば、日本的な自己疎外の構造、と言っても過言ではない。その故に、我々はえてして、世俗的な欲望と、世間の常識という客観的な認識に身を任せるのであるが、その事で得る事が出来るのは、ほんの一時の満足に過ぎない。その満足感が過ぎ去ると、また、飢餓感に襲われる。これは文明が高度化すると、しばしば、見られる現象である。人々から、神が遠退いた、と言えるのかも知れない。 だが、それで、本当に、生きている、と言えるだろか?影浦は、今、この寒々しい状況が極限まで、達したのではないのか、と感じていた。神を恐れぬ我欲に捕らわれた人間達が幅を利かしているからだった。そして、人々の無意識も、その事はとうに知っている。だが、明確には、意識をされずに、その解決は、そう簡単な事では無かったのである。 確かに、人々は自分自身を取り戻そうと、あらゆる試みに手を染めて、試行錯誤を行っている。仕事や趣味に没頭する者、金儲けに邁進する者、社会福祉や宗教活動に勤しむ者など、その行動は多岐に渡る。だが、その方向は必ずしも正しい、とも言い切れず、その事で、逆に、人を傷つける者、あるいは、自らが危険な状況に陥る者も、そう、少なくは無かったのである。それは、もしかすると、自己の認識を客観的認識と言う他者に依存して、自らを空しくした所為なのかも知れない。自らの確かなものを顧みず、遠くに在るガラクタに憧れて、フラフラと虚空を彷徨ったのである。そして、ある時、確かなものを得たのだ、と、他愛なくも、錯覚をして、迷妄の世界へと落ち込んだ。 その様な人間はまだ、少数の様に思いたいが、その危険性を持つ人間は増え続けている。もし、悪魔的な想念が日本全土に広がるならば、其処へとなびく人間は予想外に多そうなのだ。日本が恐ろしい道に踏み出さ無い、とも言い切れない。心が何時も満たされない不幸を背負う人間が増えている様に思うからである。他国と比べるなら、個別的な異常犯罪に留まっているのは、むしろ、幸いである、と言うべきなのかも知れない。 古今、東西で輩出した卓越した宗教家、あるいは、予言者達は、世の終わりに、神の名を騙る悪魔達が人を唆して、暴れさせて、世界を混乱に引き込むだろう、と言う様な事を言っている。不幸を背負う人間は悪魔の甘言に欺されやすい。これは必ずしも、他人事ではない。他人事と思っていると、足許を掬われ無い、とも限らない。まだ、確認出来ては居ないけれども、悪魔的な想念を持つ社会の敵は必ず、何処かに存在している。そして、今、個々人の心の在り様が試されている事も確かであった。 だが、言代主の呪いであろうか?今、迷妄の世界への誘惑は高まっている。共同体の心を無視した、我欲に捕らわれた人間達が金メッキの鎧を幾重にも着込んで、幅を利かせるからである。貧困者にとって、その様はとても、まぶしいが、その影には、途轍もなく深い闇がある。そして、其処には、至高の世界を装った迷妄の世界への入り口がある。ブラックホールのごとく、人々の魂を吸い込んでいる。だが、其処に君臨するのは、「皆」と呼ばれる亡霊であった。 「皆」の亡霊は迷い込んだ人間を更に、益々、迷わせて、魂無き亡者へと変えて行く。そして、彼らの脳内に入り込む。自らが唯一絶対なる魂として、彼等の上に君臨するのである。彼らはその亡霊に従って、ただの肉と成る事で、安易な生を約束される。いや、その様な錯覚を植え付けられる。その故に、物質的で、表層的な偽の平安がはびこるのである。いや、その様な偽の平安は既に、其処此処に、はびこっている。自らの魂の無き事を一時、忘れさせる平安である。実を言えば、魂を奪われた人間も、やはり、自らの魂を欲したのである。だが、狡猾なる「皆」の亡霊は人の世界を狭くして、客観的認識と言う美名の下に、自由な思考を妨げる。魂を取り戻すのは、そう容易な仕事ではないのであった。 その故に、「皆」の亡霊の囚われ人は自己の悲しい喪失を協調、と称して、賛美する。無論、それは協調ではなく、自らの奴隷化なのだが、その事になかなか、気付かない。「皆」は一体として、繋がって居り、「皆」が考える様に考えて、「皆」が行動をする様に、行動をする。「皆」の亡霊が、あいつは魔女だ、と宣言すると、皆が機械的に反応をして、魔女と呼ばれた自分の仲間を、よってたかって、貶める。それが亡霊に魅入られた人間の、やり切れなく悲しい生き方だった。だが、「皆」は本来、魂などは持っては居ない。魂に取って代わるなど、心得違いも甚だしい。「このままでは、日本は何とも、薄気味の悪い、陰湿なる世界へと落ち込んで仕舞う」影浦には、その様な心配もあるのであった。 言うまでもなく、「皆」の亡霊は必ずしも、生物としての人間を滅ぼす、とは限らない。だが、ヒューマン・ビーイングとしての絶滅は招来し得る。そして、ヒューマン・ビーイングの衰退はやはり、人間の生命力を萎えさせる。あるいは、日本社会の出生率の低下は、その様な問題が影響している事も考えられる。経済的な理由や環境ホルモンの影響ばかり、とは言えないのである。同じ図式はしばしば、他の高度文明社会にも、見られるが、おそらく、其処にも、構造的に似た、その社会特有の問題があるのだろう。だが、我が国では、その様な社会問題が共同体の危機につながる事を知っていながら、未だに、何の対策も取られていない。 いずれにしても、今、巷を覆う似非宗教の氾濫や、人々の持つ言い知れぬ不安や焦りも、全ては、その様な、様々な社会問題に起因している。魂の危うい兆候は至る所に現れていた。「自分をどう取り戻すのか?それはもう、社会の問題に成ってしまった、まあ、危機感は在る訳だから、望みが無くも無いんだが・・」影浦はそう言ったきり、黙ってしまった。その後の事は白い濃霧に包まれている。濃霧の中には、果たして、何が眠っているのか?模索をするが、分からない。そして、宮城も、同様らしく、口を噤んだままである。重苦しい静寂が辺りを覆った。と、熊野が間を外すように、言った。「なるほど、分かりましたよ、二番目の敵の正体が!」それは「皆」の亡霊を操って、魂を抑圧する権力の権化、それを信奉する集団が新たなる敵なのに違い無い。熊野はそう言うのである。影浦も、その事は同感であるが、今、彼の心は其処に無かった。 その数日後、典子からの電話が入った。葉書や手紙が山のように舞い込んでいて、処理に追われて大変だ、と言う。影浦は急いで、札幌へと飛んで帰った。舞い込んだ書簡の内容は好意的なものが殆どである。しかし、精神病者から、と思われるものも混在して居り、中には、脅迫まがいのものすら在った。自分の事を書いたのでは、と、見当違いの邪推をして、抗議をする長文の封書なども含まれている。だが、それはやましい気持ちの裏返しでもある。そして、おそらく、彼等は自らの邪なる心の内を無意識かも知れぬが、気が付いていた。その事を意識させる作品は彼らにとっては耐え難い。その様な抗議の書面はその故の嫌がらせであるのに違いなかった。 それにしても、あまりの誤解や曲解には、さすがの影浦も呆れてしまう。ただ、人々に、かなりの刺激を与えた事は確かであった。吉と出るのか、凶と出るのか?それは想像も付かないけれども、寄せられた書簡のチェックには、細心の注意が必要である。好意的な内容に、罠の紛れている事も、十二分に考えられる。また、未知の仲間からの信号も、一朝一夕に、読み取る事は難しい。彼らも、相当に警戒して、気を使って、書いているのに違いないからである。明日には、宮城が駆け付ける。典子はそれと、入れ替わって、戻る手筈と成っていた。 |
|||||||
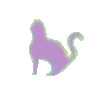
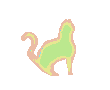
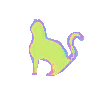
| |||||||
| Cotosiro | |||||||