|
可能世界・陰の神話 第七章第二話 |
祈言宗 This was revised in September 6, 2008. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
その一 フリーライター 新宿のとあるアパートに小林茂という男がいた。フリーライターを仕事としている。だが、ほんの六ヶ月ほど前までは、出版社に持ち込む原稿がしばしば、突っ返される状態で、殆ど売れては居なかった。本人は気付いては居なかったが、その語り口が紋切り型で、その内容も凡庸であるので、全く面白味に欠けるである。小林は原稿が突っ返される度に、憤慨したけれども、採用をされなかった事は当然だった。だが、今は差し当たり、多忙な毎日である。やけくそ気味で手掛けた仕事が何故かは知らぬが、注目された。あるいは、やけくそ気味の気分が彼の本来の語り口や視点を引き出したのかも知れない。いずれにしても、その所為で、テレビのゲストやコメンテーターなど、新たな仕事も随分、増えた。「ひょっとして、俺は天才かも知れん」彼は半ば本気で、そんな事も考え始めた。だが、良い事はそうは続かない。此処に来て、多くの問題が一挙に溢れ出して、彼の行く手に立ち塞がった。 茂は今、眉間に深い皺を寄せて、神田の書店街を徘徊している。焦りが顔に染み出していた。街は春もたけなわの休日である。天候に恵まれて、街路は多くの人々で埋め尽くされた。学生風の一団が弾む様に闊歩している。男女の若いカップルが何やらヒソヒソと語らいながら、小林の脇を擦り抜けた。子供を連れた若夫婦もいる。「チッ、楽しそうで、結構だ!」茂は彼らを横目で見ながら、忌々しそうに呟いた。買い物でもした帰りだろうか?進行方向をふと見ると、主婦らしき女性の一団が歩道の真ん中で、談笑している。「くそったれ!ヘラヘラ、笑ってんじゃあねぇよ!邪魔くさい!」彼は腹立ち紛れに呟いた。原稿の締切は間近であるが、構想すら纏まっては居ないのである。道行く人は誰も知らぬが、彼は崖っ縁へと立たされていた。 実を言えば、あのサンツーリストの事件が起こった当時、彼は失業者も同然の状態にまで落ち込んでいた。書いても、書いても、採用されず、気分の滅入る日が続いたのである。其処で、彼はその事件が起こったその日に、事件の特異性を感じて、その謎解きに取り組んだ。そして、サンツーリスト首謀説を捻り出したのである。それが冒頭に述べたやけくそ気味で手掛けた仕事であった。もっと、取材をするべきではあったのだけれども、その取材が自分の謎解きを否定する事も考えられる。そして、他人に先を越されると、せっかくの思い付きが無駄と成る。彼は焦りにも似た感情に突き上げられて、気持ちの整理も付かぬ侭、急いで原稿を書き上げて、週刊、渦潮へと持ち込んだのである。また没に成るのでは、と不安であったけれども、奇妙にも、その時に限り、採用された。彼は今でも、その時の不思議な感覚を覚えている。何故かは知らないけれども、原稿が採用された事に現実感が持てなかったのである。まるで、夢の中にでもいる様な、妙にふわふわとした感覚だった。 だが、今と成っては、それはもう、大して気に成る問題では無い。原稿が紙面に載ると、予想外に注目をされたのである。茂はその事に十分、満足していた。そして、出版社も、その反響の大きさに気を良くして、この問題をシリーズ化した。無論、その原稿は全てが小林に任されたのである。茂はこの余りにも都合の良い状況に戸惑ったけれども、同様の事件が頻発をしていた事も在ったので、編集部の決断は当然であったのかも知れない。いずれにしても、編集部の思惑は見事に当たって、渦潮の売り上げは一挙に延びた。そして、不思議な事に、その後、茂が行った取材は全てが彼の当初の謎解きを支持したのである。それはまるで何者かが、その様に細工をしたかの様だった。少なくとも、小林はそう感じたのである。しかし、小林は余り意識しては居なかったのだが、彼が都合の悪い情報を無視した事も確かであった。いずれにしても、小林はその様な不思議に都合の良い状況の許で、他の仕事にもあり付いた。無論、同業他社も手を拱いている筈もなく、すぐに、例の事件や同類の事件の謎解きを特集して、後を追って、売り出し始めた。「謎の集団失踪」など、その手の文字が洪水の様に巷に溢れて、見る間に、陳腐なものへと変わって行った。一時は相乗効果で売り上げも伸びたけれども、内容的には、そうも変わらぬ。売れ行きが頭打ちと成るのに、幾らも時間は掛から無かった。だが、茂に取って、この仕事は全ての糧の源である。読者の関心を引き付け得る新たな発想が必要だった。 しばらく歩くと、ビルの谷間に篠櫛屋書店の看板が手招きでもする様に現れた。神田でも、一、二を争う書店である。小林は藁をも掴む心境で、書店のドアを押し開けた。小手先でも物まねでも何でも良い。とにかく何か、新しいアイディアが要るのである。本の表題を確認して、あるいは直接、手に取って、まだ見ぬアイディアを探し求めた。だが、思いの外、店内は混雑している。ふと振り向くと、誰かの肩がぶつかった。顔を上げると、小林とほぼ、同年輩のサラリーマン風の男である。「あ、済みません」小林は咄嗟に頭を下げた。だが、男はスッ、と素通りして、返事などは帰って来ない。「馬鹿野郎、どう致しまして、ぐらい、言えないのか?何、考えてんだ!」小林は心の中で、怒鳴り散らした。 それにしても、何故、立ち読みなどをするのだろうか?歩き難くて、し様が無い。自分の立ち読みは許せるが、他人の立ち読みなど、許せぬのである。「くそっ!邪魔なんだよ!」茂はそんな一人に近付くと、知らぬ振りしてドン、と当たった。三十四、五のやけに気取った金縁眼鏡である。当たり所でも良かったのだろうか?相手の手から本が外れて、床の上にバサッ、と落ちた。しかめっ面がクルッ、と振り向く。「あっ、失礼!」小林は何食わぬ顔で謝ると、上目を使って相手を覗いた。相手がジロジロと、小林を見る。「ざまあ見ろ!」小林は心密かに、呟いた。 だが、やはり気分はすぐれない。「もう、出ようか?」茂はふらりと踵を返して、出口の方へと歩き始めた。と、その傍らに、人の込み合う場所が在る。頭上を仰ぐと、「新刊コーナー」の看板がこれ見よがしに掛けられている。彼は素通りしよう、と思ったけれども、歩く内に、考え直した。ひょっとして、参考に成る本が在るかも知れ無い。彼は其処に近付くと、首を伸ばして、そっと、覗いた。見ると、それは今、評判と成っている祟り神の悲劇、と言う小説である。忙しさに紛れて、読んでは居ない。釣られる様に手に取って、パラパラッ、とページを捲って行った。すると、祟り神、美保関、言代主、などの文字や挿し絵が怪しげなイメージを呼び起こす。そう言えば、あの失踪事件も美保関である。「これは使える!」小林はニンマリとして、一冊、買った。 小林は家に戻ると早速、それを摘み読んで、失踪事件との関係を作り始めた。現実離れはして居るが、そんな事など言っては居れ無い。一通りのアイディアを纏めると、急ぎ原稿を書き上げた。読み返すと、想像以上の出来映えである。彼はその表題を、「怒りを買ったオカルトツアー・言代主の祟りか!」と、決めて、鉛筆を嘗めると、満足そうに書き付けた。彼にとって、それが真実であるか、どうかなど、もう、どうでも良い問題と成っていたのである。「何時も、真面目ったらしい謎解きでは、読者も飽きる、読み物として、面白ければ、おそらく、出版社も認めるだろう、これはあくまでも、ひとつの可能性だから」小林はそう、都合良く考えていた。だが、妙な感覚も脳裏を過ぎる。ひょっとして、自分は、いや、影浦は真実を書いて居るのでは無いのだろうか?何故かは知らぬが、そんな想像が脳裏を過ぎる。小林はふっと、問題の小説に視線を送った。だが、あり得ぬ話だ。彼は無視する様に視線を反らした。 その二 見慣れぬ女 宮城は二週間ほど前、渦潮の記事を一読して、筆者である小林に興味を持った。その男はサンツーリストの事件が宗教絡みである事を臭わせて居り、想定される邪教集団と言代主との関係にまで言及している。具体的な教団は調査中と言う事で、書かれては居なかったものの、確かな根拠で書かれたのなら、まだ見ぬ仲間、とも考えられた。すぐにでも会って話をしたいが、一応の調査は必要である。宮城は小林を探り始めた。小林のアパートは新宿駅の近辺の個人商店の建ち並ぶ、その裏手の住宅街に所在をしている。そこらの建物は皆古く、ビルの谷間に隠れる様に、ひっそりとした雰囲気で佇んでいた。 アパートの前の小路を渡ると、其処は小公園であり、その生け垣が目隠しの役割も果たしてくれる。張り込むのには、お誂え向きの位置取りだった。今、宮城は公園のベンチに腰を掛けて、其処からアパートを窺っている。宮城が張り込みを開始してから、既に十日が経過をしていた。だが、小林を仲間とする事は、とうの昔に諦めている。調べたところ、あの記事には、取材による裏付けが殆ど為されては居なかったのである。影浦の本を摘み読んで、ただ真似ただけの代物だった。 だが、あの記事そのものは問題である。仕事自体はいい加減でも、それは他のどの記事よりも実態に近い物だった。言代主が知ったなら、ただで済むとも思え無い。あの怨霊が何等かの動きに出る事は確かな様に思われた。「此処で待てば、必ず何者かが現れる」宮城はそう踏んだのだった。今、公園では、八、九人の幼い子供がゴム鞠の様に戯れている。滑り台を逆走しては、しきりと辺りを駆け回って、無邪気な歓声を響かせていた。「言代主の事など、幻なのでは無いのか?」その様な錯覚にも捕らわれる、のどかで凡庸なひとこまではある。 だが、事実は全くの逆だった。気付く者は数少ないが、無邪気に、はしゃぐ幼児達すら、邪悪な念に捕らわれ兼ねぬ、今の日本はそれ程の危機的状況にも在るのである。宮城は全神経を集中させて、まだ見ぬ敵をひたすら待った。そして、午前の十時頃、見慣れぬ女が現れた。小林の棟に近付くと、彼の部屋の前で立ち止まって、手紙の様な物を差し入れる。年の頃は二十七、八、服装は地味で、化粧気などは全く無かった。「町内会の回覧、てえとこかな?」宮城は気にも留めずに眺め見ていた。だが、様子がおかしい。こそこそと、しきりに辺りを窺うのである。「何だろう、あの女は?」一瞬、脳裏に疑念が走った。 と、女がアパートを離れて、歩き始めた。目で追うと、どうやら、新宿駅の方向に向かうのらしい。宮城はゆっくりと腰を上げると、女の後を追い掛け始めた。頭に被ったネッカチーフが付けるのには格好の目印である。女の警戒心も極めて希薄に見えるので、尾行はいたって簡単だった。だが、簡単過ぎる。「考え過ぎかな?恋愛か何かの縺れで、嫌がらせにでも来たのかも知れ無い」宮城は一瞬、足を止めると、女の姿を見送った。だが、スナックに入り浸りで、面食いの茂がこんな女を好むだろうか?「もう少し尾行を続けてみよう」宮城は再び歩き始めた。 女は小林のねぐらを離れると、新宿駅から国鉄の電車へと乗り込んだ。だが、どうも様子が普通では無い。時折、目付が鋭く変わって、辺りの乗客を見据えるのである。何か小馬鹿にした様な、薄ら笑いも時折、漏らす。だが、それは優越感の表れでは無く、鬱積をした劣等意識の裏返しの様にも思われる。その背後には、彼女の求める仮想世界を現実の様に錯覚をする、混濁した意識も垣間見られた。おそらく、彼女の劣等意識は何者に対しても屈し得ぬ、超越的存在を切望させた。また、その様な混濁をした意識の故に、それを得た、と思ったのである。だが、心の底では、偽物である事を知って居る。最前からの妙な態度はその様な心の奥底の無意識的な表現だった。そして、其処には、宗教的な偏執狂の、際だった特徴も見て取れる。何等かの宗教に関わる事は確かな様に思われた。そして、その宗教は邪教であるのに違い無い。女は益々、怪しく成った。ならば、小林の部屋に差し入れたのは脅迫状では無いのだろうか?宮城の予測はまさに今、現実のものに成ろう、としていた。 女は秋葉原を経由して亀戸で下車した。駅前の商店街を擦り抜けて、亀戸天神の方へと歩みを進める。「果たして、何処へ向かうのか!」既に住宅街の真っ直中で、人の通りも多くは無い。その分、尾行は難しかった。見失っては元も子も無いのだけれども、近付き過ぎると、覚られる。「こんな時、本職だったなら、どうするのだろう?」宮城は取り敢えず、距離を開けよう、と、歩速を緩めた。辺りが妙に静かに思える。「どうか、振り向いてくれるなよ」宮城はソッ、と呟いた。が、何故だろう?女の歩速がやにわに緩んだ。「気付かれたのか!」宮城は一瞬、肝を冷やした。だが、女は別に振り向きもせず、古びた一軒家へと吸い込まれて行く。「女のねぐらだろうか?」宮城は一瞬、近付こうか、どうしようか、と逡巡した。住人の目が気に掛かるのである。彼はゆっくりと辺りの様子を眺め回した。 此処は既に亀戸天神とは目と鼻の先で、一軒家ばかりが軒を並べた、何の変哲も無い居住区である。人の通りは多くはないが、それだけに、余りウロウロしていては、怪しまれぬ、とも限らない。「仕方がない、表札だけでも確認しよう」彼は通行人を装うと、家の前をゆっくり歩いた。だが、宮城が其処に見た物は表札では無く、白木で出来た看板である。其処には、墨で黒々と、「祈言宗 東京支部」と、書かれて在った。 |
|||||||
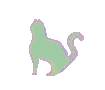
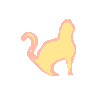
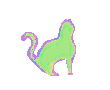
| |||||||
| Cotosiro | |||||||