|
可能世界・陰の神話 第十三章第二話 |
エミシの秘密 その一 This was revised in December 7, 2006. This was revised in September 20, 2008. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
かくして、野上は本来の愛瀰詩(エミシ)の意味を探り始めた。そして、彼は強い事を意味する愛瀰詩と、夷狄を意味する愛瀰詩との関係についても考え始めた。だが、それは彼にとって、そう簡単な事では無かったのである。それは彼が、恵比寿の神が古来からの神であり、倭人の神である、と言う信念に凝り固まっていたからだった。その故に、彼は愛瀰詩の持つ二つの意味が元来、別物であった、と言う事を望んだのである。だが、その考察の最中に、克服すべき問題が持ち上がった。彼が単なる想像として無視した例の同一神説がそれほど簡単には、無視出来ぬ事が分かったのである。野上が言った。「私は此処でも、大きな難関にぶつかりました、超えがたいほどの難関でした」そして、彼は一瞬、苦しそうに顔を歪めると、冷えた茶をゴクリ、と飲み干した。その様からは、野上が自分の信念と真実の狭間で、相当に苦しい思いをした事が窺い知れる。そして、彼がどの様な難関に遭遇したのかも想像し得た。影浦は自分の推測を試そうと、探る様に野上に問うた。「なるほど、同一神説と記紀の記述の整合性、エエト、つまり、同一神説を裏付ける様な記紀の記述が気に成ったのではないですか?」すると、野上の眼が見開いた。「エッ?何故、分かったのです?」と、驚きの色を隠さない。だが、彼の態度は大げさ過ぎて、影浦は少々、気分を害した。野上の性格は分かっているが、気分というものは御し難いのである。「いや、ちょっとした当て推量ですがね?」影浦はとっかかり、皮肉っぽい調子で、話を始めた。 まず、古事記の全体を見渡すと、それは大きく三つの部分に分かたれている。ひとつは神話部、次が象徴的歴史部と思われる神武紀から開化記の辺りまで、そして、最後が崇神天皇以降の歴史部である。少し注意をして、それらを見ると、その各部には、繰り返し、同じ主題が語られている事に気付く。それは天津神と国津神、そして、天尊族と畿内先住民族との歴史的な関係であった。此処に、野上を悩ませる問題があったのである。まず、その神話部を見ると、天尊族は大国主命、そして、言代主命などに国譲りを強いて、畿内の支配権を奪取した、と言う記事がある。その政治的な激変の結果、言代主命をはじめとする先住民の神々は多少の変質を余儀なくされた。だが、それら国津の神々は打ち捨てられる事も無く、大和の治世に入ってからも、各々の神社に祭られている。また、象徴的歴史部に見える神武天皇の東征に於いては、天尊族が八十建を打って、エミシを懲らした。だが、その後、天尊族は八十建の一族と姻戚関係を持つに至った、と言う記述も見える。 そして、歴史部に見える崇神天皇の時代、天皇は世情不安を治める為に、出雲族の意富多々泥古(オオタタネコ)なる人物を起用して、出雲族の神、大物主命を祭らせた。祟りを恐れての事とは言われて居るが、これは明らかに、出雲族の不満を和らげる為のパフォーマンスであり、政治的意図は明白である。つまり、これらの記事は天尊族が畿内住民を屈服させた後、懐柔をする為に、どう扱ったのか、を記して居るのであり、野上が其処に、神話部に見られる言代主と象徴的歴史部に見られる八十建の近似性、つまり、言代主と蝦夷との近似性を見出したとしても、それほど、不思議でも無かったのである。 言代主と八十建は共に、大和の勢力によって、追い詰められて、非業の最後を遂げている。八十建がエミシ、と呼ばれた事を其処に重ね併せると、言代主がエミシである事も想像し得た。しかも、彼等はほぼ、同一地域に出没して居り、共に縄文の臭いを発散している。ならば、同一神説が有力だった。野上は打ち破ろうとした風説を自分の研究が裏付け兼ね無い、と言う抜き差しの為らぬジレンマを背負ったのである。「どうでしょう、当たってませんか?」影浦はそう述べると、野上を覗いた。と、野上が首を項垂れる。「はい、ご推察の通りです、私は本当に疲れ果てて仕舞いました、何をする気にも成れません、軽い鬱病であったのかも知れません」推理を深めて、真実が見えて来るほどに、自分の信念は崩壊して行く。その精神的な苦痛には、計り知れぬものが在っただろう。彼が此処に、こうして居るのが、不思議な様にも思われる。いずれにしても、野上と言う男は極めて、不思議な人物だった。彼の様な気質であれば、都合の悪い資料など、無視をし勝ちなものである。よしんば、無視はし得ぬとしても、何らかの理由をこじ付けて、ねじ曲げて仕舞うものだった。事実、彼は既に、その様な事を遣っている。しかし、彼の探求心がその様な小賢しいこじつけを、彼の眼前に突き付けた。彼はそれがこじつけである、と自覚せざるを得なかったのである。野上は其処が並の人間とは異なっていた。論理の構築に当たっては、自らの信念を優先させるが、検証に於いては、虚心坦懐に資料を見ている。若くて、頭脳が柔軟である所為もあるのだろうが、やはり、ただ者では無さそうだった。そして、まさに、その事が野上自身を追い詰めた。彼は事実と彼の持つ硬直をした世界観との抜き差しのならぬ葛藤に追い込まれたのである。 野上は相当の努力家、と思われた。彼の話の端々に、知識の豊富さが窺い知れる。だが、その多くは知識のままに留まっていた。世界観には、何の寄与もし無かったのである。ある種の知識を受け入れたなら、彼の世界は混乱をして、崩壊すらもし兼ね無い。その様な恐れが在るものだから、彼は無意識に、その種の知識を自分の思考から排除したのである。幸か不幸か、硬直をした彼の世界はその事で、辛うじて、守られていた。だが、恵比寿の問題の探求が彼の世界観を揺るがした。真実を探ろうと欲すれば、受け入れ難い真実も真正面から見ねば為らない。信念と真実とは、二律背反の様に遠ざかり、修復のし様も無いのであった。彼はその事に耐え切れず、自らの精神を閉ざして仕舞った。鬱の病へと陥ったのである。並の人間であったなら、其処で終わって居ただろう。自分の狭い、誤った世界観にしがみついて、一生を終えたのに違いない。だが、彼は少し違ったのである。意識レベルの低下した中、黙々と想念の塵を寄せ集めつつ、まるで、陶芸師か何かの様に、幾度も幾度もこねくり回した。心の奥底から湧き上がる新たなる世界への道程である。彼に取って、鬱の病は再起の為の準備であった。野上が言った。「二年ほどは、そんな状況が続きました、ですが、ある朝、やにわに明かりが射し込んだのです、再度、この問題に挑む事が出来ました」 それまでの野上は日本人、という物を狭く固定的に考えていた。その文化も天尊族のものが受け継がれており、それは永遠のものである、と、彼は堅く、確信していた。だが、本当にそうなのだろうか?虚心坦懐に事物を見れば、永遠なるものなど、何処に在ろうか?永遠なる文化も、永遠なる国家も、永遠なる民族も、そんなものなど、在りはし無い。歴史を見れば、誰もが分かる事だった。文化や文明や民族の血は国境や山や海を越えて、至る所に伝わって行く。あるいは融合して、あるいは分離して、時として、衰退しながらも、多様な文化、文明を産み出して、多様な民族を作るのだった。日本人と言えども、その例外では無い。「当時、倭人と呼ばれた人々も、今の我々とは違って居ました」 日本列島には、縄文期、縄文人と名付けられた旧モンゴロイドが日々の糧を得る為に活動していた。また、多様な人々が少数ながら、絶え間無しに流入して、多様な文化をもたらした。そして、彼らは縄文人と混血して、多様な部族を作って行った。また、その血を受け継いだ人々は列島の中で、数多くの交易、闘争を繰り返す。そして、その文化や血を融合させて、時には、分岐させて、大勢に於いては、政治的、文化的統合へと進んで行った。弥生と呼ばれる激動の時代がそのテンポを急速に早めたのである。弥生から古墳の時代へと至る期間は列島諸部族融合による倭人創生の時代、とも言えそうだった。だが、漢人によって、倭人と呼ばれた弥生人に、同一民族としての自覚は在ったのだろうか?そこら辺りは疑わしかった。発掘された骨の形状から遺伝的特徴には、差の在った事も認められる。その事は当時の弥生人の意識にも、反映をされた筈だった。おそらくは、その言語も今以上の違いが在った、と想像出来る。当時、「倭」と、呼ばれた彼等に取って、「倭」は、あくまでも、漢人の概念だったのでは無いのか?野上はそう考えた。だが、その概念が弥生人の民族意識を触発して、助長した事は考えられる。各部族の交易、戦闘、更には、その融合を通して、彼らの民族意識はより明確なものへと進化をしたのに違い無い。 ならば、エミシの源初的な概念も、その過程で、産み出されたのでは無いのか?そして、その概念は北九州で産まれたのでは無いのか?野上の脳裏には、その様な閃きも過ぎったのである。時代は少し下るが、中国の魏志倭人伝(東夷伝)には、卑弥呼の統治する女王国の事が記されている。それは邪馬台国を中心とする連合国家の概要であった。野上はその中に、注目すべき記事を見出したのである。其処には、女王国の東の海を渡ると、また国が在り、其処には、倭種が住んでいる、と記されている。この倭種、という極めて奇妙な概念が野上には重要な様に思われた。野上は女王国の位置を北九州の何処かに在った、と考えている。倭人伝の記述、遺跡などの分析、そして、その宗教形態などを考慮に入れると、そう考えるのが最も自然で無理が無い、と考えたのである。ならば、女王国の東の海を渡った土地は今の四国か本州である。其処に倭種が住んで居た。だが、東夷伝(魏志倭人伝はその一部)が北九州の弥生人を倭人と呼んだのに対して、その東の地の住人を倭種と呼んだのは奇妙に思える。倭人なら、単に倭人、と書くだけで良いでは無いか?それをあえて、倭種と表現した裏には、何か奥深い理由が在りそうだった。おそらく、北九州の弥生人は邪馬台国の成立以前から、四国、及び、本州の弥生人に多少の異質性を感じて居た。その血に近いものを感じながらも、全くの同一種族とは思わ無かった。そして、漢人はその様な説明を斟酌して、それを「倭種」と、表した。野上はそう推測をした。 一方、北九州の弥生人には、彼我を分け隔てる言葉が必要だった。そして、自らを呼ぶ倭人、という言葉を輸入した様に倭種、という言葉も輸入したのではないのか?野上はそう考えた。おそらく、当時、北九州の弥生人はそれを倭の種(ヲノシュ)と、発音した。そして、野上はそれをヲノシュ、エヌス、エミシ、などと変化して、愛瀰詩、と成った、と考えた。奈良から平安期に掛けての愛瀰詩の発音の変遷を考えると、そう不自然でも無く、野上はこの考えが気に入っていた。「愛瀰詩の源初的な意味は此処から出たのだ、と思うのですが」野上はそう一気に話すと、穏やかな表情で、微笑んだ。地獄の苦しみから逃れ得た開放感の表れだろう。だが、愛瀰詩が輸入された概念などとは、さすがの影浦も首をひねった。「こじつけに過ぎるのでは無いのか?」そんな想いが先に立つ。だが、当時の状況や漢人と倭人の文化レベルを考慮に入れると、あながち間違い、とも切れ無かった。 当時、弥生人はあらゆる文化や物品を大陸から持ち込んで、吸収している。事物の呼び方にしても、例外では無い。それは自らを表す「倭」にしても同様だった。無論、各々の部族名はあったのだろうが、民族を表す適当な言葉はおそらく無かった。その故に、倭人、という言葉を輸入した。部族融合が進む中、必要とされたからだった。だが、北九州の弥生人が本州の弥生人に異質性を感じていたのなら、彼らを倭人と呼ぶ事は無かっただろう。其処で、倭人と同様に、倭種という言葉も輸入した。野上はそう考えたのに違い無かった。だが、当時、「倭種」を「ヲノシュ」などと、発音したのかどうか?そして、それが野上の言う様な音韻変化をしたのかどうか?そこら辺りは微妙に思える。「なるほど、そうなのかも知れませんね」影浦はそう言葉を濁して、あえて、同意は与えなかった。野上が言った。「ええ、この事は間違い無い、と思います、そして、北九州の弥生人達は、その倭の種の力を過大に評価して居たんです」 |
|||||||


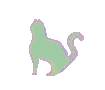
| |||||||
| Cotosiro | |||||||