|
可能世界・陰の神話 第十三章第三話 |
エミシの秘密 その二 This was revised in September 20, 2008. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
北九州の弥生人が倭の種の力を過大に評価していた、と言う野上の話は影浦にも、分かる様に思われた。だが、野上がどの様な根拠で、そう言うのかは、聞いてみなければ分からない。「さて、どう言う事でしょう?」影浦は少し首を傾げると、そう問うた。すると、野上が自信ありげに語り始めた。野上に拠れば、それはデマが一人歩きを始めると、途轍も無い怪物に変貌をする、その様な状況に極めて、似ていた。弥生時代、列島各地の情報は主に交易の担い手を媒介として、様々な地へと運ばれている。そして、北九州の弥生人も、彼等からの情報で、外の事情を知ったのだった。その中には、東方の弥生人、つまり、「倭の種」の情報も含まれている。遥か東方にある作物がたわわに稔る肥沃な大地、そして、豊かなる文化を誇る精錬された人々。「倭の種」の話はその様な美しい色付けを施されて、誇張をされて、伝わったのに違い無かった。それらの情報は絶対量が少なく、また、幾度かの中継を経て、伝えられる物も多いので、誇張をされて、変質をした事はむしろ、当然である様に思われる。つまり、情報が不完全である為に、古代人の想像力は嫌が上にも、掻き立てられたのである。 その事は中国の山海経を見ても、想像が付く。話に尾ひれの付く事は想像するに難くは無かった。遥か東方の倭の種の国は豊かで、強大なる力を持つ、と言う鮮烈なイメージによって、彩られたのである。そして、その様な鮮烈なイメージは畿内文化への憧れと共に、倭の種の国からの侵略と言う恐怖心をも募らせた。だが、当時、彼等の実際の敵は近隣に巣くう他部族である。倭の種への彼等の恐れは少なくとも、その時点では、現実的脅威とは言い難かった。古代人に特有の知られざるものへの恐怖感、そう言った方が的確である。だが、古代人の彼等に取って、現実的脅威と心理的な不安とに、明確な区別など在ったのだろうか?真剣に心配をしたのに違い無かった。しかも、当時の弥生人は小さな部族が衝突し合って、戦乱の真っ直中に在ったのである。もし、倭の種の大国が襲って来たなら、狭い内海など、苦も無く渡って、津波の様に押し寄せるだろう。その意味では、大陸からの侵攻などとは、比較にも成らぬ脅威であった。そして、その様な印象が長年に渡って、蓄積をして、北九州の弥生人の潜在意識へと刻み込まれた。更に、その様なイメージが荒ぶる神々として、彼らの深層に心的印象を成したのである。 だが、その一方で、彼等はその様なイメージに自らの姿も投影していた。彼等の血の基層には、縄文人の血が受け継がれて居り、その心にも、縄文の魂が受け継がれている。その事がしばしば、彼らのいにしえの記憶を呼び覚まさせた。そして、自分達と畿内住民との近縁性を意識させた。かくして、「エミシ」は脅威と郷愁、そして、神秘性と親近感、それらを同時に併せ持つ特異にして、神聖なる概念として、彼等の心に刻まれたのである。また、その事が古代人のロマンを更に掻き立てて、東方への志向を益々、強めた。無論、大和の東征も、この事が下地に在ったのである。また、倭の種、と言う極めて特異な言葉には、霊的な概念も垣間見られる。既に、この頃、夷(エミシ)の神は自らの登場を予感する胎児であった、とも言えるのである。「ですが、影浦さん、夷が祭られたのは、ずうっと、後の時代、そうですね、やはり平安期に入ってからだ、と思います」野上はそう述べると、まるで、同意を促す様に、影浦の顔を覗き見た。だが、影浦は小首を傾げた。その事は誰もが認める話であって、殊更に言う程の問題ではない。影浦は無言で、野上に視線を送った。と、野上が言った。「先ほども、申しましたが、確かに、恵比須の神の萌芽は弥生時代に芽生えて居ました、ですが、神として意識をされるのには、まだ幾つかの条件が必要であったのです」 北九州の弥生人は愛瀰詩に荒ぶる神々のイメージを抱いていた。更に、自らの魂をそのイメージに投影していた。その意味で、愛瀰詩の原初的な概念には、霊的な要素が内在していた。だが、それは愛瀰詩と言う現実の対象が在ってのイメージである。未だ、神の要件は欠いていた。「でも、影浦さん、その要件が平安時代に整った理由、お分かりでしょうか?」野上が突然、そう問うた。 だが、やにわに、漠然と問われても、そう簡単には、思い付かない。野上が自分で説明せず、殊更に、そう問い掛けた意味も分からない。「きっと、自慢をしたいのだ」影浦はそう考えた。そして、あれこれと考えるのも、面倒臭いし、あり合わせの知識で、正解が出るとも思えない。「さあ、何でしょうね?」影浦はあっさりと、降参して、そう問うた。野上が言った。「実を言いますと、その要件は大きな歴史的変動の為に、整ったんです」北九州の弥生人は漢人との接触や朝鮮半島との関わりから、大陸の激動を目の当たりにして、心理的な圧迫を受け続けていた。そして、その事が北九州諸部族の統合を促し、また、武力増強の圧力を強めて、彼らの戦闘能力を高めたのである。だが、その間、畿内での武力の増強は幾分、緩慢と思われた。それより以前、部族間ルールが確立されて、ある種の政治的な統合が完成しつつあるからだった。大国主を戴くかなり緩い部族連合がそれである。畿内はその事によって、政治的な安定を得て、農業生産、そして、経済の活動に集中をする事が出来たのだった。独自な文化の高度な進化も想像するに難くは無かった。 だが、やがて、畿内の繁栄にも、暗い影が落とし始める。彼等の奢りと大陸の激動の嵐の故である。北九州では、曲がりなりに、周辺部族を統一した邪馬台国の時代、また、大陸では、魏、呉、蜀の三国並立の時代から晋の時代に掛けて、中国は朝鮮半島への影響力を弱めざるを得なかった。中国内部の覇権争いの故である。そして、その様な大陸の混乱が、朝鮮半島の全域を激動の淵へと引きずり込んだ。北方では、高句麗が力を伸ばして、半島の覇権を窺っている。そして、半島の諸部族も覇権を争い、新たな秩序に向けて動き始めた。後年、それは百済、新羅、として立ち現れる。だが、その激動は半島だけには留まら無かった。その波紋は海をも渡って、日本の列島へと押し寄せたのである。北九州の倭人に取って、その影響は特に深刻だった。半島の激動を押さえるべき中国が頼りに成らない当時、半島の政治的不安定は取りも直さず、北九州の倭人国家の問題でもあったのである。彼等はその様な問題の解決策を模索した。だが、その為には、早急に部族連合から脱却をして、より強力な国を造らねば為らない。その故に、彼等の軍事力は益々、強大と成ったのである。そして、邪馬台国の政治的な求心力も増したのである。当然ながら、その様な状況は同時に、支配地域の拡大を要請する。北九州の連合国家、大和の東征はまさに、この過程で為された出来事だった。彼等は初めから、畿内を目指して、進軍をしたのである。 大和に取って、北九州は余りにも、大陸に近過ぎる。政治的な激動に何時、巻き込まれぬ、とも限らぬのである。その事が大和に政治中枢の移動を強いた。また、その故に、大和は支配地域の拡大を意図したのである。大和は畿内に向かうしか、仕方が無かった。愛瀰詩の国、畿内はあらゆる面で、その様な大和の要請に適合していた。大陸からは適度に離れており、良港や作物の豊富に採れる土地も在る。政治の中枢を其処に置くなら、大陸の激動にクッションを置いて、耐え得るだけのゆとりも持てる。事実、大国主の連合国家はその様な環境の許で、豊かなる発展を遂げたのである。おそらく、当時の畿内は縄文の魂と弥生の文明とをミックスして、ある意味で、最も倭人らしい、その様な文化を誇ったのである。だが、北九州の大和は羨望を持って、その様な繁栄を垣間見ていた。そして、我が物にせん、と欲したのである。いにしえからの愛瀰詩への潜在的な恐怖など、大陸の激動から来る危機から見れば、物の数でも無かっただろう。彼等は蛮勇を以て、東へ上った。そして、おそらく、その東征には、激動の朝鮮半島から逃れ出た伽耶の一族も加わっていた。彼等の国は日本で言う任那の位置に当たり、北九州の大和とは親密であった、と考えられる。任那の位置は新モンゴロイドの文化と旧モンゴロイドの文化との最後のしのぎあいの場であった、と思われるので、古代日本語の使用すら、在り得ぬ事とは思われない。いずれにしても、その様な事情が大和の主張する任那領有の根拠であった。ちなみに、この問題は既に、時間が解決している。 いずれにしても、当時、東アジアの歴史の流れは急速に、部族国家から民族国家へと進化をしていた。核と成る部族が相次いで現れて、周辺部族を統合しながら、政治的な求心力を更に強めたからだった。その激動は海をも渡り、大波と成って、日本を襲う。列島は騒然としたのに違い無かった。だが、その波に上手く乗った大和に対して、大国主の部族連合はその形態が完成し、爛熟の域に在ったが為に乗り遅れた。自らの豊かさに安住し、危機への対応を怠ったのである。結果、畿内は大和によって、無惨なまでに蹂躙された。相手は着々と武力を磨いて、体制の強化を計って来た大和である。如何なる策謀も役には立たず、勝負は初めから決着していた。だが、畿内文化の遺産の多くは大和によって、引き継がれた。征服民、懐柔の為でもあったのだろうが、その背後には、奥深い心理的要因も隠されている。大和が古代から引き継いだ愛瀰詩に対する憧れと劣等意識、それがその要因だった。その故に、出雲の神々を祭った如く、その文化をも継いだのである。野上は言った。「実は、影浦さん、エミシの概念は此処に至って、変わらざるを得なかったんです」愛瀰詩の多様な概念は大和東征の成功と共に、概念の分裂を余儀なくされた。混沌の中に統一された多様な意味が次第に明確と成って、意識をされ始めたからだった。 その昔、愛瀰詩の概念は倭の種という具体的な対象によって成立していた。つまり、荒ぶる神々や縄文の魂への郷愁は、その対象が在っての話であった。しかし、その対象は今や、次々と大和の中に吸収されて、その特徴を失いつつ在る。つまり、倭種は倭人と成り、愛瀰詩の概念の中核が其処で、まさに消えんとしていた。そのままでは、「愛瀰詩」はもう、死語と成るしか仕方が無かった。しかし、「愛瀰詩」の概念はしたたかに生き延びたのである。大和の現実的要請と彼等の内なる魂が「愛瀰詩」を欲したからだった。そして、その現実的要請とは、大和の歴史と神話の再編、及び、その記録への要請だった。自らの系図と、その足跡を明らかにして、その精神的柱を確立せねば為らない。愛瀰詩はその物語に於いて、重要な役割を背負わされていた。これを除いては、歴史そのものが成り立た無い。だが、畿内の旧支配部族(倭種)をその体内に取り込んだ今、愛瀰詩の概念をその侭にして、記録する事は難しかった。多少の変更はせねば為らない。其処で、大和は策略を巡らせた。そして、都合の良い事に、言代主の残党がそれとは知らず、その役割を担ったのである。彼等は縄文の精神と、少なからず、縄文の血を引き継いで居り、しかも、大和には、まつろわ無かった。渡りに船とは言え無いまでも、それはまさに、大和に取っての在るべき愛瀰詩、と言えたのである。大和は北に逃れた残党を愛瀰詩、と呼んだ。これならば、旧支配部族(蝦夷の末裔)も表だった反対などせぬだろう。大和はそう計算したのである。 一方、再三に渡って戦いに敗れた言代主の一族は次第に、北方のいわゆるエミシと混血して、その血は益々、縄文的色彩を濃くして行った。愛瀰詩の呼称がアイヌの先祖、あるいは同型種と思われるエミシを指し始めたのは、その為なのに違い無い。だが、それは蝦夷の概念に本来、潜む縄文的色合いの故でもあった。無論、当時の倭人が其処まで意識したとは思え無い。だが、彼等の無意識はどうだったろう?そうした事を感じて居ても、不思議な事では無さそうだった。さて、一方、精神的な面に於いても、愛瀰詩の概念は必要だった。だが、その心情が投影される昔の愛瀰詩はもはや、無い。夷狄の愛瀰詩が在るだけである。その故に、その様な大和の心情は新たなる愛瀰詩を希求して、心の愛瀰詩が呼び起こされた。猛々しく、しかも、懐かしい心のふるさと、愛瀰詩。その心情は今や、旧支配部族のものとも成って、ついには、人としての愛瀰詩から精神的愛瀰詩を遊離させて、神格化への萌芽を産んだのである。既に、精神的な愛瀰詩は切っ掛けさえ在れば、神と成り得た。そして、その動きは蘇我氏の衰退と共に始まった。 |
|||||||
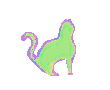


| |||||||
| Cotosiro | |||||||