|
可能世界・陰の神話 第十三章第四話 |
神と成った恵比寿 This was revised in December 7, 2006. This was revised in September 20, 2008. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
恵比寿が神として、登場の時を窺っていた丁度その頃、蘇我氏の権勢は他の追従を許さぬまでに高まって、主である筈の朝廷を欲しいがままに操っていた。だが、少し不思議な事がある。蘇我氏は何故、自らの精神的柱に仏教を据えたのだろうか?本来ならば、日本古来の神々がその位置には座るべきだった。当時、仏教には、拒否反応を示す氏族もそう少なくは無かったのである。事実、蘇我氏はその為に、多くの政敵に悩ませられた。だが、蘇我氏の一見、奇妙に見えるその様な選択には、そうせざるを得ぬ理由があった。蘇我氏が実権を握る少し前、祭と政の体制は物部氏など、古来の神々を奉る有力氏族に握られていたのである。新興の蘇我氏が彼等を凌ぐのには、旧来のその様な体勢に風穴を開ける事が必要であった。一見、信仰心から、と思われる仏教重用の背後には、その様な政治的意図が関わって居たのである。 だが、それは意識に於ける原因であって、その底流には、無意識による動因が深く密かに蠢いていた。そして、その動因とは、多くの氏族に共通の、神々の体系への冷めた心と秘めたる根深い反逆心だった。無論、それは自らの神々が大和の神々の下に置かれて、変質を余儀なくされたからである。蘇我氏の隆盛はその様な情勢の成さしめた、当然の帰結であったのかも知れない。また、この事は蘇我氏が帰化氏族と旧支配氏族、双方に関わる事を暗示していた(此処に言う旧支配氏族とは、大和に国譲りをした先住氏族を指す)。蘇我氏がいずれの系統から出たものなのか?野上は先住氏族の色が濃い、と考えたが、通説は帰化氏族の方へと傾いている。 いずれにしても、蘇我氏がそれら氏族の不満を利用して、巧みに操った事に変わりは無かった。大和の神々の体系などは蘇我氏に取っては、邪魔だったのである。そして、それは多くの氏族に共通の秘めたる心情でも在るのであった。無論、皇室を戴いた彼等としては、その様な心情を露骨に表明する事は難しい。もし、その様な心情を露わにしたなら、失脚の憂き目を見る事は日を見るよりも明らかだった。その故に、彼らは大和の神々の体系を建前上は尊重しつつ、内面的な、精神的な拠り所については、それを仏教に求めたのである。つまり、彼等の仏教への肩入れは精神的な不満から来る代償行為であった、とも言えそうだった。さもなくば、皇室を利用して、自らの利益を計る様な伝統は生まれ無かっただろう。ちなみに、この伝統は大東亜戦争の時代のみ成らず、今も根強く残っている。 さて、仏教に異を唱えた物部氏は蘇我氏との政治闘争に敗れて、衰退した。また、その様な情勢の許で、皇室の実権も失われつつある。政治の実権は蘇我氏が握って、当時の日本の政治は氏族の新たなる連合による集団的指導体制によって、行われる様に成っていた。では、具体的に、どの様な経緯で、皇室の実権が失われて、集団指導体制が産まれたのだろう?野上はまず、新しい帰化氏族の存在に目を付けた。彼等は仏教との関わりが極めて、深い。その分、大和の神々への想いは薄く、その事が相対的に皇室の権威を失墜させた。また、先住氏族の復古意識も関係した、と考えられる。いにしえの部族連合への郷愁である。その事が蘇我の氏族を保護者と成した、集団的指導体制を産んだのである。そして、おそらく、これらのもたらす状況は他の氏族の権益とも一致した。蘇我氏の力はその様なバランスの上に成り立っていた。時代は貴族政治へと向かい始めた、かにも思われた。 ところで、蘇我氏がもし、先住氏族の末裔ならば、先住氏族にも、政治の中枢へ返り咲く、その様な可能性が残されていた。既に、皇室には、蘇我氏の血が色濃く流れており、皇位継承に付いても、蘇我氏の影響力は絶大である。蘇我氏がその事を望んだならば、皇室そのものの奪取すら、不可能な事では無いのであった。神話の根底に仏教を据えて、新たな神話を構築すれば、事は足りる。後は政治力だけの問題だった。皇位継承者が常に健在とは限ら無い。然も無くば、蘇我氏自らが手を下して、チャンスを作るだけだった。 だが、蘇我馬子の子、蝦夷はその様には動かなかった。同族である聖徳太子の一族に対抗意識を持つ余り、太子の子、山背大兄王を退けて、田村皇子(後の舒明天皇)を推したのである。そして、聖徳太子の一族の追い落としまでも謀って行った。どうやら、蘇我蝦夷には、新たな神話を構築し得るだけの思想が無かった様である。逆の側面から見るならば、当時、既に、大和の神々の体系は固定観念として、相当に人々の心に染み込んでいた、とも言えそうだった。その故に、蘇我氏は皇室を利用する事で、満足をしたのではないのだろうか?だが、実を言えば、これは権力の論理と矛盾する。権力は元来、その権力固有の精神的な拠り所を必要とするからである。いずれにしても、蘇我氏は状況を見誤って、恐ろしい迷路へと迷い込んだ。そして、それとは知らずに、奈落の淵へと歩んだのである。 さて、舒明天皇は馬子の娘を娶ったとは言え、山背大兄王に比べると、蘇我氏との血の関わりは薄かった。仏教の扱いにしても差が在って、求める体制にしても同様である。その事はすぐに、天皇と蘇我氏との亀裂と成って、表面化した。明らかに、蘇我氏は協力すべき相手を間違っていた。だが、それは権力を目指す者の宿命の様にも思われる。血縁の濃いライバルこそが最も危険な存在だった。だが、蘇我氏のその様な迷走は皇室の復権を密かに狙う何者かの誘導であった、とも考えられる。蘇我氏同様、仏教を重んずる聖徳太子と、その一族もまた、その何者かに取っては邪魔だったのである。いずれにしても、蘇我氏の関わる一連の事件は皇室に漁夫の利を与えたのらしかった。 注 ; 聖徳太子は実は、景教(キリスト教系の宗派)を信仰していた、と言う説がある。だが、景教と仏教とは、その深い部分で共通性を持っているので、当時の社会的な状況を勘案すれば、国を治めるに当たって、彼が仏教を重んじた、としても、不思議ではない。当然ながら、景教を表だって、取り上げたなら、恐ろしい混乱を招く事は必死であったからである。 さて、蝦夷の子、入鹿は意に染まぬ舒明天皇に対抗する為、自らの一族である古人皇子を太子に推した。古人皇子が太子に成れば、実際の政治は彼が行う。蘇我氏の意向も通り易い。実権は蘇我氏に戻る筈だった。だが、もう一人の実力者、山背大兄王が邪魔だった。入鹿は何と、彼を暗殺して仕舞う。其処に至って、全ての邪魔者は沈黙して、恐怖政治の荒波が巷を覆うか、にも思われた。だが、事はそれほど、単純でも無い。入鹿の計算は大きく外れた。 丁度その頃、皇室と蘇我氏との確執は決定的なまでに高まっていた。表面下では様々な策謀が交錯している。その中心には、舒明天皇の子で、その後継者とも目される中大兄皇子が居り、蘇我氏の追い落としを画策していた。其処に、山背大兄王の暗殺である。天皇側の憎悪の念には、計り知れぬものが在っただろう。そして、此処に至ると、その心情はその他の氏族にも言えるのだった。恐怖政治では適わない。人々の心はまるで潮でも、引くかの様に、蘇我氏の下から離れて行った。 「動き出すのなら、今しか無い!」中大兄皇子と中臣鎌足(後の藤原鎌足)は兼ねてよりの計画を今、する事に決めたのだった。そして、入鹿は彼らによって殆ど、公然と殺された。無論、これはリンチであるから、本来ならば、入鹿を殺した鎌足等は何らかの咎めを受けて当然であったが、その殺害は半ば、公然と支持された。多くの氏族が持っていた蘇我氏への鬱積をした憎悪の念の故である。いずれにしても、蘇我氏の隆盛はこれで終わった。そして、天皇の復権が成し遂げられた。同時に、藤原氏の隆盛も約束をされたのである。 だが、これは蘇我氏の失敗と言うよりは、氏族連合への志向と言う、時代錯誤のもたらした必然的悲劇、とも考えられる。中央集権の流れに竿を刺して、敗れ去ったのに違い無かった。それとも、イデオロギーを見失った精神的混迷にでも因るのだろうか?いずれにしても、時代が大きく動いた事は確であった。これが大化改新のあらましである。 だが、天皇を中心とする新勢力には、未だ、大きな不安が存在していた。何時また、蘇我氏の様な勢力が頭を擡げぬ、とも限らぬのである。それを未然に防ぐ為にも、大和政権の正当性を内外に知らしめて、その精神的拠り所を明確に示す事が必要だった。そして、その仕事は鎌足の子、不比等とその盟友、太安万侶らの太氏一族によって成し遂げられる。古事記、日本書紀の編纂である。(古事記、日本書紀は纏めて、記紀、と呼ばれている)大和政権はその事で、ようやく、宗教的権威を取り戻した。そして、政治的な正当性を確かな物へと高めたのである。 かくして、記紀(古事記、日本書紀)は各氏族の神々を天照大御神の下に置いて、鉄壁なヒェラルキーを形作った。その神々の階層は概ね、各氏族のランク付けとも成っている。以前から、大和の神々の体系に漠然と内在していた事柄が文書として、明確に示されたのである。その書の内容を知った旧支配氏族は複雑な想いを抱いたのに違い無かった。無論、その書には、縄文の魂が欠落しており、いにしえの自由な神々は天照大神の出来の悪い弟など、として、影の部分に追い遣られている。そして、その様な神々は弱き者、服従すべきもの、として描かれていた。つまり、記紀は内的信仰心を満足させるものとは成り得なかった。そして、その様な心情は旧支配氏族のみ為らず、全ての氏族の心情でもある。それは無論、自らの一族の貴重な神話が皇室や藤原氏などの政治的な都合によって、変えられてしまったからである。彼らの氏族の誇りが少なからず、損なわれた事は確かであった。 無論、彼らがその様な自分の心情をどの程度、意識していたのかは分から無い。たが、彼等の魂が内的信仰心の新たなる拠り所を希求した事は確かであった。皇室の復権にも関わらず、仏教の普及が進んだ裏には、その様な事情もあったのである。だが、記紀編纂の反作用はそればかりでも無さそうだった。記紀はいにしえの部族連合への回帰志向、つまり、縄文の神々への郷愁を厭が上にも、掻き立てたのである。だが、大和の支配が盤石と成った今、その様な部族連合への回帰など、もはや、現実的願望とは成り得ない。その故に、彼等はそれを精神的なものへと転化した。縄文の心の拠り所として、心の愛瀰詩を求めたのである。仏神融合が進んだ裏には、その様な事情も在るのであった。神を仏とする事で、大和の神々の体系から、自らの神を解き放ったのである。 「如何でしょう、こう考えて来ますと、恵比須の神の誕生も、見えて来る様に思うのですが」野上はそう述べると、一息、付いた。影浦が言った。「つまり、縄文の心を体現する神が必要だった、そして、内的恵比須が意識をされた?」野上が答えた。「エエ、都が平安京に移される頃には、雄々しく戦った過去を回顧する風潮も在ったのでは無いのでしょうか?」「うん、その心情が内的恵比須を呼び覚まして、祭る事と成った?」影浦がそう話を受けた。と、野上が深く頷いた。そして、言った。「はい、そうです、話は少し変わりますが、私はこの事に、恵比須と言代主命との運命的な奇縁を感じるんです」 恵比須の神は元を正せば、北九州の倭人達の意識から出たものであり、言代主命は愛瀰詩の代表として、祟らぬよう、大和が祭った神だった。違う神で在る事は明らかである。だが、その神々は同じ縄文の心が産んだ共通の根を持つ神々であった。恵比須は荒ぶる愛瀰詩のイメージが縄文の魂と結び付いて、意識をされた神であり、また、一方の言代主命は愛瀰詩として自らの魂を守ろう、と、最後まで抵抗をしたが、敗れ果てて、恨みを持って、隠り身の神と成ったのである。陰陽の違いは在るものの、その想念には、相通ずるものが在りそうである。そして、その事は言代主の怨念が恵比須に伝わって、共振し得る事も暗示していた。野上の抱える大問題とは、まさにこの事に他ならなかった。 野上が言った。「私が先生の本を読んだのは丁度、そんな時でした、私は大変な衝撃を覚えました、縄文の魂への抑圧は、まさに恵比須への抑圧でもあったからです」恵比寿は何時からか、荒ぶる神では無く成っていた。縄文の魂を押さえられて、腑抜けにされて、福の神へと貶められた。余りにも、無惨な変貌である。恵比須の魂は忘れられて、今や金欲や物欲だけが恵比須を祭る理由なのである。「恵比寿が祟りを為したとしても、少しの不思議も無いんです、どうか、為すべき事をお教え下さい!」 だが、影浦は幾分、戸惑った。「自分のメッセージが伝わって居ないのでは無いのか?」その様な疑念も、心を過ぎる。おそらくは、理屈だけの解釈だった。だが、言代主は現実に、祟り神と成って、現れている。彼の疑問に答える為には、そうした事も言わねば為らない。だが、野上の場合、その事を正直に告げるのは危険な様に思われた。影浦には、三木に付いての苦い経験が焼き付いている。彼の精神の状態は今、日を増す毎に悪化しており、回復の兆しすら、見せてはいない。野上には、その様な二の舞など、させたく無かった。影浦は魂の深みで考えるよう、彼を諭すと、仕事の都合を言い訳に、引き取るように促した。後は、野上自身の問題であり、其処に無闇に立ち入る事は慎まねばならない。影浦はそう考えたのである。 |
|||||||
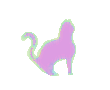
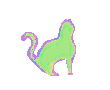
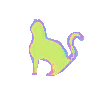
| |||||||
| Cotosiro | |||||||