|
可能世界・陰の神話 第十四章第二話 |
神々の里 This was revised in December 8, 2006. This was revised in Novembar 25, 2007. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
影浦はこのところ、ふと気が付くと、野上の事を考えていた。あんな具合に帰した事が心の何処かに、わだかまって、後ろめたい気分に陥るのである。今にして思うと、野上に真実を告げなかった事がその原因であった。彼の鋭敏な洞察力に対して、それは余りにも、不遜であったのではないのか、と言う後悔の念があったのである。だが、今と成っては、致し方ない。野上が彼自身の力で、真実を見抜く事を期待するしか、仕方がなかった。それにしても、野上の語った恵比須の話は彼の凡庸では無い才能を窺わせている。影浦は今、その洞察と発見とに、大きな刺激を受けつつあった。其処には、野上本人ですら気が付かぬ、奥深い真実も隠されている。それは恵比寿と言代主命との間に横たわる深遠なる魂の関係であった。つまり、恵比寿は言代主命の本来あるべき姿であって、実の所、怨念の無き、縄文の魂の具現なのである。 言代主の魂が怨念に汚れた自らを厭って、恵比寿と言う神を呼んだのではないのか?影浦には、そう思われて、仕方なかった。そして、その発想をもたらしたのは、野上の研究に他ならない。野上の飽くなき執念が、恵比須の神の誕生の具体的な経緯を掴んだのである。無論、影浦も、縄文の魂が各々の時代を通して、日本人の心に引き継がれて、恵比寿に於いて具現した、その理由に付いては認識していた。熊野が以前、見抜いた如く、脳の音への反応がその様な魂を保ったのである。 だが、それは単なる物理的な反応では無い。縄文の文化と魂の特筆をすべき力であった。さすがの野上も、この様な背後に隠れた動因と大きな力には、気付いて居ない。言代主、恵比寿同一説への余りにも、強い敵愾心が彼の思考を狭い範囲に押し留めたのである。彼は確かに、自分の硬直した世界観に気が付いて、もっと、柔軟な世界観へと修正した。だが、長年、培われて来た習性は恐ろしい。彼はやはり、気付かぬ内に、ある種の知識を自分の世界観から、排除したのである。だが、縄文の魂が歴史の上で、どの様にして引き継がれたのか?野上の鋭い洞察力は其処に於いて、輝いている。影浦は今、其処から受けるイメージを自らの推理に組みつつ在った。 鳥取県の八雲村には、神代に創建された、と言われるほどの古い歴史を持つ熊野神社が在る。祭神は熊野大神とも言われる神祖熊野櫛御気野命(カムロキ、クマヌノクシミケヌノミコト)である。この神は極めて、古い神らしい。ならば、この意味の不明な神の名は縄文語で、出来ているのでは無いのか?そして、それは神産霊神、高皇産霊神などと同様に、縄文語の系譜に属する、と思われるアイヌ語で解読をする事が可能なのでは無いのか?影浦はそう考えたのである。そこで、彼は早速、辞書を持ち出して、アイヌ語での解読を試みた。すると、それは予期した以上に上手く填った。「神祖熊野櫛御氣野」はアイヌ語で「kamuy-rok-kuma-nesir-mek-ka」の様に分解をする事が出来たのである。 まず、一見、枕詞の様に見える「神祖」(kamuy-rok)は日本語で、「かむろき」あるいは「かふろき」などと読む。(カフロキはカムロキが訛ったものである)無論、此処に当て填めたアイヌ語の「kamuy」は神を意味しており、また、「rok」は座る事を意味する複数形の動詞である。その故に、「Kamuy-rok」は熊野大神が元々は単身の神では無く、複数の神々で在る事を明示していた。また、「kuma」は魚などを吊して干す為に横に渡される木の棒を意味しており、それは転じて、横に長いものを意味するのである。その後に続く「nesir」は山を意味する。従って、「kuma-nesir」は「連山」を表す言葉であった。 その事は熊野の地名が連山を背景とする山間に点在する事からも窺える。熊野は実は、野原などでは無く、山地を表す言葉であった。そして、「mek-ka」は刀の嶺を表している様に思われる。つまり、「mek-ka」は本来、畝の形を表現するので、山の連なる形状を刀の嶺に見立てたものと思われるのである。従って、「かむろき・くまぬのくし・みけぬ」は「カムイロク・クマネシル・メクカ」と、読まれるべきであった。つまり、神々が刀の嶺状の連山に腰掛けて集う心的印象、として解釈し得た。江戸時代の国学者、本居宣長はこの神を須佐之男命であろう、と述べたけれども、この神は実は、複数の神々であるから、彼の解釈は間違いである。 だが、現在の通説はこれを「熊野に座す奇霊の神」と解釈している。つまり、「くまぬ」は熊野、という地名であって、「櫛御=くしみ」は「奇霊=くしひ」の変化したものであり、正体の分からぬ霊の意味なのだ、と言う。だが、この解釈には、大きな問題がありそうである。おおよそ、地名というものは本来、その地形やその歴史的由来から産まれるのが普通であるから、通説はこの意味で、推論の手順が逆に成っている様に思われるのである。逆の手順が必ずしも、間違いを生ずる、とは言えないけれども、通説は明らかに間違いである。それは通説が日本語の起源と思われる縄文語への考察を全く、しない事に原因がある。おそらく、都合の悪い真実に目を背けたのである。 さて、熊野という地名の生成について、考えるなら、「熊野櫛」は弥生時代、おそらく、「くまぬくし」などと、発音された。それが文字が流入して、書面に書かれる様に成ると、やがて、「熊野の櫛」と、読み慣らされる様に成る。其処で、その熊野の部分が地名と成った。あるいは、むしろ、連山を表すクマネシルがその侭、地名と成って、日本語の変遷と共に、熊野へと変化した、と考える方が良いのかも知れない。いずれにしても、クマネシルが漢字で、「熊野櫛」と表記をされた事が其処には、大きく関わっていた。つまり、始めに、「クマネシル」という、山々を表す単語が在った。次には、それが神々の状態を表す、「カムイ・ロク・クマネシル・メクカ」という、慣用的語句の中に使われた。山々の頂に腰を掛けて集う神々のイメージ、それがこの言葉の本来の意味であったのである。 だが、それはやがて、「かむろき、くまぬくし、みけぬ」と言う、神々の呼び名として使われ始める。また、その時期に、「熊野櫛」の部分が「くまぬのくし」と、発音をされる様に成った。その表記がたまたま「熊野櫛」で在った事がその様な読み方を可能にさせたのである。いずれにしても、熊野が地名と成ったのは、これ以降の事なのに違い無かった。熊野は実は野原では無く、本当はクマネシル、つまり、連山だったのである。山ならば「熊山」と成っても、おかしくは無い。それが「熊野」と成ったのは、クマネシルという縄文の単語が先行して居たからに他ならない。そして、この地名が生まれた背後には、畿内に於ける大和の覇権奪取という政治的激変もあったのである。 さて、通説の解釈に戻るけれども、「熊野櫛御気野」の「櫛御」の部分が奇霊である、という解釈も奇妙であった。大凡、古代人の祭る神々は刀や火、そして偉大な人間など、必ず具体的な何かの象徴として、崇め奉ったものだった。その事は神を祭る上での鉄則である、と言っても過言ではない。訳の分からぬ侭、祭るなど意味を為さぬし、考え難い事でもあった。だが、弥生的な支配体制の強まる中で、この神々が奇霊として、変質して行った事は考えられた。当時の支配層がこの余りにも、縄文的な神々の在り方に危惧を抱いたからである。その故に、訳の分からぬ神として、その神性を奪ったのでは無いのか?影浦はそう考えた。 「くまぬくし・みけぬ」は「熊野櫛御気野」と、表記をされた。彼等はこれを大凡、「くまぬのくしみけぬ」と、読んで、容易に「熊野の奇霊」と、解釈し得た。意図的であった、と断定する事は出来ないけれども、それは大和の支配の固定化で、確定的なものと成ったのだろう。単身の神、熊野大神はこうして、産まれた。だが、それは本来の神々の祭られ方とは、まるで違うものである。その故に、それら縄文の魂は神々の秩序に抑圧されて、鬱積をして、熱を持ち、怨念の炎を発したのである。おそらく、今、それは我々の現世(うつしよ)に発露を求めて、じわじわと染み出して、彷徨っている。祟り神、言代主の出現はその先触れであったのに違いない。恐ろしき祟りの神々が一瞬、脳裏を過ぎって行った。 その昔、熊野大神は単身の神では無く、実は八百万の神々だった。八雲を見下ろす山々にどっか、と座って、その足を中腹の沢に掛けて、憩う巨大な神々。縄文人の心には、その雄大なる心的印象が生き生きとした情景で躍動していた。それこそが、神祖熊野櫛御気野命の本来的な姿であった。旧暦の神無月には、日本中の神々が出雲大社に集う、と言う。だが、「カムイロク・クマネシル・メクカ」の意味からすると、それは元来、熊野大社の神事であった様に思われる。ならば、その神事は何時頃、そして、何故、出雲大社へと移されたであろうか? おそらく、それはこの単身の神とされた神々の神性の変質と関わりがある。つまり、大和はこの神事の余りにも、愛瀰詩的な印象に、ただならぬ危険を感じたのだろう。それをその侭に認めると、先住民の反抗の拠り所とも成り兼ねない。出来得れば、葬り去りたい神事であった。だが、旧支配氏族の纏まりはその神事に拠って、成立している。迂闊な介入など、し兼ねたのである。為政者に取って、纏まりを欠く社会ほど、恐ろしいものは存在しない。次善の策が必要だった。 其処で、大和は大国主命の為に創建した出雲大社に目を付けた。地理的位置も極めて近く、祭神は大国主命であるから、旧支配氏族と同じ、出雲系の神である。其処に神事を移すくらいは妥協の範囲と思われた。また、その祭神、大国主命は大和に国譲りをした神でもあって、大和に取っても都合が良い。大和は旧支配氏族を威圧して、あるいは宥めて、神事を移したのに違い無かった。神有月が出雲の暦として語られたのは、それ以降の意図的喧伝のたまものだった。 弥生の支配の体制は縄文の神々の聖なる集いを、熊野に座す奇霊の神、として変質させた。そして、更には、その神事までをも歪めたのである。愛瀰詩の荒ぶる魂が新たな神を希求したのも、当然の事とは言えそうだった。そして、野上の見抜いた如く、その心情は大和の側にも、在ったのである。恵比寿が神として誕生するのに、そうは時間も掛から無かった。そして、その陣痛は野上があの時、語った如く、記紀の誕生と共に、始まって居る。それはまさに、恐ろしき歴史の皮肉と言うべきだった。 さて、弥生の支配の体制と弥生の文明の発展は倭人と倭種とを融合させて、縄文の魂を押し込めた。文明の効率の論理の故である。縄文の魂は制度上、そして、生活上、失われたかにも思われた。だが、それは消えずに、しぶとく残った。倭人の文化と心に根ざした脳の特性の故である。長年に渡って、発露を求めて、怨念をも伴って、燻り続けた。だが、大和の体制が盤石と成った当時、縄文的な生き方は現実的願望とは成り得なかった。その故に、倭人の本来の魂は心の奥底にまで内向して、精神性を深めたのである。心の愛瀰詩が歴史の激動の中で、神格化をされて、ついには、恵比須と成って、現れたのである。そして、それは当然ながら、個々人のささやかなる自己の確認でもある。自らの尊厳の証であった。 だが、あの時、野上が嘆いた如く、恵比須は今、金欲の神へと貶められて、大きな怨念を呼ぼうとしている。いや、その怨念は恵比寿が金欲のみならず、物質欲によって、貶められた事で、今や、祟りの神々に成ろうとしている。いや、既に、その怨念の一部は現実世界へと浸み出していた。その所為で、自らの神を見失い、邪教に走る者も跡を絶たない。そして、恐ろしい犯罪も後を絶たない。多くの人が自分自身を失って、迷妄の淵を彷徨っていた。事実、まやかしの宗教が我が物顔で闊歩している。全ては文明に埋没して、皆の亡霊に魂を売った逃れ難き咎めであった。自分の認識の整合性は蔑ろにされて、皆の亡霊との整合性にのみ捕らわれている。 抑圧を解いて、個々人の尊厳を取り戻し、古来からの怨念を癒さなければ、更なる災いが起こるだろう。言代主の怨霊が更に怨念を吸収して、恐ろしき魔物と化すのであった。「だが、こんな日本の有様で、魂の開放など、出来るのだろうか?貧者を搾取し、仕事を奪って、あまっさへ、怠け者、と罵倒をして、排斥をする今の社会で、人の尊厳が保てるだろうか?社会が発狂せずにいられるだろうか?」海外の情勢を見るに付け、影浦はつい、そんな風にも思うのである。最前から騒ぐ虫の音が怪しい予感を抱かせる。何かを知らせてでも居るのだろうか?影浦はふっと、耳をそばだてて、意味するところを探るのだった。 |
|||||||
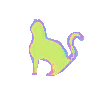
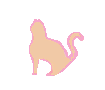
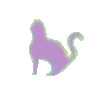
| |||||||
| Cotosiro | |||||||