|
可能世界・陰の神話 第十四章第三話 |
誤算 This was revised in December 8, 2006. This was revised in September 20, 2008. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
中臣は電車を降りると、バス停へと向かって、歩き始めた。だが、時計を見ると、終バスの時刻を二十分ほども経過している。「変だな?何時もなら、十分に間に合うのだが」中臣はふっと、小首を傾げると、駅の大時計へと視線を移した。だが、やはり、それは腕の時計と大差は無い。「乗った電車でも、遅れたのかな?」しかし、それらしき騒ぎなど、無かったのである。そして、その様なアナウンスも聞いた覚えがない。「うたた寝の所為で、気付かなかったかな?どうも、分からん?」中臣は不思議な気分で、辺りを眺めた。だが、人の通りは閑散として、バスの来ぬ事を暗示している。タクシーは幾台か、並んでいるけれども、何故か、乗る気も起こらない。「歩いてみようか?三十分ほどで、着くだろう」彼はふらっ、と歩き始めた。時折、吹き付ける僅かな風がやけに冷たく身体に刺さる。しばらく歩くと、頭が重くて、少し熱っぽい事に気が付いた。「チッ!風邪でも、引いたか?」中臣はコートの襟を立てながら、前屈みと成って、自宅に急いだ。それにしても、今日の街は妙である。車は一台も通らぬし、猫の子、一匹、見当たらない。自分の歩く足音が乾いた響きで、こだましていた。「薄気味の悪いくらいだ」中臣はふと、上目を使って、辺りを眺めた。 と、何だろう?奇妙な気配を背後に感じる。感覚からして、一丁向こうの塀の辺りだ。「ん、何だ?」彼は咄嗟に、振り向いた。だが、妙だ。人影は見当たらず、人の気配すら、感じられない。「妙だな、誰か居ると思ったが・・錯覚か?」中臣は少し首を捻ると、再び、コツコツと、歩き始めた。犬の遠吠えが何処かで、聞こえる。風が一層、冷たく感じた。やはり、風邪を引いたのらしい。「しまったな、やっぱり、タクシーに乗るべきだった」中臣は少し後悔していた。辺りを覆う静けさが妙に不気味に思われる。気が付くと、身体が妙に強ばっていた。彼は自分に気を入れて、背筋を伸ばすと、歩く速度を少し早めた。と、その刹那、彼の背後で、靴音らしき音がやにわに鳴った。聞き耳を立てると、それは付かず、離れず、一定の間隔を保ったままで、影浦の後を付いて来る。嫌な予感が脳裏を過ぎった。「尾行者だろうか?こんなところで、冗談じゃない」中臣は更に、歩みを急がせた。すると、背後の足音も同じテンポで、付いて来る。やにわに、汗が滲み出して、心臓の鼓動も早まった。気の所為か、背後の怪しい足音がやけに大きく鳴り響く。中臣が止まると、そいつも止まった。背筋の辺りに悪寒が走る。中臣は知らぬ間に駆け出していた。と、後ろの怪しい足音も、執拗に中臣を追って来る。もはや、尾行者である事は間違いがない。中臣は必死で、足を前へと運んだ。しかし、息はすぐにあがって、大粒の汗が滴り落ちる。焦るほどに足が縺れた。 「ああ、追い付かれて仕舞う!誰か、居ないのか!」中臣は人の影を必死で探した。と、少し先の暗がりに電話ボックスの灯りが見える。「そうだ、壱岐に電話しよう!」何故、そんな風に考えたのかは分からぬけれども、中臣は必死の想いで、駆け寄った。そして、ドアをしゃにむに開けると、受話器をムンズと、掴まえた。だが、電話番号が想い出せない。「エエト、電話の番号は?」中臣は滴る汗をその都度、拭って、うる覚えの番号を必死で押した。しかし、掛からぬ。「エエイ、掛かれ!」中臣が思わず、電話を平手で叩くと、いきなりベルが激しく鳴った。何故かしら、悪魔の笑いにも思われる。「逃げなければ!」中臣は咄嗟にドアに手を掛けた。だが、ドアは開か無い。「わあー!何なんだ!」中臣はパニックに陥って、力任せにドアを揺すった。顔を上げて、向こうを見ると、闇に蠢く怪しい影がすぐ其処にまで、迫って来ている。ニタッと、笑った白い歯が闇夜を一瞬、切り裂いて、威嚇をする様に不気味に光った。「ああ、殺される!」中臣は意識がスーッと、遠退いて、ヨロッと、ドアへと凭れ掛かった。と、何故だろう?ドアがいきなりバタンと、開いた。預けた身体が支えを失う。中臣は一瞬の内に、もんどり打って、そのまま、路上へと転がり落ちた。意識が妙にはっきりし無い。ふっと、辺りを見回すと、彼は見も知らぬ部屋に転がっていた。見回すと、其処は書斎風の部屋である。見覚えの在る書棚が在った。「ン、何だ?」中臣は、はっきりしない意識の中で、再び、部屋を見回した。と、窓際の机にも、見覚えが在る。「あ、俺の部屋じゃ無いか?」だが、これはどう言う事なのか?中臣は訳が分からずに、戸惑った。しかし、足音は聞こえぬし、当面の危機からは逃れたらしい。「まあ、とにかく良かった」中臣はゆっくりと身体を起こすと、傍らのソファーに腰を降ろした。 気が付くと、電話のベルが鳴っている。何時から鳴って居たのだろうか?彼はふらっと、立ち上がると、部屋の中を眺め渡した。すると、其処は中臣が身を隠しているホテルの一室である。どうやら、夢を見ていたらしい。電話はしきりと鳴ってはいるが、彼は上目で、受話器を眺めた。最前の夢が脳裏を過ぎって、受話器を取る事が怖いのである。「どうしようか?」中臣は少し躊躇した。だが、中臣の今の隠れ家は草嘉と壱岐以外には、知らせて居ない。漏れる事など、考えられぬし、多分、彼等のどちらかだろう。彼は自分をそう納得させると、恐る恐ると受話器を取った。と、聞き慣れた声が呼び掛ける。「あ、もしもし?あ、中臣か?俺だ、草嘉だよ」「ああ、草嘉か、脅かすなよ」「エッ?」「いや、何でもない、それより、どうしたんだ?亜真野の奴でも、化けて出たのか?」草嘉の声を耳にして、妙に安心をしたのらしい。思わず、飛び出した軽口だった。だが、草嘉の様子は少し、おかしい。冗談への反応が鈍いのである。「何か、在ったんだな?」中臣は咄嗟に、そう問うた。草嘉が言った。「うん、ちょっと、誤算が在ってな」 草嘉の目論んだ計画は一分の狂いも無く実行されて、それ自体は上手く行っていた。だが、猿女等を拘束しよう、というその矢先、その歯車が狂い始めた。猿女と建比良が消えたのである。しかも、米国で、厳重監視下に在った筈の、あの亜真野にすら、逃げられていた。米国を出た形跡はまだ、無いものの、あのしぶとい亜真野であるから、直に、舞い戻って来るのに違いない。彼の親派は数も多いので、隠れ家に事は欠かぬだろう。そして、彼が報復を企んでいる事も確かであった。「どうだろう、しばらくの間、宮城の道場にでも、匿って貰っては、何時までも、ホテル暮らし、とも行かんだろうし、君をガードする余裕も無く成った、本当に済まんのだが、こう成っては、どうしようも無い」草嘉の声には、張りが無かった。長い付き合いの中臣にも、こんな草嘉は覚えが無い。「そ、そうか、分かった、壱岐と一緒に座禅でも組むかな?連絡を取って、すぐに向かうよ」「うん、済まんな、亜真野の事、見縊ってたよ」草嘉はポツリ、と、そう言った。その声には、抑揚が無く、そして、力も感じられ無い。「大丈夫か?」中臣は思わず、そう問うた。草嘉が言った。「ああ、地下に潜られたのは失敗だったが、計画は露見したのだし、まあ、これからだよ、じゃあ、切る、気を付けてな」そして、草嘉は電話を切った。だが、その静寂が妙に重苦しい。中臣は受話器を持って、しばらくの間、佇んでいた。 草嘉の心の状態は深刻な様に思われる。彼は今回の失敗で、部長の椅子を失うのかも知れ無い。閑職に追い遣られる事も考えられた。だが、あの草嘉が果たして、そんな問題で滅入ったりなど、するのだろうか?「落ち込みの理由は他に在る」中臣はそう考えた。草嘉は電話の最後の部分で、「見縊って居たよ」と、自嘲気味に話をしている。亜真野等の逃亡を許した事が草嘉の高いプライドを傷付けたのに違い無かった。草嘉が亜真野について語る時、しばしば、さげすむ様な口調を取った。学者としての亜真野に、それ程の業績が在るのでも無く、神憑り的な言動も許せぬらしい。そして、見え見えの権謀術数をあえて、行う厚かましさ、虚仮威しの様なあの目付き、草嘉の物の見方からして、評価の下がるのは当然だった。「亜真野は三流以下の人間だよ」彼は時折、そんな酷評も下したのである。 だが、そんな亜真野に草嘉は負けた。いや、負けた訳では無かったけれども、草嘉には、同じ事だった。「あんな男に出し抜かれる、とは」そう思ったのに違い無い。そして、自尊心は打ち砕かれた。草嘉の落ち込みの原因は其処に在るのに違い無かった。だが、それが単なる落ち込みに留まる、とは言い切れない。あの抑揚の無い話し様には、鬱病の兆候も垣間見られる。これは中臣の専門ではないのだけれども、草嘉に鬱病の心配がある事はやはり、否定は仕切れなかった。一般的に言われる事だが、この様な心の病には、努力や勤勉は禁物である。病と闘う意識すら、その回復を妨げる。打ちのめされた心には、全ての責務から解き放たれた完全なる休息が必要だった。だが、草嘉の立場を考える時、その様な休養が許される、とも思えない。たとえ、周りが勧めても、彼は仕事をし続けるだろう。悪化の確率はやはり、高い様に思われる。「杞憂で在れば、良いのだが」中臣は心の内で、呟いた。 影浦は中臣からの連絡で、初めて、草嘉の計画と、その後の経緯を知らされた。「何故、相談してはくれ無かったのか!」悔しさが怒りと共に込み上げた。中臣の避難は当然としても、亜真野の勘や洞察力などを考えるなら、あまりにも、ずさんな計画である。草嘉が中臣を動かしたのは強盗計画の前日だった。亜真野は米国に追い遣って居り、問題は無い、と踏んだのだろう。だが、亜真野はおそらく、その事から、草嘉の陰謀を見破ったのである。草嘉は確かに、亜真野の力を見縊って居た。「それにしても、亜真野達はこれから、どう動くのだろう?」影浦には、酷く気に成った。今や、亜真野等の心の動きは手負いの虎のそれである。亜真野は冷静であったとしても、部下の方は分から無かった。勝手に弾けぬ、とも限らない。そして、もしも、そう成れば、社会不安は一挙に増して、恐ろしい事態にも成りそうだった。不安や恐怖は長く続くと、人間性まで、歪めて仕舞う。疑心暗鬼が蔓延して、人々を力への崇拝へと傾斜をさせる。そして、人々は尊敬や愛や真実までが、力によって獲得される、と信じてしまう。いや、その様な錯覚を産むのであった。そして、これはまさに、祟り神の望む状況でもある。巷に蔓延した憎悪の炎が彼の力と成るからだった。もし、これ以上、社会の不安が増大したなら、どんな災いが降り掛かるのか?無人格な大きな力と、その力への根深い怨念、そして、自由な魂が三つ巴と成って凌ぎを削り、和解などは在り得ない。こんな状態がずっと続いて、果たして、生き残る者は在るのだろうか?いや、世界を産み出し、見つめる心は裂けずに居る事が出来るのだろうか?破局の幻影が脳裏を過ぎった。 |
|||||||

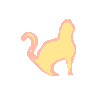
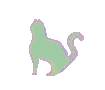
| |||||||
| Cotosiro | |||||||