|
可能世界・陰の神話 第十五章第三話 |
言寄せの祭具 This was revised in December 3, 2007. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
二年ほど前、輪島のとある崖下で、大量の銅矛が発見された。それは影浦が祟り神蘇生の儀式との関係を推測した、あの問題の銅矛である。その発掘は今、主として、金沢文化大学の考古学講座が行っていた。だが、その数量は途方も無い。そして、それはまだ、発掘中でもあるので、出土品の殆どは未整理の侭、考古学教室の別棟に山積みと成って、保管されていた。無論、この銅矛は決して、ありきたりの資料では無く、むしろ、貴重な出土品である。しかしながら、チームの構成員は各々、別の仕事にも携わって居り、限られた予算での発掘でもあるから、増員なども難しく、処理の遅れは仕方なかった。だが、深夜、その一室からは、何時もの様に明かりが漏れた。ひとりだけ、それらの資料に執着をして、徹夜の作業をする者がいる。名は関元一郎、と言う。彼はこの大学の考古学学科の助手として、一年ほど前、この大学に赴任をしていた。彼はその一本一本を観察して、あらゆる特徴をノートに記すと、荷札を付けて、写真を撮った。しかしながら、それは単調な仕事にも拘わらず、かなりの時間を必要とする。処理が済んだ銅矛はまだ、数百本にしか成っては居らず、まだ、二千本ほどが未整理であった。 この銅矛は極めて、貴重な出土品である。島根以東での銅矛の発見は稀であったし、畿内では、しばしば見付かる銅鐸ですら、出た事の無い地域から出土している。前代未聞の数量でもあり、銅矛は発見された当初から、大きな反響を呼んだのである。だが、その形状に限って言えば、それは既に、知られたものであった。それは以前、島根県の荒神谷で、見付かった大量の銅矛と酷似している。(荒神谷での銅矛発見は事実です)また、発見時の銅矛は整然と並べられて、埋められて居り、その様な状況も、荒神谷のものと似通っている。この二つの地域から出た銅矛の間には、何らかの関係も想像をされたのである。だが、それは果たして、どの様な関係なのか?学者達の注目は自然と其処へと集まった。 荒神谷の銅矛は紀元一世紀から三世紀の辺りに制作されて、埋められたもの、と言われている。だが、輪島の銅矛が埋められたのは、四世紀の後半である事が判明していた。それはあの崖下の同じ地層から発掘された単甲(古代の鎧)の年代から割り出されている。つまり、荒神谷の銅矛と輪島のそれとの年代差は何と、一世紀から三世紀ほども在ったのである。この遠く隔てられた時間と空間に、如何なる事実が隠れて居るのか?学者達はこぞって、その謎に取り組み始めた。エックス線による透視や銅矛に含まれる鉛の同位体分析、含有成分の測定、鋳造方法の比定など、あらゆる手段が投入をされたのである。その結果、輪島の銅矛はその全てが同じ組成と判断された。また、同じ鋳造方法である事も、ほぼ同時期に確かめられた。銅の産地も同様である。だが、荒神谷の銅矛とは、その組成、鋳造方法ともに異なっていた。つまり、荒神谷で見付かった銅矛とは違った場所、違った時期に作られた事が推測されたのである。 大和に追われた島根の部族が能登に住み着いてでも居たのだろうか?それとも、その銅矛は大和の勢力拡大の証だろうか?様々な憶測が飛び交い始めた。そして、その銅矛には、更なる謎も秘められていた。刃の形状は全てが同じにも関わらず、柄を差し込む部分の形状は全てが微妙に違ったのである。どうやら、鋳造をした後、一つ一つ削ったらしいが、何故、その様な作業が必要なのか?学者達も首を捻った。他にも、謎は数知れ無い。学者達はその様な謎にも魅せられて、発掘調査は今もなお、継続していた。だが、今の所、銅矛以外で出土したのは、あの単甲のひとつだけで、生活の臭いなど、全く、し無い。つまり、其処は当時も人家など無い荒れ地だった、と推察された。だが、何故、そんな所に大量の銅矛が埋められたのか?今や、発掘現場は学者の社交場とも化していた。しかし、関元だけは、違ったのである。彼は発掘現場には目もくれずに、ひとり、資料室に閉じ籠もって、銅矛だけを調べ続けた。実を言えば、そうせざるを得ぬ特殊な事情があったのである。 関元は以前、熊野の居る講座に大学院生として籍を置いて、ドクターを目指して、研究していた。また、熊野とのその様な関係が宮城との関係も作って行った。影浦などとも其処で出会った。言代主の話など、誰も口には出さ無かったが、その場の雰囲気、と言うのは恐ろしい。関元は影浦の作品に触れる内に、その秘密に気が付いたのである。彼の大学での今の仕事は輪島の銅矛の研究である。だが、その動機は祈言宗の陰謀に対する、ある配慮が関わって居た。関元は昨年、熊野の下で助手と成った。また、その時期に銅矛の秘密も聞いたのである。誰かが銅矛を守らねば為らない。其処で、関元はその役割を買って出た。 だが、金沢に来て、いざ、仕事を始めると、思った以上に苦労は多い。昼間は学生が大勢居るし、見張りも楽だが、夜中と成ると、そうも行か無い。保管室での寝泊まりは殆ど、日課と成って居た。「この侭では、自分の仕事が全く出来ない!」関元は何度か、投げ出したい気分にも陥った。だが、自分の選んだ道である。彼はひとり、黙々と、銅矛の整理に勤しんだ。それにしても、チャンスは何処に転がって居るか分から無い。その様な不自由な状況が彼をして、貴重な発見へと導いたのである。無論、其処に、彼の努力と忍耐があった事は言うまでもない。彼は今、大きな成果を得ようとしていた。 銅矛の柄を差し込む部分の形状はその各々に、微妙な違いを確認出来た。偶発的な問題では無く、意図的なものであるらしい。つまり、其処には、それぞれを違える合目的的な理由が在りそうだった。既に、学会では、それは大きな謎として、幾多の論議にも晒されて居る。関元は日夜、銅矛と向き合う内に、その意味する処に気付いたのである。関元は以前、影浦から、神祖熊野櫛御気野命に付いての、彼の持論を聞かされていた。その神は実は、単身の神では無く、八百万の神々で在るのらしい。「これら、意味不明な銅矛は熊野大神、つまり、荒ぶる神々の依り代だったのではないのか?」彼はそう考えたのである。それが事の始まりだった。 神々は弥生の支配の体制により、熊野の土地から遠ざけられた。また、熊野の地を見下ろす連山に、天下る事も許され無かった。能登の古代人はその代用として、銅矛を使ったのに違い無い。つまり、それは祟り神を此の世に送る悪魔的な儀式であった。儀式の時、それら、輪島の銅矛は切っ先を天へと向けられて、並べられる筈だった。神々はその柄から銅矛へと依り憑いて、切っ先から此の世へと舞い戻るのである。つまり、天下るのでは無く、地から銅矛へと依り憑いて、切っ先からこの世へと蘇る屈辱的な儀式であった。また、その銅矛は弥生の支配の象徴でもある。儀式に於いて、神々は二重の恥辱を受けるのだった。能登の住人はカムイロク・クマネシル・メクカ、つまり、神々の座す有様を全くの逆とする事で、呪いの儀式へと変えたのである。南方美穂は何処かで、その事を知ったのだろう。銅矛を奪いに来る事は十中、八、九、間違い無かった。 儀式の時、彼女は神々の恥辱が何処から来るのか、と言う事の子細を神々に告げる筈だった。神々の深き怨念はそこで、極に達するのである。彼等が銅矛の切っ先からこの世に蘇る時、その怨念は炎と成って、この世の全てを祟るのだった。人々はまるで、気付いて居ないが、その戯画的警告も為されて久しい。「こんな物、無ければ良いんだ!」関元は度々、その柄の部分を削り取って、使えなくしようか、とも考えた。だが、彼も学者の端くれである。真理への糸口を断ち切る事は彼の良心が許さない。関元はその様な誘惑を忘れる様に銅矛だけを見つめ続けた。 おそらく、その儀式の系譜は少なくとも、一、二世紀の島根までは遡る事が出来そうだった。勿論、あの荒神谷で見付かった銅矛も熊野の連山の象徴である。だが、それは悪魔的な儀式では無かっただろう。その昔、島根の部族は西方との交易や戦闘を通して、北九州の強大な軍事力を知らされた。島根の部族がその力を欲した事は想像するに難くはない。従って、当初の銅矛は熊野連山の象徴でも無く、単に武力の象徴だった。ところが、銅矛はやがて、熊野連山の象徴としても使われ始める。それは活動範囲が拡大して、移動が頻繁と成るに従って、熊野の祭事は移動先でも必要とされて、熊野連山の代用も必要とされたからだった。 だが、大和の畿内の征服で、儀式は徐々に変質して行く。祟りの神々を呼び覚ます呪い儀式へと変わったのである。時期としては、熊野神社の祭事が出雲大社へと移された、その前後、五十年ほどの範囲と思われる。無論、その様な祭事の担い手は北に逃れた言代主の一族しか在り得なかった。そして、今、南方美穂はその儀式を為さんと企てている。「果たして、銅矛は守り切れるか?」関元はそんな不安とも戦っていた。そして、関元の脳裏には、不可解な疑念も渦巻いている。碁石が峰の神殿に存在するであろう洞穴が何故、祟り神蘇生の儀式に必要なのか?其処が今、ひとつ、解らぬのである。「何か、別の意図でも在るのでは無いのか?」その様な疑念がしばしば、襲う。その所為だろうか?関元は不可解な不安にも捕らわれていた。 |
|||||||
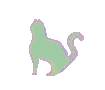
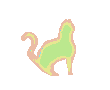

| |||||||
| Cotosiro | |||||||