|
可能世界・陰の神話 第十六章第三話 |
フラクタル This was revised in December 3, 2006. This was revised in September 23, 2008. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
影浦には、あの怪現象が単なる物理現象である、とは、どうしても思えなかった。あるいは、それは祟りの神々の怨念が可能世界を混乱させた、その結果ではないのか?そして、その混乱が複数の可能世界を現実化させて、ひとつであるべき現実世界を混乱させた、のではないのか?彼は逆崎との議論で、その様な感を強くしていた。だが、影浦のその様な直感は果たして、本当に当たっているのか?彼はまだ、確信をするまでには至っていない。そして、目の前の機械的運命論者は可能世界そのものを否定している。いずれにしても、更なる思索が必要だった。だが、見たところ、逆崎は少し、だれ気味である。そして、影浦自身も、幾分、疲れを感じた。「さーてと、茶でも入れようかな?」影浦はそう呟くと、「よいしょっ」と、言って、腰を浮かせた。と、逆崎が「あ、私がやります」と、素早い身のこなしで、立ち上がった。影浦に、立ち上がる暇も与えない。「それとも、俺が鈍いのか?」いずれにしても、若い、と言う事は素晴らしい。影浦はその身のこなしに感心しながら、「おっ、済まんな」と、浮かせた腰を元に戻した。 それにしても、「よいしょっ」と、言うのは、どうも行けない。このところ、しばしば出るのだけれども、自分の老化を感じて仕舞う。「何で、出るんだ?」影浦は何時もの様に反省していた。だが、言ってしまったものは、しようがない。そして、一説には、掛け声は怪我の防止に役立つ、とも言う。特に、筋肉の反応が遅く成った年寄りには、有効らしい。自分は年寄りとは思わぬけれども、用心をするに超した事はない。「まあ、こんなところで、若ぶって、見栄を張っても、仕方がないしな?」彼はタバコを一本、取り出すと、何とは無しに、火を付けた。そして、一息、吸って、灰皿に置くと、紫煙がゆらゆらと立ち昇る。天井と床の中間辺りに棚引く様に漂うと、次第に拡散して、辺りの空気へと溶け込んで行く。「けど、この煙がこの先、何処に行って、どう成って行くのか、なんて、そんな事、誰にも分からんよな?」影浦はふっと、そう呟くと、立ち上る紫煙をボーッと、眺めた。と、逆崎がキッチンの方から呼び掛ける。「ン?今、何か言った?」影浦は身体を伸ばして、問い掛けた。 逆崎が言った。「ですから、誰が見て居ようと、見て居まいと、客観は客観ですよ、客観的に決まってるから、現実は何時も一つなんです」どうやら、逆崎はまだ、影浦の言いたい事が分かっていない。「だが、どう説明しようか?」話のし様が難しい。上手い表現も見付からないので、影浦は仕方が無しに、沈黙していた。気が付くと、紅茶の香りが漂っている。「ん?」影浦は少し、戸惑った。緑茶が出て来るもの、と思っていたが、逆崎は紅茶の様に思ったらしい。これは年代の違いだろうか?それとも、紅茶を飲みたくて、自分の都合で入れたのか?「まあ、いいか!」影浦は戸棚からカップを取り出すと、卓袱台の上に二つ並べた。と、ポットを抱えた逆崎が戸口の隅から、こちらを覗く。目線が会うと、「いやあ、緑茶が見当たらなくって、紅茶でも良いですよね?」と、上目を使った。ホントかどうかは分からぬけれども、入れたものはしょうが無い。影浦は注がれた紅茶を少し啜った。 それにしても、逆崎の運命論は気に入ら無かった。どう見ても、彼の思考は客観性と必然性とで、がんじがらめに固まっている。影浦は密かに逆崎の矛盾を探し始めた。と、機先を制したつもりだろうか?逆崎が言った。「影浦さん、全ての物事には、それを認識させる道具が在りますよね?」「エッ?どういう事?」「ハイ、原因と結果の因果関係、それと、論理式に見られる様な論理的関係、例えば、AはAであって、Bではない、と言うような・・」「あ、そう言う事ね!」「エエ、つまり、我々の未来は必然的に因果関係と論理的な関係によって決定されます、数学などには、ある矛盾無き論理体系に含まれる、原理的に真偽を確定出来ない論理式がある、と言う理論も在るようですが、それは単に我々の認識能力が不完全である、と言うに過ぎ無い様に思うんです」「あ、そうなのかな?良くわからんが」「いえ、全てが論理的関係と因果の関係によって決まるのなら、そう考えるしか在りませんから」影浦は一瞬、逆崎が数学の不完全性定理を物理学の不確定性理論と混同しているのではないのか、と考えた。けれども、彼は数学的な理論として述べたのであるから、それはそうでは無さそうである。不完全性定理など、何時、知ったのだろうか?影浦には、少し意外に思われた。 だが、問題は彼がまだ、認識の主体に気付いて居ない事である。数学上、あるいは、物理学上、原理的に認識出来ぬ物を一体、誰なら認識出来る、と言うのだろうか?そして、前出の論理式の真偽を果たして、誰が真である、あるいは、偽であると、判定出来るのだろうか?つまり、その様な認識を確定させ得る者は誰なのだろうか?そして、その何者かは論理と因果とで確定させるだろうか?影浦には、そうは思え無かった。彼は少し考えて、ひとつの仮定を投げ掛けた。 影浦の考えでは、ビッグバンは因果関係の結果ではなく、因果関係の原因である。論理的な関係も、あるいは、ビッグバンの結果であるのかも知れない。影浦はまず、その事を逆崎に指摘した。すると、逆崎は仮定としては、分かる、と言う。影浦は言った。「だから、認識不能な実在がこの世界を確定する、言い換えると、その様な実在がこの世界をその様に認識する、と言う事も考えられる」すると、逆崎が、「いや、ちょっと、言ってる意味が、分からんのですが」と、小首を傾げた。影浦が言った。「だからさ、因果や論理の関係で、全てが説明出来る、とは、どうしても思え無いんだ、少なくとも、そのままの形では、此の世の外には適用し得ない、そう思うんだ」「エッ?此の世の外、ですか?」「あ、いや、原理的に我々の到達し得ぬ、あるいは知り得ぬ、その様な何か、と言い直した方が良いのかな?」 だが、逆崎に納得した様子は見られ無い。彼はその知り得ぬ何ものかも、やはり、確定的存在であって、現実世界との必然的関係を持っている、と断言をするのである。だが、その様な確定性や必然性を感じて居るのは当の逆崎本人である。つまり、彼が存在をしないなら、その様な彼の認識も存在しない。そして、彼の現実世界はその様な認識と逆崎自身との関係によって成り立っている。現に、影浦のその事柄に関する認識は異なっており、影浦とその様な事柄との関係も逆崎とは異なるのである。影浦には、可能性の概念を考えるに当たって、この事を考慮する事が重要である様に思われた。そして、その知り得ぬ何ものかに因果が存在せず、論理もまた無いのなら、どちらの考えが妥当をすのるか、など、設問自体が意味を為さぬ様にも思われる。「それは原理的に知り得ない、少なくとも、脳では知り得ない、つまり、論理演算や因果関係から、その事を知る事は不可能である」と、そう言う以外に無く、それ以上の事は確定的には語れない。 つまり、逆崎の認識と影浦の認識のいずれかが正当である、と言う可能性だけが確かな結論として、残るのである。影浦には、必然性の概念が其処に至って、可能性に飲み込まれる様にも思われた。そして、それは必然性が可能性の単なる一形態にしか過ぎぬのであるから、当然の様にも思われる。だが、可能性の概念は必然性の概念が消滅したその状態に至っても、なお、厳然として、息づいていた。ただ、それはいわゆる他者への客観的な認識では無く、個別の想念に関わる問題であり、意識的、あるいは表層的には、信念の問題とも成りそうである。ならば、原理的に知り得ぬ何かは、我々個々人それぞれと、個別的関係を持たねば為らない。そして、その関係を規定し、それらの関係同士を規定し、世界を成立せしむる、ある種の論理は在るとはしても、それは現実世界を存続せしめる物理的な論理とは随分と異なる様に思われた。 だが、此処まで来ると、それは可能性を考える精神自体が現実世界に対して自由か否か、という、基本的問題へと立ち返り、まさに原理的に認識不能な、その様な様相を呈するのである。彼の、あるいは彼女の考え方が此の世の必然に因って現象する、と言う事は容易であるからである。そして、この様な真偽判定不能とも思える状況が論理と因果とに縛られた我々、意識体の認識の限界なのでは無いのか?あるいは、それはゲーデルが見出した不完全性定理が、実在そのものに、真偽を判定出来ぬ論理式が内在をする、と言う事を示しているのかも知れない。いずれにしても、その様な論理式の存在は可能性の概念がこの世界のある状況を示している事は確かな様に思われる。少なくとも、影浦は、この議論で、その様な感を強くしていた。しかし、逆崎はまだ、必然性の概念に執着している。可能性を考える、と言う行為は取りも直さず、百パーセントの蓋然性、つまり、必然に到る道を探る事であり、何かが起こるのには、必ず、そうさせる確定的な理由が在る。彼はそう考えていた。 逆崎が言った。「影浦さん、この間、素粒子に関する本を読んだのですが、こんな話が在りました」そして、彼は電子雲について、語り始めた。物理学の部外者は時として、原子核の周りを廻る電子に付いて、太陽を廻る惑星にたとえて、説明しようと試みる。だが、実際の電子は粒子の姿で軌道を回るのでは無く、雲の様に原子核の周りを包む様に運動している、と言う。「つまり、その電子の居れる全ての範囲に確率的な在り方で、しかも同時に存在をする、と言うんです」逆崎はそう述べると、影浦の顔を覗き見た。と、影浦が悪戯っぽく、笑みを浮かべて、言った。「うん、電子が何分の一かづつに割れるのじゃ無くて、作用する場合の単位はきっちりと、一個分なんだろ?」「あの、それはそうですけど、まじめに聞いて下さいね?」「あ、済まん、済まん」影浦はにやりと笑って、謝った。 逆崎が言った。「ですから、この事はサイコロの六の目が六分の一の確率で出るからと言って、出た目の数は六分の一では無い、その事と同じ関係では無いのでしょうか?」だが、影浦は突然、聞かされた奇妙な論理に困惑した。「エーッ?そっちこそ、真面目に話せよ」影浦は思わず知らず、吹き出して、逆﨑の顔を覗き見た。だが、逆崎は憮然とした面持ちで、言う。「エ?これは冗談ではありませんよ?電子の存在のあり方について、譬えたんですから」そして、彼は向きに成って、その説明をし始めた。「ただし、電子とサイコロとでは違う部分も在ります、サイコロは何処で転がしても良いですし、時間に制限も在りません」「うん、でも、だいたいはルールで決められてるぞ?」「あの、この場合は数学的な確率ですから、その様なルールは無いんです」「あ、そう」「つまりですね、電子とサイコロとでは、確率の成立する時空の軸が異なるんです!」 逆崎の言わんとする所はこうだった。無論、確率は数学的なもので、直接的には時空の軸とは関わりが無い。だが、ひとつの現象を実際に見る時、当然、時空は無視し得ない。そして、サイコロの場合、その確率の在り方は空間には関係せずに、時間軸を横から見て、計算をする様なものなのだった。だが、電子の方はそうでは無く、時間は任意の一点に決められている。そして、電子はある特定の範囲に於いて、その同一時点に、確率的に存在をするのである。従って、それは空間に対しての確率だった。つまり、ひとつのサイコロを転がすと、同一時間に、六から一までの目がランダムに出ている。そんな状況に極めて似ていた。「ですから、現実というのは、たくさん在って、ええと、それを我々は何らかの理由で、ひとつしか見られない?あれ?変だな、あ、ちょっと、待って下さい?」ちょっとした思い付きであったのだろう。途中で混乱を来したらしい。逆崎は黙りこくると、腕を組んで、考え込んでしまった。 だが、逆の意味で、今の逆崎の話には、重要な示唆が隠されている。いみじくも、彼の言った、たくさんの現実こそが可能世界そのものでは無いのか?電子の確率的な在り方は波動であって、粒子では無い(これは筆者の見解です)。電子を認識するのには、粒子化をする事が必要だった。つまり、電子は何かに衝突をして、粒子化をしたその瞬間、確率的存在では無く成って、ただの一点に現実として、その姿を露わに示すのである。従って、粒子化をする以前の波動と言うエネルギーは実在ではあるけれども、現実に於ける存在では無い。確率的な在り方、とは、現実化への可能性であり、電子の波動は現実と成るべき実在だった。だが、波動が現実へと現象をするのには、粒子化されて、何ものかの認識を得る事が必要である。認識者の無い現実などは存在のし様も無いからである。現実とは、認識者、在っての実在である、と言うべきだった。 ところで、物は何故、見えるのだろうか?現代の人間は光が物体に衝突し、反射して、目に届く故、見えるのだ、と、その様に教えられて、納得している。だが、本当に、それだけだろうか?古代ギリシャの哲学者、エンペドクレスはその事に関して、次の様に述べて居る。物体が見えるのは目から何等かの粒子が放たれ、物体に届くからである、と。一見、悪い冗談の様に見えるけれども、影浦は其処に、奥深い真理を見出していた。つまり、エンペドクレスの粒子は実は目から出るのでは無く、また物理的な存在でも無い、認識を欲する魂の精神作用、なのでは無いのか?そんな突飛な着想だった。影浦は認識と言うものを、カオスから分かたれた認識者と認識される物との相互作用、と考えている。そして、それは感覚器官を通して行われるが、認識自体は精神そのものの作用であった。従って、認識に物理的存在以外の実在が関与をしても、不思議である、とは言い難い。可能世界は確かに波動として存在し、魂が認識を欲した時に、それは瞬時に粒子化をされて、認識される。そう考える方が自然ではないのか?影浦には、その様に思われた。 あるいは、この可能世界は哲学者の考えている可能世界とは違うのかも知れ無い。だが、其処に収束をする事は在り得る様に思われる。いずれにしても、因果関係で、現実と可能世界の関係を説明する事は困難である。その関係は因果関係では無く、論理的な関係か、然も無くば、極めて無秩序な関係か、あるいは、イメージで左右をされる関係である。全ては必然である、と最初に言えば、全ては必然と成り、全ては可能性の実現である、と、最初に言えば、全てが数学的な確率に基づいて、存在をする。少なくとも、頭の中では、前提が全ての現実を決めるのだった。無論、いずれの考え方を取るとしても、其処に、此の世の因果に抵触をせぬ限りは、と言う条件が付帯する事は言うまでもない。どのみち、現実化する可能世界はひとつしか無い。それが必然であろうが、無かろうが、である。ならば、可能性を信じた方がより良い世界に我が身を置ける。功利的には、そう成る様にも思われた。だが、確たる根拠など存在し無い。必然性と可能性との、フラクタルな様相が少し見えただけだった。 ただ、今、人知れず進行している怪現象の、その一端は分かる様にも思われる。宇宙を支える全ての想念、それに支えられる現実の時空、そして、その間に在る全ての認識、それらの調和がある何らかの因子によって突き崩された。それが可能世界と数学的確率を混乱させて、確率的な実在が現実の中へと混じって仕舞った。あの祟り神、言代主と権力の権化、亜真野、そして、もしかすると、影浦達の恐ろしいほどの想念がその様な混乱を産んだのである。各々はその実現を互いの力によって阻まれている。そして、普通なら、各々の時空を産み出して、自らの実現を計るのだった。だが、その各々は今の現実に固執した。その事が可能世界を混沌とさせて、認識自体を分裂させた。つまり、幾つかの現実を混在させた。整合性の無い今の世界はその産物である、と考えられる。そして、その事は強い想念を持つ影浦達が未だ整合性の在る現実に、留まって居る事からも窺い知れた。 確かに、この様な類の現象は小規模なものなら、今までにも数知れず、生起をしていた。霊能者や超能力者、そして、邪なる予言者などがその能力で、その様な認識を行う場合、極、限定された時空の一部が彼等の想念により変えられたのである。その結果、在り得べからざる超常現象、あるいは、予言の実現として立ち現れた。だが、それは認識の整合性を損ねるもので、魂への陰湿なる冒涜である、と言っても、過言ではない。問題の多き行為であった。多くのまともな予言者達はその事を十分に心得て居り、その故に、極めて、慎重な表現で、人類への警告を為したのである。だが、多くの場合、それらの警告は受け入れられず、結果、まともな予言は現象として現実世界を覆うのだった。それは因果と論理とに捕らわれた頑迷なる認識の咎めでもある。そして、報いでもあるのであった。一方、邪なる予言者や霊能者などには、その予言の実現と引き替えに、恐ろしいリスクが課せられた。彼等の力はこの世の理から生まれたのでは無い。この世の外から借り受けた、いわば対電子の如き一瞬、現実世界に現れる泡の様な力なのである。借りた物は返さねば為らない。いや、対電子が瞬時に消え去る様に、否も応もなしに、奪い取られた。だが、彼等の大半がその事を知らない。その故に、ある時、突如として、返済を迫られて、奪われるものは魂だった。 西欧には、悪魔に魂を売り渡して、超自然的な力を身に付けた邪なる人間の話が伝わっている。だが、その結末は何時も悲惨なものだった。自分ばかりか周りの者まで、奈落の底へと落としたのである。だが、祟り神と化した言代主や亜真野達の想念はそれを遥かに凌駕している。全世界が整合性無き混沌へと追い遣られるのか?あるいは、ふんだんに使われた借りた力がある時、一挙に奪われて、世界の破滅を招くのか?それは影浦にも分から無かった。だが、それをそのままに放置をすれば、いずれかは必ず遣って来る。其処には、何者かの意志も感じられるが、もしも、その何者かがこの世界の崩壊を意図して居るなら、それがたとえ神にしろ、その様な事などさせられ無かった。 |
|||||||
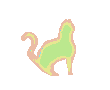

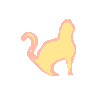
| |||||||
| Cotosiro | |||||||