|
可能世界・陰の神話 第十七章第四話 |
祟り神・かく悟りたまえり This was revised in December 10, 2007. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
丁度その頃、碁石が峰の一帯は異様な嵐に見舞われていた。森の木々は弓なりと成り、もぎ取られた小枝が宙を舞う。卵ほどもある大きな雹が横殴りと成って、地面を叩いた。一瞬、稲妻が闇を引き裂く。渦巻く雲を蛍光させて、轟音と共に、地に落ちた。一瞬、閃光が木々を貫く。無惨に裂かれた大木が紅蓮の炎を吹き上げた。漆黒の闇に炎が揺らめく。嵐が火炎を大きく煽った。引き千切られた炎と火の粉が激しく、宙へと巻き上げられる。辺りの木々を燃え上がらせて、たれ込める雲を怪しく染めた。碁石が峰の至る所で、真っ赤な炎が燃えていた。ふと見ると、怪しく渦巻く黒雲がずんずんと、地上に接近して来る。一瞬、雲の狭間から、龍の鱗が怪しく光った。光が微かに屈折している。空間が妙な具合に歪み始めた。時空が裂けたのに違い無い。奇怪なる生き物や魔物や死霊が此の世へと向かって、浸み出し始めた。どうやら、幻夢が此の世を飲んで、虚無へと変えよう、として居るらしい。幻もいずれは失せ果てて、全てが消え去るからだった。だが、未だ、無事な空間がある。碁石が峰の神殿だった。今、相容れぬ二つの魂が凌ぎを削って、戦っていた。 キメラは一斉に反転すると、衰弱をした亜真野に襲い掛かった。最後の留めの一撃である。が、錯覚だろうか?動けぬ筈の亜真野の身体が素早い動きで、キメラを交わした。二の矢は無い。全てのキメラは一瞬、間合いを外されて、ふらっと、宙に浮遊した。亜真野の望んだ一瞬である。彼はすかさず、鏡を取り出し、頭上、高くに差し上げた。銅の鏡が激しく唸る。キメラの羽が大きく震えた。共振をしたのに違い無い。もはや、キメラは羽ばたく事すら、出来ないらしい。全てのキメラはふらふらと、他愛なくも、吸引された。自らの衰弱をおとりと為した亜真野、苦肉の策略である。一転して、亜真野の勝利か、とも思われた。 だが、キメラの攻撃はなおも続いた。彼等は吸い込まれん、とするその直前、緋色の卵を産み落とす。それはすぐに孵化をして、極彩色の蚕と成った。蟻酸と毒糸とを吐き出しながら、亜真野へと向かって、じりじり迫る。亜真野は鏡を唸らせて、素早く、蚕を吸い込んだ。だが、蚕の成長は早いのらしい。鏡に吸い込まれるその一瞬、見る間に成虫へと変化を遂げた。そして、卵を産み落とし、銅鏡の面へと消えるのだった。幾ら、力で、ねじ伏せようとも、恨みの念と同様に消し去る事など、叶わぬらしい。怪しいキメラの毒の蒸気は益々、濃度を増すのであった。 皮膚がじりじりと焼け焦げる。激しい頭痛が亜真野を襲った。この侭、時が経過をすれば、亜真野の敗北は確実である。しかし、亜真野の振る舞いは極めて、奇妙なものだった。彼はなおも愚かしく、銅の鏡をかざし続ける。苦しみ藻掻く亜真野を横目に、言代主はせせら笑った。「無駄な事を!せいぜい、そうして、あがくが良いわ!」侮蔑に満ちた一言である。彼は勝利を確信していた。だが、良いのだろうか?亜真野の執念は凄まじい。苦しみを耐える亜真野の姿に、敗者の影など微塵もなかった。 苦痛は強ければ強いほど、憎悪の念を掻き立てる。そして、極限にまで到達した時、恐ろしき念を産むのであった。既に、それは熱を持ち、現象への時を窺っている。そして、まさにそれは今、鏡の面へと、凝縮していた。「時は至れり!」苦痛に耐える亜真野の腕が銅の鏡を高く掲げる。一瞬、鏡が唸りを上げて、目映い閃光を辺りに放った。だが、それはただの光では無い。金色に輝く甲虫の密なる群の姿であった。輪郭はエメラルドの緑に縁取られている。鋭い羽音を響かせながら、金色の渦へと変貌し、キメラへと向かって襲い掛かった。極彩色のキメラも蚕も、鋭い顎で、かみ砕かれる。産み落とされる卵もろとも、金色の甲虫の餌食と成った。実を言えば、金色に輝く甲虫は言代主が放ち、銅の鏡に封印された、あの灼熱の甲虫だった。にも関わらず、何故、彼等は言代主を襲うのだろうか?其処には、極めて、巧妙な亜真野の策謀が隠されていた。銅の鏡に念じ込まれた逃れ難き想念である。言代主の敗北と、国津神々の大和への服従、その歴史の記憶に他為らなかった。 その昔、大和に屈服をした国津の部族は辺境の地へと移されて、防人など、防衛の任を負わされた。多くの場合、同族への威圧と攻撃である。彼等に取っては、心の痛む屈辱的な仕事であった。鏡に捕らわれた甲虫達はそんな歴史の想念を無意識の奥底へと刷り込まれたのである。そして、その様な想念に従って、同じ経過をなぞったのである。今の彼等は明らかに、同族に弓を引く防人だった。自らを産んだ神にまで、その矛先を向けん、としている。千七百年余りを経過して、言代主はまたしても、ひとり、孤立したのである。心の奥底に秘められた想念の力は恐ろしい。時として、それは此の世を動かして、逆らう事を許さ無かった。祟りの神々の怨念はまさに、その歴史が産んだ産物である。歴史の記憶を拒否する事は祟り神としての自己存在を、否定する事でもあるのであった。 その故に、彼の産み出した甲虫も歴史の想念には、逆らえ無かった。怨念に心を奪われた咎めであるのに違い無い。それが亜真野の見出した言代主、最大の弱点だった。この様子では、最後の秘儀など、為されて居ない。勝利の予感が亜真野を捕らえた。何時しか、神殿は掻き消えて、亜真野は野外に佇んでいる。自然の洞穴は見られるものの、魔性の気配など、何処にも無かった。見上げると、夜空に瞬く無数の星が冷たい光を放射している。おびただしい亡骸も、既に、無く、ふたつの祟りの怨霊が亜真野と向き合い、佇んでいた。 亜真野は鉄剣を右手にぶら下げながら、憔悴したふたりに近付いた。「どう料理をしてくれようか?」激しい殺意が亜真野を捕らえる。両の拳に力が入って、二の腕の筋肉が微かに震えた。だが、亜真野は何故か、歩みを留めた。そして、鉄剣をだらりと下げると、押し殺した声で、述べ立てた。「言代の神よ、とこしえの服従を誓いたまえ、然も無くば、奈落の底へと落とすしか無し、返答や、如何に!」すると、言代主が一瞬、怯んだ。そして、哀願をする様に、必死の形相で、述べ立てた。「勝ちたる者よ、一刻の猶予を与えたまえ、御大津の神と語らわせたまえ!」亜真野としても、何の納得も与えぬ侭に、殺す事には不安が在った。大和の過去の過ちを繰り返す事にも成り兼ねない。「いずれにしても、猶予は一刻、新月があの山際に掛かるまで、それ以上、一時たりとも与えぬぞ!」亜真野は恫喝をする様に、二つの怨霊に促した。 その昔、言代主は幾多の戦いに敗れ果てて、船を沈めて、自殺した。果たせぬ恨みを抱きつつ、心を残して、死んだのだった。やはり、その時、建御雷は幾分かの猶予を与えて、妥協を探るべきだった。そうして居れば、言代主の怨念も、これ程の物では無かっただろう。亜真野は今、その怨念を服従に変えよう、と目論んでいた。言代主と御大津姫とは、互いに相手を抱える様に、洞穴の中へと吸い込まれて行く。歩く姿に力はなく、亡霊の様に儚げである。「果たして、如何なる態度に出るのか?」亜真野は地べたに、どっかと座って、その返答を待ち受けた。 一刻ほど、経って、言代主が現れた。傍らには、御大津の姫が寄り添っている。はやる気持ちをようやく堪えて、亜真野は返答を待ち受けた。と、言代主が一歩、進み出ると、穏やかな口調で、語り始めた。「勝ちたる者よ、我にひとつの願い在り!」声の響きは凛として、先ほどの憔悴した面影など、微塵も無い。亜真野は一瞬、憮然としたが、黙って、耳を傾けた。願いと言うのは、他為らぬ御大津の姫への想いであった。自分が果てるその前に、御大津の神を正しく祀って、神送りの儀式をさせて欲しい、と言う。亜真野は内心、頷いた。その昔、言代主は御大津姫命を祭る祭主であった。しかし、時は味方せず、言代主は打ち破られた。責務を全うし得ぬまま、海の藻屑と消えたのである。 言代主が再度、言った。「どうか、最後、我が祭りを全うさせたまえ!」だが、亜真野は少し躊躇した。服従の表明が為されて居ない。「言代の神よ、封印の城に戻るなら、その願い必ずや叶えよう、然も無くば、奈落の底へと落とすほか無し!」亜真野は声高に、そう言った。すると、敗者の言代主が膝を折って跪く。頭を下げると、恭順の意を素直に示した。満足して然るべき状況ではある。だが、亜真野には、言代主の落ち着きが気に入らなかった。「果たして、この落ち着きは何処から来るのか?」一瞬の疑念が其処に生じた。と、言代主が目敏く覚る。そして、自らの今の心境を淡々として、語り始めた。 確かに、命在る内は恨みも、此の世の理だった。だが、死したる後では、話も違う。如何なる魂であろうとも、世の理からは解き放たれた。自由を得て、少なくとも、怨念などに関わる必要など、無かったのである。だが、怨念を抱いた魂は自らを此の世へと繋ぎ止めて、その理に捕らわれた。今、言代主には、その事が、とても、愚かしく恥ずかしい、忌むべき行為にも思われる。「我が身を省みれば、破れたる事、幸いなり」言代主はそう述べた。敗北が彼を救ったのである。だが、もし、破れなければ、恨みの炎で、我が身を焦がして、迷妄の淵を彷徨っただろう。此の世の全てを焼く尽くすまで、消える事など、在り得なかった。だが、彼は戦いに敗れ去り、祟りの業は封じ込まれた。「長い年月、何を遣って来たのだろうか?」そんな想いが胸を突く。そして、その様な回顧の時が大事なものを蘇らせた。御大津の神に為すべき責務、神送りへの責務であった。彼の言う幸運とは、まさにその事に他ならなかった。 だが、亜真野は内心、せせら笑った。今回の無惨な敗北は言代主に、底知れぬ痛手を与えただろう。狼狽をして、気弱に成るのも、当然の事とは思われる。自らの敗北に意味を見出して、何等かのこじ付けをし無ければ、正気すら、保ち得ないのに違い無い。「何を、世迷い言を!」亜真野はそう蔑んだ。「しかし、此処では、抑えて置こう」指摘などしても、詰まら無い。神送りをして、満ち足りた気分で、滅びるのなら、此の上の無い幸せ、と言わねば為らない。「言代の神よ、約した事は必ずや守ろう、早く儀式を!」亜真野はそう急き立てた。と、言代主が微かに頷く。そして、御大津姫へと視線を送ると、微笑みながら、手を伸べた。敗者への思惑や侮蔑など、勝者の心理の常である。愛瀰詩を蔑んだ大和の歌謡も、その事を如実に表現している。言代主はその事を幾多の敗北から知ったのだった。幾ら、態度を取り繕うとも、欺かれなどはし無かった。 だが、それも止み難い人の心理であって、消し去る事など、叶わない。むしろ、そんな心根を哀れにすらも、思うのだった。勝者への憎しみも既に、無い。言代主の眼差しは御大津姫へと注がれていた。しかし、これは、どうした事か?涙がやにわに溢れ出て、頬を伝わって、したたり落ちる。ふと、見ると、御大津姫も泣いていた。忘れた筈の涙であるが、断ち切れぬ何かが苛むのである。止み難い生への執着だろうか?絶ち難い此の世への未練だろうか?彼等はひたすら、互いを見つめて、溢れる涙を流し続けた。 と、夜空の一画、北東の辺りに、まばゆい閃光が閃き渡る。極めて、巨大な流星である。光の塵を振り蒔きながら、碁石が峰の真上を走ると、見る間に、それは遠ざかり、南西の闇へと消え去った。おそらくは、美保関へと落ちるのだろう。二人が呪縛から解放される天啓の様にも思われた。だが、亜真野には、何の変哲も無い流星である。「何を何時まで、めそめそと!」言い知れぬ苛立ちが亜真野を捕らえる。両刃の鉄剣を素早く抜いて、二つの神に近付いた。此処に至っては、是非も無い。言代主は意を決し、最後の言葉を彼女に告げた。御大津の姫は既に、静かに目を閉じて、けなげな様子で、合掌している。此の世に在って、始めて知った、ほんの僅かな安らぎも、もはや、これまでの様だった。彼女の胸に去来をするは果たして、如何なる想いであろうか?怪しげなる妖気は掻き消えて、浄化を願う心情が痛々しいほどに読み取れる。常人ならば、心を打たれて、殺意も鈍る筈だった。しかし、亜真野は非情にも、瞬時に鉄剣を振り下ろす。彼女の喉が切り裂かれると、一瞬、血飛沫が飛散した。御大津姫の華奢な身体が一瞬、しなって、崩れて、落ちる。スローモーションの様に、地へと倒れた。 覚悟は出来て居た筈だった。だが、激しい悲しみが心を引き裂く。言代主は我知らず、御大津姫の名を呼んでいた。だが、答えは無い。彼は思わず走り寄り、彼女をしっかりと抱き締めた。滴り落ちる鮮血が彼の袖口を真っ赤に染める。彼は彼女を抱き竦めると、その場にジッとして、動か無かった。袖口を染めた血の上に彼の涙が滴り落ちる。一瞬、淡い斑点を成すと、鮮血の中へと消え入った。人としての言代主の偽らざる姿であるのだろうか?彼は押し寄せる悲しみをジッと、堪えて、御大津姫を抱き上げた。だが、悲しんでばかりも居られない。最後の神送りをせねば為らない。彼は祭壇へと遺体を運ぶと、静かに其処へと横たわらせた。去り難い想いが彼を捕らえる。だが、時間はそれを許さ無かった。言代主は踵を返して、口を結んで、其処を離れた。 |
|||||||
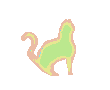

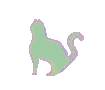
| |||||||
| Cotosiro | |||||||