|
可能世界・陰の神話 第十七章第五話 |
神送り This was revised in September 24, 2008. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
言代主の右手には、柳の枯れ枝が握られている。直径は三十ミリほど、長さにして、五十センチほども、在るのだろうか?彼は大地に胡座をかくと、簡素な小刀を取り出した。そして、小枝を払い落とすと、素早い動きで、表皮を剥いだ。まずは、白木の棒を作るのである。そして、それが完成すると、刃を寝かせて、その中程から先端へと、慣れた手つきで、滑らせた。切り屑が薄皮の様に巻き上げられる。だが、小刀は白木の先端、数センチの辺りで、一旦、留まり、薄皮を取らずに、其処に残した。その作業は削る位置を変えながら、幾度も幾度も、繰り返される。薄皮は次第に層を成して、美しい造形を現し始めた。すると、言代主はそこで、一旦、手を止めた。そして、少しばかり、手を加えると、白木の棒に幾重にも重ねられた薄皮が鳥の翼に似せられて、上手い具合に整えられた。薄皮を作らぬ先端部には、鳥の頭の彫刻がある。此の世と神の世とを往来して、魂を運ぶ鳥だった。鳥居に留まる鳥である。最後の仕上げが為されると、それは祭壇の前の白木の台に、厳かな様子で、捧げ置かれた。言代主はその正面に、ゆっくりと座ると、柏手を打って、頭を下げた。左手に、白木の碗を捧げ持ち、右手には、小さな木べらを携えている。木べらは椀へと幾度も運ばれて、その都度、祭壇へと向かって、差し伸べられた。神の国へと旅立つ者への最後の食事に違い無い。言代主の送りの言葉が夜のしじまを振るわせながら、木々の狭間を流れて行った。想えば、それは彼に取っての長い間の念願だった。そして、それはまさに今、彼の手によって、行われている。言代主の全身からは、至福のオーラが揺らぎ出ていた。 だが、亜真野の顔には、冴えが無かった。言い知れぬ不安が湧き出して、しきりと胸を突き上げる。言代主や御大津姫への訳の分からぬ嫉妬も在った。だが、亜真野は既に、彼らを打ち破って、惨めな敗者へと追い遣っている。今更、何を恐れて、何を妬む、と言うのだろうか?「馬鹿げてる!疲れの所為だ」亜真野はその様に自分を納得させて、湧き出す不安を押し込めた。神送りは直に、終わるだろう。二つの神も消え果てる。気分は苛立ち、憎悪も湧くが、今、しばらくの辛抱である。亜真野は敗者の為す、自己満足とも思える神送りを冷ややかな眼で、見つめ続けた。と、最前、捧げられた鳥木から、淡い光が浸み出し始めた。そして、空中へと放散して行く。それはあたかも、ダイアモンドダストの如き、神秘に満ちた、きらめきである。ただの光とは思えない。亜真野は幾分かの疑念を持って、放散する光を眺め続けた。放散されたきらめく塵は宙で次第に凝縮しながら、祭壇の方へと棚引いて行く。そして、祭壇の真上に着いて、雲の様に漂うと、見る間に、それは形を成して、輝く白鳥として、立ち現れた。御大津姫の亡骸が翼の下で、安らいでいる。白鳥の翼を微かに透かせて、陽炎の様に揺らいで見えた。 だが、これは果たして、どうした事か?亡骸の少し頭上には、もうひとりの御大津姫が浮遊をしている。不思議な物でも見る様に、自分の亡骸をジッと、見ていた。それは紛いもない御大津姫の魂である。どうやら、彼女は自分の死が分からぬらしい。言代主が子細を述べると、彼女はようやく、納得をして、静かに深く、頷いた。と、白鳥が御大津姫の方に首を回して、彼女に、乗る様に、と、背中に誘う。彼女は白鳥の首を優しく撫でると、ふわり、と、その背に舞い降りた。何と、美しい姿であろうか!言代主は立ち上がり、感、極まって、述べ立てた。「八百万の神々よ!御大津姫命、今、まさに、神と成らんとす、いざ、神々の基へと、導きたまえ!」すると、白鳥が首を上げて、一際、高く、クーッと、鳴いた。御大津姫が白鳥に、頷く様に微笑み掛ける。白鳥が大きく羽ばたくと、それは御大津姫を乗せたまま、宙へふわっと、浮遊した。御大津姫の全身からは、虹色のオーラが揺らぎ出ている。白鳥の全身をも飲み込んで、光の塵と成って、飛跡を作った。既に、御大津姫を乗せた白鳥は碁石が峰の上空にいる。孤を描く様にゆっくりと、言代主を見下ろして、旋回していた。何と、優雅な姿であろうか?言代主はただただ、白鳥の飛翔を眺め続けた。と、白鳥がまばゆい光を一瞬、放った。そして、急速に速度を増すと、天の川へと飛跡を作った。御大津姫と白鳥はもはや、一個の彗星である。光の塵を振り撒きながら、星々の間を飛翔した。そして、見る間に、小さく成って、一瞬、チカッと光を放つと、銀河の直中へと、消え入った。御大津姫は神と成り、神々の基へと戻ったのである。 言代主は美保津姫の消えた辺りを瞬きもせずに、ジッと、見ていた。言い知れぬ寂しさが込み上げて、胸を異様に締め付ける。「自分も、すぐに行ける、と言うのに、これはどうした事なのか?」為すべき仕事は為し終えた。もはや、此の世に未練は無い。今、心を覆う寂しさは神送りの興奮の薄れ行く虚脱感なのに違い無かった。天球の星々が瞬いて、神々の祝福を暗示している。言代主は銀河を仰いで、ひとり、感動の余韻に浸るのだった。だが、一方の亜真野は不機嫌だった。言代主の至福の時が如何にしても、許せぬのである。敗者は惨めで在らねば為らない。「さあ、早く支度を!」亜真野は勝者の残酷さを露わに示して、言代主を急き立てた。言代主が黙って、頷く。そして、泰然と祭壇の前を離れると、静かに大地へと胡座をかいた。と、何故だろう?亜真野の心に、最前、感じた、妙な不安が頭を擡げる。亜真野は理由が分からずに、自分の心理に戸惑った。言代主は此の世に未練を残して、逝くのでは無い。純粋な魂へと浄化をされて、神の基へと戻るのである。「もう、二度と、迷う事など、無いだろう」亜真野はそう確信していた。だが、彼のその様な確信は、本当に正しいのだろうか?たとえ、言代主は迷わなくとも、理不尽な抑圧がある限り、怨みの想念は染み出し続ける。そして、怨みの象徴を此の世へと向かって、放つのだった。新たな言代主の出現も在り得ぬ事では無かったのである。おそらく、亜真野も無意識ながら、その事は良く知っていた。しかし、意識には、上らずに、訳の分からぬ不安へと、形を変えて、現れたのである。「言代主さえ、消えてしまえば!」亜真野は今、殺意のみに捕らわれていた。 言代主は目を閉じて、心持ち身体を前に倒した。亜真野の殺気を背後に感じる。一瞬、鉄剣が唸りを上げて、言代主の首を跳ね上げた。鮮血が辺りに飛散する。言代主の胴体が大地の上にドッと、倒れた。身体がヒクヒクと痙攣している。そして、痙攣が治まると、言代主の無惨な遺体が星影の下で、微かに光った。「だが、何と、呆気の無い最後だろうか?」亜真野に、ふっと、疑念が芽生えた。言代主の滅亡が何故か、俄には、信じられ無い。妙な不安と寂しさがない交ぜと成って、亜真野を襲った。「これは一体、何なのか!」言代主は既に、無く、魔性の気配も感じられ無い。ならば、今の妙な不安は、そして、怪しげな寂しさは果たして、何処から、来るであろうか?亜真野はまたしても、不可解な自分の心理に戸惑った。そして、また、その事に対して、苛立った。「自分は勝ったのだぞ?考える事など、何も無い」亜真野はその様に自分に言い聞かせると、怪しい不安を押し込めた。と、その刹那、底知れぬ眠気が亜真野を捕らえる。激しい戦いの疲労だろうか?あるいは、戦いを終えた安堵だろうか?彼は眠気に抗し切れない。ふと、松の大木を目にすると、ふらふらと、その根本へと足を運んだ。そして、崩れる様に、腰を下ろした。辺りに漂う木の葉の香りが何時にもなしに、心地が良い。亜真野はふっと、顔を上げると、山の稜線に目を遣った。見ると、東の空が白んで見える。「朝が来る ・ ・ 」亜真野がポツリと、呟いた。小鳥の囀りが何処かで聞こえる。「全ては終わったのだ」亜真野は瞼を静かに閉じた。安堵感が心地の良いまどろみへと彼を誘う。今し方の戦いが脳裏を過ぎって、勝利の感触が亜真野を酔わせた。彼はすぐに、寝入って仕舞った。 夢の世界は異様に明るく、荘厳な光で満ちあふれている。亜真野は何故か、躊躇をしたが、その侭、足を踏み入れた。と、死んだ筈の言代主が微笑みをたたえて、佇んでいる。敗者の惨めさなど微塵も見えぬ気品に満ちた姿であった。「くそっ、お前は敗けたのだぞ!」亜真野は彼を睨み付けると、蔑む様に罵倒した。だが、言代主の態度は変わらない。涼しげな眼で、亜真野を見つめた。何故かは知らぬが、心が怯む。亜真野は思わず、目線を反らした。と、何故だろう?まばゆい光がやにわに失せた。気が付くと、辺りは漆黒の暗闇である。怪しい予感が脳裏を過ぎった。と、その刹那、彼の心の深みから、言い知れぬ怨みが浸み出して来る。そして、彼の心を揺すり始めた。だが、その怨みとは、果たして、何か?亜真野は一瞬、理解が出来ずに、暗闇の中で、戸惑った。彼は怨みをジッと、見つめた。と、それは他人からの怨念では無く、亜真野自身が心に抱き、遠い昔に押し込めた、忘れた筈の怨念だった。 昔、宮雄は父、足救に反抗してまで、自らの神を追い求めていた。だが、足救に力で押さえられ、彼は挫折し、打ちのめされた。今、蘇った恨みの念はその事への怨念に他為らない。だが、彼は神々の秩序を受け入れて、帰依した筈では無かったのか?其処への怨念を消し去って、生まれ変わった筈では無いのか?いや、確かに、それは間違い無かった。「ならば、これは、何なのか!」亜真野は戸惑い、そして、恐れた。宮雄が足救に反抗した時、足救は大和そのものであり、権力の権化そのものだった。だが、今や、宮雄が足救と成って、神々の秩序を信奉している。怨念が蘇った理由は分からぬけれども、その怨念は確かに、足救と成った今の亜真野へと向けられていた。 怨念は凄まじい圧力で、亜真野を襲った。亜真野は必死に堪えるけれども、怨念の力は凄まじい。彼の心をしきりと揺すって、飲み込まん、として、攻め立てた。この侭では、この怨念に飲み込まれてしまう。自らが神々の秩序を呪いを与える忌まわしき怨霊と成るだろう。その様な事は許されぬ。亜真野は神々の秩序を思念して、自らの行く道を思い起こした。そして、怨念を打ち砕こうと、力を強めた。だが、怨みの念も、同様に、負けじと力を増して来る。各々の放つ思念の炎が想念の闇を真っ赤に染めた。だが、奇妙な事に、互いの力は拮抗しながら、バランスを取る様に、増大している。もし、この状況に変化がないなら、決着は付かぬ様にも思われた。何時、果てるとも知れぬ攻防である。だが、亜真野の生身の肉体は果たして、この戦いに、耐え切れるのか?既に、亜真野の頭脳は大量の酸素を要求している。そして、彼の心臓は張り裂けんばかりに鼓動をしている。攻めぎ合いがこの侭、続けば、心臓が保たぬ様にも思われるのである。死への恐れが亜真野を捕らえた。しかし、力を緩めたならば、亜真野は怨霊と化すだろう。それは自らの死を持ってしても、阻止しなければ為らない。彼は止む無く、思念を強めた。 既に、血管は皮膚に浮き出し、限界にまで、膨張している。心臓は握り潰されでもするかの様に、重い痛みを訴え始めた。やにわに、目眩が亜真野を襲う。意識がスーッと、遠退いた。「死ぬのだろうか?」亜真野は一瞬、覚悟を決めた。既に、眼は光を感じず、身体の痛みも感じられ無い。気が付くと、怨念の圧力も消失していた。「勝ったのだろうか?それとも、自分は死んだのだろうか?」亜真野は一瞬、自分に問うた。だが、次の瞬間、視力が戻ると、眼前には、凄まじい形相の怨霊が亜真野を睨み付けて、浮遊をしていた。亜真野とは全くの瓜二つ、双子の様な怨霊である。気が付くと、亜真野自身も浮遊をしていた。ふと、大木の根本を見下ろすと、自分の身体が寝そべっている。死んだ様に動かぬけれども、生気は消えてはいなかった。二つの戦う魂の、生への飽く無き執念が肉体を死から、守ったのである。勝った者が自分の身体を手に入れて、自らの想念を生きるのだった。 |
|||||||
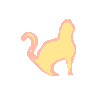
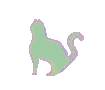

| |||||||
| Cotosiro | |||||||