|
可能世界・陰の神話 第三章第二話 |
隠された魂 This was revised in Frbruary 28, 2012. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
宮城が影浦を連れて、帰京をしてから、既に、三日が経過している。だが、最初の会合以来、話し合いは中断して、何の進展も、為されていない。影浦の疲労が予想外に厳しく、休ませる事にしたのであるが、宮城はしばしば、焦りを覚えた。こうして、何もせず、手を拱いている間にも、祟り神と成った言代主は着々と、あの恐ろしき力を養っている。それをその侭、放置するなら、あの忌まわしい羽虫達がイナゴの様に群を成し、日本列島を覆うだろう。そして、人々の心へと、侵入して、猜疑心や妬みの心、陰湿なる衝動を、増幅させるのである。 そう成れば、人々の間の信頼感は急速に、失われて、我欲に捕らわれた人々が自らの利益のみを考え始める。正しき人々を押し退けて、貧しき者達を蹴散らして、癌の様に増殖し、日本の社会を蝕むだろう。また、その事が国政をも、揺るしかねない恐ろしき事態を生み出すのである。そう成る前に、祟り神を癒し得る、何らかの手段を見出して、対処する事が必要である。宮城はそう、考えていた。古来より、祟り神が国政に、悪しき影響を及ぼす事例は、そう、希でも無いのである。 大阪のホテルで、宮城が見た幻を考慮するなら、影浦はその問題解決のカギを握る重要な男であるらしい。その故に、宮城はあの時、急遽、札幌に出向いたのである。事情を話して、協力を求める為だった。だが、彼が影浦に電話をした時、宮城は、影浦の精神の状態が幾分、不安定である事を察知した。また、その事から来るであろう猜疑心も、見抜いたのである。 ただでさえ、信じ難い話を持ち込むのであるから、その様な状態にある影浦を、ありきたりの手段で、説得する事は難しい。その故に、宮城は自分の霊力を示さねば為らぬ、厄介な羽目に陥ったのである。最初に、電話で、ボソボソと、怨霊などの話をあえて、したのも、その伏線のつもりであった。だが、宮城にとって、これも、初めての体験であったから、その方法については、適切であった、とは言い難い。影浦に、かなりの動揺を与えた事は確かであった。 ただ、宮城の見た幻に、あれほど、はっきりと、現れたのであるから、影浦が並の人間でない事は確かである。あるいは、啓示の主が宮城に、その存在を教えたのかも知れない。そして、影浦の情緒不安定は、自分自身がこの問題の渦中に居る、と言う意識されざる予感の所為であった、と言う事も、考えられる。いや、むしろ、その事は確かである様に思われる。影浦の魂はその時点で、既に、あの祟り神と戦っていたのかも知れないのである。影浦の今の疲労と休息は、彼の意識がその事を理解する絶好の機会である、と考える方が良いのかも知れない。「いずれにしても、しばらく、静観した方が良さそうだ、焦って動くと、かえって、不味い」宮城はこの所、焦りを感じる度に、そう、自分に、言い聞かせていた。 だが、その日の午後、七時頃、その影浦から、電話があった。午前中こそ、ホテルで、うたた寝などをして、のんびりとした時間を過ごしたらしいが、午後からは、ホテルを出て、あちらこちらと、歩いた、と言う。どうやら、体力の方は戻ったらしい。彼の口調から判断すると、精神の状態も、幾分、戻った様に思われる。宮城はふと、議論の再開を期待した。だが、本人がその気に成らなければ、良い結果は望めそうに無い。「まあ、今日、一日はゆっくりと、休んで下さい、明日、また、電話します」宮城は差し当たり、その様に、言葉をかけた。当然、「ああ、そうさせてもらう」と、言う様な、ありきたりの答えが返って来るもの、と思ったのである。 だが、影浦の返事は全く、意外なものだった。良い店があるので、飲みに行こう、と言うのである。予期せぬ誘いに、宮城は若干、戸惑った。昨日まで、疲れが取れない、と嘆いて居たのに、これは果たして、どういう事か?宮城は思わず、「えっ?飲みに、出るんですか?」と、問い掛けた。と、影浦は、「ええ、良いでしょう?熊野さんと、ご一緒に、どうですか?」と、追い打ちを掛ける。宮城は一瞬、「疲労を助長させないだろうか?」と、思案したが、断ると、その事自体が精神衛生上、余り、良くない、と言う事も、考えられる。彼の疲労は大方が精神的なものであるのだろうし、ホテルに、一人で居るよりは、人の居るところで、ワイワイと、やる方がましなのかも知れない。宮城は余り、酒は嗜まないが、結局のところ、誘いを受けた。 それにしても、影浦の飲み屋での、子供の様なはしゃぎ様は意外であった。見栄も、外聞も、あったものでは無い。宮城は驚いたが、無理に、そうしている様にも、見えないので、元来は、陽性型の人間らしい。いや、むしろ、それは極楽とんぼ、と言う方が適切なほどである。結局、宮城は熊野、共々、幼児の様な影浦につき合わされて、更に、数軒を梯子した。そして、延々と、飲み続ける羽目に陥ったのである。気が付くと、時刻は既に、午前の四時を十分ほども、経過している。もはや、梯子をするべき店もない。タクシーを拾って、影浦をホテルに送る頃には、空が白々と、明け始めていた。 影浦の機嫌はすこぶる、良いが、この調子では、今日の議論の再開は、夢のまた、夢、の様である。「それにしても、これ程の大酒のみとは」宮城は幾分、閉口していた。だが、その別れ際、影浦が言った。「明日からまた、始めましょう!いや、こう見えても、わりと、タフなんですよ?」だが、話の様子から、判断すると、それは明日では無く、どうやら、今日のつもりらしい。「おやおや、本当に、大丈夫なの?」宮城は幾分、不安に成った。だが、影浦は酔った勢いだろうか?「熊野さんの教室で、良いんですよね、一時までには、伺いますから」そんな風に勝手に決めると、心許なく、ふらふらと、ホテルの階段を登って行った。 宮城は今、熊野の控え室で、その影浦を待っている。だが、熊野は此処には、居なかった。二時までは、野外実習の為の準備だ、と言う。彼はその事をすっかりと、失念していた。天才には、時折、見られる症状である。いずれにしても、熊野は何を考えて居るか、分からない、妙な部分を持ち併せて居た。それにしても、影浦はまだ、現れない。時計を見ると、一時を十分も、経過している。「電話でも、して、聞いてみようか?」宮城はチラッと、電話を眺めた。 だが、今日は、この講座のスタッフが二人ほど、部屋の中で、仕事をしている。間もなく、皆、出払って、今日は帰らぬ、と言うので、それは良いのだけれども、電話を借りて、喋るのは、何とは無しに、気が引ける。「まあ、じきに来るだろ?」と、考えて、結局、電話を諦めた。すると、此処のスタッフが出払った数分後、ドアがコツコツと、叩かれた。見ると、それは影浦である。見たところ、疲れた様子など、感じられない。「なるほど、タフなんだ」宮城は妙に、感心した。 影浦は熊野が戻ると、待ち兼ねた様に、話を始めた。言代主が何故、祟り神として、この現代に現れたのか?その謎が少しではあるが、分かった、と言う。其処には、日本人の持つ精神の未だ、知られざる構造が、極めて、深く関与していた。それは縄文的な魂と弥生的な合理精神の、その歴史的関係に醸し出された極めて、根の深い構造である。言代主が現れた今、影浦は、その二つの精神の軋轢が極限に達した様に、感じたのである。彼はその軋轢を産む、未だ、知られざる構造について、語り始めた。 日本人の心の底には、縄文文化の魂が存在している。日本人がその遺伝的基層として、縄文の血を持つ如く、その文化的、精神的な側面をも、受け継いだからに他ならなかった。それが本来の日本の魂、すなわち、縄文の魂である。だが、その精神は何時しか、弥生文化に抑圧されて、その表現を妨げられた。その発露は祭りなど、特殊な状況でしか、許されない。縄文の魂は権力の忌む精神であり、我々、日本人の各々が無意識とは言え、それを抑えたからだった。そして、その抑圧の論理こそが、弥生文化に基づく合理主義的な精神だった。 だが、それは文明の精神であり、権力と組織の精神である。個の精神とは、馴染まない。その故に、縄文の本来の魂は心の奥底へと、押し遣られて、其処に、弥生的合理主義的精神が覆い被さる、我々、日本人の精神は、その様な二重構造を持つに至った。そして、その事が縄文の魂に、弥生的な支配体制への拭い難き怨みを抱かせたのである。影浦は、この怨みの念を縄文の怨念、と名付けていた。 影浦は言った。「この精神の構造は、言代主が大和に破れて以来、我々の性と成りました、個を殺し、全体につくす、これは日本的な自己疎外の習性と言っても、良いのかも知れません、もちろん、組織に関係したこの様な自己疎外は他国にも、見られます、しかし、我々の自己疎外はあくまでも、我々の歴史に根ざした日本固有の問題です。縄文の怨念に関わる、基本的な問題はどうやら、この辺りに、在りそうです」 すると、宮城が僅かに頷いて、確認をする様に、問い掛けた。「つまり、言代主の怨霊は我々の心が産み出した、いや、現象させた?」「エエ、本当に怨霊が居るのなら、そう考えるしか在りません、しかも、彼はただの怨霊ではありません、我々、個々人の心に巣くう、縄文の怨念、そのものなんです」 その昔、縄文人は弥生的な文化を受け入れながら、その血も同様に受け入れて、あるいは、力によって、押し付けられて、倭人の血と文化とを形成して来た。縄文人の社会に取って、その様な文化と血の受け入れが必要であったからに他ならない。そして、その先進性が輝いて見えた事も、推測し得る。また、戦いに勝ち、権力を握る者は、その殆どが、弥生的な色合いの濃い勢力であったのである。弥生文化に基礎を置く合理主義的な精神を重く見て、縄文の魂を軽んずる様な社会的な傾向が蔓延するのは、当然の事ではあったのである。 影浦は言った。「ですから、縄文的な精神は権力に取って、忌むべきもの、と成りました、それは弱き者の精神であり、また、権力に反抗する精神でも、在った訳です」宮城が言った。「なるほど、それで、権力は縄文の神々を序列化、あるいは、変質させて、縄文文化の排斥に、血道を上げた?」「エエ、そして、個々人も、権力におもねて、取り入る為に、あるいは、生き抜く為に、自らの縄文の魂を押さえたんです」 各々の時代の支配者達は個の精神である縄文の魂を忌むべき精神として、抑え続けた。そして、縄文の魂は心の奥底に圧縮されて、熱を持ち、恐ろしい怨念として、現れたのである。それは現代の日本人の心にも、受け継がれている。また、それは十数世紀に渡って、燻り続けた、怨霊としての言代主の、恨みの念でも、あるのであった。祟り神、言代主の出現はまさに、その様な我々の精神構造と歴史的な環境に、起因している。いずれにしても、陰湿な犯罪が増加している今、個々人の秘められた怨念が増大している事は確かであった。 影浦が言った。「今の日本人は言って見れば、抑圧した者と抑圧された者との混血です、そして、抑圧者は大和に代表される弥生的な合理主義的精神であり、被抑圧者は言代主一族に代表される縄文の魂であった訳です」 実を言えば、この様な精神的、あるいは社会的な関係は、今でも、社会のあらゆる場所に見る事が出来る。金持ちや一部の特権階級は別として、個は組織の為に喧伝される効率の論理を押し付けられて、あるいは、植え付けられて、自らの行動を抑制しているのである。また、その故に、多くの人々が疲弊している。その事は電車で、居眠りをする人間が他国に比べて、異常に多い事からも、推測できる。個の論理が悉く、葬り去られる今の状況下で、社会への怨念が増殖するのは至極、当然の成り行きではあったのである。 その事は同じく、組織や子供らに見られる陰湿な虐めが増大している事からも知る事が出来る。それは社会全体の具象的な鏡であるからである。そして、祟り神、言代主の力はその様な社会の状況に、支えられている。また、精神の二重構造は、日本人の魂が権力に関わるほど、抑圧される、という避け難い矛盾も、内包している。弥生の合理主義的精神への傾斜は即、縄文の魂への抑圧でもある。その事は抑圧者、自らの魂と云えども、例外では無い。彼らもまた、縄文の魂を宿している。その権力志向が自らの縄文の魂を、激しく、抑圧する事は自明であった。影浦はその様に、述べると、一息、付いた。 宮城が言った。「なるほど、その怨念は、その様な人間に、自らの権力志向を呪わせる、権力者は無意識に、自らを滅ぼそう、とするのかも知れ無い、と?」 影浦が答えた。「エエ、そうです、でも、まあ、その様な自己破壊の問題は必ずしも、物理的に、権力に近いから起こる、と言うのでは無く、むしろ、心の有り様の問題でしょう、いずれにしても、あの怨霊はその様な日本の現状が呼び込んだんです、無論、問題は、そうした自らを呪う、隠された性癖の為に、権力者が滅ぶ、と言う事では無くて、国家と、国民が巻き添えを食らう、と言う事なんです」 そして、影浦は少し、考えると、続けて言った。「あるいは、第二次大戦での降服の遅れも、権力者達の、その様な性癖が関係したのかも知れません、平たく、言うと、あの当時、討ちして、止まん、と言いながら、実は、兵士を見殺しにした類いの意識ですかね・・美しい言葉で、それを飾るなら、滅びの美学、と言うのでしょうが、実態は、滅びの美学の押しつけであった訳です・・もし、あの時、少しでも、降服の決断が遅れていたなら、日本は本当に、滅びて居たのかも知れません・・」 影浦の言葉には、迫力があった。確信があるのに違いない。宮城は無言で、頷いた。影浦が言った。「ですから、言代主の怨念はその様な抑圧者に向けられている、つまり、倭人の権力機構と、それを支える人間達に向けられて居る、彼は縄文の魂を解放したい、のかも知れません」 すると、熊野がその傍らで、ぼそっと、問うた。「あの、弥生的支配、なんですが?」「あ、自分勝手な造語ですからね、説明が要りますね」影浦は皆まで聞かずに、頭を掻いた。 熊野が言った。「イエ、大体は分かります、縄文的な魂を抑圧する事によって、権力の求心力を高めよう、とする支配の体制、そう、考えて良いでしょうか?」「エエ、その主体が弥生文化の担い手だった、いや、弥生文明、と言う方が良いのかも知れません」 大和の出現以前、各部族は各々の神々を戴きながら、互いの神々を尊んだ。その意味で、彼等の魂は自由で在り得た。だが、それは同時に、権力の求心力が希薄な事を意味して居り、弥生の文明とは馴染ま無かった。弥生の文明に限らず、文明、と名の付くものは必ず、効率を追求して、その故に、権力強化を要請して行く。そして、その事は古代に於いて、神々を抜きにしては、語れ無かった。 文明は個々の神々を統一して、あるいは序列化をして、個のルーツと成るべき神々を権力を支える神々へと、変質させる。また、その事が文明を高度に育て上げて、更なる権力集中へと導くのであった。奇しくも、それは記紀の神話の筋立てに、はっきりとした形で描かれている。縄文の神々は抑圧されて、個々人は文明の器官へと組み入れられて、個のアイデンティティーすら、無くすのだった。その図式は今に到るまで、変わって居ない。祟り神、言代主の出現も、其処に、関わるのに違い無かった。 と、宮城が首を捻った。そして、戸惑い気味に、言った。「でも、妙ですね、もし、あの祟り神が縄文の魂を復活させようとしているのなら、その神と戦おうとしている我々は弥生の支配体制に荷担する、と言う事にも成り兼ねません、いや、そんな筈は在りませんけど?」 だが、影浦は一瞬、絶句した。祟り神の怨念は確かに、弥生の支配体制へと向けられて居り、滅ぼそう、として居る事も、間違いは無い。そして、弥生の体制が崩壊すれば、縄文の魂は解放される。怨霊に対決をする事は、その解放を阻害する事に成るのだろうか?影浦は妙な矛盾に陥った。と、熊野が傍らでボソッと、言った。「でも、相手はあくまでも、怨霊です、余り難しく考えるのも、問題ですよ、全てが滅ぼされたなら、解放どころでは在りません」熊野の指摘は尤もである。「あ、そうだよな?」と、影浦は思わず、赤面した。 それにしても、何と、迂闊な事だろう?言代主への妙な想い入れが、そんな具合にさせたのだろうか?あるいは、推理に酔いしれた論理的暴走の結果だろうか?単純な真実すら、曇らせる思考という物の危うさである。影浦はつい、知らぬ間に、その様な罠に填ったのである。 言代主の怨念は当時の大和政権、また、それを支える生身の人間に向けられている。だが、その弥生の支配の体制は魂の抑圧という、基本的な部分で、現代の支配と同一だった。縄文の魂は古代と同様に、抑圧をされて、個々人は弥生の支配に奉仕する組織の部品として、生かされている。そして、今、抑圧者と抑圧される者の血は混じり合い、弥生の支配に奉仕している。つまり、今や、全ての日本人が言代主の標的なのである。例外などは在り得なかった。と、熊野が言った。「言代主が怨霊では無いなら、彼は解放者なのかも知れません、しかし、現実はそうじゃ無い、これからは、弥生的な支配の体制と、あの恐ろしき怨念と、本来の縄文の魂の、三つ巴の戦い、と成るのでしょう」 |
|||||||


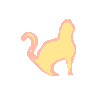
| |||||||
| Cotosiro Home | |||||||