|
可能世界・陰の神話 第四章第二話 |
モルモット This was revised in March 7, 2012. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
落雷の音が遠くに、響く。亜真野は書類を書く手を休めると、ふっと、顔を上げて、窓越しに見えるキャンパスに、視線を向けた。と、雨が僅かに、降り始めている。「にわか雨か?」亜真野はそう、呟くと、机上の書類へと、視線を戻した。大した仕事では無いのだが、今日中に書き上げて、防衛庁に、送らねば為らない。亜真野は急ぎ、ペンを走らせた。が、その刹那、一瞬、閃光が辺りを照らす。少し、遅れて、凄まじい轟音が響き渡った。窓ガラスを叩く雨音が、急速に、激しさを増して行く。「ああ、本降りか?通り雨なら、良いのだが・・」亜真野は再び、顔を上げると、見るとも無しに、窓を見た。 横殴りに降る大粒の雨が激しく、ガラスの面を打ち据えている。其処で、砕け散った雨水が滝の様に、流れ下った。それはまるで、透明なカーテンか、何かの様である。人の失せたキャンパスが、陰鬱な様子で、滲んで見えた。植え込みに、点々と咲く紫陽花が身をすくませる様に、佇んでいる。その様が秋のようやくの到来を告げる様にも、思われた。「それにしても、これほどの雨に成るとはな」亜真野はふっと、手に持ったペンを机上に置くと、降りしきる雨をじっと、見つめた。 実は、今日、此処に、中臣が来る事に成っている。久方ぶりの訪問である。既に、戦時心理研究所は軌道に乗って、通常の活動にいそしんでおり、立ち上げ当初の、中臣との頻繁な会合は無く成っていた。だが、今朝、中臣からの電話があった。大事な話があるらしい。電話を受けたのは、秘書室の真野美香子であったが、彼女の話では、中臣は、「用件は会ってから、話す」と、言って、電話を切った、と言うのである。どうやら、込み入った話であるらしい。亜真野は少し、気に成っていた。 ふと、気が付くと、部屋のドア越しに、ノックが聞こえる。美香子は今、出かけているので、秘書室を素通りして、来たらしい。時間からすると、中臣だろう。亜真野が、「どうぞ?」と、返事をすると、ドアがスッと、開かれて、中臣が姿を現した。チラッと、時計を確認すると、約束通り、きっかり、三時の訪問である。「やあ、お珍しい、まま、どうぞ、こちらへ」亜真野は鼻先に落ちた金縁眼鏡を慌てた様に、グイッと、押し上げると、満面の笑みで、部屋へと招いた。 だが、本当の事を言うと、これはある種の牽制である。美香子から聞いた電話の様子から、ひょっとすると、また、厄介な問題を持ち込んで来るのではないのか、と言う予感も、あったからである。そして、不幸にも、その予感はどうやら、当たったらしい。中臣が抱える分厚いファイルが、その事を強く、暗示している。あるいは、予想以上の難題であるのかも知れない。亜真野は警戒しながらも、素知らぬ顔で、椅子を勧めた。が、中臣は何故か、椅子には、座らない。背筋を伸ばして、かかとを合わせると、「ご覧下さい」と、言って、ファイルを示した。中臣がこの様な態度を取る時は、大抵、用件は頼み事なのである。しかも、それは厄介なものがしばしば、あった。研究所の立ち上げ当初、亜真野は中臣の要求の為に、随分と、苦労をさせられたのである。「チッ、やはりな・・」亜真野は内心、舌打ちしたが、素知らぬ顔で、受け取った。 ファイルを開くと、新聞などの写しらしい。その脇には、中臣自身の筆跡で、何やら、覚え書きの様な文字が書かれてあった。「ん?何ですかな?これは」亜真野は訝る様に、問い掛けた。中臣が言った。「はい、これは島根での此処、二年ほどの犯罪と事故、自殺などを集めたものです、ですが、どうも、様子が普通ではありません、霊的な作用、としか、思えんのです」 と、亜真野の顔がわずかに、歪んだ。だが、それは、何を想っての事だろう?中臣はその意味を読み取ろうと、亜真野の顔を覗き見た。だが、亜真野は既に、報告書へと、視線を落として、ただ、パラパラと、ページを捲っている。見たところでは、内容に、それほどの興味は示していない。最前の表情と言い、この態度と言い、余り、良い状況とは言い難い。「何を考えているのだろう?」中臣は妙に、もやもやとした、嫌な気分に陥った。と、亜真野がページを捲る手をやおら、止めて、言った。「でもねぇ、映画じゃあないんですから・・思い過ごしじゃあ無いんですか?」 それにしても、随分と、嫌みな言い方である。良くある事ではあるのだけれども、中臣は少し、ムッと、した。私費まで、投じて、調べ上げたと言うのに、その様な言い方は無いだろう。中臣は亜真野の態度に、釈然とせぬものを感じ取った。霊現象に、並々ならぬ関心を示す亜真野にしては、余りにも、素っ気が無さ過ぎる。「虫の居所でも、悪いのか?」中臣は一瞬、そうも、思った。だが、少し、違う様にも、思われる。中臣は取りあえず、「いえ、これはまず、間違い在りません・・」と、短く答えた。亜真野の反応を見たかったのである。 と、亜真野が言った。「けど、霊現象で、これだけの事が起こる、と言うのは・・ちょっと、考えられませんな」そして、彼はファイルを閉じると、一瞥もくれずに、机上に置いた。その態度は妙に、冷ややかである。中臣は、「それは本当に、本心なのか?」と、疑った。無論、確証などは無いので、その時点では、疑念の侭で、止まったのだが、実を言えば、彼の観測は当たっていたのである。 亜真野は既に、この問題を察知しており、その霊象が言代主のものである事も知っていた。彼は中臣以上に、この問題を深刻に、受け止めていたのである。しかし、彼には、この問題を伏せねば為らぬ、秘められた事情が在った。あの霊象が露見するなら、自分の秘密の計画も、あるいは、露見し兼ねない。亜真野はその霊象を察知した当初から、その様な危惧を抱いていたのである。言代主と亜真野とは、原理的に敵対する魂である。中臣の学者としての洞察力を考えるなら、あの霊象から、その敵対者の存在を推定する事は決して、不可能な事では無かったのである。 いずれは、中臣を使って、あの霊現象に対処するのが、亜真野の目論見であったが、もし、中臣が亜真野に疑いを持つ事に成ると、それはその計画にとって、非常に、具合が悪い状況と成る。しかも、その計画の為の実行条件は、中臣の洗脳をはじめとして、まだ、何も、揃ってはいないのである。「出来得れば、この問題を有耶無耶にして、少し、時間を稼ぎたい」亜真野の心境はその様であった。だが、中臣の態度からすると、あの霊象が言代主によるものである事も、既に、掴んでいるのに違いない。ならば、自分の当初の計画は変更せざるを得ないだろう。次善の策が必要だった。「だが、中臣はどの程度、掴んだのだろう?」中臣への対応はそれによって、決めねば為らない。亜真野はのらりくらりと、言葉を交わして、中臣の反応を窺った。 一方の中臣は亜真野のいい加減とも思える受け答えに、苛立っていた。今日の魂胆は分からぬけれども、何事によらず、もったいぶって、人を焦らして、悦に入るのが、亜真野の奇妙な癖なのである。報告だけで、用が足りるのなら、ファイルを渡して、サッサと、退散したい場面であった。だが、今回の問題では、亜真野の協力が欠かせ無い。とにかく、早急に、納得させて、動かす事が必要なのである。 中臣がこの問題に気付いた切っ掛けは、島根での心理学についての講演だった。数ヶ月前、島根の県警から、社会心理学の特別講師として、招かれたのである。中臣の他にも、異常心理学、精神分析学などの専門家が招かれている。他県では見られぬ異常犯罪、そして、事故や自殺など、その様な事件の急増が問題視されたからだった。講演は三日に渡って、行われた。だが、中臣はその講演の最中、それらの現象に、心理学では説明し切れぬ、怪しげな影を感じ取った。つまり、それらの異常な事故や自殺は霊象ではないのか、と感じたのである。そこで、彼はその後も、島根を訪れた。自らの課題として、取り組んだのである。だが、調査の時間は限られて居り、その解析は難航している。人も、資金も、不足していた。 この問題を解明する為には、研究所の枠をはみ出す様な、大きなプロジェクトを組まねば為らない。しかし、亜真野の意向で、所長と成った中臣には、その様な力など、殆ど、無かった。霊象の研究に興味を示して、金まで出す人間など、見つける事は難しい。亜真野を頼るしか、無いのである。中臣は亜真野の気持ちを反らさぬ様に、熱心に、説明をし続けた。 「まだ、確証は無いのですが、言代主の怨霊では無いのか、と、その様な感触も、持って居ります」「エッ?美保神社の?あの言代主命ですか?」亜真野はさも、意外である、という顔つきで、中臣の話を促した。 中臣が言った。「はい、墳墓の発掘も、進んでいる、と聞いていますが、その関係者が相次いで、妙な事件に遭って居ります、とても、偶然では、片付きません」中臣はそう、言いながら、ファイルの中程を急いで、開くと、数枚の紙片を亜真野に示した。どうやら、何かのグラフらしい。亜真野は話を促す様に、中臣の方へと、視線を向けた。 中臣が言った。「ご覧下さい、あの墳墓から半径、三十キロ地点で、計った地磁気と重力の値です、数ヶ所で、計ったのですが、あ、これが重力で、そっちが、地磁気ですね」「あ、なるほど?」 「ごらんの様に、この二つの値は異常なバラ付きを見せて居ります、特に、重力は千酌の方に傾きながら、変動します、垂直方向に対して、零度二十分ほどですが、これはなまじの霊力ではありません」 中臣は目を逸らさずに、話し続ける。亜真野はそんな中臣に、この問題への異常な執着を読み取った。学者としての興奮も、垣間見られる。亜真野が進言を無視すれば、中臣は別の協力者を探すだろう。そう、おいそれとは、見つからぬ、と思うけれども、万が一、と言う事も、無くはない。もし、そう成ると、ひょんな事から、伏せて置きたい事柄が明るみに出ない、とも限らない。中臣を手の内に入れて置いて、勝手な行動をさせない様に、コントロールする事が必要なのである。 「止むを得ないか?」亜真野はそう、断を下すと、納得した風を装って、言った。「うん、一応、調べる必要はあるかも知れませんな、でも、調査の計画はあらかじめ、教えて置いて下さいよ、資金の事も、在りますしね、後は、月に一度、報告して頂ければ良いでしょう、まあ、自由に、遣って見て下さい」そして、机上のファイルを手に取ると、中臣にスッと、手渡した。中臣の予測に反して、それは意外なほどに、すんなりとした了解である。中臣は少し、戸惑ったけれども、「はっ、有り難う御座います」と、丁重に、頭を下げた。そして、ファイルを小脇に抱えると、踵を返した。 だが、その刹那、亜真野が背後から、呼び掛ける。「は?何でしょう?」中臣がくるりと、振り向いた。亜真野が言った。「あの、あなたのスタッフは何処まで、知っているんです?」中臣が言った。「イエ、まだ、言代主の事は知りません、伏せてありますので」「あ、そうですね、スタッフには、まだ、その事は知らせない方が良いでしょう、あくまでも、フィールド探査、と言う事で通して下さい、よろしいですね?」亜真野は釘を刺す事も、忘れ無かった。 その一週間後、中臣は研究所員で、霊能者でもある壱岐真彦を呼んで、約束の計画書を持って行かせた。了解はすぐにでも、貰える筈である。中臣は壱岐の帰りを心待ちした。だが、壱岐の持ち帰った返答は全く、意外なものだった。調査団の派遣は見送りたい、と言うのである。「何故なのか!」中臣はひどく、戸惑った。そして、怒りも、込み上げた。「何があなたに任せるだ、冗談じゃあ無い!一体、どう言う事なんだ?」傍らの壱岐を振り向くと、八つ当たり気味に、問い掛けた。 だが、壱岐も、理由など、聞いては居ない。戸惑い気味に、首を傾げる。亜真野の意図は何処にあるのか?中臣は想像を巡らすが、嫌がらせ、としか思えない。壱岐をその場に立たせたままで、部屋の中を歩き回った。意地悪そうな亜真野の顔が脳裏に浮かんで、我慢が為らない。「ようし、直談判だ!」中臣は手前の椅子を払い退けると、机上の電話に腕を伸ばした。だが、何という間の悪さだろうか!電話のベルがやにわに、鳴った。「くっ、誰だ?こんな時に!」中臣は忌々しげに、受話器を上げた。と、それは何と、亜真野である。すぐに、こちらに来て欲しい、と言う。「良いだろう、望むところだ!」中臣は計画書を小脇に抱えると、あわただしく、部屋を飛び出した。 「やあ、中臣さん、先ほどは、どうも、失礼しました」中臣がドアを開けると、恐縮をした風に、亜真野が迎える。「あ、いえ、それで、どの様な、ご用件です?」中臣は上げた拳をすかされて、仕方が無しに、そう、問うた。と、亜真野は中臣を椅子に座らせて、押し殺した声で、話を始めた。「いや、実はですね、壱岐君には、知られたく無かったもので、何も、言わずに返したのですが、あれでは、どうも、不味いんですよ」 亜真野の話はこうだった。もし、中臣の予測が当たって居るなら、調査団は相当の危険に晒される。だが、各構成員には、怨霊の事は伏せられて居り、危険への認識など、殆ど、無かった。つまり、不意打ちを食らう訳である。もしも、怨霊が居るのなら、無事に済む、とは思え無かった。「まあ、そういう事で、何か、別の方策を考えては頂け無いでしょうか?危険な事は避けたいのです」亜真野はそう、述べて、話を終えた。どのみち、自分の立場を考えて、予防線でも、張ったのだろうが、指摘自体は的を射ている。中臣としても、納得せざるを得なかった。 だが、代替策は問題である。亜真野の意向を取り入れて、しかも、成果を上げるなど、二律背反も、甚だしい。「こんな事なら、最初に、言えば良いじゃ無いか!」中臣はそう、心の中で、怒鳴ったが、学長の亜真野を前にして、態度になどは表し兼ねる。「分かりました、考えてみましょう」中臣はそう、言って、一応、話を承ると、一礼をして、踵を返した。と、背後から、亜真野がボソッと、呼び掛ける。「あ、中臣さん、モルモットは、どうでしょうかね?」「えっ、何です?それは」「ええ、ちょっと、思い付いただけなのですが」亜真野はそう、前置きすると、恐るべき計画を語り始めた。 それは一つの実験だった。研究所とは、縁もゆかりも無い人間を、目的を知らせずに募集して、美保関へと送り込む。そして、彼等を何等かの方法で、コントロールして、島根に居るであろう怨霊を刺激する。そうすれば、何等かの反応が現れるだろう。そのデーターを遠隔操作で、収集するのである。これならば、モルモットが怨霊に襲撃されても、研究スタッフは安全なのである。 「どうです?名案でしょう?」亜真野は冗談めかして、そう、言った。だが、内心はどうやら、本気らしい。中臣は思わず、ぞっと、した。霊能者すら、危険な場所に、ずぶの素人を送り込むなど、正気の沙汰とも、思われない。悲惨な結果と成る事は、日を見るよりも、明らかである。 だが、ひょっとして、それが亜真野の狙いなのかも知れ無い。怨霊に捕らわれた人間が果たして、どの様に変わって行くのか?この研究では、実は、その解明も、重要だった。亜真野はその状況を意図的に作ろう、と考えたのに違いない。中臣は余りの事に、絶句した。と、亜真野が言った。「確かに、人道的に、問題がない、とは言い切れません、ですが、他に、方法が見当たらない、まあ、一つの案、ではありますがね?」「し、しかし、犠牲者を出すのは」「でも、霊現象と決まった訳でも、無いんでしょう?犠牲者が出るとは限りません、第一、放置できぬ、と言ったのは、中臣さん、あなたなんですよ?」 何と、恐ろしい男であろうか!中臣は内心、身震いしていた。必要ならば、我が子であろうと、差し出すだろう。憎しみの様な感情が心の奥底から、浸み出していた。だが、亜真野の言い分も、分からぬでも無い。自分の予測が正しいのなら、あの怨霊はより多くの犠牲者を産み出すだろう。その為にも、早急に事態を把握して、対応策を練らねば為らない。だが、亜真野の策など、受け入れ兼ねる。「まあ、検討はしてみますがね?」中臣は呆れた風に、言い残すと、そそくさと、部屋を後にした。 さて、それから、一週間が経過した。まだ、代替策は出来て居ない。安全と迅速、そして、亜真野に課せられた守秘の義務など、余りにも、制約が多過ぎる。中臣はふと、気が付くと、亜真野の案に捕らわれていた。人間としては、ともかく、学者としては、興味のある提案ではあったのである。「最小限度の犠牲者で、解決の方策が見付かるのなら・・いや、そんな事は許されない!くっそ、亜真野の奴!」中臣は揺れる心を押し殺して、他の方法を模索した。そして、また、一週間が経過した。亜真野からは、どう成ったのか、と再三に渡る催促である。このまま、時が経過をすれば、亜真野の事だ。手を引いて仕舞う事も考えられる。亜真野の案が脳裏を掠めて、そして、中臣を突き上げた。 「だが、そんな恐ろしい事が出来るだろうか?どうすりゃあ、良いんだ!」中臣は自分の良心と魔性の狭間で、身動き出来ずに、苦悩していた。その間も、時間は矢の様に、経過して行く。学者としての本能だろうか?それとも、亜真野の意志に操られでもしたのだろうか?中臣はついに、悪魔の計画に乗ったのだった。 中臣は亜真野の了解を取り付けると、代理人を使って、潰れ掛かった旅行社、サンツーリストに資金を入れた。事実上、其処のオーナーと成ったのである。そして、「オカルト・ツアー・山陰の旅」を企画させた。オカルト好きの人間を募って、モルモットに仕立てるのが目的である。悪魔の計画は動き始めた。始めてみると、オカルトツアーは予想外の反響である。応募者は定員数を遙かに、越えた。そこで、中臣はアンケートの形式を取り、心理テストなどを行って、その選別に取り組んだ。 万が一、このツアーに、霊能者などが紛れたならば、実験に予期せぬ影響が出るかも知れない。また、ツアー本来の目的が覚られない、とも限らぬのである。彼等の除外は当然であった。そして、参加者の選別をし終えると、中臣は実験の為に、「オカルト体験のノウハウ」と、題した一冊のマニュアルを配布した。それは参加者毎に、少しずつ、違って居り、彼等の為すべき行動の一切が事細かに記述されている。更に、ツアーのメンバーとサンツーリストの社員達には、催眠による暗示も掛けられて居た。霊体験をする毎に、所員の詰める連絡事務所に逐次、報告をさせねば為らない。 催眠の目的はその指令と、為すべき行動の徹底であり、念を入れて、実行された。また、事務所への連絡はファクシミリによるものと、決められた。万が一、彼等が怨霊に捕らえられて、操られた時、音声による接触は危険に思える。それは彼等を通して、事務所の位置が探査されて、怨霊を招き寄ない、とも限らないからである。その為に、連絡事務所は霊現象の未だ、及ばぬ浜松市街地に設置された。この神経質とも思われる用心深さは、その全てが、亜真野の差し金である。過剰とも思われるプロテクトが幾重にも掛けられて、初めて、実験は動き始めた。それにしても、哀れなのは誘いに乗って、モルモットにされた参加者だった。隠された陰謀が在るなどとは想像すらも、出来ぬだろう。彼らはまだ、見ぬ霊を想像しながら、喜々として、死出の旅路へと向かうのだった。 (ですから、良い子の皆さんは、怪しい話には、乗らない方が良いでしょう、怖いですから) |
|||||||


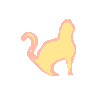
| |||||||
| Cotosiro Home | |||||||