|
可能世界・陰の神話 第五章第一話 |
悪しき予感 This was revised in March 18, 2012. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
海淵辰夫は駿河湾で、漁師を生業とする老人である。このところ、ひとつ、気掛かりな事があって、ともすると、気分は沈みがちであった。だが、日々、為すべき仕事はせねば為らない。老人は漁から、戻ると、仲間と連れだって、漁協での定期の会合に出席した。心配事の所為で、余り、出たくはなかったけれども、これも大事な付き合いである。だが、会合の後、慣例と成っている気心の知れた仲間との飲み会は辞退した。彼は会合を終えると、急いで、迎える者のない自宅に戻った。そして、手早く、着替えを済ませると、炉端に座って、刻みタバコに、火を付けた。だが、どうにも、気分が落ち着かない。彼はしばらくの間、仏壇などをチラチラ、見ながら、「どうしようかな?」と、思案した。何かの迷いがあるらしい。 だが、タバコを吸い終えて、仏壇を振り返ると、「やっぱり、行こう」と、呟いて、重い腰を持ち上げた。そして、隣の台所に、足を運ぶと、食器棚の一番、上から、ブリキの菓子箱を取り出した。其処には、数種類の駄菓子が詰められている。彼はその蓋を開けると、そこから、数個の駄菓子を取り出した。そして、それを和紙に包んで、ビニール袋に収めると、左手に、その持ち手の辺りを巻き付けて、何やら、せわしげに、家を出た。 見たところ、急いでいる、と言う風情だが、何故か、バス停には、向かわない。彼はバス停とは、逆方向に、国道を少し、歩くと、そこから、分岐する裏山への小道を歩き始めた。木々を透かして、遠くを見ると、小高い崖が連なっている。老人の位置からは、見えないけれども、その崖の中腹には、稲荷の祠が鎮座していた。今、行く獣道の様な細道は、其処への参道と成っている。彼は祠を目指して、歩き続けた。 実を言えば、老人の心配と言うのは、彼の孫、康夫の事であった。特に、今日は朝から、無性に、康夫の事が気に成って、妙に、気分が落ち着か無い。「お稲荷様にでも、相談しようか?」彼はふと、そう思い付いて、祠へと足を向けたのだった。だが、お参りをする事、自体が何故か、不安にも思われる。家で、ぐずぐずと、思案したのは、その様な心理の為だった。 二週間ほど前、珍しく、康夫からの電話があった。社員教育の一環として、催眠術を施されている、と言う。新しいオーナーの方針で、心理面の強化を図る、と言う事であったが、康夫はそれを嫌がっていた。「胡散臭くて、気味が悪い、止めたいよ」などと、不満げである。確かに、康夫の会社は極、普通の旅行会社であるから、社員教育に催眠術、などと言うのは、少し、奇妙に思われる。「何か、良からぬ仕事でも、始めたか?」康夫から、話を聞いた時、フッと、その様な心配も、脳裏を過ぎったのである。 だが、康夫に、業務内容を聞くと、オーナーが変わっただけで、他には、変わった事は何も無い、と言う。オーナーが一度も、顔を出さない、というのは、気に成ったものの、「まともな仕事をしてるなら、心配ないよな?」と、老人はひとまず、安堵したのである。テレビなどを見ると、最近は、寺などで、坐禅をさせる会社もあるらしい。あまり、感心はしないが、軍隊式の訓練を取り入れる会社もある、と聞く。なら、催眠術だって、そう、不思議では無い、のかも知れない。康夫はぐずぐずと、愚痴をこぼしたけれども、その時、老人は、「そんなもん、気の持ち様で、どうにでも成るだよ」と、康夫を諭したのである。 康夫は両親に早く、死なれて、老人の手、一つで、育てられた。その所為か、康夫には、昔から、わがままな所が目に付いた。今にして思うと、甘やかしが過ぎたのかも知れない。そして、今、そろそろ、会社や仕事にも、ようやく、慣れて、世間を知ったつもりに成る時期でもある。会社への不満を口にするのも、一度は通る道なのかも知れない。だが、わがままの虫と、こらえ性のなさは心配である。「困ったものだ、まあ、康夫も、その内、慣れるだろう?」老人は当初、そう、考えていた。 だが、日が経つに連れて、妙な胸騒ぎを感じ始める。具体的にどうこう、と言うのではないのだけれども、何故か、康夫の事が気に掛かる。「何故だろう?」あるいは、年の所為で、心配性に成った、と言う事だろうか?「とにかく、上手く、遣ってくれれば、それで、良い・・」老人は妙な胸騒ぎを感じる度に、そんな具合に、呟いていた。だが、あれ以来、康夫からは、何の連絡も、して来ない。「電話しようか?」とも、思うけれども、煩がられるので、掛け難いのである。「電話くらい、くれりゃ良いのに」老人はぶつぶつと、一人、呟きながら、緩い坂道を登って行った。 老人は雑木林を抜け切ると、そこで、一息、息を入れて、切り立った崖を仰ぎ見た。其処からは、急な勾配の石段が葛折と成って、上へと続く。祠はその途切れる辺り、海の臨める高台に鎮座していた。顔を上げると、西に傾いた太陽が切り立った崖の岩肌を鮮やかな朱の色に染めている。老人は眩しそうに、目を細めながら、一歩、一歩、と、登って行った。ふと見ると、今し方、通ったばかりの雑木林に、崖の影がくねくねと、たなびく様に伸びている。日の傾きを知らしめる黄昏色の風景である。ふっと、右手に、目を振ると、其処には、真っ青な海が広がっている。朱色に染まった波頭が逆巻く様に水面を走って、次々と、岩浜に打ち寄せると、一瞬の内に、飛沫と成って、空を舞う様に、辺りに、散った。 老人はふと、足を止めると、そのパノラマをジッと、眺めた。息も、少し、切れている。彼は足下の石段に腰を据えると、刻み煙草と真鍮のパイプを腰の脇から、取り出した。そして、目を細めながら、一服、付けた。紫煙がゆらゆらと、立ち昇る。老人の目が紫煙を追った。夕凪なので、紫煙は少し、立ち上ったところで、拡散しながら、漂っている。そして、次第に薄れると、夕焼けの空へと、溶け込んだ。時がゆっくりと過ぎて行く、心の和むひとときである。老人は何時しか、その緩やかな時間の流れを楽しんでいた。だが、紫煙が消えると、康夫の事が想い出される。「おお、こうしては居られない、日の暮れる前に、済ませ無くては」老人はゆっくりと、腰を上げると、再び、狭い石段を歩み始めた。 少し、登ると、其処は断崖の中腹である。傾斜は幾分、なだらかと成って、石段は雑木の林へと、入って行った。奥の方には、粗末な鳥居が連なって居る。雑木と共に、アーチを作って、木漏れ日が石段に所々、影を落とした。老人はその木漏れ日の揺らめきを楽しみながら、ゆっくりと、石段を登って行った。祠の屋根が僅かに見える。木々を縫って、射し込む光が夕焼け色に祠を照らした。「お稲荷様、良いお日和です」老人の顔に、笑みがこぼれた。老人は祠の側に歩み寄ると、菓子を供えた。と、康夫の顔が脳裏を過ぎる。老人は目を閉じると、両手を併せて、一つ、パンと、柏手を打った。だが、ふっと、稲荷に目を遣ると、稲荷の顔が何故か、厳しい。「気の所為だろうか?」老人は怪訝な面もちで、稲荷の顔を覗き見た。 と、その時、一陣の風がやにわに、吹いて、雑木林がざわざわと、呻く様に、ざわめいた。何かを語っている様な、不思議な響きのざわめきである。老人はそのただならぬ気配に、驚いて、ふっと、灌木の梢に目をやった。と、景色がぐるぐると、回り始める。足がふらついて、力が入らぬ。老人は堪らず、地面にしゃがみ込んだ。気が付くと、辺りは闇に包まれている。そして、何とした事か?その暗闇のただ中に、康夫の顔が浮かび上がった。顔の色は青白く、頬は異様に痩せている。何か、物を言いたげに、老人をジッと、凝視していた。 だが、それは本当に、康夫だろうか?余りにも、無残な変貌である。老人は目を見開いて、凝視した。と、やにわに、光が辺りに満ちて、康夫の顔が掻き消えた。夕日に照らされて、朱を帯びた、何時もの祠が在るだけである。「こ、これは!?」老人は唖然として、稲荷の祠をジッと、見つめた。「だが、あれは一体、何だったのか?気の迷いなのか?夢なのか?」老人はその時、絞り出す様な悲痛な声を聞いた様にも、感じたのである。「やはり、何か、良からぬ事でも、在ったのだろうか?」言い知れぬ不安が心を覆った。 老人は家に戻ると、すぐに、康夫の会社に電話を入れた。だが、呼び出し音が虚しく、響く。「おっかしいな、何時もなら、まだ、仕事中の筈だが、家かな?けど、誰もいないなんて、普通じゃない」老人は少し、首を捻った。だが、考えていても、埒はあかない。老人はすぐさま、受話器を持ち直すと、康夫のアパートへと、電話を入れた。だが、康夫は出ない。「まだ、戻っては居ないんだ」老人は一旦、電話を切ると、三十分ほど、我慢して、再び、電話を掛けてみた。だが、応答は無い。「そうか、会社ぐるみで出掛けてるんだ、社員旅行かな?いや、きっと、大きな仕事で、出払ってるんだ、連絡くらい、くれりゃあ良いのに」老人は都合の良い想像へと、逃げ込んで、心の不安を払おうとした。だが、内心は、納得などは、出来てはいない。老人は落ち着かぬまま、寝床に潜った。 雨雲が垂れ込める薄暗い河原を老人は一人、彷徨っていた。「けど、此処は何処だ?」老人は怪訝な面持ちで、辺りの様子を窺った。と、顔を失った亡霊達が闇から、フッと、現れて、空をふらふらと漂うと、再び、闇へと消えて行く。「もしや、その中の誰かが、康夫では無いのか!」老人の目はその消え行く姿を必死で、追った。だが、視界は利かない。辺りに漂う陰鬱な靄がしばしば、濃密に広がって、光を遮るからだった。ふと、気が付くと、川の流れる音がする。そして、小石の転がる音がした。「そうか、此処は、賽の河原だ!もしや、さっき、転がったのは康夫の積んだ石ではないのか?」老人は咄嗟に、辺りを見回すと、悲痛な声で、康夫を呼んだ。だが、返事など、無い。顔の無い亡霊達が何処からとも無く、現れて、老人の声を擦り抜けると、闇へと、消え入るだけである。「駄目だ、もう、康夫は居ないんだ」老人はそう、納得すると、元、来た道を歩み始めた。 と、背後から、弱々しい声が呼び掛ける。「康夫か?」老人は半信半疑で、振り向いた。と、陰鬱な靄の直中に、ひとつの顔が浮き出している。頬はげっそりと削げ落ちて、顔色は死人の様に、青白い。だが、老人には、康夫である、と、すぐに分かった。悲しそうで、不安げ眼が何か、物を言いたげである。「康夫、何が在ったんだ?何が、そんなに悲しいんだ?」老人は慰める様に、そう、言った。すると、康夫が、か細く、言った。「元に、戻して・・元に、戻して」 だが、元に戻して、とは、どういう意味か?「えっ、何を戻すんだ?どうすれば、良いんだ?」老人は必死に成って、呼び掛けた。だが、返事など、無い。老人が思わず、康夫の方に踏み出すと、闇に浮かんだ康夫の顔がまるで、何かに引かれる様に、スーッと、老人から、退いた。河原の上をふらふらと浮遊して、川を横切ると、対岸まで、行って、闇へと、消えた。凍てつく様な寂しさが老人の胸を締め付ける。「やすおーっ!」老人は悲痛な声で、呼び掛けた。しかし、その声は虚空に響いて、むなしく、帰るだけである。老人は何も無い闇に取り残された。 老人は自分の声で、目が覚めた。枕元の時計を見ると、既に、真夜中の二時である。老人は意識するとも無く、上半身を起こすと、闇を見つめて、考え込んだ。最前に見た不気味な夢が不安な想いを抱かせる。「正夢だろうか?いや、ただの夢に決まってる、けど、元に戻して、とは、何だろう?」考えるほどに心が揺れる。「もう一度、電話しようか?」とも、思うけれども、何故か、怖くて、掛けられない。悪い事など、想いたく無い。老人は布団に潜って、鬱々とした。そして、知らぬ間に、寝入って仕舞った。 老人は翌朝、電話の音で、目が覚めた。昨夜の夢が、そして、祠での幻影が、一挙に脳裏を駆け巡る。「康夫からなのに違い無い!」老人は咄嗟に、布団を払い除けると、急いで、受話器を取り上げた。だが、それは康夫では無く、康夫をサンツーリストに世話してくれた、魚問屋の境田である。「あ、海淵さん、実は、大変な事に成ってるんです」声が妙に、重苦しい。「あ、あの、康夫の事かね?」「はい、けど、落ち着いて、聞いて下さいよ?」境田はそう、前置きすると、小さな声で、話し始めた。康夫の行方が分からぬのだ、と言う。しかも、会社ぐるみ、社員や社長の行方まで、不明と成って居るらしい。既に、家族間では、連絡も取られて、警察への届け出も済んでいる、と言う。「どうして、早く、知らせてくれ無かったんだね!」老人は思わず、声を荒げた。 |
|||||||
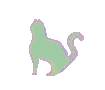


| |||||||
| Cotosiro Home | |||||||