|
可能世界・陰の神話 第六章第一話 |
まともな被験者 This was revised in December 23, 2009. |
野口博正の提供による あるひとつの可能世界 |
|||||
|
「なるほど、あなたのご心配も、まんざら杞憂でも無いようですな」亜真野は中臣のもたらした報告書に目を通し終えると、無表情にそう述べて、ファイルを畳んで、デスクに置いた。それは美保関での実験の分析結果と、中臣の現状認識とを取り纏めて、報告書としたものである。中臣が言った。「ええ、思った以上に事態は深刻です、早く対策を考えなければ、いけないのですが・・」 「うん、で、何か、妙案でも?」「あ、いえ、あれだけの霊力です、まずは、弱点を研究しなくては・・」「うん、そうでしょうな、ですが、どうなんでしょう、それ、中臣さんの研究室だけで、何とか、成らんものでしょうか?いえ、大所帯に成ると、何かと・・マスコミにでも、嗅ぎ付けられますとね、厄介ですから」 亜真野の秘密主義は異常とも思える程、徹底していた。何故、こうまでするのか?中臣には、亜真野が研究スタッフすら、信用していない様に見えるのである。いや、それはまず、間違いなかった。「亜真野はこの問題について、重大な何事かを知っていて、それを隠しているのではないのか?」中臣は最近、亜真野の言動を見るに付け、その様な想像に、捕らわれるのである。時には、亜真野の秘密主義の背後に、何か、陰謀めいたものが在るようにすら、感じてしまう。だが、根拠などがある訳でもないので、妙だ、とは思いながらも、深く考える事はしなかった。 今の中臣には、問題の霊象を解明して、解決をしなければ為らない重要な責務がある。亜真野の思惑を詮索するほどの労力も、心の余裕も無かったのである。「まあ、あの秘密主義も、きっと亜真野の性癖なんだろう」彼はその様に自分を納得させて、気にせぬ事に決めていた。だが、今、亜真野は中臣の研究に、更なる足枷をはめようとしている。もし、それを受け入れるなら、研究は益々、困難を極めるだろう。彼の悪癖の皺寄せを自分だけが被るのは、どう考えても間尺に合わない。研究が遅れたなら、非難されるのは自分に決まっているのである。中臣は怒りを堪えて、静かに言った。「はい、仰る事は分かります、ですが、人も時間も、足り無いのが、実情です、研究所の総力を挙げてましても、相当に難しい状況ですので」中臣は、言うべき事を素直に言った。 だが、何故だろう?亜真野の顔が一瞬、歪んだ。意に染まぬ返事であったので、きっと、苦虫でも、噛み潰したのだ。中臣は心の中で、ニヤリと笑った。亜真野が言った。「まあ、仕方ありませんかな?よろしく頼みますよ?」それは苛立たしさを抑える様な、妙に低い声である。そして、どういう意味かは知らないけれども、机上の報告書を手に取ると、再び、ポン、と机上に戻した。妙に気に成る仕草ではある。中臣は一瞬、亜真野がまた、別の難題を押し付けて来るのではないのか、と疑った。 だが、亜真野は何も言わない。二人の間に、妙な空気が漂った。いずれにしても、早めに退室をした方が良さそうである。中臣は手短に、研究所内の連携について、他の教授達と打ち合わせをする旨を亜真野に告げると、「それでは、失礼いたします」と、踵を返した。また、後ろから、何かを言われるのではないのか、と、心配であったが、それもない。中臣はひとまず、安堵して、亜真野の部屋を後にした。 中臣が建て屋の外に出ると、身を切るような風が吹き始めている。「雪でも降るのか?天気予報は確か、小雨、と言っていたが・・」彼は忌々しそうに薄暗い天を一瞥すると、別棟と成っている自分の研究所に、前屈みと成って、足を急がせた。もうじき、春だが、自分にとって、果たして、どの様な季節と成るのだろうか?ふっと、その様な想いが中臣を捕らえた。だが、仕事や心の、重い荷物を背負った中臣には、想像する事すら、厭わしい。彼はその想いを胸の奥深くに、しまい込んだ。 それから、一週間ほどが過ぎ去った。中臣は研究所内の連携について詰めを行うと、その報告の為に、再び、学長室へと足を運んだ。だが、気分は重い。「また、何か、難題をふっ掛けられるのでは無いのか?」と、重苦しい不安も頭を過ぎる。これはもう、条件反射、と言っても良かった。「何故、ああも、人の気持ちを逆なでするのか?」今では、顔を見ただけで、気分が自然と滅入るのである。中臣は憂鬱な気分を引きずりながら、学長室のドアをノックした。 と、亜真野は例の満面の作り笑いで、椅子を勧める。中臣は言われた通りに椅子に座ると、亜真野の出方を窺いながら、決定事項を語り始めた。だが、亜真野の様子は何時もと違う。中臣の報告に、「なるほど」と言って、素直な様子で頷くだけで、例の悪癖が出ないのである。虫の居所が良いからだろうか?「いいや、その内、途方も無い要求をふっかけて来るのに違いない?」余りの亜真野の変貌ぶりに、疑心暗鬼が逆に募った。中臣は早々に話を切り上げて、退室をしようと考えていた。 だが、話を終えて、退室をしようと、踵を返すと、思い出した様に亜真野が言った。「あ、中臣さん、こないだの報告書ですが、ちょっと、気に成りましてね、あ、お時間は良いですか?」中臣は内心、「ああ、やっぱり、来たか?」と、呟いた。無論、お時間、云々については、単なる社交辞令なのに決まっている。もし、中臣がうっかりと、「ハイ、忙しいので」などと言ったなら、後で、どんな仕返しが在るか分からないのである。「はあ、何でしょう、少しだけでしたら」中臣はそんな具合に探りを入れた。亜真野が言った。「確か、あの報告書には、怨霊の力が日増しに強く成っている、と、そんな具合に書かれて居ました、そうですよね?」 だが、中臣には、亜真野の意図が測り切れ無い。彼は、「あ、ハイ、そうですが?」と、戸惑い気味に、返事した。亜真野が言った。「ですが、普通では、ちょっと、考え難い、いえ、疑う訳ではありませんがね?」亜真野の意図は分からぬけれども、要求などでは無さそうである。おそらく、ちょっと確認をしたいのだ。中臣は少し安堵すると、言った。「ええ、これは私の想像ですが、力を注ぐ何者かが、居るように感じています、人間なのか、怨霊なのか、それは、はっきりとは分かりませんが、一人や二人では無いでしょう」 だが、亜真野を見ると、彼の態度は腑に落ちない。人に話をさせながら、中臣などには、目もくれない。さきほど外した金縁眼鏡を弄ぶ様に拭いていた。「ははあ、また、例の奴だな?」中臣は内心、呟いた。そして、妙に安堵した。出そうで出ないお化けよりは、出て貰った方がましである。中臣の心は知らぬ間に、そう考えるほど追い込まれていた。 これまでも、このような事は度々、あった。長く付き合った者ならば、誰もが遭遇をする悪癖である。人を焦らして、悦に入る余りにも幼稚な悪戯だった。「幼児期の異常な体験が、コンプレックスでも産んだのだろう、それがある部分、幼児のままに留まらせている、ひょっとして、彼は便秘症では無いのだろうか?」中臣は半ば意図的にこじ付けて、その様な想像もするのであった。 だが、コンプレックスの方は間違いが無い。それも、相当に根の深い心の癒されぬ傷であろう。亜真野の人格の形成に直接、関わる何かであった。心理学者の性癖だろうか?それとも、彼の亜真野への、積もりに積もった憤懣だろうか?「こう成ったら、必ず、これを突き止めて、化けの皮を剥いでやる!」中臣は亜真野の心の探求に異様なファイトを燃やすのだった。 だが、その間も、亜真野は眼鏡を弄んでいる。「煙草、良いでしょうか?」中臣はそう問い掛けた。だが、亜真野は煙草を嗜まない。駄目なのは初めから承知していた。すると、予想通り、亜真野は、「エッ?ああ、灰皿が無いのでね、あなたも、煙草など止めたまえ」と、言う。「なるほど?悪い奴に限って、こういうところで、いい人ぶるんだ」中臣は心の内で、呟いた。だが、その遣り取りが引き金と成ったらしく、亜真野は続けて、喋り始めた。「ところで、中臣さん、言代主の事は言って無いでしょうね?」 またしても、機密保持の確認らしい。中臣は一瞬、辟易とした。だが、相手が亜真野では、しようがない。「ええ、教授会で、兵隊には、伏せる事にして在ります、ですが、研究の足枷にも成りますのでね、早い内に知らせませんと」中臣は即座に、そう返事した。だが、亜真野は言う。「いや、もう少し待った方が良いでしょう、シュミレーションへの対応、とか、何とか、そういう事で通して下さい、これは大事な事なので、よろしくお願いしますよ?」手枷足枷を填めて置いて、仕事は極力、急げ、と言う。「何、考えてんだ?こいつは」中臣はやにわに怒りを感じた。 動揺を避けたい、と言うのが、亜真野の何時もの口癖なのだが、此処まで来ると、それも怪しい。「きっと、何かの裏がある、やはり、こいつも、調べねば」中臣はそう考え始めた。しかし、それは今では無い。最優先で為すべきは怨霊の研究に必要な最良の環境の整備であった。その為には、亜真野のご機嫌を取らねばならない。腹立たしいが、此処は我慢のしどころであった。 だが、今日はその辺の決心が少し怪しい。亜真野の態度が癇に障って、我慢がならない。押さえようとするほどに、積もりに積もった憤懣がしきりと中臣を突き上げた。無論、その様な憤懣をストレートに表す事など、出来はしない。「なら、何か、要求を突き付けよう」中臣は咄嗟に、そう考えると、日頃、暖めていた提案を今、する事に決めたのだった。 今度の研究では、早急な成果が要求される。だが、今の研究所では人員、資金、共に不安が在った。先日、亜真野は中臣の研究室だけで遣れるかなどと、途方も無い話を真顔で言ったが、とても本気とは思え無い。中臣は今後の為にも、防衛庁との協力は是非とも必要である、と考えていた。「どうでしょう、その橋渡しを、して頂きたいのですが」中臣は抑えた声で、そう述べた。亜真野の性癖を考えると、即答を期待する事は出来ないけれども、彼の頭の片隅にインプットをする事は重要である。そうして置けば、選択肢のひとつには入るだろう。そして、それが必要ならば、亜真野の事だ、彼は自分の発想として、取り入れるのに違い無かった。極めて爵で、腹立たしいけれども、全ては研究の為である。中臣は口角に泡を飛ばして、その必要性を力説した。案の定、亜真野の答えは、「その時では無い」と、にべも無い。拒否の理由は分からぬけれども、計算通りの返答ではある。中臣は一物も二物も抱え込んで、亜真野の部屋を立ち去った。 一方の亜真野は中臣の退室を確認すると、デスクの上に両ひじを突いて、顎の所に拳を当てた。何か、考え事をしているらしい。彼はやがて、ブツブツと、呟き始めた。もし、誰かがそれを聞いたなら、何者かと会話をしている様に聞こえるだろう。これは彼が考えに行き詰った時に、しばしば、現れる習慣だった。だが、どうやら、結論には至らぬらしい。彼は諦めた様に、背もたれへと身体を預けた。そして、腕を組むと、再び、顎に拳を当てて、考え込んだ。 最前の中臣の提案も、問題だが、それ以上に、中臣の唐突に要求を持ち出す姿勢が癇に障った。亜真野は其処に反抗的な意思を感じたのである。「うーん、全く、厄介な奴だ、いつから、あんな風に成ったんだ?結構、難物かも知れんな」亜真野は呻く様に呟いた。実は、亜真野も、防衛庁との協力は考えていた。だが、今では無い。それはMICが進んで、主要組織のコントロールが容易に成ってからの話であった。それをあの中臣は、今、すぐにでも、協力したい、と言う。「自分の目論見を知っていて、引っ掻き回すつもりでは無いのか?」中臣の最前の提案はそんな疑念を抱かせるほど、悪しきタイミングで行われていた。 防衛庁の霊象に対する認識は極めて、浅いものである。その様な物は錯覚か、如何様、としか思って居ない。そんな所へ話をしても、埒が開くとは思え無かった。無論、機密の保持など、望むべくも無いだろう。マスコミなどに嗅ぎ付けられて、こき下ろされるのに違い無かった。そう成れば、研究所の存立にも関わって来る。そして、言代主の動きも心配だった。世間が騒げば、怨霊の耳にも当然、入る。自らの敵が何処に在るのか、彼は即座に知るだろう。魔の手を伸ばして来る事は百パーセント、間違い無かった。人の事はいざ知らず、MICを危険には晒せない。「中臣の奴、監視の要、在りだな?」亜真野の眼がギラリ、と光った。 さて、それから二ヶ月が経過した。だが、あれ以来、亜真野は中臣とは会っては居ない。意思の疎通は書類や電話、あるいは壱岐を通じての間接的な遣り取りだった。話に聞くと、中臣以下のスタッフは休暇も殆ど返上して、家に帰る事も希なのだ、と言う。「暇が在ると、人間、ろくな事を考えない、忙しいのは良い事だ!」と、亜真野はえらく機嫌が良かった。中臣は亜真野の指示には忠実で、言代主の事は漏らして居ない。そして、スタッフ達の極度の疲労も亜真野に取っては都合が良かった。彼等の洗脳が遣り易く、事実、その効果も現れている。言代主の事を除いては、全てが順調に進行していた。 だが、そんなある日、突然、中臣が現れた。無精髭をまばらに生やして、頬もげっそりと削げ落ちている。相当に疲れが在るらしく、落ち窪んだ眼が座って見えた。その中臣が顔を合わせるなり、亜真野に迫った。「亜真野さん、もう限界です!人が全く足りません、スタッフの大幅な補充を認めて下さい!アルバイトでも結構です!この侭では、みんな、病気に成って仕舞います」何時に無く、凄みの利いた要求に亜真野は一瞬、たじろいだ。亜真野は中臣が自分の裁量で、人員を補充していた事は知っていた。だが、これ以上の増員などは認め難いし、アルバイトなどはもっての他だ。何時もの亜真野なら、すぐに突っぱねる筈だった。 だが、今の中臣を前にして、いきなりの拒否はさすがにし兼ねる。反発を食い、粘られる事も考えられた。亜真野は言った。「ええ、心配してはおったのですが、そんなに大変だったとは!けど、今日、明日、という訳にも行きません、もう少し頑張っては頂けませんか?」だが、中臣は返事もせずに突っ立っている。どうやら、疑って居るのらしい。亜真野は中臣を座らせて、その現状を説明させた。面倒ではあるが、致し方ない。 亜真野は時折、相槌を打ちながら、「もう少しですから」と、労った。中臣は終始、不満げだったが、その対応でも利いたのだろうか?「お願いしますよ!」と、言い残すと、あわただしい様子で立ち去った。それにしても、中臣の行動は癇に障る。どういう訳かは知らないけれども、亜真野が嫌がる提案を是非、遣りたい、と言って来て、何時もしつこく食い下がる。一度や二度の話では無い。所長に推したのは亜真野だったが、中臣の存在そのものが疎ましい物とも成りつつあった。その都度、要らぬ気を使って、宥め賺して遣らねば為らない。「ああ、嫌だ、嫌だ!」亜真野は思わず、呟いた。だが、今や、中臣の才能は亜真野に取って、欠かせぬ武器とも成っている。あの怨霊を滅ぼして、MICが軌道に乗るまでは、我慢をするしか、し様が無かった。 亜真野は脇机の引き出しから、一冊のファイルを取り出した。美保関での実験に関する報告書である。彼はおざなりな様子で、ページを捲った。実を言うと、彼には、漠然とした不安が在った。実験データーの分析に、何となく、見落としが在る様に感じるのである。彼はその都度、ファイルを取って、眺める様に成っていた。既に、その大方は暗記をしている。だが、問題がある個所などは見つからなかった。「考え過ぎかな?」亜真野はファイルを弄ぶと、机の上にポイッ、と放った。 だが、何故だろう?やおら、脳裏に、疑問が走る。それは今までの漠然とした感覚とは少し違った。亜真野は慌てて、ファイルを取ると、パラパラと、ページを捲って行った。其処には、青く記された、「異常なし」の文字が散見される。個人別情報の症状、及び、死亡原因の欄である。それがモルモットによっては、「異常なし」と、記されて居た。少数ではあるが、死にもせず、その精神もまともな侭で、無事、帰還したモルモットも居たのである。 「これだったのか!」亜真野は唸る様に呟いた。無論、亜真野はその記載の事は知っていた。だが、迂闊な事に亜真野は、いや、あの中臣までもが、これらのモルモットを分析の対象から外していたのである。モルモット達には、言代主を刺激するよう、深い暗示が掛けられていた。ならば、彼等が全くの無傷と言うのは、極めて奇妙な事である。あの怨霊が黙って、見逃す筈が無い。果たして、彼等は本当にまともであるのか?ただ、まともに見えるだけなのか?いずれにしても、その背後には、知られざる理由が存在している。亜真野等の見落としは重大だった。 |
|||||||

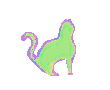
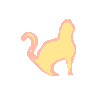
| |||||||
| Cotosiro | |||||||