|
改訂版 認識対象の正体 間主観、と言う概念は必要なのか?Ⅱ August 26, 2010. 野口博正 This was revised in October 2, 2011. リンク先を変更しました。February 4, 2012. |
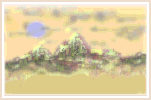
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
私は、「間主観という概念は必要なのか?」において、間主観という概念を導き出す思考 過程に問題がある事を指摘した。だが、何故、この問題を持ち出したのか、についての説明が欠落しており、言い足りない事もあったので、partⅡを書く事にした。 1.考察の動機 全ての思考には、その思考のよって立つべき大前提が必ず、ある。そして、その前提が「偽」である場合、その前提を持ち出した後の思考過程に全く、 誤謬がないとしても、その思考全体が「偽」と成る事は言うまでもない。思考の前提と成る概念、及び、世界観はその意味で、非常に重要である。 無論、これは非常に単純な真理であるから、あえて言う必要もないのであるが、複雑な思考に於いて、しばしば、この事が忘れられる様に思われるので、 念の為に言っておく。 紀元2世紀、アレクサンドリアの学者、トレミーは天動説を唱えた。しかし、今は多くの人間が信じていない。おそらく、トレミーには、自らの都合、 あるいは、信念、あるいは、当時の社会状況などの為に、その様な説を主張する必要があった、と言う事に違いない。つまり、彼の思索の前提は既に、 結論であるべき天動説であった、様に思われる。従って、彼はその思考過程において、天動説に不利な問題については、ごまかしの方策を模索した。 天体の運行に関する複雑な数学的処理はその代表的な方策であった。 その結果、途轍もない誤謬が、精密を装った数学的処理などよって、真である、と結論されたのである。 中世、と言う時代が精神的な暗闇に閉ざされたのはその所為であった、と言うのは、言い過ぎだろうか?無論、中世に於いても、ギリシャ、ローマ時代の建築技術、 数学的な技術などは、ある程度、あるいは、部分的には、受け継がれていた。中には、進歩したものも、少なからず在った、と思う。 だが、知恵や若干の技術(特に、哲学的考察、自然科学的考察、数学など)については、退化した様に思われる。 少なくとも、天動説に於いて使われた数学的な技術を初めとする、さまざまなノウハウが哲学的な知恵の退化をもたらした、と言っても、決して、 過言ではないのかも知れない。 元来、その様な技術の根底には、あらゆる現象への真摯な思索、あらゆる認識についての整合性を求める心がある。また、 その様な技術の多くは哲学的思索や文化、そして、自然科学的な法則に基礎付けられる。しかし、人々がその様な原理、法則を生み出した精神的基盤を忘れると、 技術は、しばしば、その様な基盤から切り離されて、自己完結的に自らの態様を変えて行く。その事は概念を扱う技術、政治的な技術、などについても、当て嵌まる。 確かに、この状況を技術の発展、と言う観点のみで捕らえると、必ずしも、直ちに技術の退化をもたらす、とは言い得ない。 技術の進歩はその状況で、急速に進む事も、そう、希ではないからである。 だが、この様な社会的な状況は、知恵にとっての危機を招来させる可能性も併せ持つ。精神基盤を忘れたその様な技術が頑迷な信念を擁護する為に、 あるいは、ある特定の人間の利益の為に、無反省に使われる、と言う事も、そう希ではないのである。 私は最近の社会の情勢、特に教条主義的な活動が活発化する状況を見るにつけ、その様な退化が起こりつつあるのではないのか?、と言う危惧を抱いてしまう。 そして、憂鬱な気分に陥るのである。特に、間主観、と言う概念には、その様な危険を感じてしまう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
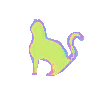
|
近年、ある種の人々はその種の哲学的な概念をさしたる吟味もせずに、自分の功名心、利益などの為に、使っている。その概念が誤謬を含まないのなら、 さしたる弊害はないのかも知れない。だが、誤謬を含む概念をいとも気安く使うのは問題である。特に、思考過程に持ち込むと、その結論は必ず、「偽」と成る。 暗黒の中世への逆戻り、と言う事も、決して、有り得ぬ話ではないのである。本当の事を言うと、さして、学識のない私がこのような事を語るのは心苦しい。 けれども、この様子では、天動説の様な間違いが、再び、世界を席巻しない、とも限らない。 十年ほど前、顕著に成ったアダム・スミスへの回帰志向も、あるいは、その兆候であるのかも知れない。 ふざけた事を言うな、とお叱りを受けるかも知れないが、私は至極、まじめである。確かに現在、科学技術の進歩は目を見張るばかりである。 だが、哲学は果たして、どうなのだろうか?単なる、言葉遊びに堕落しようとしている様にすら、感じ取られる。学識のない私ですら、そう感じるのであるから、 多分、その様な傾向はあるのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特に、間主観の概念が気安く使われる事に、我慢がならない。具体的に述べる事は差し控えるが、難解な概念を、思索とは無縁の動機で、気安く使い続けると、
それは時として、恐ろしい悪魔に変身する。そして、その悪魔が人をして、責任の所在の不明確な社会的暴挙へと誘うのである。必ず、そう成る、
とは言えないけれども、魔女狩りを初めとする、その様な危険は増している様に思われる。魔女狩りに関して言えば、中世に於いて、
その多くは根拠のない密告であったそうであるが、それは今、一部のメディアなどを通じて、既に、息を吹き返しつつある。おそらく、
それは人々がその様な魔女狩りに、乗りやすい心理状態に成りつつある、と言う事とも関係がある。その様な事で、前回は、少し過激な発言と成ってしまった。
2.前回の陳述の補足説明、及び、認識対象の正体 注:近代西洋哲学では、一般的に、私の言う認識主体は「subjectum」と、言う単語で表されており、「対象への認識を構成する自我」を意味するそうです。 現在、それは「主観」、あるいは、「主体」と、邦訳されております。従って、フッサールの言う「主観」も、その様な意味で、使われているものと思われます。 さて、ここからは、間主観という概念に、何故、誤謬がある、と考えるのか、について、補足的に説明したい。私は前回、 「認識主体が行う認識は第一義的には、主観的なものであり、私と言う認識主体は物理的にも、心理的にも、あるいは、他の立場に於いても、 他者とは違う位置に存在するので、その見る角度、及び、認識が他者と異なる事は当然である。従って、厳密に言えば、 私の主観的世界は他者との共有物には成り得ない」と、述べた。 しかし、この言明に対して、ある反論が予測される。それは、おそらく、「フッサールは何者かの主観的世界が他者との共有物である、などとは言っていない。 彼は自然的世界、文化的世界が多くの主観の共有物である、と言っているのである。従って、主観的世界が共有物になり得ない、と言う指摘は、 見当違いの反論である」と、言うものである。 しかしながら、フッサールが前提とした自然的世界、文化的世界とは、果たして、客観的な世界なのか?それとも、主観的な世界なのか?どちらにしても、 自然的世界、文化的世界を前提とするからには、フッサールは既に、それらの世界を認知している、と言う大前提がなければならない。認知していなければ、 其処に論が及ぶ事など、あり得ない。そして、認識と言うものは本来、主観的なものである事は確かである。ならば、フッサールが、「主観」、「間主観」、「 客観」という概念の関係を考えるうえで挙げた、自然的世界、文化的世界は、やはり、フッサールの主観的世界に他ならない。思考過程に於いて、 最初に提示されるのは、その様な主観的世界である、と言う事である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
その事はフッサール自身も認めている。彼が「主観」、「間主観」、「客観」の関係について、述べた時、最初に挙げたのは主観的認識であった。 フッサールの場合、この「最初」というのが、「因果関係なのか、論理的な順番なのか」は、はっきりとは分からないが、彼が、 「認識と言うものは元来、主観的なものである」と、考えた事は確かである。従って、フッサールが提示した自然的世界、文化的世界はやはり、 フッサール固有の主観的世界に他ならない。 そして、もし、フッサールが提示した世界が客観的世界であると、仮定すると、間主観の概念を持ち出すまでもなく、それは既に、 それぞれの主観(認識主体)の共有物なのである。そして、言うまでもなく、主観的認識というのは、 その主観的認識を持つ主観(認識主体)の存在を前提としなければ、存在し得ない。そして、万人に共通であるべき客観的世界、 自らの主観的認識を持つのが主観(認識主体)である。私としては、フッサールが問題の陳述に於いて、 「自然的世界と文化的世界が主観的世界なのか、客観的世界なのか」をはっきりさせなかった事に、疑問を感じる。其処に考えが及ばなかった、と言うよりは、 むしろ、上記の過程で、浮かび上がった論理矛盾を隠す為ではなかったのか?、とも思うのである。其処で、以下では、その様な論理的矛盾について、考える。 さて、フッサールの「自然的世界、文化的世界が多くの主観の共有物、云々」と言う言明は記号論理学的には、おそらく、正しい。だが、私に言わせると、 意味不明である。もし、正確に言うつもりなら、 「主観的な(もしくは、客観的な)世界としての自然的世界、主観的な(もしくは、客観的な)世界としての文化的世界は多くの主観(認識主体)の共有物である」と、 言わなければならない。主観的にしろ、客観的にしろ、認識主体がその様な認識を持つのであるから、そう表現するのが最も正しい。 |
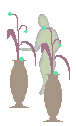
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
真理を追究しようとするなら、難解な表現ではなく、最も正しい表現を使うべきである。然もなくば、間違いを引き起こす。難解な表現、あるいは、概念を使う事で、
深い理解をせぬ侭に、分かった様な気分に陥る、と言う場合が大半なのである。その様な状態での考察が真理に到達出来る、とは思えない。
尤も、厳密に見れば、主観的な認識に共通のものなど、全くない、と断言出来るので、この場合、「主観的認識には似たものがある」と言うのが正しいのである。 また、それ以上の説明は不必要である。認識対象は現象として、認知されるが、その現象は既に、認識主体に応じて、異なっているのであるから、 このような言い方しかできないのである。だが、間主観の概念にこだわる人はおそらく、「主観的認識には、似たものがある」という説明には留まらず、 難解な概念、あるいは言い回しでもって、間主観の概念の妥当性を主張するのに違いない。 しかし、この場合、「似たものがある」というのが、ここでの思考の終着駅である。線路はその向こうには、敷かれていない。それにも拘わらず、 思考を推し進める、と言う行為はもはや、こじつけ、としか思えない。私には、トレーミーの数学的な辻褄合わせと同じように感じられる。 尤も、この種の思考はその大前提を除くと、部分的には、理路整然としている様に思われる。しかし、肝心なところで、「全てではないにしても」とか、 「おおよそ」とか、言う類の言葉が現れて、微妙な誤謬が混入されるのである。トレミーが天体の観測結果と数学的結論との微妙な違いを神のみ業とした様に、である。 おそらく、難解なのはその所為である。又、その所為かどうかは知らないけれども、私はまだ、正しい哲学というものを知りません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
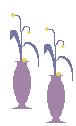
|
いずれにしても、認識はあくまでも、認識主体と認識対象との特有の関係によって、生起する。また、主観的認識にしろ、客観的認識にしろ、この関係から独立しては存在し得ない。 従って、単に「文化的、自然的世界は多くの主観の共有物である」とした先の言明は受け入れられない。どうしても、この事を表現したければ、やはり、 「主観的な(もしくは、客観的な)世界としての自然的世界、主観的な(もしくは、客観的な)世界としての文化的世界は多くの主観(認識主体)の共有物である」 と言うしかないのである。 しかし、その言明はさし当たり、「客観的世界を共有する」と言う意味合いに於いてのみ、「真」と成る、と言う事が出来る。その文脈に於いて、 間主観の概念が入り込む余地など、何処にもない。フッサールの意図は此処に於いて、破綻するのである。間主観的現象など、存在しない。 何度も、述べるが、客観的認識はそれそれの主観的認識が比較、検討される事で産まれるのであり、主観的認識が最初から共通点を持つ、と言う事は出来ないのである。 また、上記のプロセス以外に、認識の客観化への道は存在しない。 従って、「自然的世界、文化的世界が多くの主観の共有物、云々」と言う言明に対する私の指摘は表現に於ける表層的な問題では決して、ない。 それはその後の考察に影響する極めて、重要な問題である。概念というものは、先に述べた様な客観的認識を構築するプロセスで造られる。百歩、譲って、 言うならば、共有出来るのはその様な諸概念と、それらで構築された客観的世界だけである。だが、それが完全に同じ認識で共有出来ている、とは言い難く、まして、 主観的世界に至っては、共有など、とても可能とは思われない。だが、ひょっとして、「主観的な概念もあるだろう?」と、反論する人がいるかも知れない。そして、 その場合の主観的概念、と言うのは、おそらく、意味内容が主観的である、と言う事ではないのである。多分、概念そのものが主観的である事を意味している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
だが、その様な概念など、あるのだろうか?もし、その様な概念があるならば、あるいは、それが本当に概念ならば、その概念を共有する事はひょっとして、 可能なのかも知れない。そして、もし、そうならば、その様な概念が間主観の概念の基礎と成るのかもしれない。だが、やはり、この問い掛けは意味不明である。 客観的認識にしろ、主観的認識にしろ、それを説明しようとするなら、説明しようとする認識の概念化、つまり、思考が必要である。そして、 それは主観的認識の客観化のプロセスに他ならない。概念化をする為には、想定的にしろ、他者の存在を必要とするからである。他者を想定しない概念化など、 あり得ない(この場合、自己も対話相手としての他者と成る)。言い換えると、概念化は客観化に他ならない。従って、概念そのものが主観的である、 などという事はあり得ない。思考が情報交換の一種である、と言う事を忘れては為らない。 たとえ、ある概念に誤謬が含まれるかどうかは知らないけれども、その概念が人々に対して、少なくとも、似た意味内容を持つのでなければ、それは概念として、 意味を成さない。その事は主観的な意味内容、たとえば、悲しい、とか、うれしい、とか、そう言う内容を含む概念にも、当て嵌まる。 従って、上記の問い掛けは、意味不明であり、全く、反論に成ってはいない。しかし、以下の様な反論的主張は想定出来る。それはおそらく、 「あなたは、現象は認識主体に応じて異なっている、と言った、だが、認識対象そのものは各認識主体に共通ではないのか?」と言うものである。 だが、その事については、都合上、もう少し、後に申し述べる。 さて、再三、同じ事を言って、恐縮であるが、フッサールは自らの思索に、文化的世界、自然的世界、と言う概念を持ち出した。その時点で、 それらの世界を考える基準は既に、彼の主観的な世界観であった。従って、間主観という概念は意味を成さないのである。間主観、 などという概念をひねり出さなくても、「各々の主観的認識をそれぞれが情報交換して、客観的認識を形成する」と言えば、事は足りる。 前回、述べた様に、その過程を間主観的現象、と呼ぶのなら、異存はないが、おそらく、フッサールはそれを認めないだろう。 いずれにしても、「我々は客観的世界という共有物を持っている」と言う事で、満足する訳にはいかないのだろうか? だが、フッサールはどうやら、思考に於ける終着駅の向こうに、すがるべき何ものかを求めたのである。そして、おそらく、 彼は個人としての認識と集団としての認識との違いを見過ごしていた。前回も述べた様に、 彼は、個々人の間に生じた客観的認識がその集団の持つべき主観的認識を形成する、と言う事に気付かず、個の認識と集団の認識を混同してしまった。 だが、ひょっとすると、この問題に気付いていたのかも知れない。その故に、意図的ではないと思うが、微妙な誤謬を混入する事で、 その様な論理破綻の難局を回避しようとした様に思われる。そして、終着駅の向こうにあるべき、と確信する何ものかに辿り着こうとした、のではないのだろうか? だが、思考の終着駅には、真実という何ものも通さぬ壁がある。この壁を通り抜けた、と確信した瞬間、その思考は「偽」と成るのである。 例えであるが、私の目の前に一匹の犬がいる、とする。そして、その犬を見ながら、果たして、その種類は何であろうか?、と考える、とする。 この場合、私はその特徴などを観察して、自分の脳内に蓄積された諸概念と比較する。そして、それがプードルだ、と分かる。この場合、 これがこの思考の終着駅である。それ以上、先には進めない。蛇足ながら、思考の終着駅について、申し述べた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
なお、「個々人の間に生じた客観的認識がその集団の持つべき主観的認識を形成する」という言明に関連するアメーバーについての記述が 5.権力と進化の前段に、あるので、ご一読下さい。私の考え方がご理解頂けるもの、と考えます。 さて、再三、述べている様に、私は世界、と言うものを認識主体と認識対象との関係で考えている。従って、最初に認知される世界は主観的世界に他ならない。 他方、客観的世界は、「私という認識主体」と、「本来は認識対象である認識主体として振る舞う現象」との情報交換の結果、生起する。 勿論、このような他者は実際に認識主体である可能性がある。ただ、その事を知る事は不可能なので、自分と他者の比較から、類推して、彼らも認識主体であろう、 と結論し得るだけである。尤も、私はこの類推は正しい、と考えている。 いずれにしても、客観的認識を得る為には、自己だけではなく、他者が認識対象を認識している事が必要である。 従って、認識主体にとって、その認識は二次的な世界に過ぎない。主観的世界があって、始めて、客観的世界が存在し得る。 その故に、人々の利害関係がその認識に顕著に影響する文化的世界は客観化される事が難しく、逆に、自然的世界は比較的、客観化がされやすいのである。 たとえば、過去に敵対した、あるいは、現在、対立している国同士の歴史観などは客観化される事は難しいが、自然科学の成果などは、比較的、容易に受け入れられる。 先に述べた類推が正しければ、主観的認識は認識主体の数だけ、存在する。言い換えると、それは無数に存在する。 又、その故に、同一の認識対象についての認識も無数にある。無論、似た認識がある事は否定しないが、同じものなど、ひとつもないのである。 |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ただ、各々の主観的認識に、共通項はある、と言う主張があるかも知れない。そして、もし、その主張が正しいのなら、 その共通項は間主観という概念の基礎に成り得る。だが、私はその様な共通項は認めない。無論、犬には、犬に共通の認識方式がある事は否定しないし、 似た様な状況で、複数の犬が似た様な認識を得る事も否定はしない。だが、複数の人間が、「あの帽子は赤い」と言ったとしても、それは、 それぞれが同じ「赤」を見ている、とは断言出来ない。それは「赤」と言う概念を教え込まれて、 色彩に於けるある特定の状況を「赤」と言っているに過ぎないのである。誰も他人の見た「赤」を認知する事など、不可能である。 更に、彼らが、その帽子は赤い、と言った時、彼らによって表現された「赤」は既に概念化されており、彼らの主観的「赤」とは言い難い。 つまり、それは客観的な「赤」である、と言う事が出来る。 そして、前回、私は、「私と言う認識主体は物理的にも、心理的にも、あるいは、他の立場に於いても、他者とは違う位置に存在しているので、 その見る角度、及び、認識が他者と異なる事は当然なのである」と、述べた。つまり、似た主観的認識はあるが、同一の認識対象について、 完全に共通する主観的認識など、あり得ないのである。その様な共通項を求める為には、概念化、客観化、と言う作業が必要である、と言う事を忘れては為らない。 その事は少し前にも、申し述べた。 私は前回、世界は認識主体とその認識対象の存在で、成り立っている、とも述べた。この場合、認識対象はほぼ、「現象」と同義である。従って、 前回はその様な表現方法を取っていた。しかし、厳密に言えば、認識対象は実は、現象とは少し異なる。現象と言うのは、 先に述べた様に、認識対象が発する刺激を認識主体がある情報として捕らえた結果、現れるのである。たとえば、他者がその現象を既に認識していたとしても、 私がその現象を認識するまで、それは私にとっての現象ではない。その前提に立てば、その刺激がたとえ、同一刺激が同一時間に私とあなたに捕らえられるとしても、 それによって現れる現象は各々に応じて、程度の違いはあるものの、異なっている。つまり、 その刺激がもたらす情報が私とあなたとでは少し異なる、と言う事である。 従って、ある認識主体の文化的世界、そして、自然的世界はその様な現象の総体でしかない。夜空に輝くオーロラという現象にしても、厳密に言えば、 それは元来、ある認識主体に提示される、彼の認知能力に応じた個別の現象と言うしかないのである。たとえば、昆虫と人間が見るオーロラを想像してみて下さい。 いずれにしても、フッサールの言う文化的世界、自然的世界を現象の総体、として捕らえる限り、フッサールの論理はここでも、やはり、破綻する。 しかし、「その現象を認知させる認識対象そのものは、いかなる認識主体にとっても、共通ではないのか?」という反論的な疑問を提示する事は可能である。 そして、「フッサールの言う自然的世界、文化的世界、と言うのは、その様な認識対象の総体を指すのである」と言う事も可能である。ならば、認識対象の正体、 とは果たして、何であろうか?そして、その様な認識対象は本当に、いかなる認識主体にとっても、共通のものであるのだろうか? 以下では、その事について考察する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
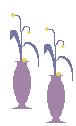
|
だが、その前に、どの様な認識主体にとっても、確実に共通である、と考えられるものは何であろうか?おそらく、それは何かを認識している、 と言う事だけである様に思われる。言い換えると、全ての認識主体は、「自己と他者との区別を行っている」と言う共通項を持つ。この場合、自己が認識主体であり、 他者が自分の思考、肉体を含む全ての認識対象である事は言うまでもない。そして、その認識は現在、と呼ばれる時間軸上の一点に於いて、 彼の前に現れる現象によって、産み出される。無論、このような現象はある刺激が情報として認知される事によって現れる。つまり、この関係は因果関係ではなく、 論理的な関係である、と言う事である。そして、前に述べた理由で、その様な現象をもたらす刺激、すなわち、情報が各々の認識主体にとって、 完全に同じ意味を持つ事はあり得ない。たとえ、それが物理的には、同じ刺激である、と認定された、としても、その持つ意味は、認識主体に応じて、 様々に異なる。其処で、その様な刺激を発信するもの、すなわち、認識対象の正体が問題と成るのである。 |
|
だが、認識対象に確固とした正体など、あるのだろうか?直感的には、調べようがない様にも思われる。私は一瞬、認識対象というのは、 思考に於けるひとつの終着駅であるのかも知れない、と考えた。 我々にとって、認識対象は常に、過去に存在している。我々はその存在を現在、現れている現象で、確認しているだけである。そして、その確認した内容、 それぞれには、酷似したものはあるにしても、それらはやはり、それぞれの認識主体に応じて、異なっている。ならば、その正体はおろか、 「認識対象が我々にとって、共通であるのか、どうか」すら、知り得ないのではないのか?つまり、認識対象が我々にとって、 共通のものである可能性は否定し得ないが、共通ではない可能性も否定し得ない、と言わざるを得ないのではないのか? 「原理的に、確定的には、語れない」と言うのが正しい認識である様に思われる。 そして、其処が思考の終着点である様に思われる。ならば、それを無理矢理、確定させて、論を展開しても、その結論が「偽」と成る事は明白である。 つまり、認識対象を我々に共通のものである、と言う前提から出発させた議論は成り立たない。従って、間主観という概念も成り立たない。
|
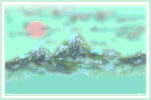
| だが、認識対象の正体は本当に知る事が出来ないのだろうか?私は、「完全に正体不明である、とは言い得ない」と、考え直した。 前回、私が述べた物理学に於ける波動性についての見解がその様な考えを示唆したのである。その考え方で、物理現象を見るなら、 実在としての波動性がある蓋然性の範囲で、現実化するのが物理現象である。それは取りも直さず、認識対象が確固とした正体など、持たない、 と言う事を示唆している。言い換えると、現象として現実化する前の認識対象は、ある可能性に過ぎない。(ちなみに、この順序は因果関係ではなく、 論理的な順序である)。そして、その可能性が現実化する為には、認識主体の存在が必要なのである。 再三、述べている様に、ある現象の様相はその現象を認知する認識主体に依存している。そして、認識対象はある可能性から、ある蓋然性の範囲で、 ある特定の状態を選択して、現象として、現れるのである。つまり、それは、「認識主体とその様な可能性の関係は、主観的認識と同様に、 それぞれの認識主体に固有のものである」と言う事である。ならば、間主観という概念はやはり、意味不明である。意味不明な概念は概念とは言えないから、 使えない。人をして、分かった様に錯覚させるだけである。仮に、その概念を使用可能と考えるとしても、それは宗教に任せるべき範疇に在る。 今、私はそう、確信している。 | |
| 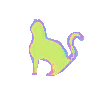
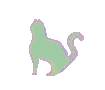
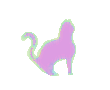
|
Cotosiro
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||