|
改訂版 妙な概念 間主観、と言う概念は必要なのか? July 31, 2010. 野口博正 This was reviced in October 3, 2011. リンク先を変更しました。February 4, 2012. |
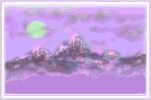
|
||||||||||
|
私はこの所、いろんな理由で、暇なので、時折、様々なキーワードを使って、自分のホームページを検索している。ついでに、其処に現れた他のホームページ、それは書籍の紹介などが多いのだが、その題名、内容などを確認したりする。結構な時間を使うので、暇潰しにはもってこいである。そして、一ヶ月ほど前、私はその検索の最中、妙な言葉をヒットした。確か、客観的時間、と言うキーワードで、検索した、と記憶している。たまたま、其処で、間主観という言葉を見付けたのである。気に成って、二、三日前、再び、検索したら、見付からなかったが、何処かで、似た様な言葉を見た記憶がある。試みに、自分の書棚を調べてみた。 すると、十数年前、共同主観という意味不明な言葉に釣られて購入した本が一冊、出てきた。面白くないので、数ページを読んだだけで、お蔵入りと成った本である。それを書棚から引っ張り出して、ぱらぱらと捲った。すると、そこにフッサール、と言う哲学者の名が載っている。そして、これまた、お蔵入りと成っていたフッサールの「現象学の理念」という本を想い出した。だが、読む気などは、はなから無い。私は広辞苑を引っ張り出して、間主観性の項目を引いてみた。 |
|||||||||||
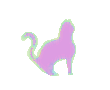
|
その説明に拠ると、間主観はフッサールの用語である。そして、フッサールは自然的世界も文化的世界も一個の主観の所有物ではなく、多くの主観の共有物である、と考えたらしい。そんな事態が本当に実態として存在するのか?と、私は疑わしい様に思ったが、広辞苑に拠れば、フッサールはこの事態を間主観的現象、と呼んでいる、と言う。また、この現象に於いて、統一的な客観的世界が成立する、と言うのである。分かる様で、分からない。間主観という概念が、どうしても怪しく思える。「間主観の概念を産み出した思考過程に、間違いがあるのではないのか?そんな概念など、ひねり出さなくても、主観性と客観性の概念だけで、事は足りるのではないのか?」私の直感はその様であった。 だが、それは本当にそうなのか?この種の哲学は苦手であるので、そうは即断も出来かねるのである。私はもやもやとしながら、その問題について、考え始めた。だが、すぐには、結論が出てこない。それは恐らく、私の思考がフッサールの論理の枠に、はまり込んでいたからである。其処で、私はさし当たり、間主観という概念を横目で見ながら、自分の考え方を点検し始めた。 | ||||||||||
|
私はある時、火事を目撃して、消防署にその状況を連絡した。だが、この場合、電話に出た署員はたまたま、酷く疑い深い人間であった。彼は電話口で、「其処は何処です、本当に火事ですか?あなたが火事を見た、と言う根拠は何ですか?」などと、問いを発する。私がその妙な問いにうろたえながら、話をすると、彼はどうでも良い様な言葉尻を捕らえて、「それは証明に成っていない」と、いちゃもんを付ける。果たして、私はどう説明すれば、良いのだろうか?現に、火事は起こっており、私は今、それを目撃している。従って、自分の主張に正当性がある事は疑いようがない。 だが、この消防署員は彼の考え方に沿って、火事が起こっている事を証明せよ、と言うのである。 |
|||||||||||
|
この非常時に、そんな悠長な事で、良いのだろうか?いや、彼の論理に乗っている限り、証明などは出来ないだろう。私は怒りに身体を震わせて、まくし立てた。「本当に火事だって、言ってるだろ、来てみろよ、燃えているから」すると、消防署員は、私の剣幕に押されたらしく、「しょうがないですねー、じゃあ、確かめに行きますよ」と、ようやく、重い腰を上げて、出動してきた。そして、消火が終わると、彼は私の側に来て、「あ、やっぱり、燃えてましたね、疑って、どうも、すみません」と、納得をした様子で、謝罪した。
無論、これは作り話である。私は概念を切り刻んで、その切り刻んだ概念を飴細工の様にこねくり回す哲学が非常に嫌いだ。到底、真実に近付いている様に思えない。むしろ、遠ざかっている様にすら、思われる。私の頭が悪いのか?邦訳が不適切であるのか?それとも、その様な哲学そのものが間違いなのか?はっきりとは分からないが、殆ど、理解が出来ないし、私の直感を触発しない。簡単に言えば、その様な書籍を読んでも、全く楽しくないのである。多分、その様な哲学に対する私の理解力が足りないのだろうが、私は昔、臆面という言葉を捨てたので、自分の問題は高い棚に上げておく。 私は自然科学でも、他の学問でも、基本的な法則、及び、概念はシンプルでなければならない、と考えている。 |
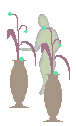
|
||||||||||
|
切り刻まれて魂を失った諸概念の難解性や、その様な諸概念による複雑きわまる構築物はその思考がある種の誤謬を内包している証である、とも思うのである。この事は多分、間主観性の観点に立っても、当たっている。難解な概念、多分、この場合、独りよがりの概念、と言う方が適切なのかも知れないが、それが間主観性を持つ、とは思えないし、客観性を持つとも思えない。百歩、譲っても、間主観という概念は極、限られたフッサールの信奉者の間でのみ、間主観性を持つのである。だが、果たして、それがフッサールの目指したゴールだろうか?
思索をする人間は多かれ少なかれ、自分の思いつきと思考に酔いしれる傾向を持っている。そして、千鳥足で歩いている事にも気が付かず、実態から遊離をして、あらぬ方向を目指すのである。 さて、悪態はこのぐらいにする。ここに来て、私の考え方がようやく、纏ったので、いよいよ、本題に入らなければ為らない。間主観という概念が世界を説明する上で、本当に必要であるのか、と言う問題である。しかし、その事を論じる前に、私自身の世界観を知ってもらう必要がありそうである。私はその世界観に基づいて、考えるのであるから、それは当然の順番である。また、その世界観については、そう考えるに至った道筋と共に、既に、文明と生体 進化論への基礎的考察、及び、日本文化の源流、その論理的帰結としての世界観などに説明があるので、参照して下さい。 ただ、基本的な考え方は説明の必要がありそうなので、極力、思考過程を省いて、以下に述べます。 まず、世界は認識主体とその認識対象の存在で、成り立っている。私の立場から言うならば、認識主体は私であり、私と言う生体、私の思考を含む全ての現象が認識対象である、と言う事に成る。認識対象と成らないのは認識主体としての私だけである。 | |||||||||||
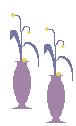
|
「くどいようで恐縮ではあるが、この様な認識対象は無数にあって、物理現象に限らず、現象の全てである、と言う事を強調したい。」
ただ、これは認識主体が全ての認識対象を認識出来る、と言う事ではない、と言う事は当然である。つまり、認識主体の能力に応じて、認識可能な対象が決められる。従って、先に述べた全ての認識対象は正確には、認識対象と成り得る現象、と言い直されねば為らない。だが、それは少し、面倒なので、以下では、その様な言い回しは使わない。
ちなみに、認識対象は現象そのものではありません。しかし、理解を容易にする為に、此処ではこの表現を使います。 また、その様な現象として現れる全てが認識主体として振る舞うであろう、という事も言って置かねば為らない。 何故、「認識主体である」と、言い切る事が出来ないのか、と言うと、私にとって、認識主体は私のみであるからである。つまり、他者を認識主体とする考えは、私がその様な私自身と他者の態様とを比較、観察した上での、単なる類推に過ぎないからである。そして、この類推は記憶への信仰と同様に、僅かな傍証によるだけであり、確たる証拠など、持ってはいない。 参照:9.文明と自我・ 10.自我についての補足説明 | ||||||||||
|
それにも拘わらず、上記の様な認識対象を人間のみに限定して、論じるならば、私以外の人間も認識主体として振る舞う、と言う類推を否定する人間はまず、いない。 あるいは、全ての人間が認識主体である、と言い切っても、反論する人は小数である様に思われる。従って、上記の類推は確かな客観性を持っている。 其処で、私はこの類推を人間を含む全ての現象に拡張した。動物しかり、鉱物しかり、その他、諸々の現象、しかりである。それらの現象は多くの場合、互いに反応する事が可能であるからである。そして、その反応の仕方は反応すべき相手や周囲の状況によって異なるが、それらの反応は、それぞれ、独自の規則性に基づいて行われる。それは相手を認知して、その相手に応じて、論理計算をして、反応するからである。この意味に於いて、人間同士の反応や、化学反応、あるいは他の反応との間に、特別の相違は見当たらない。あらゆる反応は、それぞれに特有の、ある規則性を持っている。 それにも拘わらず、上記の様な認識対象を人間のみに限定して、論じるならば、私以外の人間も認識主体として振る舞う、と言う類推を否定する人間はまず、いない。あるいは、全ての人間が認識主体である、と言い切っても、反論する人は小数である様に思われる。従って、上記の類推は確かな客観性を持っている。其処で、私はこの類推を人間を含む全ての現象に拡張した。動物しかり、鉱物しかり、その他、諸々の現象、しかりである。それらの現象は多くの場合、互いに反応する事が可能であるからである。そして、その反応の仕方は反応すべき相手や周囲の状況によって異なるが、それらの反応は、それぞれ、独自の規則性に基づいて行われる。それは相手を認知して、その相手に応じて、論理計算をして、反応するからである。この意味に於いて、人間同士の反応や、化学反応、あるいは他の反応との間に、特別の相違は見当たらない。あらゆる反応は、それぞれに特有の、ある規則性を持っている。 その故に、我々が物質と呼ぶ現象も、そのほかの現象も、認識主体として振る舞う、と言う類推が成り立つのである。先に述べた様に、それらは反応する相手を認知して、反応する、と考えられるからである。ただ、たとえ、物質が反応する相手を認知するとしても、物質に理解力など認められないから、認識主体とは認めない、と言う人間もいるかも知れない。しかし、もし、物質に理解力がなければ、同条件で、同じ反応をする、などという芸当が可能な様に思われない。つまり、その様な反応も、他者と自らの関係についての単純な論理計算に基づいて、生起するのである。そして、論理計算はとりもなおさず、思考である。 |
|||||||||||
|
我々、人間の脳は複雑な論理計算を行うが、道ばたの石ころの分子にしても、その反応に於いて、単純な論理計算の一翼を担っている。つまり、ある刺激が情報として、与えられると、ある一定の反応を示すのである。我々は脳内で、思考という情報交換をしているが、物理的反応、あるいは、化学的反応なども、情報交換の様相と考える事が可能である。そして、情報交換は思考そのものである、と言っても、過言ではない。ただし、その場合も人間の反応と同様に、ある範囲の蓋然性がある事は確かである様に思われる。 なお、この事に関連して、物理学では、物質、たとえば、ニュートリノ、あるいは、電子などは粒子の性質と波動の性質を併せ持つ、とされている。しかし、私はもう少し、踏み込んだ意見を持っている。別稿でも、しばしば述べているが、それは、粒子と波動を同列に扱う事は出来ない、と言う事である。そう考えた理由は電子が波動である状態を見たものは誰、一人として、いないからである。つまり、その様な波動性の妥当性は粒子を観測した結果、導き出された推測であり、波動そのものを直接、見た結果ではない、と言う事である。波動性はその様な推測で確認出来るが、波動、そのものは確認出来ない。 |
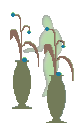
|
||||||||||
|
なら、その様な波動はどの様な存在なのか?私はその答えについて、以下の様に考えた。波動は実在ではあるが、現実ではなく、現実と成るべき可能性である。従って、波動が現実として現象する為には、その可能性に基づく、ある蓋然性の範囲に於いて、認識者に認識されて、粒子と成る事が必要である。その故に、その粒子が現れる位置は確定的には、予測する事が出来ないのである。つまり、「ある範囲に現れる筈である」と言う蓋然的予測しか、可能ではない。やはり、波動性は可能性なのだ、と、私はそう結論した。論題とは少し離れたけれども、ついでなので、申し述べた。
さて、寄り道はこのくらいにして、考察を本題に戻す。もし、先の認識主体についての類推が適切であるなら、私という認識主体の認識対象は認識主体としても、振る舞う。その場合、それらの認識主体は私という存在を現象としての私(体格、肌の色、顔つき、あるいは、物理的強度、など)によって、認知する。つまり、私は他者に対して、その様な情報を送っている訳である。そして、その種の「情報の送り」は生化学反応、電気信号などとして、私の体内、脳内に於いても、起こっている。つまり、私の体内には、無数と言って良いほどの認識主体と無数と言って良いほどの認識対象が存在する。あるいは、無数にある、と言い切った方が適切であるのかも知れない。 無論、これらの認識主体と認識対象はその立場を常に併せ持っている。この論理を私の体外に広げるならば、世界には、無数の認識主体、無数の認識対象が存在する、と言わなくては為らない。また、世界が一個の認識主体として振る舞う、と言う類推も成り立つのである。ただし、第一人称である私について言うならば、私が唯一の認識主体であり、他の一切が認識対象である事は当然である。また、その時、私という存在は、他者にとって、第二人称、あるいは、第三人称で示される認識対象である事も当然である。 |
|||||||||||
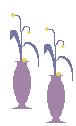
|
ちなみに、第一人称、第二人称、第三人称、と言う概念は、その概念が指し示す具体的実態を持った複数の何者かの相互の関係を表すだけで、実態そのものを表す概念ではありえない。たとえば、此処に山田、と言う人物がいる、と仮定する。そして、私はその仮定の世界で、彼に、「あなたは少し太りましたね」と、言った、とする。この場合、山田氏は第二人称で示された。(注1)そして、「太った」というのが、この場合の山田氏の実態である。 私がこの言明に先立って、「あなたを第二人称で呼ぶ」と、言わずもがなの発言をしたとしても、それは彼が第二人称、そのもの、である、と言っているのでは決して、ない。もし、私がその様な意味で、言った、とすれば、それは論理的な関係を考慮する以前に、既に、文法的に間違っている。彼は第二人称ではなく、あくまでも、山田氏なのだから。 第一人称、第二人称、第三人称、などという概念を使う場合には、上記の事を考慮する必要がある、と言う事である。当然すぎるので、馬鹿馬鹿しい指摘とは思うけれども、ややこしい哲学の中には、しばしば、この種の誤謬が巧妙に紛れ込んでいる様に思われる。はたして、これは私の錯覚だろうか? ところで、以上の様な認識主体と認識対象との関係は情報の発信者と受信者の関係に置き換えて、考える事が可能である。 また、その場合、発信者は受信者でもあり、受信者は同じく、発信者でもある。 | ||||||||||
|
この事は日本文化の源流、その論理的帰結としての世界観 第7節 情報と認識主体、
そして、進化、情報、思考において、詳細に述べているので、参照して下さい。
なお、認識主体から見る物理世界の形式的態様については、認識主体から見る物理世界(固有の時間、主観的時間、客観的時間)において、述べているので、参照して下さい。 さて、以上に於いて、私のおおよその考え方が明らかと成った。また、それを踏まえて考えると、やはり、私の考え方と、間主観という概念の間に、論理的整合性を持たせる事は難しい。無理に、整合性を持たせようとするなら、出来ない事もないのであるが、それはただ、話を難しくするだけで、何の益も、もたらさない。むしろ、誤解や曲解を産み出す可能性を増大させる。従って、その様な概念は不必要である。私はそう、と結論した。その訳は私が今まで、述べた考え方を理解していただけるなら、分かって頂けるもの、と考えるが、少しだけ、説明したい。そして、その説明の中核には、私という認識主体の中に、多数の認識主体が存在するであろう、と言う前述の推測がある。 認識主体が行う認識は第一義的には主観的なものである。(注2)私と言う認識主体は物理的にも、心理的にも、あるいは、他の立場に於いても、他者とは違う位置に存在しているので、その見る角度、及び、認識が他者と異なる事は当然なのである。つまり、厳密に言えば、私の主観的世界は他者との共有物には成り得ない。その故に、その認識は他者の認識と比較される。それはその認識主体が自分の認識と他者の認識との整合性を探る為である。その結果、産まれるのが客観的認識である。此処には、間主観という概念が入り込む余地は殆ど無い。少なくとも、使う意味が認められない。共同主観性、間主観性、というのは、ある主観を持つ認識主体が実際は何であるのか、と言う判断を誤った為に現れる概念である、と断言出来る。たとえば、ある共同体を認識主体と考えた場合、その認識を、その共同体に属する構成員、個々の認識として、処理しようとした結果、間主観などと言う妙な概念が現れる、と、私はそう考えた。間主観性などは夢想であるし、間主観的現象などは存在しない。それが私の結論である。 ただ、間主観という概念を私なりに解釈し直して、使う事は可能である。たとえば、ある共同体を襲う奇妙な事象が生起した、とする。しかし、その事象に対する共同体構成員の認識は様々に異なる。従って、対処の方針が定まらない。其処で、意識的か、無意識的かは知らないけれども、互いの認識を比較しあって、その事象に対する客観的認識を構築して行く。そして、その様にして構築された認識が各共同体構成員の客観的な認識と成る。(注3) |
|||||||||||
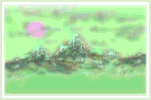
|
また、その認識が共同体の持つ認識を決めるであるが、その様な共同体の認識はその共同体にとっては、主観的な認識である、と言う事に気が付かねば為らない。私としては、この様な過程を間主観的現象、と呼ぶのなら、異存はないのである。だが、あえて、その様な概念を使う必要など、あるのだろうか?
注1:この場合、私は「私」という言葉によって、第一人称で示されるべき存在です。 注2:認識主体が行う認識、と言う表現は少し妙だ、と思われるかも知れません。認識を行うのは認識主体に限られるからです。 しかし、認識対象が認識主体として振る舞う、と言う事を想起するなら、その様な認識を便宜的に、認識対象が行う認識、と表現する事が可能です。 従って、認識主体が行う認識、と言う表現は決して不適切ではありません。 注3:この場合、必ずしも、各構成員、全ての主観的認識に変化が起こる、とは、断言出来ない。主観的認識と客観的認識とは違うのである。 | ||||||||||
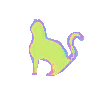
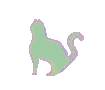
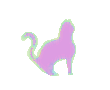
| |||||||||||
| Cotosiro | |||||||||||