|
改訂版 現なる夢 August 4, 2000 in Justnet. This was shifted to Nifty in November 19, 2003 and revised. This was revised in May 20, 2013. Hiromasa Noguti It is fixed "HTML" in February 14, 2017/ 野口博正 |
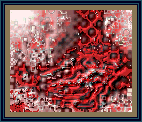 | ||||||||||
|
その五 閻魔 の 正体 | |||||||||||
|
「おい、また、来たよ」「ああ、今日は、これで、何人目だ?」ふと、気が付くと、誰かが何処かで、語らっている。恐ろしく低音で、凄みの利いた、ゾッと、する様な声である。だが、私はまだ、夢の中にいるらしく、どの様な状況で、その会話を聞いているのか、については、それほど、はっきりとは、分かっていない。ただ、何とは無しに、夢の外から、聞こえて来た様には思うのである。そして、自分が異常な状況に置かれている事にも、薄々ながら、気が付いていた。だが、どの様な異常状態にあるのかは分からないので、私は少し、不安であった。と、その不安が引き金にでも、成ったのだろうか?私の脳裏を、真っ暗な空間に放り出された時の情景が過ぎって行った。「そうだ、烏鷺の底がいきなり、抜けて、私は闇の中を落下したのだ」だが、あの後、一体、何が起こった、と言うのだろうか?真っ暗な空間を落下している最中、精霊の怒りを感じた事は朧気ながら、覚えているが、その後の事が分からない。多分、気を失っていたのだろう。果たして、何処に、落ちたのか?地獄だろうか?確か、あの時、精霊は、「地獄へ落ちよ」と、言っていた。ならば、最前、聞いた会話は地獄の鬼達の語らいなのだろうか?目を開けて、確認したいが、とても、恐ろしくて、そうは出来ない。辛うじて、理解出来るのは、体中が痛むので、どうやら、自分はまだ、生きている、と言う事くらいである。「ならば、此処は地獄では無い、と言う事も、考えられる、ひょっとすると、現世だろうか?それにしては、様子が妙だが?」私はまだ、半分、眠った状態で、いろいろと、考えを巡らせた。 「だが、最前、聞こえた妙な会話は現実だろうか?何となく、夢の様にも、感じるのである。それとも、危険な事や嫌な事は全て、夢だ、と考えたい、と言う希望的観測に過ぎないだろうか?いずれにしても、奇妙な会話はまだ、時折、聞こえるのである。気配からして、数名ほどは居るのだろうか?籠もった様な声ではあるが、奇妙な具合に、反響している。そして、その異様な響きと音色はとても、此の世のものとは思えないのである。「やはり、夢かな?それとも、此処は奈落の底か?あの精霊の言った様に、私は地獄に、落ちたのか?」何故か、朦朧とする意識の中で、様々な想像が脳裏を過ぎった。 だが、どの想像が真実だろうか?あるいは、真実に近いのだろうか?私は再度、問題点を整理してみた。まず、今も、聞こえる会話が私の眠りを破った事は確かである。それが元で、私は烏鷺の底が抜けた事を想い出して、此処が地獄かも知れない、と考えた。その事を考えるなら、今も聞こえる妙な会話は夢では無い、様に思われる。無論、声を聞いて目が覚めた、と言うのも、夢であった、と言う事も、無くは無いが、私の感覚はその可能性を否定している。かと言って、会話が醸し出す雰囲気を考えるなら、此処が現実世界である、とは、思えない。ならば、あの精霊が目論んだ通り、私は地獄に落ちたのだろうか?無論、それは実際に、目を開けて、見てみなければ、分からない。目を開けるのは、恐ろしいが、こうして、考え込んでいても、埒が明かない。私はありったけの勇気を振り絞って、そろっと、薄目を開けてみた。 | |||||||||||
|
と、そこには、巨大な数匹の鬼達が奇っ怪な姿で、たむろしている。身体に纏った怪しい炎が時折、大きく吹き上げて、此処が地獄である事を明示していた。だが、何と恐ろしい光景だろうか?鬼を包む地獄の炎が渦を成して、天を焦がすと、幾つかの青白い鬼火と成って、飛散して、ゆらゆらと宙を漂いながら、赤味がかった地獄の闇に、溶け込む様に、吸い込まれて行く。それらは皆、地獄での永遠の禁固を言い渡されて、永遠に、再生の許されぬ無感地獄へと落ちる魂だった。その事が何故か、私には、分かったのである。それにしても、何も感じる事の出来無い地獄に向かう魂達の哀れさというものは本当に、目を覆うばかりである。無感地獄とは、何と、恐ろしい地獄であろうか!私は余りの恐怖に、思わず知らず、瞼を閉じた。そして、「この情景は、夢であれ!」と、心底、願った。だが、意識は既に、はっきりしている。残念ながら、これは決して、夢で無い。これから、私はどう成るのだろう?此処にいる鬼達に追いかけられて、針の山を登るのだろうか?いずれにしても、状況がはっきりするまでは、闇雲に、動く事は慎まねば為らない。私はその場に寝転んだ侭、眠っている風を装った。そして、耳をそばだてると、辺りの気配に注意を払った。 |
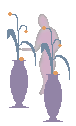 | ||||||||||
|
だが、目を閉じた侭では、やはり、状況を把握する事は難しい。私は再び、薄目を開けた。と、鬼達の足の間から、鋭く尖った幾つもの奇岩が紅の空に、にょきにょきと、聳えているのが見て取れる。地面は皆、ごつごつとした岩原である。草の一本も生えては居ない。その代わりに、硫黄の様な結晶が、そそり立つ幾つもの奇岩の根元において、塩でも、吹く様に堆積していた。だが、恐ろしい光景はそれだけでは無い。その黄色い結晶の周辺からは、血液だろうか?真紅の液体が泡立ちながら、間断無しに、浸み出して、岩の狭間へと、流れ出ている。私はその行き先を目で追った。すると、深紅の液体は、網目模様を形成しながら、岩の狭間を流れ下って、あるいは、再び、合流しながら、渦巻く濁流を形成して行く。何故かは知らぬが、鬼達はその濁流を砂金の鉱脈と呼んでいた。 深紅に染まった濁流は黄色いしぶきを上げながら、岩を削って、あるいは穿って、深い峡谷を形成している。魔物の様な奇岩の狭間を、どす黒く染まった赤い瀑布がしぶきを上げながら、落下していた。怪しげな蒸気が、死人の臭いを振りまきながら、滝壺の辺りから、上昇している。亡者達の悲鳴と嘆きが瀑布の砕ける音といっしょに、陰惨な空へと、反響していた。古い書物や絵巻物とは、比較にも成らぬ異様さである。深紅の川のほとりでは、腹を減らした鬼達が亡者達を追い掛けて、手当たり次第に、貪り食った。人間の血を啜り、肉を喰うなど、鬼に取っては、日常らしい。此処は世俗的欲望が堆積して、行き着くところの、なれの果ての世界らしい。実を言えば、鬼らも、元々は人間であった。最前と同じく、私には、その事がはっきりと、分かったのである。「なら、良心の欠片くらいは、あるのだろうか?」私はそう、心の隅で、期待した。だが、その事については、はっきりしない。鬼らの抱く悲しみを少し、感じただけだった。 いずれにしても、こんな連中に捕まると、どんな目に遭うか、分からない。かと言って、いきなり、逃げ出すのでは、目立ってしまう。「此処はひとまず、やり過ごそう」私はソッと、顔を伏せると、取りあえず、眠った振りを決め込んだ。後は、鬼等の隙を見澄まして、そっと、逃げるだけである。私は何時、鬼に踏み潰されるか、と、ヒヤヒヤしながら、そのチャンスをひたすら、待った。だが、地獄はそうは、甘くない。鬼等は私の思惑など、先刻、承知であったのらしく、「こら!亡者のくせして、死んだ振りかよ!」と、恐ろしい声で、呼び掛けた。恐怖で、躰が凍り付く。チラッと、薄目で窺うと、鬼の腕がこちらへ伸びた。私は逃げる暇も無く、襟首を掴まれると、恐ろしい力で、持ち上げられた。「ああ、喰い殺される!」恐怖の余り、私は思わず、瞼を閉じた。 | |||||||||||
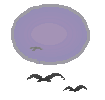 |
だが、私はすぐには、食べられなかった。鬼はまるで、からかう様に、目を閉じた私をぶらぶらと、前後、左右に、揺さぶるのである。これは何かの罰であろうか?それとも、私を食う為の準備か、何かであるのだろうか?どうせなら、一息に、ぱくっと、遣って欲しい。おそらく、鬼の身長は二十メートルほどはあるだろう。もし、鬼がうっかりと、手を滑らせたなら、私は岩に落下して、粉々と成るか、あるいは、奇岩の先端に落とされて、串刺しと成ってしまうだろう。どうせ、落ちるなら、濁流に放られる方がましである。運が良ければ、上手い事、脱出する事も、出来るかも知れない。だが、下の状態はどの様なのか?私はふっと、目を開けると、下の様子を盗み見た。と、そこに、鬼の顔がやにわに、迫る。牛の角を頭に頂く牛鬼、とか、呼ばれる黒鬼である。その鬼がやにわに、くわっと、口を開らいた。剥き出しと成った鋭い犬歯が刃物の様にギラリ、と光る。「ああ、もう、駄目だ!食い殺される!」極度の恐怖で、意識がスウッと、遠退いた。 | ||||||||||
|
が、何故だろう?私は食べられはしなかった。牛鬼に揺すられて、意識を戻すと、彼は私を地面に置いて、猫なで声で、話し始めた。「なあ、おまえ、怖がらないで、ちゃーんと、お聞き?亡者の侭か、鬼と成るのか、其処が思案のしどころよ?お前は一体、どっちにするの?」妙に、なよっと、して、気持ち悪いが、低い声とのアンバランスがある種の凄みを漂わせている。異様な妖気にも、圧倒されて、私は思わず、目線を反らした。だが、鬼の語った亡者の侭とは、果たして、如何なる意味であろうか?私は未だ、死人では無い。精霊の放つ恨みの為に、烏鷺から落ちただけである。「きっと、鬼達はその事情を知らないのだ」私はそう、考えると、意を決して、しかしながら、おずおずと、今までの経緯を鬼に語った。そして、地上への帰還を願い出た。 だが、鬼等の態度は不可解である。彼らは一瞬、沈黙した後、呆れた様子で、私を見つめる。そして、ふいっと、視線を外して、互いの顔を見合わすと、一斉に、げらげらと、笑い始めた。だが、鬼達は何故、笑うのだろう?私は訳が分からずに、ぼうっと、鬼達を眺め続けた。と、最前の牛鬼が目を剥いて、言った。「わからんのか?馬鹿ものめ、生きていようと、死んでいようと、地獄へ来た者が亡者なんだよ」すると、一角の青鬼が私を馬鹿にした様に、一瞥する。そして、へらへら、笑うと、「そうだ、そうだ!」と、おどけて見せた。だが、それは話が妙ではないか? 「でも、死人を亡者、と言うのでしょう?」私は思わず、そう、述べた。だが、青鬼は言う。「じゃあ、取って置きの秘密を教えて上げよう、此処はお前が呼び込んだ、お前自身の地獄なんだよ、お前はね、生きてる時から、此処に居たのさ」「えっ?此処に居た?どういう意味です?」私は恐い顔にも、ようやく、慣れて、目線を合わせて、そう、問うた。他の鬼等はニタニタと、二人のやり取りを窺っている。すると、青鬼は勢い付いて、べらべらと、一人で、喋り始めた。「お前はね、欲の単なる虜なのさ、何が、真実探しだい?とっくの昔に、放り出して、欲ぼけに成っているくせに!自分を大事に出来ないお前は、他人も、大事には、出来んのさ」 | |||||||||||
|
だが、彼は何を言っているのか?これが私の質問への答えだろうか?とても、そうとは思えないし、言っている意味も、分からない。遠慮無しに言うならば、支離滅裂である、と言うしか無い。私は反応のし様に、戸惑った。そして、他の鬼達を窺った。彼らも、首くらいは、捻るだろう、と思ったのである。だが、どうした事か?鬼達は、「良く、言った」と、皆、納得した様に、頷いている。「鬼の思考回路は人間のものとは、違うのだろうか?なら、何を話しても、無駄なのかも知れない」私はもう、がっかりとして、彼らを見つめた。と、青鬼が言った。「あ、そうか!お前は金儲けしか、頭に無いから、ちょっと、難しかったかねー、けど、精霊が怒るのも無理はないんだ、地獄を産んだのはお前だからね、言ってみれば、俺達はお前自身でも、ある訳さ」またしても、意味不明な言いぐさである。私はもう、呆れてしまって、何も答えずに、鬼を見つめた。饒舌な奴ほど、中身が無いのは、何処へ行っても、同じらしい。「本当は、何にも知ら無いくせに!ただ、威張ってみたいだけなのだ!」私は内心、そう、言って、眼前の青鬼を蔑んだ。 |
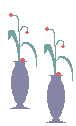
| ||||||||||
|
と、その直後、青鬼の形相がやにわに、変わった。ひょっとして、私の蔑みを知ったのだろうか?彼は恐ろしい声を張り上げて、威圧する様に、私に言った。「しのもの言わずに聞いて居れ!地獄をたっぷりと味わう事だ!お前は地獄に落ちた亡者なんだよ!」だが、私はもう、鬼を怖い、とは思わなかった。むしろ、言い知れぬ怒りすら、込み上げるのである。「姿形も奇妙だが、頭の中身も、おかしいらしい、まともな鬼はおらんのか?」私は心の中で、そう呟くと、他の鬼達を眺め回した。 が、妙である。彼らは皆がそろって、間抜け面に成っている。最前までは、威厳すら、感じられた恐い顔が今は、滑稽にすら、思われる。私はその余りの落差に、戸惑った。だが、おおよその理由は想像出来る。おそらく、鬼達は元々、それほど、賢くは無いのだろう。鬼に抱く私の恐怖心が、ありもしない威厳を感じさせただけであった、と言う事なのに違いないのである。それとも、この鬼達に、何らかの異変が突然、生じて、この様な間抜け面に成ったのだろうか?いずれにしても、この様子では、とても、相手に出来る、とは思えない。「もっと、ましな鬼を探さなければ・・」私はそう、考えた。 | |||||||||||
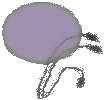
|
だが、彼らを無視して、立ち去るならば、「侮りやがって!」と、怒りを買って、たちどころに、食われてしまうだろう。「なら、どうしよう?」私は少し、考え込んだ。そして、ふっと、気が付いた。地獄には、統治者たる閻魔が居る筈だ。私の運命を決めるのは、彼を置いて、他にはない。「閻魔は何処です?」私は鬼等を見上げると、つい、うっかりと、そう言った。あろう事か、敬称を省いて、問うたのである。すぐに、気付いたが、後の祭り、私の全身から、血の気が失せた。 案の定、鬼等は一斉にギロッと、睨む。「閻魔、だと?閻魔大王と、何故、言えぬ!」恐ろしい声が頭上で、響いた。此処は、ひたすら、謝るしか無い。「あ、すいません!閻魔大王、大王様です!お許しを!」私は地べたに額を擦り付けて、何度も、何度も、許しを請うた。たが、その間、鬼等は何も喋らない。私は少し、奇妙に思って、上目を使って、鬼らを見上げた。すると、どうした事か?鬼らは皆、天の一点を仰ぎ見ている。そして、何故かは知らないが、私への怒りは感じられない。「あ、あのう、お許し頂けますか?」私はそろっと、立ち上がると、恐る恐る、そう問うた。 | ||||||||||
|
だが、妙だ。鬼等は全く、私を見ない。彼らは惚けた顔付きで、天を見上げた侭である。私が再度、問おう、とすると、声を揃えて、述べ立て始めた。「いや、良いんだよ?言い間違いは本音と言うし、どうせ、自分の事なんだ、それは、どうとでも、勝手に呼ぶさ」一言一句が同じで、抑揚もテンポも、同じである。最前までは、人格らしき物も感じられたが、今は、それも、感じられない。まるで、それは魂のない操り人形の様である。長い間の地獄ぐらしで、おかしく成ったのに違い無い。それとも、閻魔の仕業だろうか?いずれにしても、相手にするのは、時間の無駄だ。「閻魔大王、私は死んではおりません!」私は陰惨に燃える天に向かって、ありったけの声で、呼び掛けた。 気が付くと、辺りは漆黒の闇である。鬼も亡者も消えており、針の山も血の川も、うたかたの様に消えている。「閻魔は何処だ?」私は闇を手探りで、眼を凝らして、歩き始めた。と、真っ暗闇の直中に、何者かがいる。「閻魔かも知れない!」私はそう期待すると、眼を凝らして、前方を見た。だが、其処に見えるのは閻魔では無い。もう一人の自分が青白い蛍光をぼうっと、発して、闇に僅かに、浮き出していた。何故かは知らないが、身の毛がよだつ。私は二、三歩、後ずさりした。 だが、どうも、様子が妙である。其処に見える自分には、実在と言うものが感じられない。私は更に、眼を凝らして、もう一人の自分を再び、見つめた。と、それは等身大の鏡に写った自分の姿に他ならない。「何だい、これは?」緊張感が一気に解けて、私は全く、拍子が抜けた。鏡を保持する額には、黒い漆が施されている。その所為で、額は暗闇へと溶け込んで、鏡があたかも、空間の一部である様に見えたらしい。其処に写る自分を、もう一人の自分と錯覚するのも、無理からぬ事ではあったのである。 だが、本当に、錯覚だろうか?良く見ると、其処に写る自分の姿は何処とは無しに普通ではない。心の底まで見通すような、恐ろしい眼光で、私を見ている。本当に、それは鏡に映った自分であるのか?どうしても、その様な疑問が、拭い切れない。私は少し考えて、試みに、もう一人の自分をにらみ返した。もしかすると、相手が反応するかも知れない、と考えたのである。だが、期待に反して、相手は何も反応しない。にらみ合いが長く続いた。すると、不思議な事に、私の認識が変わり始めた。鏡の中の私には、私の生涯が凝縮している。私の、その時々の心や行いが、余すところなく、刻まれていた。それらが映像と成って、鮮明に、映し出されたのである。 |
|||||||||||
|
だが、それらの映像は私の理解する自分の姿とは掛け離れている。私は反射的に、その映像を自分では無い、と否定した。そして、私の自分への理解が正当である証を記憶の中に、探し始めた。だが、冷静に、自分の記憶を辿ってみると、私の理解する自分の姿は其処には、見えない。全ての記憶は鏡の示す私が本当の自分である事を示したのである。私は鏡を睨み付けたが、私の負けは明白である。私は鏡の自分に恐れを感じて、思わず知らず、眼を反らした。そして、何故か、額の縁へと、視線を移した。と、其処には、文字らしきものが見て取れる。果たして、何と、書かれているのか?私は恐る恐る、近付いて、眼を凝らした。すると、其処には、「閻魔」の文字が鋭い筆跡で、刻まれている。気が付くと、辺りには、地獄の業火が燃え盛っていた。 |

| ||||||||||
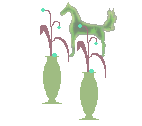
|

目次へ戻る |

| |||||||||
|
Cotosiro | |||||||||||