|
進化は偶然か、必然か?それとも? 進化とその意志? This was written in Japanese on December 4, 2013. And, it was translated into English on December 7, 2013. html言語を修正しました。野口博正/Noguti Hiromasa |
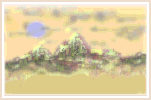
"To English Edition" |
||||||||||
|
さて、進化は偶発的な事象でしょうか?それとも、必然的な事象でしょうか?あるいは、この問いかけは、ある観点から見るならば、たいした問題ではないのかも知れません。ですが、少なくとも、私にとっては、考慮する価値は十分にあります。私は生物の進化、と言うものを、生物学的見地だけではなく、社会科学的見地、心理学的見地、また、哲学的見地からも、考察しました。その事に付いては、言葉の足りない部分はあったものの、一応、文明と生体 において、述べております。また、その様な考察に於いて、偶然と必然への考察も必要でしたが、この部分に関する説明は全く、欠落しておりました。 そして、この欠落は重大であった様に思われます。その所為で、私の考え方が旧来の生気論と同様である、と言う誤解を生みかねない、と言う事に気が付いたのです。無論、私の考えが生気論と全く、無縁かと、問われるならば、おそらく、そうでは無いのでしょうが、私は生気論者ではありません。私は、自分の進化への理解が唯物的な理解と先の生気論とを止揚した所に位置する、と考えております。物質と精神はある事象の二つの特徴であり、密接不可分なものである、と考えるからです。つまり、認識が成立する為には、認識する者と、認識対象が必要である、と考えるからです。また、言わずもがなではありますが、その関係は因果関係や論理的な順番で論ぜられるべきものでもありません。 |
|||||||||||
|
そこで、以下では、その関係への私の理解に基づいて、生物の進化が偶然の積み重ねの賜であるのか、あるいは、必然的な現象であるのか、について、また、主観としての生体について、考察する事と致しました。あるいは、以下に述べる見解は生物学の範疇を逸脱したものであるのかも知れません。ですが、私はこの考察が生物を、ひいては、人間を理解する上で、避けては通れぬ哲学的な意味を持つ、と考えております。なお、客体としての生体については、欲望の対象、自然科学的研究の対象などとして、既に、馴染みのある概念ですので、此処で触れる事は致しません。 さて、近年の生物学に於いては、進化は偶然の積み重ねの産物である、と言う考え方が、少なくとも、日本では、優性である様に思われます。また、私の理解で、その考えを簡単に申しますと、「偶然に起こる遺伝子の変異がたまたま、周囲の環境とも関係で、生体に有利に働く場合には、その生物種は生き残る確率が高くなり、不利に働く場合には、その確率は低くなる、そして、遺伝子の変化と自然環境との関係で、淘汰されなかった種だけが生き残る、つまり、たまたま、変異した遺伝子が、たまたま、上手い具合に周りの環境との関係が、生体の成長、繁殖を妨げない様に作用するなら、さしあたり、その種は生き残る、従って、進化は偶然の積み重ねの産物である」と言う様な唯物論に根ざした思想である様に思われます。しかし、その様な理解が本当に進化の実態と合致するのでしょうか?? |
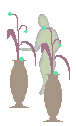
|
||||||||||
|
無論、この考え方のおおよそは、ある範囲に於いては、正しいのでしょう。しかし、無条件に、正しい、と言う事は難しいように思われます。本当に、進化を単なる偶然の産物と決め付けて良いのでしょうか? ちなみに、現在のキリスト教には、ダーウインの進化論と旧来の信仰とを両立させる考え方が産まれております。それは神の意志が進化を通じて、実現される、と言うような、どちらかと言えば、進化必然論的な考え方です。ただし、私の考えはこれとは少し違っております。 *其処で、遺伝子や生体を計算能力を持った一個の認識主体である、と考えてみましょう。無論、私はこの前提を妥当である、と考えております。ならば、遺伝子や生体の、進化に対する能動的役割についても、考えなければならないでしょう。無論、私も、進化に対する遺伝子の能動的関与の証拠が見付かっていない事、また、その様な能動的な働きを否定する研究結果のある事も、聞いてはおります。 * 注;無論、この認識主体の概念は唯一神の代用として、持ち出されたものではありません。これは認識主体とその対象の関係を重視する考えに基づく事をお断りしておきます。 |
|||||||||||
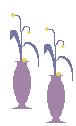
|
しかし、遺伝子や生体が自らが持つ情報を保全し、利用する為に、論理計算をする存在である事を考えるなら、おそらく、その機能は進化をもたらすであろう遺伝子の変異にも、何らかの影響を及ぼすのではないのでしょうか?特に、高等生物にあっては、遺伝子の数も多いので、その機能の発現については、それらの遺伝子同士の関係性のみならず、それらの遺伝子とそれらの遺伝子を持つ生体との関係性も、問題と成る様に思われます。ならば、遺伝子の働きが変異した遺伝子の活性化、あるいは抑制化に関わるだけではなく、遺伝子の変異そのものに関わる可能性を否定する事は間違いであるのかも知れないのです。進化を促す遺伝子の*偶発的(?)変異があった場合、先に述べた諸関係がその遺伝子の機能発現のみならず、遺伝子の変異を含む進化の全般に影響を与える可能性は相当に大きいのではないのでしょうか? また、この事は、「文明と生体 進化論への基礎的考察 4.生体に於ける変化のベクトル」を理解していただけるなら、容易に推測しうるように思われます。ともかく、進化に関しては、その様な、遺伝子や生体、そして、外部環境との相互関係について、もう少し踏み込んだ研究が必要であるのかも知れません。 |
||||||||||
|
* 注:「遺伝子の偶発的(?)変異」に添付された「(?)」はその人間の視点、あるいは、世界観によっては、「遺伝子の必然的変異」と表現される可能性もあり得る、と言う意味で、付加されました。 また、主観としての生体については、主として、「文明と生体・進化論への基礎的考察・10自我についての補足説明http://cotosiro.image.coocan.jp/ev10-r.htm」において、自我の実在についての私の見解を述べております。もし、その論理を理解されるなら、生体の自我は実在し、また、その生体を構成する全ての細胞や各器官の自我も存在する、と考える事が出来るでしょう。そして、それらは全てが自己の目的を持っており、その目的を達成すべく、論理計算を行います。そして、それは、遺伝子についても、言えますし、一個の生体についても、言える事です。 |
|||||||||||
|
ならば、遺伝子の変異が偶発的なものである、と仮定するとしても、その様にして変異した遺伝子への、他の遺伝子や生体の反応はおそらく、その生体内で行われる論理計算に基づいております。そして、その様な論理計算はおそらく、その様な変異体の機能をどの様に扱うべきか、と言うような計算も、含んでおります。その計算結果が成功をもたらすのか、否かは、分かりませんが、それは必ずや、生体の進化にも、関わる筈です。ならば、その様な生体の変化は計算結果が具現した必然的変化、と言う事も可能なのです。 そして、この様な私の結論の根底には、自分には自我があり、意思がある、と考える者は他の生物にも、ひいては、路傍の石ころにも、自我がある、と考えねばならない、と言う理屈があります。 その理屈については、どうぞ、自我についての補足説明をご覧下さい。 また、偶然と必然に付いては、それらの概念を適用する際の諸条件、諸環境について、もう少し、注意深い考察が必要なように思われます。つまり、その様な諸条件、あるいは、諸環境を狭い範囲に限定するなら、進化は偶然の産物である、と言いうる現象が、その諸条件、あるいは、諸環境をもう一段、広げるなら、必然的な現象である、と言う事が可能となる場合が多く、あります。 |
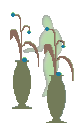
|
||||||||||
|
例えば、それは放射性物質の半減期を例に取る事が出来ます。ご存じの通り、一個の放射性元素は何時、崩壊するのか、正確な時期は分かりません。したがって、それは偶発的な崩壊でしょう。しかし、その元素が集まった放射性物質の塊が放射線を出して、崩壊して行き、半分になる時期は分かっております。ならば、その意味に於いて、その塊が半分に成る過程で起こる一個の放射性物質の崩壊は、その意味で言いますと、必然的な事象である、と言う事が出来ます。つまり、必然と偶然の概念は同一事象に於いても、視点によって、入れ替える事が出来る、と言う事なのです。つまり、私が言いたいのは、条件を付けずに、ある事象が必然であるか、偶然であるか、を問う事は無意味である、と言う事なのです。 この事については、昔、ホームページに載せた物語(陰の神話)の中で、考察しましたので、興味のある方は探してみて下さい。 さて、以上のような観点で、「文明と生体 進化論への基礎的考察 第四章」の数式を見て頂けるなら、そして、その全ての項に、概念設定のフレキシビリティーが在る事を理解して頂けるなら、そして、それらの項の相互の関係性を理解して頂けるなら、進化はある範囲では、偶然の産物である、と言えますが、もっと、範囲を広げると、必然的な現象である、とも、言えるのではないのでしょうか? また、この事は先ほど述べた自我についての考えた方に関連しておりますので、進化という事象を本当に理解する為には、全体は部分の単なる集合体ではない、と言う事を思い起こす事も、必要であるように思われます。部分の集合体である全体は部分が持ち得ない特性を与えられるからです。この事は一個の放射性元素とその集合体についての先の陳述を考慮するなら、科学的原因は異なるとしても、弁証法的な思考で、類推する事は可能でしょう。無論、この様な私の考えに否定的な人が多い事は想像出来ます。 |
|||||||||||
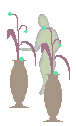
|
しかし、私の思考過程に誤りがあるとは思えませんし、誤りを見つけ出した人も居ないようなので、おそらく、その結論も間違ってはいない、と言う事でしょう。ならば、全ての現象はそれぞれのエゴを持っており、認識主体としての特徴を備えている、と考えざるを得ないでしょう。進化に限らず、全ての現象は認識主体とその対象との関係を考慮する事で、解明されなければば為らないのです。
なお、古代日本には、認識主体と客体との関係に関する哲学的な思想がありました。少なくとも、私はそう考えております。興味のある方は、「日本文化の源流・3−2・別天津の神の神性」、「日本文化の源流・5・神産霊神、高皇産霊神に見るサブジェクトとオブジェクト」などをご覧下さい。 |
||||||||||
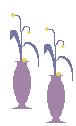
日本文化の源流" |
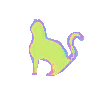
現なる夢" |
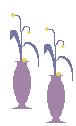
認識対象の正体" |
|||||||||
| Cotosiro Home | |||||||||||