| 日本文化の源流、その論理的帰結としての世界観 | 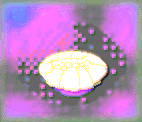 | ||||
| 修正しました。野口博正 December 18, 2011. 旧版 | |||||
|
神々に潜む縄文の精神 別天津の神の神性 |
|||||
|
日本書紀には、その一書として、静岡の御穂神社に関する、ひとつの神話が記されて居ります。その記事によれば、別天津神のひとつである高皇産霊神(タカミムスビノカミ)がある計画を建てて、御大津姫命を大物主命に娶せました。そして、この二つの神に、地に降りて、八百万の神々(国津神の事であろう)を治めるよう命を発した、と言うのです。 その目的は国土の隆昌(大和の治世に於いてである、と考えられる)の保全でした。其処でこのふた柱の神々は命に従い、八百万の神々を治める為に、その地に降り来たった、と言うのが、この神話の粗筋です。 ちなみに、別天津神は神々の基としての神々であり、神産霊神(カンムスビノカミ)、高皇産霊神(タカミムスビノカミ)、天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)の三柱があります。しかし、天之御中主神については、中国思想の影響が見られますので、日本古来の神であるのか、どうかは疑わしい、とも言われております。 ところで、先の神話の高皇産霊神は天尊族、すなわち、大和の至上神とも言われております。ならば、先の神話は少しおかしい、と感じられます。出雲系の国津神である大物主命と御大津姫命が天尊族の神の為に働いた、と言うこの記述は不自然の感を免れません。常識的に考えるなら、大物主命に命ずるべき神は、出雲族の至上神と言われる神産霊神である、と考えるのが自然ではないのでしょうか?高皇産霊神が命じた、とするこの記事には、何等かの作意が在りそうなのです。 記紀の編纂者は大和の政権を安定化しようとした藤原不比等、及び、太安万侶などである、と言われております。彼らは何等かの意図で、神産霊神が命じた、とされていた神話を高皇産霊神の話へと、すり替えたのかも知れません。あるいは、大和の支配が進む過程で、その様な変更が画策されたのかも知れません。そして、更に、高皇産霊神は神産霊神と同様に、出雲系の神であった事すら、考えられます。初めは、高皇産霊神を大和の側に奪い取り、その後、前述の神話までをも奪う為、この様なすり替えが策謀された、と考える事も可能です。ですが、実際は、どうなのでしょう?以下で、その答えに迫ります。 この二つの別天津神は共に、自然の発生原因と成る生成神、と言われております。言い換えますと、神々を此の世に発生せしむる権能を持つ神々です。古代人に取って、自然はまさしく、霊としての神々が体現をした姿であって、神々そのもの、と言っても過言では無く、この解釈は適正でしょう。つまり、このふた柱の別天津の神々はその様な古代人の意識、世界観から論理的帰結として見出された原理的な神々として理解が出来ます。 また、後に述べる理由から、この神々は縄文時代から祭られていた歴史的な神々である可能性を持っております。ただし、これらの別天津の神々はキリスト教などに見られる、全知全能の創造神とは全く異なり、あくまでも、神の国に座す神々をこの現世に発生せしむる、そのような権能しか持ち得ません。従って、本来、他の事で他の神に勝るものでも無く、その意味に於いては他の神々と同列である、とも考えられます。 また、アイヌの世界観から連想するなら、縄文人は全ての万の神々は神々の国に於いては永遠不変である、と考えていた様に思われます。言い換えますと、神々の国に坐す神々は動く事も感ずる事も出来ず、ただ存在をする存在である、という事でしょう。無論、縄文人が其処まで考えていた、とは言い切れませんが、永遠不変と言う事はあらゆる運動が存在しない事を意味します。つまり、神々の世界には、おそらく、時空はありませんので、少なくとも論理的には、その様な結論に達します。 その故に、神々は別天津神によって、此の世に送られて、初めて自らの神性に従って、活動をする事が出来るのでしょう。少なくとも、縄文人に取って、この現世は神々が自己を表現し得る唯一の場所であった、と考えられます。ちなみに、神々の序列化はその様な自己表現を疎外します。祟り神の発想はその辺りから生まれた様に思われます。 ところで、旧来の解釈に拠れば、「カンムスビ」と「タカミムスビ」はそれぞれ、「カン・ムスヒ」、「タカミ・ムスヒ」であり、「カン」や「タカミ」は単なる美称である、とされております。また、「ムス」とは発生の意味を持ち、「ビ」は「ヒ」の訛ったもので、「霊」の意味を表すそうです。つまり、「ムスヒ」は此の世での霊の体現を表します。 しかしながら、「カン」や「タカミ」を単なる美称として、全く意味を問わぬのは問題であるように思われます。意味の無い言葉などあり得ません。おそらくは意味が忘れられた、あるいは意図的に隠された、と考えた方が良いでしょう。つまり、「カン」や「タカミ」は極めて古い時代に使われた言葉であろう、と推測されます。ならば、このふた柱の神々の名前が縄文語で出来ている可能性も無しとはしません。そこで、縄文語に近い形態を持つと思われるアイヌ語の単語の中から、この神の名に近い音と意味を持つ単語を選択し、一応の解読を試みました。 すると、神産霊には、「Kamuy-mun-us-i」、あるいは、「Kamuy-mun-un-hi」と言う語句が当てはまります。無論、「Kamuy」は神を意味しており、「mun-us」は「mun-un」の複数形で植物などが群生をする光景を表現する動詞です。また、「hi」あるいは「i」は動詞、あるいは形容詞の末尾に付けられる時、その単語を名詞化します。 従って、この神の名は元来、植物が群生するかのように、この世界に多くの神々を出産する所、あるいは、神々がこの世に生を受ける状態、と言う意味合いであるように思われます。つまり、「カムイ・ムンヌヒ」あるいは「カムイ・ムンヌシ」は現象の起源を表現して居るように思われます。従って、この神の名称は以上のような意味合いを持つ縄文語の句が発展し、名詞化したものであるのでしょう。そして、この場合、動詞の終わりに付けられた「hi」あるいは「i」は動詞を名詞化しているので、それは抽象的な概念化であり、一種の魂を表現するようにも思われます。 また、同様の論理を高皇産霊に適用するなら、それは元来、「Tak-kamuy-mun-us-i」であった様に思われます。「tak」は一般的には、「言葉」と言う意味で使われますが、アイヌ語研究者の話では、その前提として、言葉を口に出す事で、この世界に霊的存在を呼び寄せる、と言うほどの意味合いも、隠されている、と言う事です。 アイヌの人々が常に、その事を意識していたか、どうかは、分かりませんが、そのような意味合いが、言葉を口に出す場合の、宗教的な、あるいは、哲学的な大前提であった様に思われます。従って、高皇産霊と言う神の名は神産霊を招く、あるいは、神産霊の能力を引き出す事を意味する様に思われます。 この事は「言代主」の称号とも相通じ、興味を引かれます。言代主命(コトシロヌシノミコト)は出雲系の言霊の神と言われており、言寄せを行うシャーマンの神格化である、と言う意見もあります。また、この神はイタコの原型とも思われますし、その名称もイタク と同様の意味を持ちますので、縄文的な色合いが感じられます。高皇産霊神は神産霊神と同様に元来、出雲系の神であった可能性が非常に高い、と言えるでしょう。 無論、以上の事は神産霊神と高皇産霊神が原初的には、神々(自然)を孕む女神と孕ませる男神であった可能性を否定するものではありません。しかしながら、先程も述べたように、縄文人の世界観には、その根底に、此の世にいる人間が言葉によって、神々、及び、自然と、魂の交流をする、と言う、いわば「tak」の思想、あるいは、言代の思想が流れております。つまり、現象を求める心が言葉(概念)と成る時、神の国から魂を呼び寄せて、その現象が現れるのです。また、その様にして現象をした神々も、観測者としての人間に語り掛ける存在でした。 これらのふた柱の生成神はその様な思想の為に、より抽象的な神々、すなわち、日本的な創造神へと進化した様に思われます。また、以上に述べたこのふた柱の神々の神性を見るなら、カンムスヒが生成の源、あるいは現象の場とすれば、タカミムスヒはそれを触発し、発現させる神である、と言う事が出来ます。ならば、高皇産霊神はある種の観察者、あるいは、認識主体であり、神産霊神を認知する事のできる唯一の存在であるように思われます。しかも、彼が行う認知は一般の人々が通常理解する一方的な認知ではなく、神産霊神を活性化させる機能を持っております。 つまり、高皇産霊神が行う認知は神々をこの世に現象させる触媒の様な作用を持っております。この事は素粒子論、及び相対性理論に於ける観測者とオブジェクト(波動)との関係とも重なります。つまり、これらのふた柱の神々は世界に於ける認識者とオブジェクトの役割、及び、その関係を表しており、また、現象(粒子)はその関係に於いて、はじめて成立する様に思われます。また、この詳細については、後で述べます。ですから、これらの神々はやはり、本来、一対でなければ、意味を為さない神々なのでしょう。 ならば、このふた柱の神々が別々の勢力、つまり、出雲と大和とに分かたれて祭られた、とする従来の説は怪しく成ります。おそらく、このふた柱の神々は何等かの政治的な理由で引き裂かれたのに違いありません。つまり、大和は何時からか、出雲系の至上神、高皇産霊神を自らの神として祭ったのでしょう。 そして、あの一書に於いて、神産霊神とのすり替えが画策された様に思われます。無論、それは大和がその神話を自らの神話に加えよう、として、画策した結果でしょう。出雲神話の多くの部分がこの様にして、大和に委譲されて、歪められたのではないのでしょうか?ならば、冒頭に述べた神話は元来、如何なる内容であったのでしょう?以下では、その謎解きを試みますが、その前に、御大津姫命、及び、大物主命などについて、その概要を述べておきます。 |
|||||
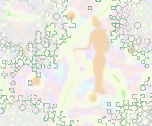
|
はじめに・日本の精神的諸問題 1.文化と文明 〜 生態系と民族 2.日本文化への基礎的理解 2−1.日本民族の形成 2−2.日本の言語 2−3.日本人の脳と日本の文化 3.神々に潜む縄文の精神 3−1.我々の精神の二重構造 3−2.別天津の神の神性 3−3.神々の変質 3−4.神々の里 3−5.恵比須の誕生 |
||||
|
4.縄文の世界観 4−1.縄文の世界〜利益と物々交換 4−2.縄文人の宗教観 4−3.「国産み」と「イタク 」の思想 4−4.我々に潜む世界観 5.神産霊神、高皇産霊神に見るサブジェクトとオブジェクト 6.認識主体から見る物理世界(固有の時間、主観的時間、客観的時間) 7.情報と認識主体 | |||||
| Cotosiro | |||||