|
改訂版 現なる夢 August 4, 2000 in Justnet. This was shifted to Nifty in November 19, 2003 and revised. This was revised in May 20, 2013. Hiromasa Noguti It is fixed "HTML" in February 14,2017/ 野口博正 |
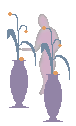 | ||||||||||
|
その一 姿 無 き 声 | |||||||||||
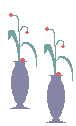 |
「果たして、どのくらい眠っていたのか?」私は夢の中で、ふっと、そう、考えた。冷たいものを顔に感じて、意識が少し、動いたのであるが、それはまだ、目覚めた、と言うほどの状態では無い。あるいは、覚醒と睡眠との狭間に居る、とでも、言うべきだろうか?夢を見ている、と言う事には、気付いているが、その夢の中の私はまだ、それが現実の様に思って、行動している、と言う、中途半端な状態である。私は、その様な状態で、「何故、この様に眠ってしまったのか?」と、言う疑問を感じたのである。無論、夢の中の疑問であるから、その様な疑問を持った理由ははっきりしない。ともかく、私はその疑問を解決するべく、自分の記憶を探り始めた。だが、奇妙な事に、それがどうも、上手く行かない。いや、それどころか、自分が何処で生まれたのか、何者であるのかすら、はっきりしないのである。私はその状況に狼狽した。そして、夢である事をすっかり、忘れて、必死に成って、記憶を探った。 | ||||||||||
|
だが、記憶はやはり、戻らない。幾つかの記憶の断片が無秩序に、脳裏に、浮かぶだけである。しかも、それが果たして、自分の記憶であるのか、どうかも、自信が無いのである。頭がどうにか、成ったのだろうか?この侭、時が経過するなら、自分の事は、永久に、想い出せないのでは無いのか、とすら、思ってしまう。私は絶望的な気分にすら、陥った。真っ暗な、だだっ広い牢獄に、一人、繋がれた様な感覚である。私は、「この状況から、逃れたい」と、切に願った。と、私の頭の片隅で、囁く様な声がした。「これは夢の中の健忘症では無いのか?」と、言うのである。私はそれを聞いて、ハッと、した。 確かに、自分は今、夢を見ている。ならば、その囁きは当たっているのかも知れない。「記憶が戻らないのは、夢の所為に違いない!なら、此処で、記憶など、探っていても、しようが無い」私はそう、考える事で、差しあたり、押し寄せる不安を回避した。だが、幾分かの不安は残されている。気分としては、まだ、眠っていたいが、精神の衛生を考えるなら、この場合、目覚めた方が良いのかも知れない。私はむずかる自分に、「目覚めるように」と、促した。 だが、躰の方はまだ、極度の疲労を訴えて、起きたくは無い、と言っている。そして、気分はやはり、眠っていたい。私は、「どうしようか?」と、思案した。考えてみると、これは夢の中の健忘症であるから、おそらく、目を覚すなら、何時でも、記憶は戻るのである。ならば、慌てて、起きる必要も無いのだろう。もっと快適な別の夢にでも、入り込むなら、健忘症の問題なども、起きない筈だ。私は安易に、そう、考えると、まどろみの中で、別の夢を探し始めた。だが、事はそう、上手くは、運ばない。私の意識は、眠ろう、とする意思に逆らって、現実へと向かって、浮上を始めた。起きようか、眠ろうか、別の夢でも、探そうか、などと、あれこれ、思案した結果、意識が活性化したものと思われる。無論、無理に、眠る必要も、無いのだが、夢の中の私は何故か、眠る事に、固執している。それで、私は、と言っても、どの自分であるのかは明確では無いが、覚醒に向かう自分を叱咤しながら、まどろみに留まろう、と、やっきと成った。 だが、その叱咤が逆効果である事は明白である。意識は益々、活性化して、睡魔は急速に萎んで行った。すると、どうした事か?背中や肩に、ごつごつとした不快な感触が伝わってくる。そして、スウスウとした寒さも、肌に感じる。こう成ると、さすがに、眠ってなど居られない。私はふっと、仰向けに成ると、渋々ながら、目を開けた。と、あり得ぬ光景が其処にある。青っぽい闇の直中に、三日月がぽっかりと浮いていて、青白い光を放射している。だが、これは、果たして、どういう事か?屋内にいるもの、とばかり、思っていたので、すぐには、状況が飲み込めない。私は仰向けに成った侭、ただ、呆然と、月を見つめた。 | |||||||||||
|
辺りには、雑草やすすきの類いが私を覆い隠すかの様に、繁茂している。風に揺れる、その様がまるで、幽霊の手招きの様に思われて、薄気味悪い。ひょっとすると、此処は悪霊の住む原野であろうか?自分は何故、此処に居るのだろうか?何処から、此処に、来たのだろうか?私は様々な疑問に捕らわれて、記憶を辿ろうとするのだが、頭がぼうっとして、想い出せない。ただ、長い事、旅をしていた様には、感じるのである。それにしても、津波の様に押し寄せるこの疲労感は普通では無い。旅の途中、ついに、此処で、力が尽きて、倒れ込んだ、と言う事だろうか?だが、その様な覚えなど、まるで、無いのである。「ひょっとして、これも、夢の、続きなのか?」私はふっと、そう、自分に問うた。 だが、おそらく、そうでは無いのだろう。「最前の夢は、この事の予感だったのに違いない」と、私はそう、理解した。そして、仰向けの侭、眼だけをぐるりと、動かして、辺りの様子を眺め回した。だが、生い茂るすすきや灌木が邪魔をしていて、視界は殆ど、利いてはいない。周りの様子を知るのには、起き上がって、確認するしか、無さそうである。躰はきついが、私は立ち上がろう、として、首を擡げた。と、その瞬間、眼前に垂れ下がるすすきの葉から、突然、夜露が滴った。そして、一直線に、顔面へと向かって、落下して来る。私は咄嗟に、避けようとした。だが、間に合わず、夜露はそのまま、額に当たった。そして、ツーッと、流れると、眉から頬を伝わって、拭う間もなく、地面に落ちた。その感触が何故か、悪しき予感を抱かせる。私は思わず、躰を起こした。 |
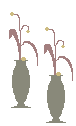
|
||||||||||
|
それにしても、何と、寒々とした風景だろうか?立ち上がって、遠くを見ると、見渡す限り、すすきや雑草に覆われた荒々しい原野が広がっている。私はその風景をただ、ぼうっ、として、見つめ続けた。と、私の脳裏に、此処と同じ風景が蘇った。「そうだ、俺は此処を歩いていたのだ!」私は記憶が戻った事に歓喜して、思わず、声に出して、そう言った。 この原野に入ってからというもの、私は何も口にせず、眠る時間すら、惜しみに惜しんで、ひたすら、此処を歩いたのである。だが、私は何処から、此処に来て、何処に行こうとしていただろうか?残念ながら、その記憶は未だに、霞の彼方へと隠されていて、輪郭すらも、見えては来ない。おそらく、それはこの原野の魔性の為せる業なのだろう。今、すべき事は意識を曇らせるこの原野から、一刻も早く、抜け出す事なのに違いない。そうする事が出来たなら、おそらく、行くべき場所も、想い出す事が出来るのだろう。「だが、どちらに、向かえば、良いのだろうか?」どちらを見ても、原野は殆ど、同じ光景が広がっている。目標にすべきものは見当たらない。考えあぐねた私は差しあたり、風下に向かって、歩き始めた。風上よりは風下に向かう方が楽だからである。だが、妙な感じだ。この一連の思考と、行動は以前、体験した様にも、思うのである。「あるいは、何回も、同じ事を繰り返しているのかも知れない」私はふっと、そう、考えた。すると、何故だろう?ひもじい想いや人恋しさが心の底から、吹き上げる。そして、最前、目覚めた時に感じた酷い疲れが数倍にも成って、私を襲った。足が自然と、止まってしまう。「もう、歩けない、俺は此処で、死ぬのだろうか?」私はつい、弱音を吐いた。 だが、それは余りにも、理不尽な結論だろう。「私には、行くべき所が必ず、ある、其処に、辿り着くまでは、何が何でも、生きねば為らない」私は疲労し切った自分にそう、命じると、重い足を引き摺る様に、前屈みと成って、歩き始めた。最前から吹いていた冷たい風がしきりと、背中に吹き付ける。湿り気が少し、増している。「これは嵐の前触れだろうか?」私はつい、しかめっ面で、天を仰いだ。だが、雨雲などは出ていない。「どうも、妙だな?」私はふっと、呟いた。と、突風が前方から吹き付けた。どうやら、風向きが変わったらしい。私はその刃物の様な冷たさに、思わず知らず、顔を背けた。と、何故だろう?その間隙を突くかの様に、恐ろしい幻影が脳裏を過ぎる。真実を見せまい、とする悪鬼や魔物、虚無への誘惑を語る物の怪達、その忌まわしい記憶の数々が現の様に、脳裏を巡る。「そうだ、想い出した、私は魔性のものと戦って、あるいは、逃れて、ようやく、此処まで、やって来たのだ・・だが、この先は?」私は旅の目的を探ろうと、蘇った記憶を辿ろうとした。だが、無情にも、記憶はすぐに、途切れてしまう。「おそらく、何時も、こうだったのだ・・」私は萎えた様に、大地に座ると、両の掌をジッと、見つめた。 時折、背後から、吹く風が嘲笑う様に思われる。あるいは、それは、他人が造作も無く、気付く事に、気付く事が出来ない愚かな自分の所為かも知れない。だが、嘲笑う者は嘲笑てくれて、構わない。それはあえて、甘受する。嘲りは嘲る者の知性の限界を示すからだ。まあ、そんな事など、どうでも良い。大事なのは、自分にしか、知り得ない事も必ず、ある、と言う事だ。私はそれを探す為に、此処まで、この様に、旅をし続けて来たのだろう。記憶はまだ、所々しか、戻っていないが、私には、そう思われる。私は再び、立ち上がって、歩き始めた。と、背後に、何者かの気配を微かに感じる。私はふっと、振り向いた。だが、目に入る物は、寒風に煽られるすすきや灌木、雑草の類いだけである。「錯覚か?」と、私は何故か、がっかりとした。 | |||||||||||
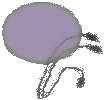 |
すると、その時、私の背後で、囁く様な声がした。「あきらめてはいけない、お前が負けた、と言わぬ限りは、お前は敗者ではないのであるから」と、言っている。私は声のする方を振り向いた。だが、姿は見えない。「神だろうか?」私は一瞬、その様な期待を胸に抱いた。だが、不幸にも、私は神、と言うものを、殆ど、知らない。産まれて、この方、神とは、ずっと、疎遠であった。悪鬼や魔物、物の怪の類いにしか、会ってはいない。素直に、神の存在を認める事は難しかった。だが、「あの声の主が神であるなら、ひと目なりとも、姿を見たい」とも、思うのである。「どうせ、魔性のものの陰謀さ」と、囁くねじ曲がった自分も、其処には、居るが、私は声の主を探し始めた。
だが、月は厚い雲に覆われていて、夜の闇は深まっている。風も、冷たさを増している。これが嵐にでも、成ったなら、神を見つける事は難しい。「千載一遇のチャンスなのに、何故、何時も、こう成る?」私はこの状況に、焦りを感じた。そして、疑心暗鬼が頭を擡げた。「これは魔性のものの仕業だろうか?きっと、そうだ!私を神に会わさぬ様に、邪魔しているのに違いない!いや、あの声自体が魔性のものの声色なのだ!」ふと、気が付くと、私の心はその様に錯綜する様々な疑心に満たされて、恐ろしい迷宮へと、踏み込んでいた。そして、私はその迷宮で、「物の怪や神など、居ないのだ、それは想像の産物だ」と言う、もう一人の自分にも、遭ってしまった。その意見は妙に、魅力的に、思われる。私はたちまちの内に、その思考回路に捕らわれた。 | ||||||||||
|
「そうだ!あの荘厳なる声も、神への憧れが産み出した幻なのに違いない、今まで、現れた物の怪や魔物も、恐れの念が産み出した幻なのだ、いや、此処にこうしている私すら、本当は、幻なのかも知れない」私はつい、その様な自己否定の極限にまで、達してしまった。だが、反面、「それは本当に、正しいだろうか?」とも、思うのである。
私が無味乾燥な、そして、時として、不気味さを漂わせる、この荒野に迷い込んだのは、確か、数十年ほども、前の事だった。そして、この原野をどうしても、抜け出す事が出来ずに、ぐるぐると、同じところを彷徨ったのである。だが、私はその間、人はおろか、虫の姿すら、見なかった。言い知れぬ恐れ、救いを求める心、そして、人恋しさが募るのも、当然の結果ではあったのである。その為に、敵対者としての魔物、物の怪を気付かぬ内に、実体として、産んでしまった。それで、私は、魔性のものや、この殺伐とした原野から守ってくれる神の存在を希求した、のではないのだろうか?だが、不幸にも、神は実体には成らなかった、のでは無いのだろうか? |
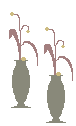
|
||||||||||
|
だが、迷宮を更に歩むと、違った道筋も、見えて来る。此処が、いわゆる現世でない事は確かである。ならば、この世界では、声は声として、存在していて、身体は身体として、存在している、のかも知れない。ならば、幻聴であろうと、無かろうと、最前、神の声として、聞いた言葉の意味内容は、厳然として、此処に、存在している、と考えなくては為らない。素直に、それを受け入れるのか?あるいは、虚偽として、拒否をするのか?おそらく、その判断は自分の選択に委ねられるのである。「自分はきっと、その判定を行う為に、長い旅を続けたのに違いない」と、私は一瞬、確信しかけた。「だが、これ以上、歩き続けて、この先、一体、何がある?」とも、思うのである。疲労感の所為であろうか?私は再び、迷宮の奥へと迷い込むと、虚無へと、向かって、歩き始めた。 と、それを引き留める者がある。最前、聞こえた荘厳な声が抑えた声で、呼び掛けた。「何がある、だと?無意味な問いなど、してはいけない、その問いは自分を迷わせるだけである、今、自分が生きている事を自覚しなさい、お前が今、何を見て、何を感じているのか、と言う事が、此処では、最も、重要なのだ」だが、私には、意味するところが分からない。「エッ、先行きを考える事が無意味ですって?どういう事です?あなたは一体、何者なんです?」私は反射的に、そう問うた。と、声の主が何かを語る。だが、聞き取れない。怪しい突風がやにわに吹いて、その声を掻き消すからである。「何故、神の声は小さいのか?」私は少し、不満に思った。だが、産まれて、この方、聞く事の出来なかったこの声を、微かとは言え、今、ようやく、聞く事が出来た様にも、思うのである。この感覚が正しいならば、辛酸を嘗めた過酷な旅も、無駄ではなかった、と言い得るのでは無いのか?半信半疑ではあるものの、私はその様な考えに行き着いた。そして、「何としても、声の主の真意を知りたい」と、言う強い衝動にも、捕らわれた。 だが、突風は更に、嵐を呼んで、凄まじい渦を成して、我が身を攻める。時折、唸る風音が魔物の咆吼の様で、恐ろしい。「私を神から遠ざけよう、と、魔性のものがやって来た」此処に至って、私はそう、確信した。そして、この確信は、少なくとも、私にとって、神や魔物や物の怪が実在である事を明示している。「だが、神を信じ切る事は、出来るだろうか?」私はそう、自問した。今まで、神は私を助けよう、とはしなかった。少なくとも、私が知る限りでは、そうであった。神の意図は知らないけれども、おそらく、今回も、そうなのだろう。神の声は聞き取りたいが、魔性のものはすぐ、側にまで、迫っている。そして、私は躰も、心も、疲れ果てている。もし、この状態で、魔性のものに遭遇するなら、戦う事はおろか、逃げ切る事すら、難しい。「早く、この場を離れなくては!」私はそう、決断すると、声の主に別れも、告げずに、荒れ狂う荒野を走り始めた。 それにしても、何処に、この様な気力が残っていたのか?自分の事ながら、不思議である。だが、それは今の自分にとっては、幸いであった。この侭、此処に留まって、魔性の嵐に晒されるなら、恐ろしき幻影を見ねば為らない。ついには、魔性の虜と成って、虚無の世界へと落ちるのである。たとえ、体力を使い果たして、私の肉体は滅ぶとしても、虚無に陥る事は避けねばならない。虚無は究極の孤独であって、究極の地獄に他ならないのだ。私は魔性の世界を知ってからというもの、何時も、慎重に振る舞って、魔性のものから身を隠したが、魔性のものは、その都度、目ざとく、私を見つけて、恐ろしき世界へと、追い立てた。そして、皮肉っぽい口調で、「見よ!その惨めで、恥ずかしい自分の姿を!もう、楽に成る方が良くは無いのか?命は有限なんだから」と、私をあざ笑った。そして、「今の地獄から逃れたいなら、本当に、平安に暮らしたいなら、虚無へと入れ」と、命じたのである。 |
|||||||||||
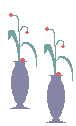
|
だが、虚無へと落ちて、平安な生活など、あり得ない。今も確かに、地獄だが、少なくとも、その地獄はしっかりと、認識出来る。地獄を認識出来るから、平安も理解する事が出来るのだ。もし、認識そのものの無い虚無の世界に、我が魂を投じたならば、地獄も平安も、認識出来ない。それは完全なる死、我が魂の消滅である。そして、それは私の世界の消滅でもある。私は自分と世界をその様な虚無から守る為に、この様な過酷な旅に出たのだろう。 だが、今、魔性のものは再び、神から私を遠ざけた。私をして、神が無い、と思わせるほど、追い詰めたのである。そして、今、魔性の嵐は猛り狂って、私を跪かせよう、と目論んでいる。だが、その様な策略に負けては為らない。たとえ、飢えで死のうとも、我が認識を守る為には、何としてでも、逃げ切らねば為らない。「だが、どちらへ逃げたなら、良いのだろうか?」魔性の嵐は今、四方、八方から、襲うのである。今まで、経験した覚えのない身の凍る様な凄まじさである。私は焦る気持ちを堪えつつ、疾走しながら、荒涼たる原野に希望を探した。と、少し、前方の闇に、樹木に覆われた小山が見える。それは霞の掛かった半円形の神秘に満ちた小山であった。「そうだ、あそこに逃げ込もう!」私は凍える手足を叱咤しながら、その小山へと向かって、荒野を走った。 | ||||||||||
|
だが、その間も、嵐は私に纏わり付いて、悪しき幻影も脳裏を過ぎる。そして、それらの幻影はあたかも、現実であるかの様に、私の行く手に、立ちはだかると、幻魔の姿を顕して、私の足を竦ませた。だが、此処で怯んで、留まれば、幻魔は必ずや、実体と成り、我が魂を襲うだろう。「走るのだ!」私は怯える心を叱咤して、そのまま、原野を走り続けた。実体と成ろうとする幻魔のさなかを蛮勇を以て、突き切ったのである。そして、脱兎の如く、森の中へと、転がり込んだ。ふと見ると、ひときわ、大きな杉の根本に丁度、手頃な烏鷺(うろ)がある。嵐を避けるのには、最適である。私は嵐に追われるままに、急いで、烏鷺へと、転がり込んだ。 凍て付く嵐が木の葉を揺すって、魔物の幻も木々を掠める。一瞬の内に、木の葉が凍って、引き千切られて、虚空を舞った。「果たして、この烏鷺は安全なのか?」もし、凍て付く風が直撃したなら、たちまちの内に体は凍って、氷に閉ざされて仕舞うだろう。疑心と不安と恐れとが心を執拗に、締め付けて、針の様に苛み続けた。魔物の咆吼が嵐に乗って、森の空気を震わせている。私は烏鷺の奥底で、躰を縮めて、恐怖に堪えた。 だが、何故だろう?凍てつく嵐は森を襲って、吹き飛ばさん、と、猛り狂うが、烏鷺は依然として、暖かく、私は未だ、無事なのだ。私は氷結して行く森を目の当たりにして、その状況に戸惑った。多くの森には、其処を守護する精霊が住む、と聞いた事はある。「ひょっとしたら、私が今、無事なのは、この森に住まうであろう精霊の、善なる力の賜なのか?」 | |||||||||||
|
だが、私はその様な精霊に遭遇した事は、一度も無い。私にとって、確かな事実は、「烏鷺に隠れている限り、私はどうやら、無事である」と、言う理由の分からぬ現実だけであり、精霊はあくまでも、想像上の産物である。ただ、事実を事実として、受け入れて、その結果も、また、同様に、受け入れる。それが今までの旅の、明瞭に認識出来る唯一とも言える成果であった。
いずれにしても、怪しい嵐は今、その力を弱めつつある。同時に、悪しき幻影も次第に、薄らぐ様に思われる。私はふっと、魔性の嵐が悔しげに呻くのを、聞いた様に思った。そして、その直後、恐ろしき嵐は急速に、力を失った。同時に、悪しき幻影も、何処かへ去った。気が付くと、森は夜の静けさに包まれている。樹木の香りが心地良く、私の心に染み込んで来る。安堵感と疲れとが、睡魔と成って、私を誘う。私は烏鷺の側壁に、意識するとも無く、身体を預けて、綿の様に、寝入ってしまった。 |
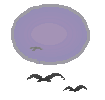
| ||||||||||
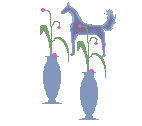
|

目次へ戻る |

その二へ続く | |||||||||
|
Cotosiro | |||||||||||