|
----- 改訂第三版 ----- 背後の世界 その1 狂気の手紙 December 18, 2015. 野口博正. |
To Old edition
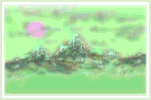
その二 克夫の生い立ち |
||||||||||
|
平成11年(西暦1999年)8月10日:克夫については、いろいろと、考えさせられる事がある。というよりは、彼の言動が、そして、彼から送られて来た、あの意味不明な手紙の内容が、妙に心に引っかかるのである。どうしても、単なる狂気の産物とは思えない。そこで、私は、今日、彼について湧き上がる疑問や彼に関する認識の変化を、その都度、書き記す事に決めた。ここに至るまでの克夫の歴史を辿りながら、彼が何を考えていたのか、探ってみたい、と思ったのである。 今から、二年ほど前、旧友の蛭田克夫から手紙が届いた。それは冒頭に述べたあの意味不明な手紙である。だが、彼とは、高校時代からの付き合いではあったものの、就職してからは、数回しか、会っては居らず、ある時期からは、手紙のやり取りも、途絶えていたので、思いも掛けぬ便りであった。「何故、今に成って、手紙など、寄越したのか?」と、私は少し戸惑った。しかも、受け取った手紙を開いてみると、それはあり得ぬほどに、長大であり、その内容も、随分と、常軌を逸している。冒頭でも少し触れたが、彼は今から、四年ほど前、精神を病み、ほぼ三年間、札幌のとある病院で、療養していた。 療養していた、と過去形にしたのは、彼が既に、この世のものではないからである。一年ほど前、恐ろしい嵐が札幌を襲った。時は夕刻、院内の患者らは、皆、食堂におり、何時もの、夕食を取っていた。その日はクリスマスの前日であったので、食堂には、クリスマスツリーが飾られている。多くの患者からは、幾分、華やいだ様子も窺えたのだが、しばしば、鳴り響く雷鳴に、不安げに、辺りを見回す患者も、そう少なくは無かった。そして、克夫も、その一人であったらしいが、彼の態度は他の者とは、少し違った。 |
|||||||||||
|
ある看護師が医者に報告したところでは、彼は動揺する患者らを横目に、ただ、黙々と食事を取っていた。だが、その背中からは、重圧に耐えてでもいるかの様な、あるいは、動揺した姿を見せまい、とするかの様な、その様な意思も感じられたらしいのである。克夫には、昔から、そういう所があった。喧嘩や競争を嫌う彼ではあったが、one of themと言う立場に置かれる事は酷く嫌っていたのである。私はその様な克夫の有様を医者から聞いた時、思わず、「克夫はまだ、死んでは居ない」と、心の中で呟いた。 おそらく、他の患者と一緒で、内心は、動揺していたのに違いない。あるいは、克夫は他のどの患者よりも、緊張していたのかも知れない。おそらく、押しつぶされそうな恐怖と戦っていたのだ。恐ろしい嵐は吹きすさび、大粒の雨を食堂の窓へと叩き付ける。窓硝子が割れんばかりの、弾丸の様な勢いである。食事を終えた患者らは、逃げる様に、次々と、自分の部屋へと戻って行った。窓の向こうで、閃光がきらめく。そして、直後に、恐ろしい雷鳴がとどろき渡った。相当、近くに落ちたらしい。院内の照明が、一挙に消えた。 |

|
||||||||||
|
患者らも、看護人らも、思わず、躰を硬直させて、窓の外を凝視する。患者らが少し、ざわめきはじめた。良い状況とは言い難い。看護人の一人が、側にある受話器に手を伸ばした。と、やにわに証明が回復した。どうやら、ブレーカーが飛んだだけであったらしい。看護人らは安堵して、食堂いる患者達を見回した。と、床の上に、患者が一人、倒れている。その脇には、空に成った食器や箸、トレーなどが散らばっていた。倒れているのは克夫である。彼は、懸命の救護処置にも拘わらず、その日の内に、逝ってしまった。
奇妙な事だが、その死因は余り、はっきりしない。結局、極度の興奮による心臓麻痺として、処理された。だが、今、考えると、「それは表層的な見解に過ぎないのではないのか?もっと、奥深い心霊的な死因があるのではないのか?」と言う様な、怪しげな疑念も頭を過ぎる。ひょっとして、これは私が、あの長大な手紙に、何らかの真実性を感じ始めている、と言う証左だろうか?いずれにしても、この謎は解かねばならない。私は今、そう考えている。 数年前、私は東京の会社を辞めて、札幌に戻った。その前年、頑健であった筈の父が突然、倒れて、呆気なく、この世を去ったからである。とは言っても、最初から、そのつもりであった訳では無い。父の葬儀を終えた三日後には、東京の自宅へと戻っていた。しかし、夜、床に就くと、葬儀の折に、ふと、垣間見たやつれた母の横顔がしばしば、脳裏に現れる。母は病弱であった所為か?何時も、父を頼りにして、生きて来た様なところがあった。「一人にしておくのは、、問題かもしれない」と、事ある毎に、考える。其処で、ある日、妻に相談すると、早速、母に電話した。「東京で、一緒に暮らそう」と、誘ったのである。だが、母は、「北海道からは、離れたくない、お墓もあるし、此処で暮らす」と、言って、受け付けない。仕方が無いので、その日は説得を棚上げにした。だが、いつまでも、札幌になど、置いておけない。様子を見ては、電話した。しかし、答えは何時も、同じであった。 「なら、どうすべきか?」私は少し、悩んだが、結局は、札幌での就職先を見付けて、しぶる妻を説得して、札幌に戻った。何に付けても、石橋を叩いて、渡らない性格の私が蛮勇を振るって、出した結論だった。 だが、あれは本当に、自分の決断だったのだろうか?私は今でも、その様な疑念に捕らわれる。突飛な様だが、克夫の念が私を札幌に引き寄せたのかも知れない、などと言うあり得ぬ妄想にすら、捕らわれる。 早く、この妄想から抜け出さねば為らない。また、その為には、克夫の事を知らねば為らない、とも思うのだ。これは、もはや、確信と言っても過言ではない。無論、この確信には、どの様な根拠も無いのだけれども、私はこの直感に従おう、と、考えている。無論、この事は誰にも、打ち明けられない。これは私だけの戦いなのだ。 | |||||||||||
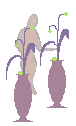
|
私は今、札幌の北東に位置する江別市に家を持っている。其処は閑静な住宅街で、妻の実家の近くでもある。騒がしい札幌の街よりは、江別の方が母も、落ち着けるのでは無いのか、と考えたのである。無論、これは妻の都合も考慮しての結論だった。そして、そんな折、克夫が精神病院に入院したらしい、と言う噂を耳にした。噂の真偽を確認すると、どうやら、それは本当らしい。私はその病院を確認すると、すぐに、病院へと駆けつけた。だが、医者は克夫が面会を拒否しており、精神状態も非常に不安定なので、面会は控えて欲しい、と言う。私は何故か、異物が喉につかえた様な気分と成って、家へと、戻った。 だが、彼との面会はそう簡単には、諦めきれない。彼の居る札幌の病院には、一時間ほどで、行けるので、私は彼の入院当初、何回か、病院を訪れた。しかし、病院の担当者は毎回、「彼は会いたくないそうです」と言って、面会させない。私は内心、「担当者の話は本当だろうか?」と、疑っていた。 | ||||||||||
|
けれども、ある日、私が病院を訪れると、たまたま、彼の母親に遭遇した。私が挨拶をすると、彼女は、唐突に、「私、これから、先生に克夫の病状を聞かなくては為らないんです」と、言って、私を見つめる。それはまるで、克夫の身に、重大な問題が起こった事を予感したかの様な顔付きである。私はその差し迫った顔付きに、負けて、「同席できるのなら、一緒に聞きましょうか?」と、言ってみた。すると、彼女は素直に提案を受け入れたのだ。私は彼女と一緒に、担当医から、話を聞いた。しかしながら、その時の私は克夫について、この様に書き綴る事に成ろう、などとは、想像すら、していなかった。 医師の説明によれば、克夫の病は心因性であるらしく、陽性型の分裂症であるらしい。だが、時として、鬱症状が現れる、と言う。日常生活での判断力については、辛うじて、保たれてはいるものの、奇妙な妄想に取り付かれており、極度の緊張状態にあるらしい。だが、その時、私の脳裏に、疑問が過ぎった。「あのう、日常生活の判断力がほぼ、保たれている、と言う事はそう深刻な病ではない、と考えて良いのでしょうか?」私はふと、気が付くと、医師にそう、問うていた。 だが、医者は首を振って言った。「いえ、彼の場合、日常生活での判断力と病の深刻さとに相関関係は殆ど、ありません」そして、医師は、「分かりにくいでしょうが、その様な症状である、と、ご理解下さい」と、付け加えた。医師の言う通り、それはイメージし難い事ではあったが、医師にそう言われると、「そう言うものかなあ」とも、思ってしまう。私も彼の母親も、何も言わずに頷いた。 すると、医師が私の方を向いて、ゆっくりとした口調で言った。「今は、もう、面会に差し障るほどの病状では無いのですが、心の病ですから、本人がああ言う以上、無理強いはしない方が良いでしょう」そして、「残念ですが、仕方ありませんな」とでも、言いたげに私を見つめる。自分としては、了解せざるを得なかった。そして、克夫の、私に対する、その様な姿勢は彼が亡くなるまで、続いたのである。 |
|||||||||||

|
その彼が何故、死が間近に迫ったその時、手紙を寄越す気になど、成ったのか?その事がやはり、無性に、気に掛かる。そして、最近は、手紙に目を通す度に、「彼の手紙には、何か、自分の気付かないメッセージが含まれているのでは無いのか?」と、感じるようにも成っていた。しかし、その反面、「手紙にしたためられた狂気に、惑わされつつあるのではないのか?手紙を読むのはもう、止めよう」と言う気分にも、陥ってしまう。私はその様な気分に陥る度に、例の手紙を摘み上げると、机の引き出しの一番、奥に、こそっと仕舞った。だが、二、三日、経つと、その手紙は再び、机の上に戻っているのである。無論、それは手紙が勝手に動いたのでは無い。私が引き出しから、取り出したのだ。だが、気分としては、それは決して、私の意思では無かったのである。ひょっして、私もまた、何かの狂気に取り憑かれたのか?それとも、克夫の狂気が乗り移ってでも居るのだろうか? 実は、手紙を受け取った前日の早朝、私は克夫の夢を見た。私が出勤しようと、家を出ると、若い頃の克夫が門の所に立っている。そして、私をジッと、見つめた。「おっ、克夫、どうしたんだ?」私は思わず、声を掛けた。だが、彼は顔を俯けて、何も言わない。私はその態度に、「本当に、克夫なのか?」と、不審に思った。そして、咄嗟に、克夫の方に歩み寄った。すると、克夫がふっと、消え失せた。そして、私は目覚めたのである。 |
||||||||||
|
実に、短い夢ではあったが、その印象は心の隅に、鮮明な映像として、焼き付いている。私はその時、何故か、その鮮明な印象に戸惑っていた。しかし、その日は仕事が忙しかった。あれこれと、考えている余裕など、ある筈も無い。私は様々な疑念を追い払い、仕事に自分を集中させた。そして、克夫の事など、すっかり、忘れて、仕事に奔走した。だが、夜、帰宅すると、克夫からの例の封書が届いていた。妻が、「これ、届いていたわよ?」と、言って、渡してくれたのだが、私はその封書を手にして、宛名書きを見た瞬間、やおら、不吉な予感に捕らわれた。 「あの夢は克夫の身に何かが起こった、その知らせなのかも知れない」と、思ったのである。私の顔色が変わったのを察知したのか、妻が訝しそうに私を見る。だが、自分さえ、はっきりしない不安であるから、説明など、出来る筈も無い。私は妻には何も話さず、すぐに、克夫の居る病院へと電話した。 だが、「病状に変化はありませんか?」と、言う私の問いに、病院の職員は、「いいえ?別に?」と、にべもない。私は、「もう少し、丁寧な説明は出来ないのか?」と釈然としない想いにも捕らわれたが、しつこく聞くと、妙な誤解にも、晒され兼ねない、と考えたので、「あ、それは良かった、では、失礼します」と、言って、電話を切った。 「けど、さっきの答えは本当だろうか?」私は遅い晩飯を食べる内、良く無い想像に捕らわれはじめた。克夫の身に何かが起こっている、様な気がして、仕方が無いのである。だが、不吉な事など、あっては為らない。「考え過ぎだ、手紙を書く気に成ったのだから、症状は改善に向かっているのに違いない」私は、無理矢理、その様な、希望的観測に従った。それにしても、手紙の内容が気に掛かる。私は机に向かうと、問題の手紙を取り出して、封を切った。 だが、読み始めると、文字は殴り書きの様に、乱れに乱れて、文章の脈絡も、定かではない。病状の程がうかがい知れる。「これでは、改善しているとは言えないな、この手紙は狂気の故の、単なる気まぐれかも知れない」私はそう、呟くと、ふっと、手紙から目線を外した。そして、少しの間、机上の一点をぼうっと、見つめた。彼の心の壊れる様が脳裏に浮かんで、心が揺れる。私は手にした書面を封筒に戻すと、心なし震えている手で、机上に置いた。 |
|||||||||||
|
しかし、彼がどの様な状態にあったとしても、私にこの手紙を書いた、と言う事実は受け止めなくては為らない。手紙は彼の私への友情が残っている事の証の様にも、感じるのである。彼なりに、何かを思い付いて、それを伝えたい、とでも、考えたのか?それとも、正気であった時の残像が、そうさせたのか?いずれにしても、読まずにいる事は出来なかった。気分は重いが、私は再び、手紙を手にした。読むのには、かなりの辛抱が必要だったが、かろうじて、読み取れた部分を解釈すると、その内容はほぼ、次の様なものだった。 「俺はある秘密を知ってしまった。意図した訳では無かったのだが、その様な羽目に陥った。それはサタンの陰謀についてだ。だが、此処の連中は唯物論者ばかりで、俺の話など、信用しない。はっきりとは分からぬが、サタンの手先もいるようだ。それで、君に会う事も躊躇した。いや、本当の事を言おう。実を言えば、自分が会社を辞めてから、君と会うのを避けたり、君に手紙を書かなくなったのも、その為だった。俺はその当時から、サタンの手先に見張られていたんだ。君に迷惑は掛けたくなかった。 だが、事態は今、切迫している。いろいろと、考えたんだが、君に頼らざるを得なかった。俺は直に、死ぬであろうが、君にだけは、分かって欲しい。俺の意志を継いで欲しい、と、そう考えて、筆を執った。 |
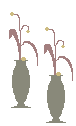
|
||||||||||
|
神は自らに対する自らの認識を欲して、世界を作った。つまり、認識者としての神には、自己を自己として認識させ得る認識対象としての自己が必要だった。その故に、神は自分自身を世界として、つまり、宇宙という物理的存在として、実現させた。そして、その運動を観察する事で、自らの認識を得ようとしたのだ。 しかし、それは思わぬ副産物をもたらした。神が自らを正当なる存在者として、認識する為には、比較をすべき存在が必要となる。つまり、その対極にあるべき不当なる存在、すなわち、世界の生成に伴う副産物であるサタンが産まれた。 おまえは仏教徒だから、知らぬと思うが、聖書には、ある天使が神に反逆し、サタンに成った、と記されている。それは実は、この事を指している。神が世界を作った瞬間、同時に、神の精神的認識対象としての、敵対者、つまり、サタンが現れたのだ。その為に、世界は正当なる存在者、すなわち、神と、不当なる存在者、すなわち、サタンの、その間に生ずる矛盾によって、動かされる事と成ってしまった。その証拠は宇宙の中にも、そして、我々の心の中にも、見いだす事が出来る。 |
|||||||||||
|
無論、神はすぐに、その事に気が付いた、だが、世界を消し去る選択はしなかった、世界の消滅は神の認識が失われる事を意味する。つまり、一旦、認識を得、意識を持った神にとっては、それは神自身の消滅に他ならなかった。神はもはや、サタンを含む、認識対象たる世界無しには、存在し得ぬ存在へと変わっていたのだ。
そこで、神は理想という武器で、サタンに対した。正義と愛の為の、そして、平和と安らぎの為の理想である。そして、神はその理想を生命体に託そうとした。何故なら、この世界が出来た瞬間、神は既に、混沌から抜け出して、混じりっけの無い真の認識者へと変化していたからだった。
一旦、世界が出来てしまうと、神といえども、宇宙の理(ことわり)を排除して、生命を生み出す事は叶わない。言い換えると、神は生命の創成を、各々の認識対象が織りなす運動の理に任せるしか無かったのである。当然ながら、これは、神が物理的運動の理を作ったのでは無い、と言う事を意味する。物理的運動の理はあくまでも、各々の認識対象が発し、あるいは、受け取る、物理的刺激によって産まれる情報交換の結果、培われた物理世界の秩序なのであり、それ以上でも無く、以下でも無かった。 ついでに言って置くが、我々は、あらゆる刺激は人間にとっても、また、物質にとっても、情報として機能する、と言う事を知らなくては為らない。ある状況の許で、物質がある刺激に対して、ある一定の反応を示す理由は、その刺激が情報として、機能した、と言う事に他ならないからだ。また、各々の認識対象は認識主体としての神の分身とも言える存在であるので、情報を交換する事が可能、と成るからだ。神はそれらの認識対象が得た認識を通して、世界を、つまり、自分自身を、理解する。無論、その理解は神は正当なる存在である、と言う理解で無くては為らないのだ。前にも、述べたが、その為にこそ、敵対者、サタンと、神の理想を背負う生命体と言う存在が必要だった。 |
|||||||||||
|
世界が出現した、まさにその直後から、物質同士の情報交換が始まった。そして、物質間の情報交換によって、物質が進化するに連れて、宇宙の理、すなわち、前に述べた、運動の理もまた、構築された。その故に、神の意思はもはや、その時点で、直接、宇宙に作用する事は出来なくなった。また、同じ理由で、神と、宇宙と共に現れたサタンの間の対立が恐ろしい矛盾と成って、生命の中にすら、忍び込んだ。 その事はひとつの生命体が他の生命体を破壊する事からも、知る事が出来る。つまり、各々の生命は各々の物質の理に従って、各々の欲望のままに、他者を食い、あるいは利用しながら、しのぎを削った。世界は神の目論見通りには動かなかった。だが、それは即、「神が負けた」という事を意味しない、各々の生命は多くの場合、種の保存の為に、曲がりなりにも、助け合いながら、無意識にではあるけれども、神の理想を実現しようと、未だ、生き続けているからだ。 しかし、世界の状況は見ての通り、神の理想とは、ほど遠い。世界は神とサタンがしのぎを削る永遠とも言える戦いの場であり、自己の論理で動き回るあまたの認識対象が反応し合って、めんめんと織りなす、矛盾に満ちた世界なのだ。見たところでは、神とサタンの戦いはその勝敗が付かぬまま、世界が終わるまで、果てしも無く、続く様に思われた。 |
|||||||||||
|
サタンは冷酷、破壊、そして、虚無へのあく事を知らぬ意思である。また、それなくしては、世界そのものが成り立たない。そこで、神は生命体に魂という物質ならざるものを吹き入れたのである。それは神自身である、と言っても過言ではない。つまり、魂は物理的存在ではないために、宇宙の物質的な理(ことわり=論理)には、影響を受けぬ筈だった。少なくとも、原理的には、そうであった。従って、神の理想は少なくとも、魂に於いては実現し得る筈だった。 だが、サタンはあくまでも、狡猾だ。宇宙の物質的理を魂にさえ、作用させた。無論、その背後には、たとえ神の望んだ結果ではないとしても、神の認識にとって、サタンは宇宙の生成に欠かせぬ存在として、宇宙と共に産まれた、と言うサタンの生得的な強みがあった。また、魂の表現は、この世にあっては、物理的存在をもってのみ、実現し得る宿命を負っている、と言う事がサタンを利した。 その故に、人々は物欲、肉欲などに捕らわれて、神から下された理想を歪め、あるいは、公然と踏みにじった。いや、そればかりではない。正義という美名の下に、平然と人を殺してしまう。サタンが神を装って、その様に唆すからだった。そして、人々は自らが為すべき本来の仕事を忘れてしまった。 |
|||||||||||

|
医者の仕事は愛を持って、生命を救う事だ。検察や警察の仕事は社会的な悪事を許さぬ事だ。だが、彼らは必ずしも、その様には動いていない。いや、彼らばかりではない。それは政治家や学者、そして、平凡なる我々、庶民、また、聖職者までもが陥り兼ねぬサタンの危険な罠なのだ。人々が神から下された各々の理想を忘れる時、世界は混乱に陥って、虚無へと落ち込む。それこそがサタンの最終の目的なんだ。 しかも、サタンはこの様な陰謀を効率よく進める為に、この世の理を利用して、強き者、指導的立場にある者に、特に、強く働き掛ける。だからこそ、神は強き者、指導的立場にある者に、高い見識を求めるのだが、最近は、真に神を信じる者が少なくなった。 | ||||||||||
|
我々は確かに、神から産まれた。いや、むしろ、我々の魂は神そのもの、と言っても過言ではない。そして、我々の対極にあるものとして、サタンが産まれた。つまり、サタンは、我々自身が正当なる存在者である事を知らしめる存在として、産まれたのに過ぎない。だからこそ、我々はサタンに対峙し、内なるサタンと戦い、神から下された理想を掲げて、その陰謀と戦わねばならない。サタンに味方をする事は神の否定、自己の否定に他ならない。俺はサタンの陰謀の為に、囚われの身だが、何とかして、人々に、この事を伝えたい。おまえに、その事を託したい。このままでは、サタンの陰謀が成就して、世界は虚無へと落ちるだろう。おまえに、世界を救って欲しい。 だが、おまえも、これを狂人の戯言として、捕らえるだろうか?だが、良く聞いて欲しい。我々の心は精神世界の、つまり、神のこの世への窓であり、神は認識を得ようとして、我々の持つ意識の窓を外界へと向けて、開くのだ。つまり、我々の意識は精神世界、つまり、神を通して、繋がり得る、と言う事だ。その故に、俺はおまえの心を知る事が出来る。何故かは知らんが、何時の頃からか、その様な事が可能と成った。俺は認識の窓をこの世だけではなく、精神世界へも、向ける事が出来るからだ。 |
|||||||||||
|
だからこそ、サタンの陰謀にも、気付く事が可能と成った。神は全てをお見通し、としばしば、言われる。多くの人はこれをただの比喩と考えて、字面の通りとは思っていない。だが、まさしく、これは真実なのだ。時空には、我々の行いの全てが詳細に刻まれている。おまえにも、いずれ、分かる時が来るだろう。俺には、その事が見えている。まだ、書き残した事は山ほど、在るが、サタンに悟られては元も子もない。また、連絡が出来るかは分からんが、可能であれば、連絡する。」 だが、克夫の見抜いた様に、私は当初、この手紙を精神錯乱の産物、としか考えなかった。彼は学生時代、サタンが俺の認知を妨害する、などと、深刻な顔つきで、私に語った事がある。 私が思わず、彼の顔を凝視すると、彼は、「良く通うスーパーマーケットなどで、待ち伏せをして、俺に毒を浴びせるんだ、いや、ひょっとすると、頭の中に入るのかも知れない」と、言う。その時、私は唖然としたが、下手な冗談と受け取った。当時、人の集まる場所などに、防犯スプレーなどを撒く妙な輩が増え始めていた。彼の被害は本当かも知れんが、サタンなど、ではあり得ない。私は冗談に乗った気分で、「ほう?それで?」と、問い掛けた。と、彼は、「うん、脳がかき回されて、まともな思考が不可能に成る、酷く疲れるんだ」と、真顔で言う。私はあの時、彼が発した薄気味の悪い雰囲気を忘れる事が出来ない。 |
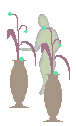
|
||||||||||
|
私はあの時、彼の精神状態を心配したが、それ以来、彼はその事については、全く、触れなかったので、いつしか、その様な心配など、忘れてしまった。しかしながら、この手紙の内容から推察するなら、あの発言は、ある種の精神病者が陥る妄想の典型であった、と考えるのが、妥当なところだ。つまり、あの発言は冗談などではなく、どうやら、本心であったらしい、と言う事だ。そして、克夫の昔の言動が本気であったとするならば、この手紙が狂気の産物である事も、また、確かであった。おそらく、この狂気は学生時代の当時から、既に、芽生えていたのだろう。当時の事を想い出すと、やり切れない想いにも捕らわれる。 私は始めて、あの手紙を読み終えた時、自分の一部が失われて行く、と感じて、心が萎えた様に成って、酷く落ち込んだ。そして、「返事はどうしようか?」と、言う迷いが生じた。あの酷い文章を目の当たりにした所為か、返事を書く意味を見出せなかったのである。だが、狂気が書かせた手紙とは言っても、彼は数少ない友人である。返事はやはり、書かねばならない。私はそう考え直すと、一応の返事をしたためて、彼へと送った。 |
|||||||||||

|
だが、案の定と言うべきか、それ以来、彼からは、何の音沙汰もなかったのである。病院に電話して、彼の様子を尋ねたが、症状は悪化の一途を辿っている、と言う。根の深い心因性の病らしく、薬も、そうは効かないらしい。いずれにしても、彼の病が悪化している事は、どうやら、確かな様だった。「やはり、単なる気まぐれだったか?」私はその様に考えると、まもなく、手紙の事は忘れてしまった。そして、彼があの様にして、亡くなるまで、意識に上る事も、なかったのである。 | ||||||||||
目次 | |||||||||||
その一 狂気の手紙 その二 克夫の生い立ち その三 奇縁 その四 克夫の能力 その五 ライフワーク |
|||||||||||
|
その六 迷える魂 その七 サタンの陰謀 その八 認識というもののミステリー |
|||||||||||
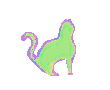


| |||||||||||
| Cotosiro Home | |||||||||||