|
改訂版 現なる夢 August 4, 2000 in Justnet. This was shifted to Nifty in November 19, 2003 and revised. This was revised in May 20, 2013. Hiromasa Noguti It is fixed "HTML" in February 14, 2017/ 野口博正 |
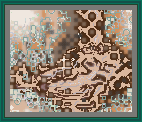 | ||||||||||
|
その二 モグラ と 亡霊 | |||||||||||
|
それにしても、魔性の原野で聞いた、あの荘厳な声は果たして、何者の声であったのだろうか?やはり、あれは神だったのか?あの声は、「未来を問う事は無意味である」と、言った。だが、如何なる理由で、無意味であるのか?もし、その理由を知る事が出来るなら、神への不信感を払拭し切れない私であっても、あるいは、神の声を聞いた、と思えるのかも知れない。私はまだ、夢の中に居たが、ふっと、そう、考えた。そして、あの言葉の意味について、考え始めた。すると、思考が幾つかの言葉に集約して行く。私は夢の中で、それらの言葉が闇に、映像として、展開しながら、別の言葉とリンクして、新たな言葉を産みす、奇妙な情景を眺めたのである。だが、言葉と言葉との繋がりがどうも、おかしい。論理的には、正しい筈だが、意味内容は体を為さない。 |
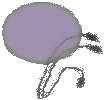
|
||||||||||
|
例えば、「悪魔と神は正反対のものである、従って、私は裸足で歩く」と、言う様な意味不明の文章が闇の中に現れて、別の文章と繋がって行く、その様が、映像として、脳裏に浮かぶのである。私はこの理解不能な状況に、呆然とした。そして、「俺は痴呆に成ったのか?」と、恐れを感じた。だが、言葉とイメージの奇妙なリンクは、私の戸惑いとは、関係無しに、益々、彩りを豊かにして行く。だが、意味は依然として、不明なのである。其処に至って、私はその事への戸惑いと、正体不明の恐れを感じて、思わず、そのリンクから、眼を反らした。すると、夢の空間が瞬時に、消えた。認識すべきものは、もはや、ない。そして、何故かは知らないけれども、私は五感を失い始めた。いや、ひょっとすると、それはそうでは無く、認識するものが失われた事による、錯覚なのかも知れない。その状況では、五感は働きようが無いからである。だが、本当に、そうであろうか?「ひょっとすると、認識すべきものが無い、と言う事と、五感が無い、と言う事は実は、同義なのかも知れない」私はふっと、そうも、考えた。 いずれにしても、私が何も、感じていない事は確かである。そして、この様な状態が恐ろしい苦痛をもたらす、と言う事を実感として、始めて知った。このまま、時が経過するなら、自分自身も、早晩、消える様に思われる。「いや、自分はもう、死んでいるのかも知れない」その様な錯覚にすら、捕らわれて、私は言い知れぬ不安にも、陥ったのである。無論、その錯覚は虚無へと入る入り口である。一歩、踏み込めば、其処には、親、兄弟、友人、そして、連れ合いなどはもとより、ひとかけらの光も、存在しない。其処は、自分の消滅すら認識出来ない、完全なる死の世界なのである。私はその入り口に突っ立って、ただ、入ろうか?入るまいか、と、その事ばかりを思案していた。そして、その重要性に気付かぬ侭に、ふっと、一歩を踏み出そうとした。だが、私は虚無へは入らなかった。何か、恐ろしい力が働いて、私を生へと引き戻したのである。実を言えば、私は虚無へ入ろうとした、あの瞬間、虚無の本質にようやく、気付いた。その事が私に内在する「存在する事」への執着心を目覚めさせた。そして、その執着心が思考の方向を逆転させて、私を生へと引き戻したのである。 考えてみると、私は感覚を失っても、なお、生きている。その証拠に、私の思考は今も、この様に働いているし、氷の様な孤独感も、感じる事が出来る。「そうだ、私はまだ、消えてはいない、諦めてはいけないのだ」私はそう、自分に言い聞かせると、感覚の無い妙な状況について、考え始めた。すると、認識者である私という存在は、認識対象によって、支えられている、と言う事に思い至った。つまり、認識するものと、認識されるのものとの関係がそれぞれの存在を保証するのである。そこで、私は認識すべきものを希求した。と、その所為だろうか?ふっと、空間が認識された。すると、何者かの気配を背後に感じる。私はふっと、振り向いた。 だが、何時から、其処に居たのだろうか?素掘りのトンネルらしい闇の中で、金色の体毛に覆われた一匹のモグラが私を見ている。「考える振りなんか、もう止しな、とっくの昔に、知ってるくせに」モグラは、私と視線が合うと、皮肉っぽい口調で、そう言った。だが、彼は一体、何を言っているのだろう?意味がさっぱり、分からない。どうやら、私を哀れんでいる様子なのだが、なにしろ、相手は脳みその少ない、取るに足らないモグラであるから、つい、「彼の言葉に、大した意味など、ある筈が無い、私を哀れむなど、生意気だ!」と、言う想いに捕らわれる。私は威圧する様に、モグラを睨んだ。あるいは、その時、私はモグラの言葉に、何らかの意味を感じていたのかも知れない。いや、少なくとも、その言葉を疎ましい、と感じていた事は確かであった。だが、その様な私の感覚は何故か、意識には上らずに、どう、モグラを追い払おうか、と、私はその事ばかりに、捕らわれていた。 | |||||||||||
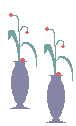 |
だが、どうしたのだろう?モグラを睨んだその直後、何の予兆も無く、突然、私の意識が遠退いた。幸い、失神は免れたのだが、気が付くと、私は酷く貧相な、骸骨の様な男に、睨まれている。そして、其処には、モグラは居ない。「何だ、これは?あのモグラがこの貧相な男に、変身したのか?」だが、そんな事など、有り得るだろうか?私はこの理解不能な状況に、唖然として、貧相な男を凝視した。ただ、彼が相当に、いじけた人間である事は窺い知れる。男はしばしば、私の心を盗み見よう、と、上目を使って、こちらを窺うのである。「何と、醜い!」私は思わず、視線を反らした。これならば、見た目のきれいなモグラの方が、余程、まし、と言うものである。「相手にせぬ方が良さそうだ」私は密かに、自分にそう、囁いた。 だが、此処は極めて、狭いトンネルである。そして、言葉を交わす事の出来る相手は、その貧相な男しか、居ないのである。果たして、無視し続ける事は得策だろうか?だが、最初から、眼を付けて来る相手に、こちらから、挨拶する、と言うのも、考えものではある。私は、「どうしたものか?」と、思案しながら、ふっと、手元に視線を遣った。と、どうした事か?私の両手が金色の体毛に覆われている。いや、そればかりでは無い。五本の短いそれぞれの指には、丈夫そうで、とても鋭い、かぎ爪までが、生えている。あろう事か、私は金色のモグラへと、変身していた。だが、この様な状況に置かれて、すぐに、納得など、出来るだろうか?私は咄嗟に、最前、見たモグラを闇に探した。 | ||||||||||
|
だが、私の他に、モグラは居ない。貧相な男が上目を使って、私を見ているだけである。そして、私が今、居る場所には、確かに、さっきまで、モグラが居た。ならば、モグラである私が今、見ている貧相な男は、さっき、モグラを見下していた自分だろうか?いや、きっと、そうであるのに違いない。私はようやく、その事に気が付くと、事の重大性に、愕然とした。
「それにしても、自分が人間である、と言うだけの理由で、モグラを見下していたなんて、以前の自分は何と、愚かであったのか!」金色のモグラと成った私は眼前の貧相な男を、まるで、他人であるかの様に客観化して、蔑んだ。そして、同時に、哀れんだ。あるいは、小さな脳しか持たない、モグラである私は既に、その男がかつて、自分であった事を忘れかけていたのかも知れない。いずれにしても、その男は太陽の光に憧れながら、自らの将来を悲観して、死を待つだけの人間である。「せっかく、忠告してるのに、話が分からぬなら、勝手にするさ!」モグラである私は皮肉まじりに、そう言うと、くるりと、男に背中を向けて、鋭い爪で、地中を掘った。 其処には、あらゆる種類の真実が宝玉の鉱脈として、埋没している。私は鋭い嗅覚で、それらを探って、餌とした。この一連の作業は、私にとって、最も価値ある、陽光と呼ばれる宝玉を我が物とする為である。「いずれは、地表に躍り出て、精一杯に浴びるのだ!」その一念がこの暗闇と孤独とを忘れさせた。宝玉の尽きない鉱脈は更に、奥へと私を誘う。そして、掘り出した宝玉が更なる宝玉へと、導いた。無論、私はそれらの宝玉を見出すと、何時も、狂喜して、掘り出す側から、食ったのである。それらの真実と呼ばれる宝玉は甘露の様に甘いのだ。私はその味覚を楽しみながら、新たな宝玉も、手に入れた。「宝玉の輝きは掘り出して、食べてみなければ、分からない、未来は認識する力が作るのだから、単なる計算による予測には、味など、ないのだ、だからこそ、先人の残した、体験から得られた知恵が重要なのだ」と、今まで得た宝玉がそう、教えたのである。 | |||||||||||
|
だが、時として、宝玉の鉱脈も、一旦、途切れる。掘る手をしばし、休めると、地中の静けさが心に浸みて、一抹の虚しさも、脳裏を過ぎる。「疲れだろうか?」理由は良くは、知らないけれども、掘り進むほどに、掘っているだけの人生が詰まらないものに、見えて来る。知らぬ間に、宝玉への食欲も、減退していた。 と、静けさのもたらす幻聴だろうか?背後で、ごそごそと、音が聞こえる。ふっと、後ろを振り向くと、最前、見捨てた以前の私が腹這いと成って、付いて来ていた。目が合うと、彼は動きをヒタッと、止める。そして、上目遣いに、私を睨んだ。「何故、自分を置き去りにした?」とても、言いたげである。彼は今、百メートルほどの後方にいるが、骸骨の様な風貌は益々、凄みを増している。彼の顔は青白く、蛍光の様に、ぼうっ、と光る。その様には、妖気すら、感じ取られる。私は思わず、ぞっ、とした。 |
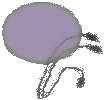
|
||||||||||
|
それにしても、何と、不気味な顔付きだろうか?もはや、人間である、とは、言い難い。ひょっとすると、彼は既に、亡霊であるのかも知れない。「こっちへ来るな!用など、無いだろ?」私は思わず、虚勢を張って、にじり寄る男に、罵声を浴びせた。だが、男は眉の一つも、動かさない。長い手足を動かしながら、まるで、蜘蛛かサソリの様に、じりじりと、こちらに、這い寄って来る。「こいつはやはり、亡霊だ!」私は心の中で、呟いた。気が付くと、掌には、じっとりと、汗が浸み出している。私はふっと、掌を見た。が、私が其処に見たものは、どうした訳か、人間の手である。「えっ、人間に戻ったのか?」私は慌てて、自分の造作を確かめた。間違いない、確かに、私は人間である。念の為、モグラの姿も、探してみたが、それは何処にも、見当たらない。其処に至って、私はようやく、人間に戻った事を確信出来た。だが、安心などはまだ、出来ない。背後に迫る亡霊は未だ、消えては居なかったのである。私が上目で、亡霊を睨むと、亡霊は、「なあ、そう、邪険にするなよ、俺は、お前なんだから」と、言って、ニタリと、笑う。そして、やせ細った右手を肩の所まで、持ち上げると、ニュウッと、私へと、差し伸べた。まるで、「お前を捕まえて、食ってやる」と、でも、言いたげである。私の背筋に、悪寒が走った。 |
|||||||||||
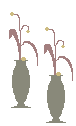 |
このままでは、あの亡霊に、取り殺されてしまう。トンネルを掘り進む筈のモグラが居なくなった今と成っては、私の位置はもはや、トンネルの端のどん詰まりである。逃げ場所などは、何処にも無い。「モグラは何処へ行ったんだ?」私は後ろの亡霊を気にしつつ、モグラの姿を必死で、探した。無論、自分がそのモグラであった事は覚えている。だが、逃げる為には、モグラの爪が必要なのだ。爪が無ければ、掘り進む事など、叶わない。愚かにも、私はトンネルを高速で掘るモグラが此処に存在する事を期待したのである。だが、その様なモグラなど、居る筈が無い。極度の恐怖が在りもしないモグラを無理矢理、私に要求させた。私はもう、錯乱状態に、陥っていた。 | ||||||||||
|
すると、亡霊がうれしそうに、言う。「おまえは馬鹿だねぇ、いくら、地中を掘ったところで、日の目を見る事など、出来っこ無いのに」そして、青白い顔で、ニッと、笑った。反論したいが、反論できない。亡霊が今、口にした言葉は自分がモグラであった時、亡霊に言った言葉と、同じである事に気付いたのである。「ああ、何と言う事だ!自分がこの忌まわしい亡霊と同類であったとは!せっかく、これほどの宝玉を手に入れたのに、こんな地中で、人知れず、取り殺されて仕舞うのだろうか?」私は亡霊と同類であった事を受け止め切れずに、自分の不運を大いに、呪った。すると、孤独感と絶望感、そして、悔しさと憤りが、ない交ぜと成って、私を襲った。と、私の絶望を知ったのだろうか?宝玉を取り尽くしたトンネルに、亡霊の高笑いがこだまする。私の気力は萎えかけていた。 しかし、生への執着だろうか?それとも、私のプライドだろうか?次の瞬間、憤怒の情がマグマの様に吹き上げた。私は亡霊を睨み付けると、大声を出して、罵倒した。「仏に成り損なった、出来損ないめ!お前の意見など、知るものか!地獄の業火に焼かれるが、良い!」だが、亡霊は全く、動じない。「ほう?でも、俺はお前なんだから、その言葉はそのまま、お前に返すよ、なに?太陽の光を浴びたい、だって?笑っちゃうね、さっきも言ったけど、なら、どうして、地中を掘り進むんだい?」亡霊は皮肉っぽい調子で、そう言って、意地悪そうに、ニッと、笑った。だが、私は何も、答えられない。と、亡霊がたたみ掛ける様に、述べ立てた。「もう、分かってるよね、本当は、お前は地表になど、出たくないのさ、モグラに成って、闇に慣れ切っているからね、本当は、光が恐いのさ!図星だろう?」彼の言葉の一つ一つが、私の心を鋭く、抉る。私は何も、反論出来ずに、ただ、亡霊を睨み続けた。 | |||||||||||
|
見ると、忌々しい亡霊は更に、私に近付いている。地中の空気が少し、そよぐと、死人の臭いが鼻を掠める。「何とかしなければ!」と、私は焦った。だが、此処は既に、廃坑の一番、奥のどん詰まりである。悪あがき、とは思ったけれども、座して、死など、待ちたくは無い。私は亡霊に背中を向けると、必死の想いで、土の壁を引っ掻き始めた。と、亡霊の声が背後で、響く。「良くも、見捨ててくれたよな!これで、おまえも、おしまいさ!」私が思わず、振り向くと、亡霊は既に、十メートルほどの距離に、近付いている。般若の様な青白い顔が真っ赤に燃える眼で、私を睨むと、薄い唇がクワッと、開いた。今にも、襲い掛からん、と言う勢いである。「ああ、とり殺される!」私は恐怖に取り憑かれると、再び、亡霊に、背を向けて、夢中で、土を引っ掻いた。 |

| ||||||||||
|
だが、無駄な事ははっきりしている。爪が割れて、血も吹き出すが、トンネルは一向に、広がらない。それでも、私は引っ掻き続けた。と、駄目を押そう、とでも言うのだろうか?亡霊が言った。「せいぜい、そうして、足掻くが良いさ、時間はたっぷりと、あるからな?」エコーの掛からぬ音色からして、すぐ、後ろにまで、来ているらしい。私はもう、半狂乱で、崩れぬ土を引っ掻き続けた。と、背後の空気が少し、動いた。生ぬるい息が頬を掠める。私の身体が硬直すると、亡霊の手が肩に触った。「ああ、駄目だ!」私は拳を握りしめると、ありったけの力で、土を叩いた。と、どうした事か?予期もせず、土の壁がいきなり、へこんだ。拳を更に、押し込むと、ぽろっと、崩れて、明かりが漏れる。拳を抜くと、まばゆい光線が眼を射貫いた。「あっ、まぶしい!」私は思わず、顔を背けて、そして、夢から解放された。 | |||||||||||
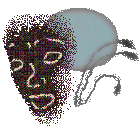 |
私のいる烏鷺の中には、朝の日差しが差し込んでいる。首を伸ばして、外の様子を窺うと、朝靄に霞む森林を幾筋もの光線が貫いている。小鳥が其処を縫う様に、さえずりながら、飛び交っている。現世ならば、普通に、見られる、早朝の、すがすがしい森の光景である。「それにしても、厭な夢を見たものだ、忘れよう」私は朝の空気を胸、一杯に吸い込むと、小鳥のさえずりに誘われて、よろけながら、烏鷺を出た。そして、精一杯に、背筋を伸ばすと、木々の梢に、視線を遣った。 だが、其処に、見られる筈の、昨夜の嵐の爪痕は何事も、無かったかの様に、消えている。そして、魔性の気配も、感じられない。魔性のものが去ったのか?それとも、あの嵐、そのものが夢だったのか?だが、夢であった、とは思えない。「やはり、此処は、精霊の森なのだ、精霊が救ってくれたのに違いない」私はそう、確信して、見えない精霊に、感謝を送った。だが、木々を透かして見える荒野は未だ、怪しい妖気を放出している。魔性のものが隙を狙っている事は、十中、八、九、間違いない。旅を続けねれば為らないけれども、ひとたび、この森を出たならば、必ずや、魔物が襲うだろう。今の体力では、戦う事も、逃げる事も、難しい。「何時まで続くか、分からぬ旅だ、此処で、英気を養おう」私はそう、考えると、荒野を一瞥して、森の奥へと、入って行った。 | ||||||||||

|

目次へ戻る |

その三へ続く | |||||||||
|
Cotosiro | |||||||||||