|
改訂版 背後の世界
その3 機縁 December 30, 2012. 野口博正. |
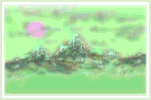
その4 克夫の能力 |
||||||||||
|
平成11年(西暦1999年)10月2日、記憶の前後関係を確認するのに手間取ってしまった。昔なら、簡単に想い出せた筈だが、年の所為だろうか? 中学時代の克夫の事はほとんど、何も覚えていない。当時、彼も私と同様に、家と学校の往復以外、戸外に出る事は希であった様で、街角などで、見掛ける事もなかったのである。彼の事は何時しか、自然と忘れてしまった。だが、記憶を辿ると、実は、何回か、見掛けている。だが、「今、見ているのは克夫ではない」と、考えていた。当時は、それが彼である、と言う意識を持てなかったのである。 これがどういう事なのか、高校時代の私には、良く分からなかった。それで、一度、この事を彼に話した事がある。すると、彼も、私と同様に、君ではない、と考えていた、と答えたのである。私はその時、何故かは知らないが、彼との運命的な機縁を感じた事を記憶している。いずれにしても、中学時代の私にとって、彼は見も知らぬ赤の他人であった。 今、考えると、それは私が幼い頃から、彼に興味を持っていた、と言う事の証であるのかも知れない。おそらく、内心は、一緒に遊びたい、と思っていたのではないのだろうか?だが、当時の私は、その様な自分の気持ちには気付いていない。それで、遠巻きに彼を眺めて、彼との自分勝手な関係を作ったらしいのである。 |
|||||||||||

|
おそらく、「一緒に遊びたいが、実際には、それがうまく出来ない」と、言うジレンマがその様な歪んだ認識を作ったのだろう。それで、中学時代、彼を見かけると、無意識に、「あれは彼ではない」と、自分に言い聞かせたのに違いない。おそらく、心の中のジレンマを意識したくはなかったのである。無論、それは心の平安が乱れるからであった。
今でも、自分の気持ちに気付かぬ事は時折、あるので、これも三つ子の魂だろうか?あるいは、私の消極性が自分の本当の心情を抑圧している所為であろうか?いずれにしても、彼と私には、似通った性質があるらしかった。ならば、彼の狂気も、また、私の中に、あるのだろうか?ふと、その様な不安も、心を過ぎる。だが、今のところ、私は至極、まともであるから、それは多分、杞憂だろう。 | ||||||||||
|
話は少し遡るが、私は高校に入学すると、油絵同好会に入会した。すると、彼もそこにいた。まんざら、知らぬ仲でもなかった所為か、他の部員よりも、先に打ち解けた。あるいは、互いのテンションの低さが気に入ったのかも知れない。それとも、幼児期の互いへの関心の所為であったであろうか?元々、消極的な二人であるから、常識的には考えがたいが、二人は奇妙に、馬が合った。 だが、私は元々、絵などには、それほどの興味は持っていなかった。学校の決まりで、どこかのサークルには、入らねばならない。それで、一番、楽そうに見えたこのサークルを選んだのである。適度に学び、適度に遊ぶ、入学当初は将来の事など、ほとんど、念頭には浮かばなかった。もっとも、その姿勢は受験の為に、すぐに変更を迫られる。私は極、普通の学生だった。 だが、克夫の入会理由は至極、まじめなものだった。後で知ったのだが、彼が小学校へ上がると、すぐに、母親が仕事をし始めて、家を空けがちと成った、と言う。家のローンの返済に当てる為であったらしい。その所為で、彼は何時も、一人きりで、家にいた、と言う。消極的な彼の性格が遊び友達を作らせなかった。 当時は昭和の三十年代、テレビゲームの類など、遠い未来の夢物語である。また、テレビも高価であったので、その様な贅沢は許されなかった。ラジオはあったが、子供向けの番組は僅かである。また、当時のラジオは真空管で、電気代も馬鹿にならない。その理由で昼間はニュースを聞く以外は、ほとんどスイッチは切られていた。それで、彼は十五分ほどの子供向けドラマ、一作品しか、聞かせては貰えなかった。彼の家にテレビが来たのは小学校の五、六年の頃らしい。だが、チャンネルは親が管理しており、勝手に見る事は許されなかった。彼は素直であったので、たとえ、親が外出しても、盗み見る事はなかったのである。 |
|||||||||||
|
だが、彼はいわゆる勉強は相当に好きではなかったらしい。従って、時間はあっても、宿題以外、勉強らしい勉強はしなかった、と言う。本を読んでは空想にふけり、絵などを描いては、飽きずに眺める、小学校の時分には、それが彼の日常だった。母親が昔、文学少女だった様で、本好きだった。彼女はその趣味を克夫にも、期待したらしく、少年少女文学全集、動物図鑑、絵画集など、様々な本を彼に与えたのである。「子供向けの話なら、他の誰よりも、知っている」それが彼の自慢であった。無論、たまには、気晴らしに、野原や公園に行って、一人遊びをしていたが、遊び相手は、幼い頃と同様に、蟻とか、バッタ、あるいは、猫、蛙などである。それでも、当時はそれで、結構、満足していた、と言う。高校時代、彼は、「俺は猫や昆虫と話が出来る」と、真面目な顔で言っていたが、今、考えると、あれも、どうやら、本気だったらしい。 |
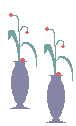
|
||||||||||
|
だが、中学にあがると、少し、心境が変わったらしい。容姿も頭の出来も中程度、本は相変わらず、読んではいたが、これと言った夢もなく、課せられる課題を淡々とこなす、どちらかと言えば、退屈な曇天の様な毎日だった。そして、その頃、両親の間で、何かの問題があったらしい。 彼は大学時代、「それが何かは分からぬが、その事も自分の心に暗い影を落としたようだ」と、分析していた。丁度、その頃、彼の母親は仕事を辞めた事もあってか、異常なまでに、克夫の面倒を見始めたらしい。時には、「彼の父親と結婚した事を祖母からは随分と感謝された」などと、克夫には、余り関係のない事まで、話し始める有様である。無論、その背後には、当時の夫との問題もあったのだろう。彼女は自分のアイデンティティーを失い掛けていたのかも知れない。 だが、当時の克夫には、その様な母親の干渉が鬱陶しくて、適わなかった。克夫は全く、覚えていないが、あるいはその時、彼は両親の問題に気付いていたのかも知れない。そして、それを心の隅に抑圧した。その所為で、彼は現実に対して、背を向けてしまったのではないのだろうか?私には、その様に思われた。当時、彼の家庭は経済的には、非常にうまく行っていた、と言う。あるいは、その豊かさが夫婦の亀裂を産んだのかも知れない。現在の社会の状況を考える時、ふと、その様な想像にも、囚われる。いずれにしても、その時、彼の心は危うい状況にあったのである。 |
|||||||||||

|
だが、ぐれる様な事はなかったらしい。元来、おとなしい彼にとって、自分がぐれるなど、考えられぬ話であった。テレビドラマの所為かも知れないが、彼は粗暴な連中や万引きを唆す連中を異常なまでに、軽蔑していた。子供であるから、意識的ではなかったものの、彼はあくまでも、良い子の侭でいたかったのである。そして、良い子を装い、影で悪さをするような卑劣漢にも成りたくはない。彼は本当の良い子で居たかった。ならば、それは誰に対しての、良い子であったろう?おそらく、克夫の場合、その対象は母親であった。母親は特に、幼少期と中学時代、彼に付き切りのような所があった。多少、うるさくは感じても、その影響は計り知れない。母親に対して、良い子でありたい、と言う彼の気持ちは当然と言えば、当然であった。 | ||||||||||
|
だが、その様な彼の心は知らぬ間に、大きなフラストレーションを抱えたらしい。中学時代の彼は自分の殻に閉じ籠もり、現実を見ては居なかった。いや、むしろ、現実と言うものに気付き始めて、その事に戸惑い、殻に閉じ籠もった、と言うのが真相であったのかも知れない。そして、その様な現実の中には、両親の間の問題も、あったように思われる。その所為か、どうかは、知らないが、中学の二年に上がった頃には、妖怪や幽霊などの落書きをしばしば、描いていたらしい。そのスケッチブックは他の落書きや絵などを除いても、十数冊にも、上ったらしい。だが、彼によると、それは酷く陰惨なタッチで書かれていた、と言う。「ひょっとすると、相当に、どろどろとした感情が渦巻いていたのかも知れない」何時であったのかは忘れたが、彼はその様な自己分析を私に語った事がある。彼にとって、中学時代は中世の暗黒の様な時代であった。 そこで、高校への入学時、彼なりの一念発起をしたらしい。画家に成ろう、と思ったのである。何故、画家であったのかは、本人にも、良くは分からぬらしい。あるいは、他の目的でも良かったのかも知れないが、多分、中学で唯一、ほめられたのが絵画だった、からではないのか、と、彼はある時、その様な事を言っていた。だが、内心では、相当の自信を持っていた節も窺える。それとも、それは私の単なる憶測だろうか?いずれにしても、油絵同好会への入会は彼にとって、その目的の為の一歩であった。彼の性格は変わりつつある様に思われた。そして、一時は、彼の心のルネッサンスは成功を納めるかにも思われたのである。私は当時、彼の決心を聞いて、取り残されるような気分に陥り、漠然とした不安に駆られた事を記憶している。 |
|||||||||||
|
だが、その様な彼の試みはすぐに、挫折させられる。彼の両親が反対だった。絵などにかまけてばかりだと、学業の方がおろそかになる。「趣味としてなら、認めるが、おまえの仕事は大学受験だ、絵の事は大学に受かってから、考えなさい」それが両親の意見であった。当時、担当の教師は彼の才能を認めていたが、なまじの事では、成功など出来ぬ世界であるから、両親の意見はあるいは、正しかったのかも知れない。だが、その反対が是であったのか、非であったのかは、別にして、その様な両親の対応は彼がその難しさを悟る絶好の機会を奪ってしまった。彼はさしたる抵抗もせぬ侭に、両親の言葉に従ったのである。そして、彼の灰色の高校生活が始まった。彼には、強い意志というものが欠落していた。 |

|
||||||||||
|
彼は高校の二年に上がると、小説などには見向きもせずに、哲学書などをあさり始めた。当然、勉強の方はおざなりである。今にして思うと、それは両親に対する密かなる反抗であったのかも知れない。私もその影響で少し読んだが、二人とも、内容に惹かれたのではなく、哲学という言葉の響きに惹かれただけの、一種の未知なるものへの憧れだった。何故かは知らぬが、学校で教えぬものには、妙に、興味をそそられたのである。ソクラテスの対話方式をまねて、議論をする事も良くあった。だが、しょせん、それは遊びであるから、哲学とは、随分と、遠いものだった。私は受験勉強の為に、その様な遊びからは次第に遠ざかってしまったが、彼はひとりで、続けたらしい。彼の独自の論理と世界はその辺りから、始まったのかも知れない。 |
|||||||||||
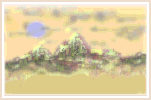
|
だが、当初、彼の世界は彼自身の正義感や当為のみで成り立つ極めて、偏狭な世界であり、現実とは酷く、かけ離れた、夢想的な世界であった。そして、彼はその様な自分の世界に、がんじがらめに縛られていた。後年、彼自身がその様に言っていたので、それはおそらく、真実だろう。「少なくとも、主観的な世界は開放系で在らねばならない、つまり、客観的な認識だけではなく、未知の論理や存在とも、整合性を保ち得る世界でなければ、その世界観は偽物だ」それが彼の後年の持論であった。だが、高校時代の彼は狭い世界に捕らわれており、唯我独尊を決め込んでいた。そして、受験勉強の方はおざなりであった。頭は私より、良い筈であったが、彼は私の通う大学に、一年遅れで、入学したのである。学部も同じ、法学部であった。 | ||||||||||
目次 | |||||||||||
その一 狂気の手紙 その二 克夫の生い立ち その三 奇縁 その四 克夫の能力 その五 ライフワーク |
|||||||||||
その六 迷える魂 その七 サタンの陰謀 その八 認識というもののミステリー |
|||||||||||
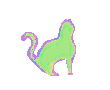


| |||||||||||
| Cotosiro Home | |||||||||||