|
----- 改訂第三版 ----- 後の世界 その6 迷える魂 December 26, 2015. 野口博正. |
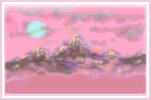
その7 サタンの陰謀 |
||||||||||
|
平成12年(西暦2000年)8月22日、仕事が忙しくて、書けなかった。しかし、このブランクはむしろ、克夫と言う人間を考える上では、必要であったのかも知れない。 1.悩める克夫 克夫は入院する少し前、「俺は貧乏で、何も出来んから、感謝は祝福で、返すんだ」と、周囲に漏らしていたらしい。冗談めかして、言った言葉では、あったらしいが、この発言は問題だ。彼の事を知らない思慮に欠けた人間が、もしも、これを聞いたなら、「貧乏の所為で、けちに成った」あるいは、「あいつは、やっぱり、普通ではない」などと、吹聴されるのが、関の山だ。私はこれを聞いた時、心の病を疑いながらも、「余計な事を言ったものだ」と、彼の不明を心で、なじった。 確かに、私は彼から、歳暮などを贈られた事など、全く、なかった。そして、その様な贈答を嫌う彼の性癖は学生時代から、あったのである。少なくとも、貧乏の所為で、けちに成った訳では、決して無かった。だが、ひょっとすると、元来、彼はケチなのだろうか?まあ、これは自分の秘めやかな冗談だが、私は学生時代、それは彼のナイーブ過ぎる性格の所為だろう、と考えていた。「彼は他人に物を贈る事に、ある種の後ろめたさを感じている」私は当時、そう、感じていた。 サラリーマンの時代、私がたまたま、居酒屋に誘うと、彼は酒を飲みながら、「接待や贈り物をすると、相手を貶めた様に感じる、それがどうにも、耐えられない」と、一度、漏らした事がある。普通の人間なら、世話に成った人間に、お礼を送ろう、と思うのは極、当たり前の心理だろう。私はその時、「随分と、奇妙な事を言う」と、感じて、戸惑った事を記憶している。 だが、彼の場合、それを、賄賂の様に考えていた節がある。そう言えば、彼は、「俺は感謝の念が希薄なのかな?」と、呟いた事も、記憶している。彼は彼なりに、いろいろ、考えていたのだろう。いずれにしても、潔癖症とも思える彼の性癖には、やはり、彼の世界と外界の間の、越えるに越えられない障壁が関わっていたのに違いない。少なくとも、私は、そう考えている。 人間は群れて暮らす動物である。そして、その群れは仲間意識、と言う絆を持っている。そして、仲間は互いに、助け合う存在である。欧米人については、知らないけれども、少なくとも、日本人は、その感覚を仕事上の付き合いにおいて、ある部分、要求される。しかし、彼の中にある問題の障壁がおそらく、その様な意識を持つ事を妨げていた。その故に、彼は個人と個人との、物欲の介在しない、魂の交流を求めたのではないのだろうか?可能か、どうかは別としてだが・・ 無論、彼の抱く他者への、この様な要求はあるいは、彼のドグマの産物なのかも知れない。 だが、おそらく、彼にとっては、これは譲れぬ信条だった。私はあの時、酒を飲んでいた事もあって、その呟きを軽く考えて、聞き流していた。だが、あの時、ひょっとすると、もう少し、親身に聞いてやった方が良かったのかも知れない。彼はその時、相当に、悩んでいたのに違いないのである。そして、その様な悩みが、彼が会社を辞めた本当の理由であったのかも知れない。 |
|||||||||||
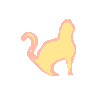
|
だが、深刻な悩みを抱える一方で、彼には、昔から、極楽トンボの様なところがあった。「心から、他人を祝福すれば、本当に、その人間には、願った幸運が訪れる」ひょっとすると、彼は本気で、そう、思っていたのかも知れない。いや、彼がそう、表出したのであるから、それは確かだ。だが、ひょっとして、その様な彼の考えは、彼が死を迎えるまで、ある部分、幼児性を持ち続けていた、と言う事の証明であるのかも知れない。それとも、私が前々から、危惧していた様に、その頃の彼は既に、普通ではなく、その楽天的な性格が狂気の所為で、入院する前のあの言動として、現れたのか? 今と成っては、いずれとも、良くは分からない。そして、妙な話だが、私は今、この妄想的発言も、あながち、ただの妄想とも言い切れない、と思うのである。実を言えば、彼と頻繁に会っていた学生時代には、少なくとも、私には、随分と、良い出来事が多かった。偶然なのかも知れないが、今にして、思えば、彼には、そう思わせる雰囲気が学生時代から、漂っていた。 | ||||||||||
|
それにしても、彼の持つ、幼児的な楽天性と、サタンに象徴される正体不明の不安は、彼の中で、どの様な関係を持つのだろうか?彼のその様な楽天性と不安は一見、同居など、出来ない様に思われる。だが、奇妙にも、彼は同時に、その両方を心の中に、持っていた。この場合、何らかの関係がある、と考えるのが普通だろう。だが、他の解釈も可能である。この対立する二つの心に、関係などは何もなく、この同居は単に、精神病の証であるだけなのかも知れないのである。果たして、どちらの解釈が適切なのか?それを判断する事は至難の業だ。実際、此処に至っても、私は結論を出し兼ねている。
そう言えば、以前、克夫は彼が中学へ通う時分、両親の間に、何らかの問題があったらしい、と語っていた。ひょっとすると、彼はその様な両親の雰囲気から、両親の夫婦としての愛情に疑問を持ったのかも知れない。いや、その様な愛情の永遠性に疑問を抱いたのかも知れない。あるいは、両親の間の愛情問題を具体的に知ってしまった、と言う事も考えられる。そして、もしも、そうならば、彼がその記憶を心の底に押し込めた、と推測する事は簡単である。また、その可能性はかなり高い。その時、彼は愛情の壊れやすさを感じ取ったのに違いないからである。だが、当時の彼はおそらく、愛情への自分の不信に向き合う事を避けていた。 母親の愛は彼を育むものであった。だが、その愛情も、永遠のものではないのかも知れない。つまり、原初的には、彼の楽天性は母親の愛情を信じる事で培われたが、両親へのその様な不信感は彼に愛情の消失という大きな不安を与えたのではないのだろうか?そして、その不安は彼の持つ自分と外界との障壁の為に、より強く、彼の心に刻み込まれた。おそらくは、そんなところが真相なのではないのだろうか? 幼児にとって、外界はそのほとんどが未知の世界である。また、未知の存在は好奇心を触発するが、同時に、ある種の恐怖も感じさせる。その故に、外界と幼児との関係は最初、母親を通じて、構築される。つまり、幼児にとって、母親はその愛情の故に、最初に外界への道筋を示す信頼の出来る存在なのである。 おそらく、この事は克夫だけではなく、全ての幼児に当てはまる原初的な心理であった。だが、克夫の場合は他の幼児とは、少し違って、その様な心理の根底には、別の要因も加わっていた。言うまでも無く、それは例の障壁である。 |
|||||||||||
|
幼い頃、彼は光のない部屋に閉じ籠もる認識を求める存在だった。そして、部屋の外には、光にあふれる、認識すべき世界があった。そして、彼はその外界に憧れていた。だが、外にあふれる、まばゆい光は自分の部屋には、ほんの少ししか、入ってこない。その故に、外界には憧れつつも、彼は余りにも、まばゆい外界との間に、超えがたい障壁を感じたのである。 あるいは、この様な彼の無意識的な認識には、幼少期の虚弱体質も、関わっていたのかも知れない。その故に、母親から注がれる愛情は彼と外界との関係において、無くては為らぬものだった。そして、その様な深層心理は中学に入ってからも、変わらなかった様に思われる。 |
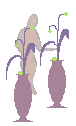
|
||||||||||
|
そして、その時期、彼は両親の問題を垣間見て、永遠であるべき愛情に疑念を持った。その様な愛情が消失すれば、恐ろしい障壁が立ちはだかって、彼を暗闇に閉じ込める。その時、克夫には、その様な不安が芽生えたらしい。また、それはおそらく、認識の消失への不安でもあり、虚無に飲み込まれる事への不安でもあった。あるいは、漠然とした愛情消失への不安があの見えざる壁に触発されて、より意識的な不安へと、成長したのかも知れない。 いずれにしても、彼は両親の問題で、増大する愛情喪失への不安を抱えながら、愛情を疑い切る事は、出来なかった様に思われる。おそらく、彼はその様な愛情への疑念を無理矢理、心に押し込めて、愛情を信じている自分を演出していた。中学に上がってからの楽天性はその様な欺瞞の上に、成り立っていたのに違いない。無論、彼は当時、自分の欺瞞には、気付いていない。そして、おそらく、欺瞞の上に成り立つ楽天主義も、無意識の為せる業だった。 また、その様な欺瞞的楽天性の為に、彼の精神はおそらく、極めて、壊れやすい状態にあったのである。押し込めた筈の愛情への不信はおそらく、事ある毎に、顔を出したのに違いない。彼の人間への、特に、女性への消極性は彼の気弱さの所為でもあっただろうが、その傾向は、その様な愛情への不信の為に助長された、と考えられる。そして、彼の楽天性はその頃から、不安を背後に従える怪しい楽天性、先の見えぬ楽天性へと、変化したのではないのだろうか? だが、「彼は本当の良い子でいたかったらしい」と、以前、私が語ったように、刹那的に成る事も出来なかったのに違いない。彼は自分の神に、忠実だった。だが、彼が彼の神に忠実であればあるほど、彼の問題の解決は困難と成った様に思われる。彼は彼の神と現実との狭間を迷い歩いて、何も解決出来ぬ侭、鬱々と、月日を重ねたのである。 | |||||||||||
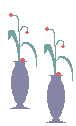
|
2.狂気か、あるいは、真実か? 今まで、書き綴った克夫の履歴と、自分の見解とを考えあわせると、彼の狂気が、彼の受動的な性格や、問題の見えざる壁だけではなく、彼の心を揺さぶる様々な事件などによって、引き起こされた、と、考えるのが妥当なようだ。勿論、克夫は彼なりに、不器用に、ではあるが、幼児の頃から、問題の不安と戦っていた。そして、高校に入ってからは、受動的で、見えざる壁を打ち破れない自分を変えようとして、彼は彼なりに、努力していた。人に嫌われても、自分の主張を押し通す反動的な行動も、しばしば、見られたので、私は少し、心配も、したのだ。 だが、学園祭などでは、誰もやらぬ仕事をひとりで、黙々と粉す姿も、私は見ている。おそらく、その時、彼は彼の神の視線を、その背中に感じていたのに違いない。大学時代の左翼との議論も、あるいは、その様な努力の一環であったのかも知れない。だが、光は注がず、三つ子の魂を変える事は出来なかったらしい。 彼は以前、「俺は冷たい人間らしい」と、漏らす事があったらしい。その時期は、確か、三十代の後半か、四十代の前半である。私も、昔、その様な言葉を一度、電話で聞いた様にも思うが、はっきりしない。あるいは、これは人伝に聞いた話を、自分の記憶であると、錯覚しているだけなのかも知れないが、最近、この様な事が多いので、気持ちが悪い。あるいは、これは、克夫が言う様に、私の無意識が誰かの意識を通して、その様な克夫の発言を聞いてしまった、と言う事だろうか?多分、これは自分の密かな冗談だが、いずれにしても、彼には、人を愛する事が出来ない、と言う一種、後ろめたい想いがあったらしい。 | ||||||||||
|
確かに、彼の若い頃は、そうであったのかも知れない。学生時代、時として、彼から感じる異様な感じはおそらく、他人に関わる一般的な行動様式の欠如から来る、よそよそしさ、あるいは、無視の態度、彼の言う冷たさ、であった様に思われる。そして、それは学生時代に私が抱いた彼についての認識でも、あった。 だが、四十の声を聞いた頃には、彼は相当に、変わっていた。他人に対して、配慮に欠ける行動はやはり、時折、見られたらしいが、誰に対しても、暖かい態度で接している、と、人から聞いた事がある。克夫を幼年時代から知っている人間の言葉であるから、これはまず、間違いなかった。あるいは、それは貧乏暮らしから、何かを悟った証なのかも知れない。 だが、彼自身は他人に優しいその様な自分を、どうやら、疑っていたらしい。おそらく、彼の無意識には、中学時代の両親の問題が横たわっていて、自分の愛情にすら、疑いの目を向けたのである。あるいは、彼はその点に於いて、自分を誤解していたのかも知れない。 ただ、彼の気弱さが他人に愛情を注ぐ事を躊躇させた事は考えられる。他人を愛するという事はある意味、その他人に、責任を負う事でもある。彼には、その様な責務から逃れたい、と言う心理があったのかも知れない。無論、それは誰にでも、経験のある事かも知れないけれども、克夫の場合、その心理はかなり、強い足かせだったのに違いない。いずれにしても、彼は様々な心の問題を抱え込んで、混乱し、苦悩していた。 そこには、彼の神とサタンの相克も、関わっていたのかも知れない。「与えられた仕事は何とかこなせるが、他人との間には、サタンが置いた壁がある」彼の主観的な認識はおそらく、その様なものだった。いずれにしても、彼はおそらく、社会的には、自分はいわゆる、駄目人間だ、と、思っていたらしい。ただ、彼を弁護して、言うならば、彼が彼の神に忠実であらんと欲する以上は、全ての問題を自分の心に引き受けて、貧困に耐えるしか、仕方なかった、と言う事は言えそうである。だが、彼は、彼の言うサタンの攻撃に耐え切れず、狂ってしまった。少なくとも、表面的には、そう見えた。 いずれにしても、彼の狂気の核心はあの手紙の中に隠されている。このところ、私はしばしば、彼からの手紙を手に取って、眺めるように成っていた。そして、彼の心を探ったのである。いや、むしろ、彼の心に入ろうとした、と言う方が良いのかも知れない。 あの手紙で、彼は人々の心を繋ぐ精神世界について、語っている。おそらくは、ユングなどの影響だろうが、彼はあの手紙で、自分は精神世界を覗く事が出来る、とも言っていた。おそらく、それは妄想であり、狂気の産物とも思えるが、何故かしら、真実性も感じるのである。実を言うと、私もユングの信者であるので、あるいは初めから、そう思っていたのかも知れない。 |
|||||||||||
|
そう言えば、大学時代、私がふと、彼の事を考えると、一時間ほど後には、必ず、彼が訪れる、と言う事がしばしば、あった。偶然なのかも知れないが、やはり、そうとも思えない。彼の意識の窓はその頃から、精神世界を見ていたのかも知れない。そして、その時の精神の状態は、いわゆる狂気とは違っているのかも知れないが、おそらく、普通ではなかったのである。 つまり、たとえ、異常な精神状態にあったとしても、その認識が全て、妄想とは限らない、と言う事だ。逆に、ある特異な精神の状態はある種の特殊な真実を垣間見せる、と言う事もなくはない。 実際に、多くの宗教的な体験はその様な状況で産まれる、と言う。自然科学に於ける発見ですら、その様な事は希ではない。差し障りのないところで言うならば、夢の中での発見である。おそらく、この様な夢は科学的にある程度の説明は出来るように思われる。それは睡眠中の無意識的な思考である。それが夢と成って、現れるのである。実際、そう考えている学者は数多いし、その様なケースも、あるらしい。 |
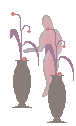
|
||||||||||
|
だが、それで、特異な精神状態での発見が全て、説明された、と考えるのは早計だ。少なくとも、私はもっと奥深い原因が隠されている、と考えている。克夫流に言うならば、その様な夢は、意識の窓が反転し、精神世界へと向けられた、その結果として、現れる。そして、夢から与えられた認識は、事実に照らして、客観的に承認されるまでは、主観的な認識である。従って、克夫のその様な言い分が間違いである、と断言する事は難しい。何故なら、克夫は主観として、その様な認識を得たからだ。克夫の言い分が現実世界の事象と全く、矛盾しないなら、少なくとも、主観的世界の説明としては、妥当である、と考えなければ為らない。 また、客観的な認識は元来、主観が必要とする認識対象であるから、世界は最終的には、主観的認識の材料として取り込まれるべき客観的認識を内包する主観的世界である。この観点から見ても、克夫が述べる推論は重要に思える。そして、克夫の精神世界は想像以上に、深そうだ、とも、考えてしまう。あるいは、その深さが彼を狂気へと誘った原因であったのかも知れない。 おそらく、彼は無謀にも、何の指針も持たぬまま、自身の精神へと潜り込み、闇雲に、奥へと進んでいった。そして、自分の精神的な矛盾、思考の論理的矛盾に、突き当たり、その矛盾について、様々に、考えながら、確かな真実を見付ける為に、更に、奥へと進んで行った。すると、やがて、彼は認識主体としての自分に気が付いた。認識主体は外界ばかりか、自身の精神も、また、認識の対象とする。認識主体は認識への意思であり、物質世界は彼の意識の眼の前に、広がっているが、彼の背後には、精神世界が広がっている。ならば、意識の窓を反転させるなら、精神世界を見る事も可能ではないのか?彼はそう、考えたのに違いなかった。ただ、この場合、彼の意識が物質世界に捕らわれているなら、意識の反転は難しいけれども、彼は無意識に行っていた意識の窓の反転を意識的に行おうとした。それはおそらく、彼がその様な自分の可能性に気付いていたからに違いない。そして、成功したのに違いなかった。 だが、少し前にも触れたが、彼は正規の宗教的修行で、そこに辿り着いたのではなかったのである。その故に、彼は精神世界で、しばしば、迷い、彼の言うサタンに行く手を阻まれた。あるいは、騙されて、魔界へと、足を踏み入れた。そして、魔物から逃れ、あるいは戦い、サタンの秘密を握ったものの、サタンに悟られ、精神病院へと、囚われたのである。私はふと、気が付くと、その様な想像にも、捕らわれた。いや、ひょっとすると、私の無意識は既に、その想像を真実として、受け入れてしまっているのかも知れない。 勿論、サタンなどが登場する想像を真実として受け入れるのは問題なのかも知れない。だが、問題である、と言い切る事は難しい。 此の世の事象は論理的な関係と因果関係によって、動いている、と言うのは、衆目の一致するところだろう。しかし、我々には、そう、見えるだけなのかも知れない。我々の認識能力や理解力は感覚器官と脳などの能力によって、制約されている。その事を考えるなら、我々の認識能力では把握できない何らかの力が、此の世を動かしている、と考える事も、可能なのである。つまり、我々はその何らかの力がもたらすものの内、論理的な関係や因果関係だけを頼りに、この世界を把握するしかない、と言う事である。従って、此の世には、この二つの関係以外の関係は存在しない、とも、言い切れない。 |
|||||||||||
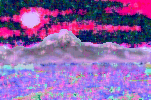
|
ちなみに、時空の存在しない世界を想定すると、因果関係は存在し得ないので、時空の誕生について、因果関係を用いる事は出来そうに無い。そして、この論理は論理的な関係にも適用出来る。つまり、因果関係の無い世界が存在する、と考える事が出来るなら、論理的な関係の無い世界も存在する、と考える事が出来る、と言う事だ。そして、この場合、普通に考えると、当然ながら、因果関係の無い世界は論理的関係の無い世界に含まれる、のだが、何しろ、相手は論理的な関係の無い世界であるから、ひょっとすると、その世界でも、何らかの因果関係が生まれる、と言う事も、考えられるし、なんらかの論理的関係が生まれる、と言う事も、考えられる。何と、不可解な世界だろうか!だが、そんな世界は存在しない、と断言する事は出来ないのだ。 その故に、神やサタンの実在を信じる、としても、それは決して、間違い、とは言えない。神やサタンは、我々にとっては、原理的に認識不能な存在である。少なくとも、克夫はそう考えていた。だが、その様な存在については、百歩、譲っても、可能性で論じるほかに無い。何しろ、相手は認識不能な存在なのだから。私は今、そう考えるが、もし、克夫にこの事を問うたなら、彼はどの様に言うのだろうか? | ||||||||||
目次 | |||||||||||
|
その一 狂気の手紙 その二 克夫の生い立ち その三 奇縁 その四 克夫の能力 その五 ライフワーク |
|||||||||||
|
その六 迷える魂 その七 サタンの陰謀 その八 認識というもののミステリー |
|||||||||||
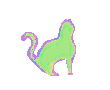
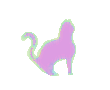
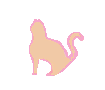
| |||||||||||
| Cotosiro Home | |||||||||||