|
----- 改訂第三版 ----- 背後の世界 その2 克夫の生い立ち December 22, 2015. 野口博正. |
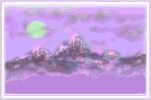
その三 奇縁 |
||||||||||
|
平成11年(西暦1999年)9月26日、今日、久々に、前回の続きを書く事にした。昔の記憶を辿って、書くのだが、忘れた事もあり、確認すべき事が多々、あったので、纏めるのに、随分と、時間が掛かってしまった。最近は仕事が忙しいので、土日しか、作業が出来ないのも、その一因と成っている。気は焦るが、致し方ない。 克夫の事は子供の頃から知っている。昔、彼の家と私が育った昔の家とは、歩いて、十数分の所にあり、遊ぶ公園も、どうやら、同じであったので、彼の事は、折りに付け、しばしば、見かけたからである。最も、当時は、彼がどこに、住んでいるのかは知らなかった。後に縁があって、知ったのだが、彼は藻岩山と豊平川の中間に位置する山鼻地区に住んでいた。ちなみに、私の家は当時、山鼻地区の北側に隣接する曙地区にあった。 だが、子供時代は、彼と遊ぶ事は全く、なかった。私は当時、どちらかと言えば、引っ込み思案な性格であったし、彼も、私以上に、おとなしく、学区が異なる事もあって、たまたま、同じ高校に通うまでは、言葉を交わす事も、なかったのである。だが、幼い当時の彼の事は、記憶には、かなり鮮明に、残っている。「何時も、一人きりで、遊んでる、妙な奴」と、言う様な若干、不思議な印象としてだ。 ただ、幼少期、彼の持つ品の良さが何とは無しに、気に入らなかった。昭和二十年代、日本が太平洋戦争に負けた、あの当時、子供は大体が、栄養失調で、青っぱなを垂らしていたが、彼には、その様な事は無かったのである。青っぱななど、垂らしておらず、身なりも、質素ながら、身綺麗だった。私と同様、貧乏であったのにも拘わらずである。さほどの意識はなかったものの、その頃の私には、彼に対して、ある種の劣等意識や嫉妬などがあったらしい。 だが、今にして思うと、彼についての、その様な印象がおそらく、高校時代の私をして、彼を数少ない友人の一人、とした一因であった。そして、何故かは知らないけれども、その事は、私が高校時代、自分の中に、彼と共通する何かを無意識ながら、見出していた証拠である様にも、思うのだ。では、その共通する何か、とは何だろう?無論、すぐに特定する事は難しい。だが、問題なのは、サタンの陰謀、と言うあの言葉がどうしても、気に成ってしまう、と言う事だ。ひょっとして、自分の心にも、克夫と同じような、サタンへの恐れが宿っている、と言う事だろうか?無論、私の理性は、「あり得ない」と、否定するのだが、直感的には、「そうかも知れない」と、思うのである。 |
|||||||||||
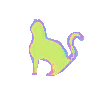
|
だが、これは結論を急ぐべき単純な問題では決して、ない。じっくりと、考える必要がある。ひとまず、回想の対象を我々の子供時代に戻す。さて、当時の私はその様に、彼をある種、特別な人間として、見ていたようにも感じるのだが、その一方で、遠目から、彼を見かけると、しばしば、「俺よりも、弱そうだ」と、優越感に浸った事も、記憶している。外で見掛ける克夫は一人の時以外、いつも、母親と一緒であったし、顔の色も青白く、背も、どちらかと言えば、低い方で、痩せて居たので、非常にひ弱に見えたのである。 それと、私の優越感には、彼の父親が建具などの職人で、それほど、裕福ではなかった、と聞いていた事も、あったのかも知れない。誰の影響かは知らないが、幼児期の私は職人という職業を蔑視していた。当時、子供であった、とは言え、私は酷く恥ずかしい人間だった。今にして思うと、その様な私の優越感は彼に対する劣等意識の無意識的な補償であったのかも知れない。いずれにしても、彼は当時の私にとって、たまたま、見かける、よその子に過ぎなかった。 | ||||||||||
|
これは高校時代に、克夫から聞いた話だが、彼の両親は彼が小学校に上がるまで、父方の祖母の家に、居候をしていたらしい。無論、それは、当時としては、いずこも同じ、貧困の所為であったが、「本来ならば、大地主の家に、産まれる筈だった」と、彼は言うのだ。余りに突拍子のない彼の話に、私は思わず、「本当か?」と、疑わしそうに、彼に尋ねた。すると、普段、おとなしい克夫が、「えっ?本当だよ!」と、気色ばむ。私は少し、たじろいで、彼の話を黙って聞いた。 太平洋戦争が始まった当時、開拓農民の二世である彼の祖父が札幌でも、有数の大地主であった、と言うのがその理由であった。だが、不幸にも、彼の父が幼い頃に、祖父が急病で、亡くなった。そして、折悪しく、その時期は彼の祖父が新しい事業の為に、奔走していた時期でもあったのである。結果、事業につぎ込んでいた多額の資金がその侭、負債として、残された。その為に、未亡人と成った祖母は相続した資産の大部分を失ったのである。グランドピアノを据えた自慢の家も、手放さざるを得なかった。僅かの土地は残ったものの、祖母は無一文の状況に追い込まれたのである。克夫は高校時代、この種の話をする時は、しばしば、「俺の家は、何かによって、祟られている」と、冗談の様に、言ったものだが、案外、あれは本心であったのかも知れない。 財産を失った祖母には、当時、幼い子供が五人、いた。「何としても、この子らを育てなければならない」彼女はそう、心に決めていたのに違いない。克夫に拠れば、彼女は、夫への様々な想いを心の奥へと押し込めて、必死に成って、働いた。僅かに残された土地を耕して、野菜などを栽培し、日銭を稼いだ。それにも拘わらず、彼女は何時も、金が無い事で苦しんでいた。そして、どうにも成らなく成ると、残された資産を切り売って、どうにかこうにか、食い繋いだらしい。 無論、その頃は、その様な農耕を行っていたのは、彼の祖母だけではなかったらしい。当時の札幌は、まだまだ、発展の途上にあって、空き地や耕作地が点在していた。開拓時代の習慣も相当に、残っており、その事情は、それぞれに違っていたが、専業でなくとも、農耕を行う家庭は、そう珍しくも、なかったのである。 だが、彼の祖母に関して言えば、それは貧困の所為だった。他には、たいした仕事も見付からず、農耕をする以外になかったのである。次男である克夫の父親が十六で、働きに出るまでに、資産はほとんど、無くなっていた。また、その後、太平洋戦争の泥沼にも、見舞われる。克夫の父親は当時、同居をしていた、その兄と共に、戦争に取られて、祖母は二人の嫁と共に、大変な生活を強いられたらしい。彼女がその様な過酷な負担から解放されたのは、戦争が終わって、二人の息子が運良く帰還してからだ、と言う。 |
|||||||||||
|
それにしても、戦争というのは、過酷なものだ。克夫に拠れば、彼の叔父、つまり、父親の兄は終戦直前、樺太で、ロシア側の捕虜と成った。捕虜収容所では、極寒の中、過酷な作業を課されたらしい。それで、仲間と一緒に、脱出を計画した。隙を見て、収容所を抜け出し、船を調達して、北海道へと漕ぎ出したのだ。どの様に脱出し、どの様に船を調達し、どの様に航海したのか?それは克夫も、聞いてはいないらしいが、大変な苦しみを味わった事だけは聞いている、と言う事だった。この事については、彼の叔父は寡黙だった、と言う。私は、克夫がこの話をした後、小さな声ながら、言葉を投げつけるかの様に、「誰かの祟りだ」と、言って、顔をしかめた事を記憶している。 だが、私は当時、まだ、高校生で、その話の重みを、まるで感じていなかった。あたかも、小説か、何かの様な気分で、聞いていた。だが、今、考えると、克夫はもっと、深刻な気分で、語っていたのに違いない。祟りか、どうかは、知らないけれども、裕福であった大地主の家が、無残なまでの凋落を味わった事は、どうやら、本当の様だった。 ひょっとして、私が幼い頃に感じた克夫の品の良さは、大地主であった家系の名残であったろうか?少なくとも、その話を聞いた時分、私はその様に考えていた。だが、その観察が妥当であったのか、どうかは、今と成っては、分からない。 |
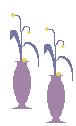
|
||||||||||
|
克夫が産まれたのは戦争が終わって、父親が帰還してから、数年ほど、後の事だった。だが、両親の使っていた部屋は相も変わらず、土間を改造した四畳ほどの板敷きの部屋と、そこに続く六畳ほどの畳の部屋、そのふた間のみである。そして、板敷きの部屋は元々は、裏庭に通じる土間だった。克夫の父親が母親となる女性と結婚する事に成ったので、板を張って、部屋としたのである。 炊事場とトイレは兄夫婦との共用であった。また、彼が産まれた頃はまだ、水道は引かれては居らず、生活用水は井戸水であった。私もおぼろげではあるが、見よう見まねで、手押しポンプを押して、水を汲んだ事を記憶している。多分、母が一緒に、手押しポンプを押していたのだ。水道が引かれたのは確か、私が四、五歳の頃の事だった。だが、彼の家の手押しポンプはその後も、しばらくは、使われないまま、流しの脇に、残されていた、と言う。ひょっとすると、それは水道への信頼感が余り、無かった所為ではないだろうか?おそらく、長いこと、使っていた井戸の方が信頼できる、と言う気分があって、残しておこうか、と、考えたのだ。 当時、内風呂のある家庭は希であったが、彼の家も、そうであった。その代わりに、個人経営の銭湯と呼ばれる公衆浴場が至る所にあって、大多数の市民はその様な銭湯で、汗を流した。当時は私も、よく、銭湯に行ったので、時たま、其処で、克夫を見付けた。だが、此処でも、「ああ、居るな」と、思っただけで、話しかけようなどとは考えなかった。多分、向こうもそうだった。互いに、何処か、ぼーっ、とした不活発な子供であったのだ。 ところで、今では、想像も出来ない事だが、当時の札幌では、下水もまだ、普及していなかったので、トイレはくみ取り式であった。また、今のような浄化槽も無かったので、便器を覗き込むと、排泄物が丸見えであった。今、思い出すと、ゾッ、とするような光景であるが、当時、それは極、日常的な風景であった。だが、匂いは、余り、感じなかった。おそらくは、トイレの通風を考えた家の造りと、肥溜めの表面に繁殖する好気性微生物が分解している所為だったろう。ひょっとすると、これが本来の排泄物処理のあり方なのかも知れない。その証拠に、くみ取った直後のトイレは鼻が曲がるほど、臭かった。 克夫の話では、両親の寝室であり、居間でもある六畳の畳部屋には、窓が無く、その為に、畳部屋は北側の板敷きの部屋から、粗末なガラス戸を通して、光を得ていた。しかし、その程度では、全く、十分ではなく、彼の両親は不自由な生活を余儀なくされた。また、板敷きの部屋には、庭に出る為の磨りガラスの填められた二枚の引き戸があり、その上には、明かり取り用の窓もあったが、その戸外、一メートルほどの所には、背の高いおんこの木が四、五本ほど、生い茂っていて、貴重な光を遮っていた。その向こうには、まだ、百平米ほどの畑が残されていた、と言う事なので、おそらく、おんこの木は開拓当時、家を守る為に植えられた防風林の名残であった。だが、その所為で、板敷きの部屋も、やはり、何時も薄暗かった、と言う。そして、それは夜も、同じ事だった。 |
|||||||||||

|
当時の照明器具は今のような立派なものではなく、天井から、ぶら下げられた直径25センチほどの丸い傘の付いたソケットに、裸の白熱電球をねじ込んだだけの、極めて、粗末なものである。しかも、彼の家では、それは節電の為に、ワット数を落としてあった。その為に、部屋の隅には、明かりが届かず、やはり、夜も薄暗かった。彼は幼児期、その様な環境の下で、生活していた。その所為だろうか?自分の居る板敷き部屋と、そこから覗き見る光のあふれる戸外とは、別世界である様に感じられた、と彼は言う。 無論、それは幼児期の体験であるから、それほど、意識的な感覚ではなかったらしいが、その感覚は青年期に入っても、消える事は無かったらしい。彼はある時、「俺には、自分の居る暗闇の世界と、光に満ちた外界がある、その間には、目に見えない壁があるんだ」と、ボツリと、言った。 | ||||||||||
|
だが、その様な貧困にも拘わらず、彼の母親は情操教育には、熱心だった。なけなしの金をはたいては、絵本やレコードなどを買って来て、彼に聞かせたり、読ませたり、した。「特に、クリスマスの日に貰ったレコードは鮮明に覚えている」彼は高校時代、ジングルベルが鳴り響く頃、そう振り返ったが、その時の彼の顔はうれしそうに輝いていた。当時の彼にとって、クリスマスは正月よりも楽しいビッグイベントだった。板敷きの部屋の隅に、小さなクリスマスツリーを飾ってもらって、二つ違いの妹と一緒に、点滅する豆電球を飽きもせずに、見つめたらしい。レコードプレイヤーは当時、蓄音機と呼ばれていたラッパ付きの手動式プレーヤーであったらしいが、そこから聞こえる歌声には、とても、感動したらしい。彼は高校時代、クリスマスの時期が近付くと、この様な話を一度は語ったものである。彼の感受性はおそらく、この様な環境の下で、育まれていた。そして、それは薄暗い、そして、薄ぼんやりとした自分の世界から、光に満ちた外の世界にあこがれる、その様な感受性でも、あったのだろう。だが、ひょっとすると、彼の狂気の原点も、この幼児期にあったのかも知れない。 克夫は未熟児同然で、生を受けた。それで、幼児期は始終、病に見舞われていた。母親は、その事に気を使う余り、育児には、相当に神経を使ったらしい。見方によっては、それはすでに、過保護であった。あるいは、その過保護ぶりが気に入らなかったのだろうか?それとも、他の理由でも、あったのだろうか?職人の父親は母親とは全く、正反対の態度を取った。「おまえは体が弱いなあ」などと、克夫のひ弱な体質をなじる様に強調して、彼の自信を喪失させた。「何故、親父が殊更に、その様な事を言ったのか?それは良く知らないけど、自分はその度に傷つけられた」彼は悲しげな顔で、一度だけではあるが、そう、述べた。そして、彼はその時、彼が幼かった頃の父親の姿をほとんど、覚えていない、とも語ったのである。だが、彼を傷付けた言葉は覚えているが、その頃の父親のイメージはその大部分が欠落している、と言うのはどういう事か?その話を聞いた時、私はどう理解して良いのか、分からなかった。 高校時代、私は、克夫から、その事に関係するらしい話を聞かされていた。母親が想い出した様に、言ったらしいのだが、克夫の幼少期、父親はまだ、若い事もあって、仕事を終えても、真っすぐに、家に戻る事は希だった。仕事上の付き合いなどで、大抵は、仲間や取引先の人間と、繁華街へと繰り出したのである。夕食を一緒に食べた事など、殆ど無いし、帰宅するのは大抵、克夫が寝入ってからだった、と言う。「まあ、口調が愚痴っぽかったから、親父に、面白く無い事でもあったのかも・・知らんけど・・」克夫はふざけた調子で、そう、言った。が、急に、真顔に成ると、「当時の父親の記憶が希薄なのは、その所為かもしれない」と、私に語った。だが、今、考えると、私には、それだけが原因とは思えなかった。 |
|||||||||||
|
当時、帰宅が遅いのは、別に、彼の父親に限らなかった。私の父も、そうだった。だが、私の持つ、若い頃の父の記憶はかなり、鮮明である。克夫の幼年期の、父親へのおぼろげな印象には、もっと、奥深い原因がありそうだった。彼の無意識がその頃の何らかの体験を抑圧しているからに違いない。その原因が父親の心ない言葉であったのか、他に原因があったのか?それは皆目、分からないが、彼はその時、生まれて初めて、深い傷を負ったのだろう。彼には、その様な自覚など、無さそうに見えたが、父親に、良い感じを抱いていない事は確かであった。 だが、父親に関する肯定的な記憶が皆無か、と言えば、そうでは無かった。始めて、父親に連れられて、スキーに行った時の情景はかなり、鮮明に覚えている、と言う。また、幼少期から、小学校時代に掛けて、二、三回ではあるが、父親の職場に連れられて行った時の記憶もあり、それも、また、肯定的なイメージの一つであった。克夫は、「その時、父に誇りを感じた」と、語ったのである。 人間とは、本当に、不思議な生き物である。父親が重い病にかかって、他界するまで、親子関係はずっと、うまく行かなかったらしいが、話の様子から察すると、やはり、愛情はあったらしい。彼の父親への感情は複雑であった。だが、彼の話から推測するなら、何らかの理由で、幼児期の彼が心に深い傷を負った事は、どうやら、確かな様である。ひょっとすると、この事も、克夫の狂気の一因なのかも知れない。それとも、克夫が言う様に、サタンか、何かの祟りだろうか? |
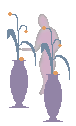
|
||||||||||
|
幼年期、克夫が戸外に出て、一人遊びをしていると、数人の子供らに囲まれて、「貧乏人のおぼっちゃま」などと、囃される事が時折、あった、と言う。私も、その光景を記憶している。多分、心ない大人が悪ふざけで、そう言っているのを聞いた悪ガキが、そのまま、克夫にぶつけたのだろう。勿論、私は当時、何時も、良い子で居たかったので、その様な振る舞いなど、しなかったのだが、実を言えば、私も、時として、そう言いたい気分に捕らわれる事がしばしば、あった。そして、優越感にも、浸っていたのだ。その意味では、私も、その様な悪ガキの一人だったのかも知れない。 いずれにしても、幼い克夫は、その様に振る舞う他人の言動や、時として、露骨に現れる父親の侮りを刷り込みの様に、受け入れたらしい。そこには、母親の過保護の影響もあったのだろう。「自分は本当に、弱いのだ」と、そう感じたのに違いなかった。消極的な彼の気質はおそらく、その様にして、作られた。 ただ、当時の彼には、何時も、一緒にいる妹がいた。その事は彼にとって、相当な救いではあっただろう。しかし、彼の前に立ち塞がる見えない壁に打ち勝って、陽光を浴びるほどの力とは成り得なかった、と言う事らしい。彼の世界は依然として、薄暗い自分の世界と、光の輝く外の世界とに、分離しており、彼は無意識の内に、その二つの世界にそびえ立つ、分厚い壁を感じていた。そして、恐らく、彼は死ぬまで、その呪縛から、解き放たれる事は無かったのである。 だが、克夫が小学校に入ると、彼の生活環境は急速に、変化し始めた。両親が祖母から、五十坪ほどの土地を譲り受けると、借金をして、家を建てたのである。未だ、貧しくはあったが、父親の仕事も極めて、順調であったので、無理を押して、踏み切ったらしい。平屋の小さな家ではあったが、彼にとっては、御殿であった。その頃、私が公園などで、たまたま、彼を見かけると、遠目から、私を一瞥する彼の目が、何故か、昔とは、違って見えた。無意識にではあったろうが、おそらく、私はその目に、自信の様なものを感じたのである。そして、私はその様な彼に、理由のはっきりしない妙な嫉妬を感じた事を記憶している。彼を蔑む材料が一つ、消失した事がどうやら、面白くはなかったらしい。私は当時、酷く、陰険な子供であった。 |
|||||||||||
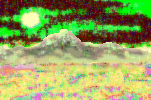
|
彼の母親にとって、家の新築は大事業であったのに違いない。彼女は彼の中学時代、「かっちゃんが小学校に上がるまでには、何とか、家を建てたかったの」と、時折、思い出した様に語った、と言う。そして、彼はその都度、「俺の為に建てたんだ」と、子供ながらに思った、と言う。だが、妙なプレッシャーも感じたらしい。 とにかく、克夫は小学校に通い始めると、幾分、積極性もあらわれて、体も随分と丈夫に成った。栄養状態の良化と、小学校での規則的な生活などが良い効果を与えたらしい。また、当時の父親は母親にせがまれた事もあったらしいが、しばしば、彼を連れ出して、運動などをさせた、と言う。その所為もあってか、大病をする事は無くなっていた。 | ||||||||||
|
当時の日本は戦後復興が軌道に乗り始めた時期にあって、エネルギーが満ち溢れていた。無論、国民の多くは、まだまだ、貧しかったが、希望に満ちた時代であった。彼の両親も、その様な時代の最中、自信を取り戻し始めていたのだろう。当時、克夫の家には、朗らかな笑いが絶えなかった、と言う。また、彼が小学校の三年の頃、二番目の妹が誕生した。最初は奇妙な生き物にしか、見えなかったが、九つも下の妹であるから、随分と、かわいい、と思ったらしい。その事で、彼の狭苦しい暗い世界は、また、少し、広がったように思われる。 そして、彼が小学校の四年に成ると、家の二階が建て増しされて、その北側と南側に、それぞれ、一部屋づつ、計、二部屋が作られた。彼の両親はその南側の広い部屋を彼と妹との子供部屋として、使う事に決めていた。小さな畑を見下ろせる大きな窓からは、何時も陽光が差し込んでいる。まばゆい光にあふれた部屋で、彼は快適な少年期、青年期を過ごしたのである。彼が幼年期に暮らしていた薄暗い板敷きの部屋は、すっかり、忘れ去られた様に思われた。「あの頃が一番、幸せだった」何時だったかは、忘れたが、彼がそう、呟いた事を覚えている。 だが、高校時代、克夫が言った様に、幼児期に育まれた自分と外界との分厚い壁は未だ、壊れては居なかった。ただ、中学時代の彼はその壁が自分の中にある、と言う事を忘れてしまっていた。その当時、彼は人を避けたがる素振りなど、全く見せず、社交的ですらあったので、本人も、そう思い込んでいたらしいが、実のところ、問題の見えない障壁は密かに彼の心に影響を及ぼし続けて、長い間、彼を苦しめたのである。そして、おそらく、その感覚は終生、彼を悩ませた。そして、中学時代のその様な思い込みと、実在化しそうな見えない障壁への無意識的な恐怖の狭間で、高校時代の彼は相当に疲れていたのではないのだろうか?そして、希望的観測による思い込みにすがる事をやめたのではないのだろうか?あの手紙に書かれていたサタンは、あるいは、その障壁であったのかも知れない。いや、おそらく、その障壁を作り出した正体を、彼はサタンである、と感じたのである。 |
|||||||||||
|
目次 | |||||||||||
その一 狂気の手紙 その二 克夫の生い立ち その三 奇縁 その四 克夫の能力 その五 ライフワーク |
|||||||||||
|
その六 迷える魂 その七 サタンの陰謀 その八 認識というもののミステリー |
|||||||||||
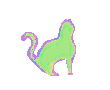
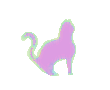
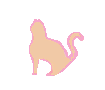
| |||||||||||
| Cotosiro Home | |||||||||||