|
----- 改訂第三版 ----- 背後の世界 その5 ライフワーク December 26, 2015. 野口博正. |
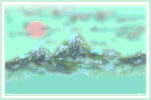
その6 迷える魂 |
||||||||||
|
平成12年(西暦2000年)2月14日、昨日、だいたいの事はうまい事、想い出す事が出来たので、その勢いで、書き綴る。 克夫が倒れたのは、予期せぬ暖気が訪れた十二月の最終週、雪を降らす筈の分厚い雲から、土砂降りの雨が降り注ぐ、クリスマス・イヴの前日だった。既に、食堂には、クリスマス・ツリーが飾られている。遠くでは、しばしば、雷が鳴っていて、一部の患者や看護人達は、季節外れの嵐に、不気味なものを感じていたが、多くの患者は、華やいだ様子で、いつもの夕食を取っていた。そして、克夫も、そこにいた。だが、彼が食事を終えて、立ち上がろう、とした、その瞬間、窓を通して、やにわに、閃光が瞬いた。一瞬、遅れて、轟音が鳴る。電柱にでも、落ちたのだろうか?食堂の窓ガラスが振動すると、院内の全ての灯りが消え失せた。 食堂はもう、全くの闇である。患者らが動揺したのか?意味不明な事をわめく者もいて、食堂内がざわ付き始めた。このままでは、まずい。電気室の係員に電話して、すぐに、自家発電に切り替えてもらわねば為らない。電話機の側にいた看護人が受話器を取った。と、その瞬間、照明が回復した。電話に出た係員が、「あ、ブレーカーを戻したら、付いちゃいました」と、説明する。電柱のトランスはどうやら、機能を保ったらしい。介護人は差しあたり、胸を撫で下ろすと、食堂の中を見渡した。 だが、ひとり、床に突っ伏している患者が見える。看護人がすぐに、駆け寄って、抱き起こすと、それが克夫であったらしい。看護人が息を確かめるが、既に、呼吸をしていない。救急車を呼び、すぐに、病院へと、運んだが、懸命の手当も、むなしく、彼は呆気なく、逝ってしまった。克夫が担架に乗せられた時、一部の患者らは興奮して、「サタンが彼を葬った」と、わめき散らしていたらしい。 それにしても、何と、悔しい、死であったろうか!死の直前、彼は一体、何を想って、逝ったのだろうか?この話を聞いた時、私は、「その時だけでも、正気であった、と思いたい」と、感じて、平静を保つ事が出来ないでいた。世間には、余り、知られていないが、彼は、いくつかの学術的な発見をして、公表している。とは言っても、彼は学者では無く、博士号も持っては居ない。また、彼は当時、会社を辞めて、実家に戻っていた。だが、再就職も侭ならず、アルバイトで、日銭を稼ぐ有様である。彼は貧困のどん底で、喘いでいた。 |
|||||||||||
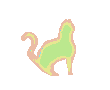
|
無論、出費のかさむ本の出版などは、夢のまた、夢であった。学術論文を出そうにも、学会の会費すら、払えない。バイトで稼いだ金はその殆どが、書籍や、パソコンなど、情報収集や思索に必要な物品の購入費に、つぎ込まれていた。それで、克夫が発表の手段として、選んだのが、当時、はやり始めていたネットのホームページだった。彼がその手段を選んだ理由はどうやら、貧困だけでは無さそうだったが、彼は何時だったか、電話で、これが俺のライフワークだ、と、私に語った事がある。 だが、彼は当初、そのライフワークについては、私にすら、何も語らなかった。そして、私も職探しで、大変だろう、と思っていたので、彼が金にもならぬ事をし始めるなど、想像すら、していなかったのだ。私が不可解な仕事、つまり、彼の言うライフワークの事を知ったのは、彼がその仕事をし始めた一年ほど、後の事だった。彼がメールで、知らせて来たのである。見ると、その最後の行には、「さしたる自信など、無かったもので、一応の形が出来るまで、知らせる事には、躊躇があった」と、記されている。私は早速、そのページを検索してみた。 | ||||||||||
|
だが、期待に反して、その内容や表現は余りにも、稚拙に思われる。取りあえず、一通りは眺めたものの、克夫の思考能力は酷く、落ちている様に感じられて、私は失望の淵に突き落とされた。それ以来、彼にせがまれて、読む以外、目を通す事は希と成った。そして、「彼の精神は大丈夫なのか?」と、むしろ、その事のほうが気に成った。彼のページの内容は全てが、奇っ怪なイラスト付きで、魔物や悪魔の話、あるいは幽霊などの話で、占められている。物理的な認識にすら、幽霊やサタンが顔を出す。心配に成るのは、当然であった。 だが、本人は至極、真剣らしい。私の酷評にも、怯まずに、昼はアルバイトで、日銭を稼ぎ、夕方、ジョギングをして、家に戻ると、寝る間も惜しんで、考え続けて、原稿を書き、訂正し、新たな発想へと、繋げていった。おそらく、それは彼のただ一つの生き甲斐であったからだった。克夫に拠れば、前日、アップロードしたホームページを、その翌日に修正して、更新する事も、希ではなかった。何故、そのホームページに興味の無かった私がその様な事を知っているか、と言えば、その都度、メールなどを送って寄越して、「間違いを見付けた、早速、修正した」などと、わざわざ、知らせて来るからだった。そして、その様な作業は彼が入院する直前まで、ほぼ十数年の間、続いたのである。だが、あの当時は、彼の様子が分からなく成った時期がある。彼からの音信が途絶えがちと成ったのだ。 当時、私は克夫が会社を辞めたのは、そのライフワークを完成させる為だったのかも知れない、と感じた事があった。そこで、ある時、電話で、怖々、聞いてみた。だが、どうも、そうでは無いらしい。理由ははっきりとは言わなかったが、どうやら、人間関係のもつれであった。彼にとって、その様な退職は不幸であったが、彼の話し様に落ち込んだ様子などは窺えず、むしろ、快活であったので、私はその時、ふっと、希望的観測に捕らわれて、安心してしまった事を記憶している。 ならば、大学時代、学習意欲の衰えた克夫が、何故、退職後、あの様な事をし始めたのか?当時の私は当初、彼の心の葛藤など、気付かなかったし、文章が稚拙な所為もあってか、単なる暇つぶし、としか、考えなかった。「そんな事より、早く、仕事を見付けろよ、嫁さんでも貰え」当時、私は電話で、彼と話をすると、しばしば、その様な事を口にした。だが、彼は、「仕事も無いのに、嫁さんどころじゃないよ」と、耳を貸さない。「まあ、そうかも知れん」とは、思ったが、「そこまでして、なぜ?」と、釈然としないものも、残ったのである。そこには、おそらく、私の心の片隅にある、彼の精神状態への懸念が関係していた。だが、相手は既に社会人だし、会う事もほとんど、無かったもので、たとえ、冗談めかしても、「精神科医に診て貰え」などとは、言えなかったのである。 その当時、克夫は既に、札幌にある彼の生家に戻っていたが、私はまだ、東京で、ある会社に勤務していた。時折、札幌に出張する事もあったので、出張が決まった前日、克夫の所に電話して、「会えないか?酒でも、おごるよ」と、誘ってみた。だが、夜はバイトで忙しい、と、口ごもる。だが、様子がおかしい。どうやら、会いたくない、と言う事らしい。私は、「そうか、残念だな」と、言って、電話を切った。だが、彼の様子は気に掛かる。私は克夫との共通の友人である角山清彦に声を掛けた。そして、札幌での仕事を終えた六時過ぎ、清彦をススキノに誘って、克夫の近況を聞き出した。 |
|||||||||||
|
だが、彼も、現在の克夫の事は余り、良くは知らないらしい。彼もまた、克夫には、全く、会っていない、と言うのだ。私は、「情報は取れないのかな?」と、幾分、がっかりさせられた。電話では、あの時、克夫は快活そうに、話していたが、清彦の話から推測すると、どうやら、それは演技であった。だが、もっと、詳しい話が聞きたい。「けど、何か、克夫について、知らないか?心配なんだ」私は即座に、そう言って、清彦の顔を下から、覗いた。すると、克彦が少し顔を曇らせながら、ぼつぼつと、言葉を選びながら、話し始めた。清彦に拠れば、彼は相当な人嫌いに成ってしまったらしい。だが、清彦は個人商店の長男で、家業を手伝っており、その店は克夫の実家に、ほど近い商店街に位置していた。克夫については、いろんな噂が、耳に入る。悪意のある、心ない噂も、多かった、と言う。清彦は、「これはあくまでも、噂だけど」と、前置きして、克夫の様子を語り始めた。 その話によると、最近の克夫はバイトを、しばしば、休んでおり、家に籠もりがちと成ってた。数少ない友人とも、疎遠と成っており、女と付き合う事も、無いらしい。好きな女性も何人かは現れた様だが、どの女性にも、声を掛ける事はなかったのである。やはり、仕事のない事への負い目であろうか?あるいは、彼の持ち前の気弱さの所為であったろうか?それとも、彼の言うライフワークの為なのか? |
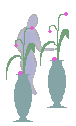
|
||||||||||
|
本当のところは分からないが、どの女性もやはり、彼にとっては、彼の世界の人間ではなく、見えざる壁の向こうに暮らす他の世界の人間であったらしい。おそらく、その様な女性と付き合う自分をイメージする事が出来なかったのである。三つ子の魂は此処にも、あった。昔は良く、飲屋などにも出掛けていたが、それもプッツリと、止めたらしい。おそらく、金が無くなったのだ。そう言えば、彼は以前、電話で、「最近は、ろくなものを食ってない」と、言っていた。なら、栄養状態も、そう良くはなさそうである。清彦はその推測を裏付けるように、「近所の人間の話では、今、克夫は相当にやせているそうだ」と、述べたのである。清彦が知っているか、どうかは、知らないが、克夫はその状況でも、なお、あのライフワークだけは、続けていたのだ。其処で、私は清彦に、克夫の趣味について、聞いてみた。だが、清彦は、「趣味なんて、無いだろ?」と、言うだけだ。克夫のライフワークについては、どうやら、噂にすら、成っていないらしい。 ならば、近所の人も、彼のライフワークに付いては、何も知らない、と言う事だ。おそらく、両親にすら、何をしているのか、未だに、話していないのだろう。無論、私は親子のギクシャクとした関係には、前々から、気付いていたが、「説明し切れぬ何かがあって、黙っているのに違い」と、当時、私はそう、考えていた。それで、想い出したのだが、私は以前、何らかの説明はすべきではないのか、と、考えて、克夫のところに、電話を入れて、その様な意見をした事もあったのである。だが、彼は、「話などしても、分からんから、おまえも、親父らには、黙っていてくれ」と、言う。私は少し、悩んだが、結局、克夫の希望に、従った。 清彦の話に拠れば、やがて、彼の両親は、彼を「怠け者の馬鹿息子」と、理解する様に成ったらしい。そして、会話も、ほとんど、無く成ったのである。それでも、彼はなお、自分の仕事を辞めよう、などとは思わなかった。「なんで、あれほど、執着するのか?」当時、私はふと、気が付くと、そう呟いていた。「彼は何かに、取り憑かれている」そう思わせるほど、彼のこだわりは異常であった。 だが、しばらくする内、彼の稚拙な文章は徐々にではあるが、読みやすいものへと変わって行った。とは言っても、時たま、見付ける予言的な記述については、以前の克夫では無い、と言う認識の許で、読む事は全く、無く成っていた。彼の狂気を認識させる様な記述が増えている事も、その一因であった。だが、学術的な記述に関しては、単純な書き間違いや、知識の不足から来る勘違いなどは、相も変わらず、見受けられたものの、その発想は斬新だった。私は何時しか、時折、目を通すように成っていた。時には、自分の評価を彼に伝えたい衝動にも、捕らわれたが、その頃に成ると、彼は電話に、出なくなっていた。代わりに、彼の母親が出るのだが、その声には、やはり、元気がない。克夫の心の状態が窺い知れた。だが、何とか、コンタクトを取ってみたい。そこで、私は彼の作品への感想を数回、電子メールで、送ってみた。すると、何時だったかは、忘れたが、珍しく、彼からの返事があった。「うん、これはノーベル賞級の発見だ」と、胸を張る様な、文面である。だが、私から見ると、それは過剰なまでの自信、と思える。そして、克夫の酷く落ち込んだ心と、過剰なまでの自信とのギャップ。「これは、果たして、どこから来るのか?!」私は、理解が出来なくて、全く以て、呆れてしまった。 | |||||||||||
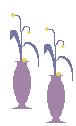
|
だが、表現が学術的では無かったからか?それとも、読む者が居なかったのか?あるいは、ホームページに載せる程度では、評価のされようも、無いのか?理由については、はっきりとは分からないが、学問的評価は得られぬ侭に、彼はあの世へと、行ってしまった。彼の一生を思う時、胸が裂けそうにも思われる。彼の狂気は、その様な認められぬ事への焦燥感と貧困の所為ではなかったか?私は一時、その様な気分にも、陥った。だが、彼の狂気は、それほど、単純なものではない筈だ。彼の不安と特異な能力、そして、彼の狂気とは、どこかで必ず、繋がっている。さもなくば、自分の生活を放り投げて、あの様に面倒な事など、始める訳がないのだ。これは克夫の妄想に過ぎない、と言う事を祈るばかりだが、彼の言うサタンの妨害は至る所に、あるらしかった。 私は昔、発表の方法について、専門家に相談してはどうか、と数回に渡って、助言した事を記憶している。無論、それはメールにして、送ったのである。しかし、彼からの返事は来なかった。何故、返事をくれないのか、と憤ったが、彼の心が相当に、内向きになっている事だけは窺い知れる。それで、私は連絡を取る事を止めてしまった。そして、彼のホームページにアクセスする事も無く成ったのである。だが、しばらくして、彼には、苦い経験があった事を想い出した。それは彼が大学を出て、ようやく、就職を決めてから、数年後、私は彼の借り家に寄る機会があった。その時に、彼の苦い経験を聞いたのである。 | ||||||||||
|
彼によれば、大学を何とか、卒業は出来たものの、就職が決まらず、ぶらぶらしていた頃、ゲームソフトを開発して、ある会社、B社へと持ち込んだ。それは丁度、インベーダーゲームが流行った少し、後の事である。だが、すぐに決定する事は難しいので、二週間ほど、待ってくれ、と言う。彼は何も疑わず、素直に、二週間ほど、待ち続けた。だが、その結果は、残念ながら、不採用の通知であった。普通であれば、他の会社へでも、持ち込むのだろうが、彼は簡単に、あきらめてしまう。持ち前の消極的な性格が災いしたのに違いなかった。 |
|||||||||||
|
だが、数年後、彼は自分のソフトが店頭に並べられているのを目撃する。多少の簡易化は為されていたが、そのアイディアは確かに、自分のものであり、盗まれた事は明らかだった。「何と言う事か!」彼は戸惑い、そして、怒った。だが、売り出した会社はB社ではない。「多分、B社が売ったのだ!」そう考えた彼はB社に連絡を取ろう、と考えた。だが、調べてみると、B社は既に、倒産している。責任者の所在も、分からない。当時、彼は既に、就職を決めており、元々、面倒な事は嫌いであるから、それ以上の調査はあきらめたのである。普通なら、疑ってしかるべき話であるが、元々、消極的で、金銭にも、執着のない彼であるから、私には、すぐに、納得出来た。 「ほら、見ろよ」彼はその時、古びた8ビットのパソコンを引っ張り出して、オリジナルのソフトを私に示した。画面はグリーンディスプレイの骨董品である。それにしても、こんな物を残しておくとは、よほど、悔しかったのに違いない。元々が、引っ込み思案の性格である。彼自身は気づいていないが、その事で、相当の心の傷を負ったらしい。おそらく、彼は自分の失望に気付く事に、恐れを感じた。それで、その失望を心の底に、抑圧したのに違いない。 「まあ、そんな事があったんで、誰も信用する気に成れんのだ、俺が何かを始めると、必ず、妙な邪魔が入る、悪霊にでも、取り付かれたのかも知れん」その時、彼は自嘲気味にそう、言った。今、考えると、その辺りから、彼の精神は変調を来し始めていたのかも知れない。彼に言わせるなら、サタンの妨害は此処にも、あった。 |
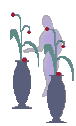
|
||||||||||
|
しかし、その頃の彼は精神の危うさを感じさせる一方で、どことはなしに、不思議な雰囲気も漂わせていた。彼自身は貧困の中で、藻掻いていながら、人には優しい。そして、彼のまわりの人間には、時として、大きな福が訪れた。それは彼の所為では無いであろうが、少なくとも、心の安らぎを与える事は友人である私が経験していた。言ってみれば、教祖のような雰囲気だろうか?だが、本人に、冗談めかして、「成ってみては?」と、訪ねると、「自分には、人への愛情が足りないし、世俗的な人間だから、すぐに、邪教に化けそうだ」と、言う。もっともな意見とは思われた。 だが、自分を俗物と分かって居ながら、彼は一向に定まった職に就こうとは、しなかった。彼はただ、黙々と修行僧の様な生活をし続けた。私には、到底、理解しかねる選択だが、社会に適応し切れぬ、と言う彼の想いが、自分を弱気にさせたらしい。だが、反面、自分の発見や認識には、「これは神の啓示である」と、言うほどの、過剰な自信を示したのである。 |
|||||||||||
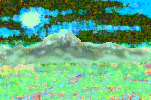
|
おそらく、彼はその様な自信と、貧困という現実とのギャップの狭間で、相当に、苦悩していたのに違いない。そして、その苦悩には、生活苦、両親への負い目、また、自分の認識を表現し切れぬ苛立ちなども、含まれていた。だが、その様な彼の苦悩が彼をして、更なる思索へと、駆り立てたのに違いない。そして、この精神的な環境の為に、彼は何時も、極度の緊張を強いられたのである。 無論、この緊張が彼の能力を育み続けた、と言う事は考えられる。だが、果たして、この様な緊張状態が十数年もの間、ずっと続いて、人は正気で、いられるだろうか?事実、彼は心を病んでしまった。それにしても、彼は何を思って、あの様な緊張に長い間、耐える事が出来たのか?私はこのところ、しばしば、心の中で、彼の魂に、問い掛けている。 | ||||||||||
目次 | |||||||||||
|
その一 狂気の手紙 その二 克夫の生い立ち その三 奇縁 その四 克夫の能力 その五 ライフワーク |
|||||||||||
|
その六 迷える魂 その七 サタンの陰謀 その八 認識というもののミステリー |
|||||||||||
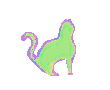


| |||||||||||
| Cotosiro Home | |||||||||||