| 日本文化の源流、その論理的帰結としての世界観 | 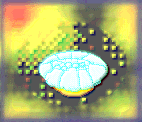 | ||||
| 修正しました。野口博正 December 31, 2011. 旧版 | |||||
|
縄文の世界観 縄文の世界〜利益と物々交換 |
|||||
|
我々の精神の根底にある縄文の魂、そして、その魂に基礎付けられる縄文的な世界観は、取りあえず、機能してはいるものの、殆ど意識をされない為に、ともすると、眠りがちです。それは先に述べた通り、我々の縄文の魂に弥生の精神が覆い被さる社会的、精神的な二重構造の故に、弥生の精神が我々の意識に対して、縄文の精神を隠すからです。 それはある種の自己疎外であるように思われます。そして、そのような自己の疎外は社会、及び、組織がその様な自己疎外の上に成り立っている、と言う様な諦観的世界観へと、我々を誘う可能性を含んでおります。我々の社会が個人の独立性や個人的自由に対して、消極的姿勢を見せがちなのは、あるいは、その所為であるのかも知れません。ただ、この様な問題は日本だけの問題ではなく、その内容こそ違うでしょうが、どのような社会にもあり得る、と言う事を付言しておきます。 いずれにしても、これは個人の尊厳や自由、そして、個々人の精神性に関わる非常に重要な問題です。この問題を放置するなら、組織至上主義の肯定に至る可能性も、全くないわけではありません。また、個々人の組織化が進んだ今日、この様な傾向を持つ社会は、強き者、富める者の自由と権利が弱き者、貧しき者の自由と権利を際限なく阻害する、と言う可能性を孕んでおります。もし、その可能性が現実と成るなら、それはヨーロッパ的な階層社会とは質の異なる、より悪辣な階層社会へと繋がるでしょう。 その様な社会は組織の論理に馴染まぬ者を幾何級数的に増加させさせます。また、その場合、社会はその様な人々を疎外するにも関わらず、彼らと彼らの疎外の心理を自らの体内に抱え込みます。そして、多くの人々を、文化と規範の基である自我の融合から閉め出すでしょう。文化や規範の堕落、そして、崩壊をもたらす事は自明であるように思われます。人間はただの労働力、また、組織の部品として存在するのではありません。我々はあくまでも、世界を知るべき、すなわち、自分自身を知るべき精神的存在、すなわち、認識主体として存在します。 にも関わらず、特に文明社会は人間を組織の部品として扱う傾向があるように感じられます。実のところ、このような社会の傾向が文化の堕落をもたらして、社会の荒廃をもたらすのです。勿論、その具体的な動因と様相はそれぞれの国家や組織などで異なるでしょう。しかし、少なくとも我が日本では、縄文の魂と弥生的な合理主義的精神の歴史的な相克がその根底にはあるのです。我々はこの事について謙虚な態度で考えなければならないでしょう。 ところで、整合性を持つ各人各様の主観的な認識が現実世界を個々人にもたらすなら、それぞれの自我が認識の主体と思われます。無論、この場合、社会、及び、組織の持つ認識は個々人にとっての客観的認識として機能する事は確かです。ですが、それはあくまでも、他者の認識である事を知っておかなければ成りません。その故に、組織至上主義は主観の否定であり、また、主観の否定はオブジェクトたる世界の否定でもあるのでしょう。個々人の認識は最終的には、すべて、主観的な認識であるからです。 従って、組織至上主義がもたらす主観的認識の否定は認識主体としての我々に無をもたらし、生の反対の極にある滅びの哲学をもたらすでしょう。我々は既に、その問題を日清戦争から始まる軍部の台頭で、経験済みです。もし、その様な哲学が再び、蔓延するなら、国家は存亡の危機にさらされるでしょう。先に、述べたように共同体には、個々の自我を融合させる精神的基盤が無くては為りません。また、本当の哲学というものはその様な原理原則を探り当てる事に他なりません。余談ですが、その意味で、整合性を持つ認識者は大切にされねば為らないでしょう。 いずれにしても、借り物の原理やシステムが賞味期限切れと成ろうとしている今日、我々は我々本来の世界観、すなわち、縄文の世界観を再認識しなくては為りません。また、其処から我々本来の精神的原理を抽出しなくては為りません。その事無しに、我々の整合性のある認識は確立される事が出来ず、自我の融合は益々、難しくなります。 つまり、社会的な求心力を維持する事が難しくなります。また、以上の事は世界の情勢についての正しい我々自身の認識も確立されない、と言う事を意味しますから、我々の共同体が進むべき道も誤りかねません。 孫子は己を知り、敵を知れば、百戦、危うからず、と言ったそうです。しかし、己を知る事は敵を知る事以上に難しく、その故に、一番、重要である様に思われます。おそらく、孫子も、その様な意味で言った様に思われます。そこで、ここではまず、その世界観を呼び覚ます為に縄文人の世界をおさらいし、以下において、その世界観に迫ってみたい、と考えます。 しかしながら、縄文時代は非常に長きに渡って続いて居ります。そこで此処では、縄文文化の最盛期と思われる縄文中期から後期の辺りに焦点を合わせたい、と考えます。その時期はおおよそ、BC2000年ないしBC1000年の辺りです。そして、その時期、列島は比較的、温暖でしたが、それは寒冷期に向かう途上であり、また、大陸では殷王朝(BC1500年頃)が成立し、新モンゴロイドの優位性が少なくとも客観的には顕著と成った時代でもあります。 逆に、縄文晩期に入りますと、縄文文化は衰退をし始めます。おそらく、その時代の列島における社会状況の激変は、列島住民に、新たな時代の到来を予感させた様に思われます。そして、その予感は的中して、列島は弥生文化と、その文化に基礎を置く政治的勢力に席巻される事と成るのです。 時代は少し、さかのぼりますが、先に述べた様に、縄文時代の後期、その文化は爛熟の域にありました。おそらく、その事が彼らの不安を増幅させていた様に思われます。今日よりも明日が良い日とは限らない。少なくとも、その様な心理は、あった様に思われます。当時、縄文人達の前途には、心理的にも現実的にも、暗雲が立ち込めておりました。おそらく、列島における社会情勢、また、大陸の政治情勢を良く知る縄文人に取っては、それはより現実的な驚異であったでしょう。 当時、四方を海に囲まれた列島で暮らす縄文人は海洋民族の性格を色濃く持っていた、と考える事ができます。また、その時期は縄文文化の隆盛期でもありますので、外界に対する好奇心は旺盛であり、非常に行動的であった、と推測できます。その故に、彼らは彼ら独自の航海技術で、列島各地の交易ばかりでは無く、大陸の旧モンゴロイド、あるいは新モンゴロイド化されつつあった旧モンゴロイド、そして、間接的かも知れませんが、力を持ち始めた新モンゴロイドなどとも、交易し、見聞を広めていたのではないのでしょうか?彼らはそうとうに大陸の事情に通じていたように思われます。 当時、新モンゴロイドは既にアジア大陸の至る所に進出をしておりました。従って、大陸の海沿いのエリアには、旧モンゴロイドの共同体だけではなく、新モンゴロイドの血を持った人々の共同体も、既に在った、と考えるのが自然です。ならば、列島の縄文人が彼らと接触していた、と考えるのも、自然です。縄文人は殷王朝、あるいは、他の王朝の事も十分に知っていたの違い在りません。ひょっとしますと、それらの王朝と直接、接触していた可能性も、全く、なくはありません。 いずれにしても、縄文人、特に、海に面した共同体の人々は交易を通して、有益と思われる新モンゴロイドの知識を積極的に吸収した様に思われます。無論、それは前にも述べた様に、列島内の競争に勝つためでした。しかしながら、少なくとも、その時期に於いては、新モンゴロイドの文化に劣等感を感じる事は無かったでしょう。むしろ、少なくとも、その初期においては、彼らは自らの文化の優位性を感じていた様に思われます。 それは先に述べた通り、縄文文化が最も隆盛を極めた時代であったからです。出土した土器や土偶を見るならば、彼らが自らの文化に誇りを持っていた事は手に取るように分かります。また、新モンゴロイドの文明の影響が未だ、微弱であった所為もあって、縄文人の世界観はおそらく、完成の域にあったのでしょう。さもなくば、神産霊神、高皇産霊神の様な抽象的な神を生み出す事など、不可能でしょう。世界観は文化の発展と共に抽象性を増す、と思われますので、その様な抽象的な世界観を表す神々が生み出されたのは決して偶然ではない、と考えます。 ところで、従来は、彼らの生活の多くが狩猟採集によって支えられていた、と、されておりました。また、ドングリなどが主要な食糧であった事は良く知られております。また、貝塚などで見られる貝殻、魚、動物の骨などから窺えるように、その食料は非常に多彩であった、とも言われております。しかしながら、近年、彼らが純然たる狩猟採集民であるという見解は変わり始めております。 栗林らしき痕跡など、農耕の痕跡も見られる、と言う事なので、様々な作物を育てていた可能性もかなり、ありそうです。栗が栽培されていたのなら、他の作物が栽培されていなかった、と考えるのは不自然です。また、当時の縄文人の虫歯の発生率は他の狩猟採集民族と比較すると、非常に高く、研究者は、「むしろ、それは農耕民族に近い」と、言っております。 当時、縄文人の集落は急速にその規模を大きくしております。それは大量の食料の安定供給が為されて居た証拠である、と考える事が可能ですので、農耕は想像以上に行われて居た、と考える方が自然です。また、その事は土器や道具の形状などからも窺える、と言われております。 無論、農耕の普及については、地域差はそうとうに、あったでしょう。しかし、その様な地域差はおそらく、各集落の交易で埋められていた様に思われます。事実、黒曜石などの交易の痕跡も見られますので、特に海沿いの共同体は数多くの交易で潤ったのではないのでしょうか?当時の交易は物々交換であった筈ですから、一見、利潤は生まれない様に思われますが、大きく分けると、二つの理由で、やはり、利潤は生じるからです。 その理由の一つは、多くの共同体が取引を繰り返す場合、経済的価値の変動が頻繁に起こる事、そして、その様な経済的価値の変動には、地域差と時間差がある事です。従って、うまく立ち回る事のできる共同体はその事で利益を得る事が可能です。つまり、交換レートの差を使うわけです。これは現在の経済でも、通用している理屈です。そして、もう一つの理由は、その様な状況を加速させる要因の存在が想定される事です。それは基軸通貨の様な役割を果たす物資です。ある時期、少なくとも、ある貿易圏では、黒曜石がその様な役割を持っていたのではないのか、と言う話を聞いた事があります。 もし、縄文文化圏に、そのような物資が本当にあったのなら、富の蓄積は純然たる物々交換経済に比べますと、ずっと、容易である様に思われます。いずれにしても、縄文人は既に、利潤の概念を持っていた、と考える方が良いでしょう。そして、激動の縄文晩期、豊穣の女神、御大津姫は既に、交易を守る神、海上安全の神へと変化を遂げていた様に思われます。いずれにしても、それぞれの共同体の優劣には、その様な経済的要因も深く関わっていた、と考えられます。 また、交易は主として、海路を使い、輸送期間も掛かりますから、食料、衣料などの保存技術も、かなり、発達していたように思われます。食料、衣料は交易の重要な対象であり、長い航海を要する交易では、特に食料の保存技術は必要不可欠である、と考えるからです。あるいは、貨幣の役割を果たす何等かの特定の物資すら存在した可能性が考えられます。頻繁な交易には、基軸通貨に類した物が必ず必要に成る、と思われるからです。 | |||||
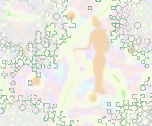
|
はじめに・日本の精神的諸問題 1.文化と文明 〜 生態系と民族 2.日本文化への基礎的理解 2−1.日本民族の形成 2−2.日本の言語 2−3.日本人の脳と日本の文化 3.神々に潜む縄文の精神 3−1.我々の精神の二重構造 3−2.別天津の神の神性 3−3.神々の変質 3−4.神々の里 3−5.恵比須の誕生 |
||||
|
4.縄文の世界観 4−1.縄文の世界〜利益と物々交換 4−2.縄文人の宗教観 4−3.「国産み」と「イタク 」の思想 4−4.我々に潜む世界観 5.神産霊神、高皇産霊神に見るサブジェクトとオブジェクト 6.認識主体から見る物理世界(固有の時間、主観的時間、客観的時間) 7.情報と認識主体 | |||||
| Cotosiro | |||||