| 日本文化の源流、その論理的帰結としての世界観 | 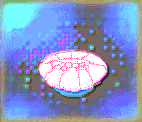 | ||||
| 修正しました。野口博正 December 31, 2011. 旧版 | |||||
|
神々に潜む縄文の精神 神々の里 |
|||||
|
鳥取県の八雲村には創建を神代にまで遡る、と言われる熊野神社が在ります。祭神は熊野大神とも言われる神祖熊野櫛御気野命(カムロキ、クマヌノクシミケヌノミコト)です。極めて古い神と言われております。ならば、この一見、意味の不明な神の名は縄文語で出来ている事も考えられます。 つまり、神産霊神、高皇産霊神などと同様に、縄文語の系譜に属すると思われるアイヌ語で解読する事が可能である様に思われます。そこで、知里真志保博士が編纂した地名アイヌ語小辞典などを参考として、その解読を試みました。すると、「神祖熊野櫛御氣野」は「kamuy-rok-kuma-nesir-mek-ka」のように解釈出来ます。以下に於いて、その意味するところを探って行きます。 さて、「神祖」は日本語で「かむろき」あるいは「かふろき」などと読みますが(カフロキはカムロキが訛ったものである)、アイヌ語の「rok」は座る事を意味する複数形の動詞であり、「kamuy」は神を意味するので、「Kamuy-rok」は熊野大神が元々は単身の神では無く、複数の神々で在る事を明示しております。また、「kuma」は魚などを吊して干す為に横に渡される木の棒を意味しており、それは転じて、横に長いものを意味する形容詞の用法でも使われます。その後に続く「nesir」は山を意味する名詞ですので、「kuma-nesir」は「連山」を意味する複合語です。 その事は熊野の地名が連山を背景とする山間に点在する事からも窺えます。つまり、熊野は実は野では無く、山地を表す言葉であった、と考えられます。そして、「mek-ka」は刀の嶺を表しているように思われます。つまり、「mek-ka」は本来、畝の形を表現するので、山の連なる形状を刀の嶺に見立てたものと考える事が出来ます。従って、「かむろき・くまぬのくし・みけぬ」は「カムイロク・クマネシル・メクカ」と、読めますので、それは神々が刀の嶺状の連山に腰掛けて集う心的印象、として解釈し得ます。以上の推理と解読との整合性はかなり高い、と考えますので、この神の名が縄文語で出来ている事はまず、間違いは無いでしょう。 * ちなみに、江戸時代の国学者、本居宣長はこの神を須佐之男命であろう、と推測したそうですが、それはおそらく間違いです。 ところで、現在の通説はこれを「熊野に座す奇霊の神」と解釈しております。つまり、「くまぬ」は熊野、という地名であって、「櫛御=くしみ」は「奇霊=くしひ」の変化したものであるので、この神の名は正体の分からぬ霊の意味を表している、とされております。しかしながら、この解釈には大きな問題が潜んでおります。そこでまず、通説の言う「Kusi-hi」の「hi」と、アイヌ語で神産霊神の名を解読した時の「Kamuy-mun-un-hi」の「hi」とを比べてみてください。 その間には、発音と意味において、共通点がある事に気付く筈です。ならば、「Kusi-hi」が元来、縄文後に由来する語句である事も、容易に理解ができる筈です。言葉の生成順で、言うなら、始めに、「クマネシル」という山々を表す縄文系の単語が在り、それが神々の状態を表す「カムイ・ロク・クマネシル」という慣用的語句の中に使われた、と考えられます。つまり、山々の頂に腰掛けて集う神々のイメージ、それこそが、この言葉の本来的な意味でした。 しかしながら、それはやがて、「かむろき、くまぬくし、みけぬ」と言う、神々の総称として使われ始めた、と考えられます。また、その時期に、「くまぬくし」の部分が「くまぬのくし」と、変化しました。その表記がたまたま「熊野櫛」であったので、その様な読み方が可能に成ったのでは無いのでしょうか? 従って、熊野が地名と成ったのは、「くまぬくし」が漢字で表記された後の事であった、と考えられます。おおよそ、地名などというものは何らかの由来が在って、初めて産まれるものであり、決して、その逆では在り得ません。実を言えば、それは野では無く、本当はクマネシル、つまり、連山であった、と考えられます。山ならば「熊山」と名付けられるのが普通でしょう。それが「熊野」と成ったのは、クマネシルという縄文系の単語が先行して居たからに他なりません。 また、奇霊という解釈も奇妙であるように思われます。おおよそ、古代人の祭る神々は刀や火、そして偉大な人間など、必ず具体的な存在が神格化をした存在でした。つまり、神々は具体的な神性を持って生まれてきます。その事は神を祭る上での鉄則である、と言っても、決して過言ではありません。訳の分からぬまま、神を祭るなど、意味を為しませんし、考え難い事でもあります。やはり、ここにも、何らかの政治的な意図が作用している、と考えるのが自然でしょう。そこで、以下では、なぜ、複数であるべき、この神の神性が不明と言われる様に成ったのか、について考えます。 しかしながら、弥生文化に基づく支配の体制が強固に成るに従って、この神々が単身の奇霊(クシヒ)の神へと、変質して行った可能性は考えられます。あるいは当初、その様な変質に、あからさまな政治的意図が関わる事はなかったのかも知れません。ですが、その根底には、この神々への恐れがあった様に思われます。当時の支配層がこの余りにも縄文的な神々の在り方に危惧を抱いたのでしょう。 もし、この神々をそのままにしておくなら、反体制運動の心の拠り所とも成り兼ねません。その故に、訳の分からぬ神として、その神性を奪ったのでは無いのか、と、その様な推測も成り立ちます。「くまぬくし・みけぬ」は「熊野櫛御気野」と、表記をされました。彼等はこれを大凡、「くまぬのくしみけぬ」と、読み、意図的かどうかは別として、容易に「熊野の奇霊」と、解釈する事が出来ました。つまり、単身の神、熊野大神は縄文の神々を権力を支える神々へと変質をさせる過程で生まれたのです。 その昔、熊野大神は単身の神では無く、実は八百万の神々でした。八雲を見下ろす山々にどっか、と座り、その足を中腹の沢に掛けて、人々に与えるべき自然の恩恵について語り合い、あるいは、憩う、様々な神性を持つ巨大な神々。縄文人の心には、その雄大なる心的印象が生き生きとした情景で躍動していたのに違い在りません。その情景こそが神祖熊野櫛御気野命の本来の姿であったのでしょう。 旧暦の神無月には、日本中の神々が出雲大社に集う、と言う言い伝えがあります。しかしながら、「カムイロク・クマネシル・メクカ」の意味からすると、それは元来、熊野大社の神事である可能性が極めて高い、と考えられます。ならば、その神事は何時、そして、何故、出雲大社へと移されたのでしょう?おそらく、それはこの神々の神性の変質と関わりがあります。 先に述べた通り、大和はこの神事の余りにも縄文的な印象に恐れを抱いておりました。それをその儘に認めると、エミシなど、先住民の血を引く氏族の反抗の拠り所とも成り兼ねません。大和にとって、縄文の神々の集いなど、出来得れば、葬り去りたい神事でした。しかしながら、その様な氏族の纏まりはその神事に拠って成立していたものと考えられます。迂闊な介入をするならば、藪から蛇とも成り兼ねません。為政者に取って、纏まりを欠く社会ほど恐ろしいものは無いからです。次善の策が必要でした。 其処で、大和は大国主命の為に創建した出雲大社に目を付けた様に思われます。つまり、先に述べた八雲の熊野神社に伝わる伝説と、今は単身の神の名として使われる慣用句から、縄文のにおいを取り去ろうとして、それらを出雲大社のものとして、移してしまった、と言う事である様に思われます。出雲大社の地理的位置は熊野神社とは極めて近く、また、祭神は出雲系の大国主命ですから、先住氏族の系列に属すると思われる出雲系の神の代表格です。其処に神事を移すくらいは先住氏族も認めるだろう。大和はそう考えたに違いありません。 また、その祭神、大国主命は大和に国譲りをした、とされる神でもあり、大和に取っても都合が良かった、と考えられます。つまり、大和の人々にも、受け入れやすい計画であった、と言う事です。大和は旧支配氏族を威圧して、あるいは宥めて、神事を出雲へと移したのでしょう。ただ、熊野神社を廃社に追い込む事は出来なかったようです。土着氏族の熊野神社への敬愛が極めて深かったからであるでしょう。神有月が出雲の暦として語られたのは、おそらく、それ以降の意図的喧伝のたまものでした。人々がその祭事と神の名の本当の意味を忘れ去った事で、大和の意図は見事に成功したのです。 そして、殆どの人々がその様な伝説の変化、神々の変質を受け入れれた、様に思われました。 | |||||
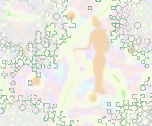
|
はじめに・日本の精神的諸問題 1.文化と文明 〜 生態系と民族 2.日本文化への基礎的理解 2−1.日本民族の形成 2−2.日本の言語 2−3.日本人の脳と日本の文化 3.神々に潜む縄文の精神 3−1.我々の精神の二重構造 3−2.別天津の神の神性 3−3.神々の変質 3−4.神々の里 3−5.恵比須の誕生 |
||||
|
4.縄文の世界観 4−1.縄文の世界〜利益と物々交換 4−2.縄文人の宗教観 4−3.「国産み」と「イタク 」の思想 4−4.我々に潜む世界観 5.神産霊神、高皇産霊神に見るサブジェクトとオブジェクト 6.認識主体から見る物理世界(固有の時間、主観的時間、客観的時間) 7.情報と認識主体 | |||||
| Cotosiro | |||||